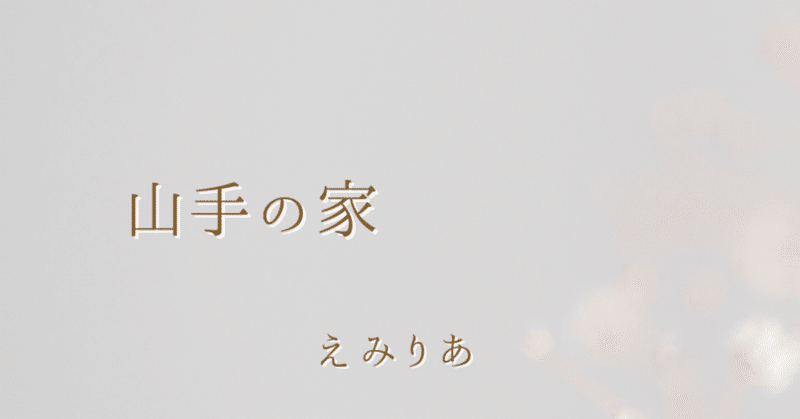
山手の家【第20話】
真の声が上がったリビングは扉が全開になっていて、南向きの窓から明るい日差しが廊下にも漏れ出していた。
リビングに入ろうとしていた瑠璃を「瑠璃さん、そこ、気をつけて」と、真の声が止めた。
「そこ、段差があるんだ」
見ると、リビングの床が廊下よりも1段下がっていた。
「こんな段差、昔はなかったぞ」
確かに、真の言う通りだ。
信子たちが住んでいたころは、毛足が長く、地の厚そうな白い絨毯をリビングだけでなく廊下にも敷き詰めていて、段差を気にすることは全くなかった。
(そういえばこのスリッパ、あの頃この家に敷いてた絨毯に見た目も感触も似てる)
瑠璃は足元を見ながら廊下とリビングの間の段差をまたいで、片足がつく時にぐらりと頭から床に倒れそうになった。とっさに片手をついてしゃがみ込む。
見えない何かに引き倒されるような感じだった。
「瑠璃さん、キッチンも段差があるから気をつけて」
リビングの入り口すぐ脇にあるキッチンは、昔と場所は変わらないけれども対面式に作り変えられ、床がリビングよりも1段高くなっている。
瑠璃はキッチンに立って、リビングを眺めた。
幸代が何を見ているふうでもなく、ただ、スリッパの足を引きずりながらぐるぐるとリビングを歩き回っていた。
「お父さん、リビング広くなったわねぇ」
「リビングの隣にあった部屋の、押し入れと扉をなくしたからな」
「2人とも、さっきと同じこと言ってる」
「えっ、そうなの? イヤだわ」
瑠璃は自分を除く大人3人が笑い合っているのを聞きながら、キッチンを全体的に見渡した。
ガスコンロも水回りも、今、瑠璃たちが住んでいるマンションに備え付けられているものと色やデザインがよく似ている。
でも、細かに見ていくと、今住んでいる家の設備の方が立派だというのがよくわかる。
水道の蛇口が洗面のシャワーヘッドのように伸びないだけでなく、ガスコンロにタイマー機能や温度調節機能がついていないとか、ガスコンロは三口だけれどそれぞれの間隔が狭いから1度に3つを使うのは難しそうだとか、ごく些細なことではあるけれども、毎日使う上でありがたい装備がないのは残念だった。
(私が便利さに慣れて、わがままになっただけかな)
ガスコンロの前に立って、ここで調理をしている自分を想像してみた。
振り返って、瑠璃の身長では届かないような壁の高い位置にコンセントを見つけた。冷蔵庫を置くなら、この場所なのだろう。
瑠璃たちが今使っている冷蔵庫は、真が独身の頃から使っている小型のタイプだった。それでも、そこに置けばガスコンロとの間は狭くなる。
瑠璃が調理中に、真が冷蔵庫から飲み物を出そうとすると、瑠璃が一度ガスコンロの前からよけなくてはならなくなるのが容易に想像できた。
(あれ、ちょっと待って。信子さんのあの冷蔵庫、ここに置ける?)
今、義人たちの家で使っている冷蔵庫は、信子が元々この家で使っていたものだ。
義人たちが以前使っていた冷蔵庫は買い替え時が迫っていたので処分し、信子が引っ越しの荷物と共に持ってきた、買い替えて間もない最新式の冷蔵庫を使うようになったのだ。
有名寿司店の大将の自宅には立派な最新式の業務用冷蔵庫を置くものなのかと瑠璃は感心したが、信子から「あの冷蔵庫は大将が亡くなってから買い替えたのよ」と、聞かされると、お金がないと騒ぐわりに、どうしてこんなに立派な冷蔵庫を買えるのだろうと疑問を抱いた。
(あんな大きな冷蔵庫、ここに置いたらガスコンロが使えない)
瑠璃たちが使っている冷蔵庫よりも大きな冷蔵庫を置けば、ガスコンロの前に人が1人、立って調理するのは難しくなる。
真珠のぐずる声が聞こえてきた。
「あらあら、泣いてるわ」
「母さん、段差気をつけて」
瑠璃の目の前を、幸代が小走りで駆けていった。
幸代の耳に真の言葉は届いていないようだった。
風が通り抜けられるようにリビングの窓を開けた方が良いかもしれない。
瑠璃はキッチンを出ようとして、段差があることを思い出して立ち止まった。
(うわ、段差の境目がわからない)
キッチンとリビングのフローリングの色と柄が同じなので、境目が見分けづらくなっていた。
境目のところにフローリングの色とは違う滑り止めをつけた方が良いかもしれない。
瑠璃はおそるおそるリビングの床に足を下ろした。
リフォームで張り替えたというフローリングの床にクッション性があるのか、それとも内覧の客用に用意されていた白く毛足の長い素材のスリッパのせいなのか、足元が少しだけ沈み込んだ感じがした。
瑠璃はリビングの窓を開けた。ベランダの柵の外側に目の細かいネットが張られている。
(前に来た時には、こんなの無かったよね?)
網目越しに、坂の下に広がる街並みが見えた。建物と建物の間から、この街のシンボルとして有名なタワーの頭の部分が見えた。
ここからもう少し坂を上がった北山手だったら、もう少しダイナミックな眺望が拝めるのかもしれないが、駅にも買い物に出かけるにも、この場所はちょうど良い気がした。何より、ベビーカーを押して坂を上り続けるのは考えただけでも疲れる。
義人が腰に手を当てて「どうですか。住めそうですか」と、瑠璃の隣に立った。
「父さん、この家、エアコンはついてないんだね」
「ま、エアコンはお前たちが好きなものをつけなさい」
玄関で真珠をなだめていた幸代が「なんだか、寒いわね」と、さっき瑠璃が開けた玄関脇の窓を閉めてしまった。
(こんなに蒸し暑いのに、寒いってどういうこと?)
瑠璃は幸代のツイードのジャケットの背中を呆然と眺めた。
「瑠璃さん、汗すごいじゃん」
額だけでなく、首筋や腕にも玉のような汗がにじんでいるが、真は瑠璃のワンピースにできた汗染みを見て声をかけたのだろう。
「ここ、サウナみたいでしんどい」
「エアコンつけないと、夏は絶対厳しいよな」
束ねていた髪の後毛も汗で湿っている。
こんなところに住めるのだろうかと思いながら、リビングを見渡していると、真珠がさらに激しくぐずり出した。
瑠璃は玄関に飛んで駆けつけた。
「暑いんで、窓開けますね」
ベビーカーを覗き込んでいた幸代が顔を上げ、ちょっと驚いたような表情を浮かべた。
幸代の答えを待たずに、瑠璃は窓を開けた。
タオルで真珠に風を送っていると、幸代が急に語り始めた。
「この家、元々は真のおばあちゃん、お父さんのお母さんが住んでいたんだけどね。最後の方は認知症になって、よく『怖いおばさんが家に来て、私のことを閉じ込めるの』って、私に訴えてきたのよ」
瑠璃はタオルを振っていた手を止めた。
「私は『そんな怖い人、見たことないですよ』って言うんだけどね、お義母さん何度も同じこと繰り返し言ってたの。だから、私も変なこと言っちゃったらごめんね。先に謝っておくわ」
幸代が無邪気に笑った。
「お義母さんはお茶目で可愛いから、きっと、面白いこと言ってそうな気がしますよ」
口ではそう返しながらも、『怖いおばさん』と『閉じ込める』、この2つの単語が瑠璃の頭の中をぐるぐる駆け巡って止まらなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

