
「共感力」が戦争を引き起こす?
前置き:「ドヤ顔で語るための読書」の主旨
あなたは1年前に読んだ本の内容を覚えているだろうか。
素晴らしいインプットをしてもアウトプットしないといずれ忘れてしまう。
このサイトでは"他人に語るシチュエーション"と共に内容を紹介する。
今回お伝えしたい内容
「共感力を高めるオキシトシンを吸う実験。吸うと他者に預ける金額が増えたが、例のトロッコ問題では1人側が同胞である時に5人側を犠牲にする割合が増えた」ということ。

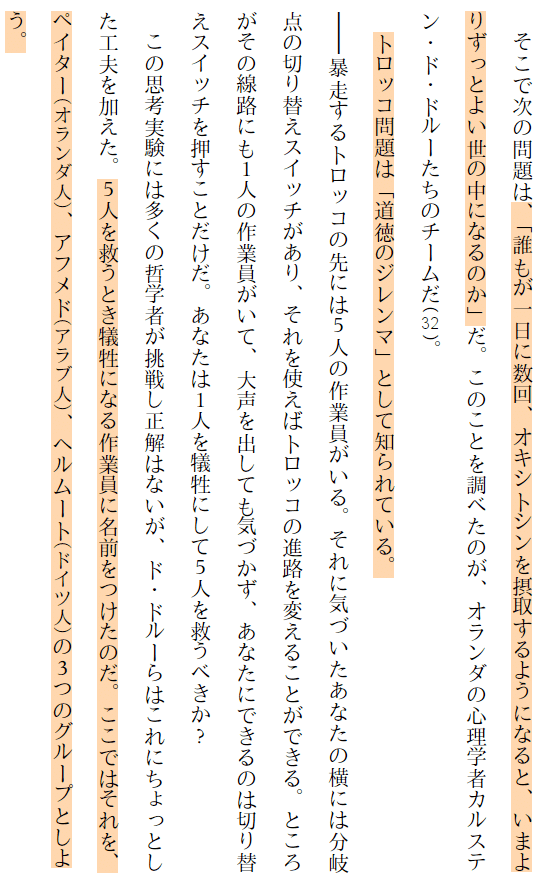

他人に語るシチュエーション
・思いやりや共感の話になった時
事件やニュースから思いやりや共感の話になった時に語る。
使い方の会話例
自分「共感力について残念な実験結果がある」
相手「どんな?」
自分「ドーパミンとかテストステロンとか聞いたことあると思うが、共感に関する神経伝達物質にオキシトシンというのがある」
相手「ふーん?」
自分「それを鼻に噴霧して吸わせると、他者に一時的にお金を預ける実験で金額が増える。愛と絆のホルモンとも呼ばれてる」
相手「へ~」
自分「そして残念なのは次の実験。道徳とかで出てくるトロッコ問題って知ってる?」
相手「まっすぐ行くと5人ひいてしまうけど、曲がれば1人だけひいちゃう、みたいなやつだっけ?」
自分「そうそう。5人よりも1人の犠牲を選ぶのが"合理的"な判断ではあるわけだ。この実験を少しいじる。1人側に名前を付けた。被験者(選ぶ人)と同じ国の人っぽい名前を付けた時と、馴染みのない外国の人っぽい名前を付けた時で1人側を犠牲にする判断に差が出るかという実験」
相手「なるほど。日本人が被験者なら鈴木裕子さんとザードルさんみたいな感じか」
自分「そう。そして残念なのはオキシトシンを吸わせたときの変化。オキシトシンを吸わせて共感力を高めると、ザードルさんなら犠牲にするのに鈴木裕子さんなら犠牲にできず5人側を犠牲にしちゃうという割合が大きく増えたらしい」
相手「まじ?」
自分「愛情とか絆とか共感というのは、言い換えると身内びいきとなるということみたい。敵対する集団それぞれで共感を高めると、集団びいきが強まって対立が激化してしまうというわけ」
後書き
本サイトは「ドヤ顔で語るための読書」とは言ってますが、もちろんそこは入り口で最終ゴールではありません。
本サイトで興味を持った本があれば是非読んで欲しいですし、そこで得た知識を「いつか忘れるもの」ではなく「人生に役立つもの」として活用して頂ければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
