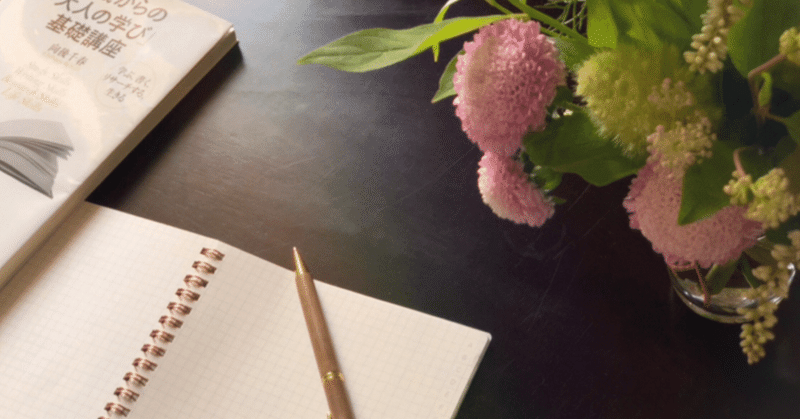
新しい学び ついに第1回の講座がスタート
こんにちは
アメリカNY州に住んでいるErikaです。
2023年10月から松村亜里さんが代表を務めるNYLB研究所にて
ポジティブ心理学コーチングを学び始め、
2024年4月にコーチとしての認定を受けました。
これから海外で暮らす日本人駐在家族が幸せに生きていくための
お手伝いをしていけたらいいな、と考えています。
また、学びと並行して、2022年より駐在家族向けのWebサイトでの
運営ボランティアにも携わっています。
ポジティブ心理学コンサルタント®️養成講
座がついにスタート‼︎
これから約5ヶ月間にわたって、毎週Zoom上で集まって学んでいく予定です。
この講座の特徴は、なんと言っても反転学習形式であること。
「反転学習」って聞いたことありますか?
これまで学びはいろいろな形式を経験してきましたが、
録画を見て自分のペースで学びを進めていくもの
オンラインもしくは対面で集まって、その場でインプットのみの学び
オンラインもしくは対面で集まって、インプットとアウトプットの両方
上記2つのいずれか、の形式で+次回までの実践課題あり
反転学習
の5つがありました。
上記選択肢のうち、皆さんはどれが一番定着する学びになるでしょうか?
私の場合は、5から順に定着度合いや実際に行動まで移せる度合いが高かったように思います。
(1と2は自分の学びへの意欲次第で、私の中ではそこまで差がないかも)
では反転学習とはどんなものか?
反転学習とはわかりやすく言うと
集団でインプット中心の学びをし、
個人でアウトプットをする学習方法が一般的であるのに対し
その逆の形式で行うことです。
今回のポジティブ心理学コンサルタント®️養成講座(略してポジコン)では
2週間に1度、受講者がZoom上に集まります。
その間に松村亜里さんによる録画講座を各自見て学びます。
そして毎回のテーマの基礎的な内容を知った上で参加する反転学習会では、
BORで少人数に分かれて、学んだことに関するディスカッションや印象に残ったこと、感想のシェアなどアウトプット中心に行います。
その後BORから戻ってくると、チャットでディスカッションの内容の要約や感想、共通点などを短時間でアウトプットしていきます。
個人的にはこのチャットでの更なるアウトプットが結構難しくて、でも楽しい時間です。
最後に次回までにやってみることもチャット上で宣言するので、
自然と行動する確率が上がります。
2週目には1週目に学んだ内容を練習&実践する場があるので、
さらに知識が定着し、実際に行動にまで繋げることができるのです。
第1回はどんなことを学んだの?
講座の詳しい内容はこちらには書きませんが、
第1回は
🌟幸せを増やす科学的な方法
🌟幸せのメリット
🌟幸せと成功のメカニズム
について学びました。
また、コミュニケーションのスキルとしてとても大切な
ACRについても学びました。
ACRとはActive Constructive Responceの頭文字を取ったもので
「積極的建設的傾聴」と訳します。
理論としては理解できても、実践するのはなかなか難しい。
とくに夫や子どもたちに対してできているか、と問われると。。。
ここから心掛けたいと思います。
私自身の気づきと感想
みんな違う<多様性がある>からこそ学びが深まる
⏩BORで「事前録画を視聴してみて、一番印象に残った内容」をシェアしてみると、同じ動画を見ているのに皆感想が違うんです。
これまでのその人その人の環境や経験が違うからこそ、同じインプットでもこれだけ多様性がある気付きに繋がるのだなぁと。勿論共感ポイントもありますが、こうして異なる視点で捉えている人の話を聴くことでより学びが深まるのだなぁと感じました。自分自身のWhat’s goodの内容の変化に驚く
⏩第1回で「2種類の幸せ」について学ぶのですが、幸せの捉え方に関して以前の私とは違う着眼点が育っているのだ、と気付くことができました。
BORで小学校教諭をされている方と子どもの幸せの種類についてお話を聴くことができて、日本の教育現場にも思いを馳せることができました。それぞれの場所、立場で学びを実践ししている方の話を聴くことができ、
希望を感じた‼︎
⏩前回PPCの際も感じたことですが、本当に世界中から様々なバックグラウンドを持つ受講生が集まっています。
一人ひとりのできることは少しずつでも、「幸せは伝染する!」を信じて行動を起こすことで、大きなパワーとなるのだろうなぁと希望を感じました。
今週はいよいよ少人数のグループでの練習会も始まります。
引き続き学びのアウトプットをしていきたいと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
