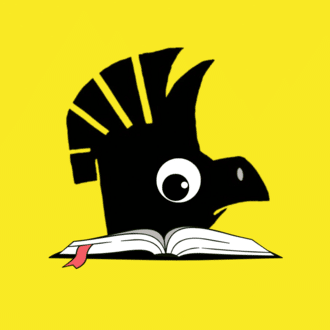レビュー『恐怖の哲学 ホラーで人間を読む』
怖いものに惹かれてしまうのはなぜだろう?
そんな疑問から手に取ったのが本書。
ホラー映画を題材に「怖さの仕組み」をユーモアを交えつつ解説している好著です。
本書の魅力は、恐怖を定義、分類し、さまざまな先行研究や理論の長所と欠点を指摘しつつ、結論へとすすむ点。
「これからの哲学は、脳科学、生物学とシームレスにつながるべき」と語る著者は、哲学や認知科学、脳神経科学と多様な知識をふまえて「恐怖の正体」に迫っています。
怖いはずのホラー映画を、人はなぜ楽しめるのか。
ときに恐怖と笑いが同居するのはなぜか。
そもそも人はなぜ恐れるのか。
そういった疑問から、ホラー映画・SF映画をもとに「人間の意識とは何か?」という問題にまでふみこみ、「意識の表象理論」という最新理論も紹介されます。
人間の複雑さを読み解くのに参考になります。
そして驚かされるのが本自体のボリューム。
448ページもあり、通常の新書の2倍はあります。
長ければいいというものでもありませんが、大のホラー好きという著者の情熱がつたわってきます。
かなりの分量であるはずなのに、楽に読み進めることができ、それは著者独特の語り口に秘密が。
独特の語り口が親しげで読んでいて楽しく、思わず声に出して笑ってしまうような場面も。
著者の戸田山和久さんは、科学哲学専攻の名古屋大学大学院教授を務められている人物。
そんな著者が「なぜぼくたちは多彩なものを恐れるのか?」という質問に答えてくれるのが本書です。
おなじみのホラー映画を分析し、哲学から心理学、脳科学までと多様な知を縦横無尽に駆使し、「恐怖の実態」に迫っていきます。
冗談をまじえつつも論理的に執筆されており、わかりやすかったです。
哲学の魅力を再確認させてくれる本で、映画ファンには新しい視点を与えてくれる一冊。
いいなと思ったら応援しよう!