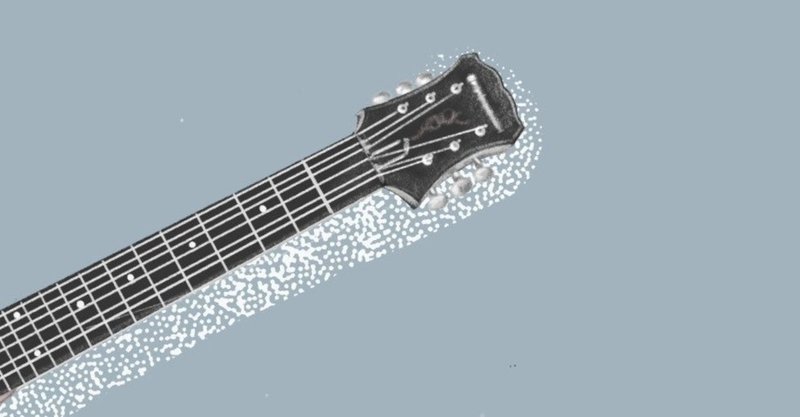
Vol.10 毎日の練習
「じゃあ、もう一回最初からやってみようか 」
「あいよ」
女神の言葉にキュアドレインが上機嫌に答えてベースを構えた。店長がシンバルでリズムを刻み始める。つるぎこは慌ててギターを抱えた。
シンバルとドラムにベースが絡まり重厚な低音が作り上げられる。1,2,3,5,6,7,8 ここだ。たどたどしいギターの音がなんとか滑り込む。左手が覚えたてのコードを必死にたどる。
上手く入れた、と余計なことを考えたのがよくなかった。気がつくと指がもつれる。慌てて追いつこうと入る場所を探るが、気が焦るばかり、たちまち今の音も見失ってしまう。
「はいはい、ストップ」
女神が手を打ち鳴らしながら言った。
「ごめん」
つるぎこは謝罪の言葉を口にする。もう何度目だろう。
「大丈夫大丈夫、できるまでやればできるようになるから」
女神の励ましがむしろ胸に刺さる。店主の無言の眼差しと同じくらいに。心の内でため息をつきながら、つるぎこは安請け合いを後悔した。
◆◆◆◆
そもそもの始まりは酒場アンディフィートで流れていたラジオ番組だった。キュアストライクとキュアドレインは廃工場の崩壊を生き延びた気晴らしにとアンディフィートの扉を開いた。相変わらず他に客はいない。二人はカウンターに向かう。
「マスター、美味しいやつと…何にする?」
キュアドレインが慣れた調子で注文して、つるぎこに尋ねる。
「あー、ジンジャーエールで」
「はいよ」
店主は不愛想にグラスをカウンターに置いた。そういえば店主はつるぎこ同じくらいの年齢に見えるが本当は何歳なのだろう。店主は雑な調子でグラスに酒とジンジャエールを注ぐ。
「とりあえず、乾杯」
「ん」
キュアドレインとつるぎこがグラスを合わせる。カウンターに戻った店主は少し背伸びをしながら柱の上にくくりつけられたラジオの電源を入れた。
『最近、ドブヶ丘も結構治安良くなったよね』
ラジオからノイズ交じりに男の声が流れてくる。他愛もない内容だが、店内の静寂を紛らすには充分だ。
「それで?」
ラジオの音を聞き流しながら、つるぎこが口を開いた。
「あれはなんだったの?」
問い詰めるつるぎこに、キュアドレインは目を逸らしてしばし考えこみ答える。
「わからん」
「おい」
「いや、本当にわからないんだって」
責めるようなつるぎこの視線にキュアドレインは少し慌てたように答える。
「最近少し調子が悪いなとは思ってたんだ。細かい制御が効かなかったり、半殺しにしようとしたらとどめさしちゃったり。でも、あの時は……」
つるぎこは廃工場での惨劇を思い出す。
あの時のキュアドレインの粘液は完全にキュアドレインの制御を外れているように見えた。
「なにがあったんだ?」
「……わからない。あの女を呑み込もうとした時、粘液が言うことを聞かなくなったんだ。まるで、粘液自体が意志を持ったみたいに」
「意志を?」
「うん、全部を壊そういうような黒い意志」
軽く身震いをしてキュアドレインは右腕をさすった。今は大人しく腕の形を保っている。
「結局、その腕は何なんだ?」
つるぎこが問う。
「うーん」
キュアドレインは曖昧に唸り、目を逸らす。
「わからないのか」
「うん」
「女神さまからもらったんじゃないのか?」
「多分、違うと思う。この町に来て、川に落ちて死にかけてて、気が付くとこうなってた」
キュアドレインは遠くを見つめ、記憶をたどるように言葉を紡ぐ。つるぎこは眉を上げて考え込む。女神以外に異能を与える存在があるのだろうか?
「ちょっと、外すよ」
ラジオを聞いていた店主がそう言って立ち上がった。
「あーい」
「勝手に飲んだら殺すからね」
「はいはい」
二人に釘を刺すと、店主はぽてぽてと店の外へ出ていった。
「そういえば、マスターって何歳なんだろうね」
扉が閉まるのを見て、キュアドレインはふと口を開いた。
「私と同じくらいに見えるけど」
「見た目はね。でも、さすがに中学生は酒場の店主しないでしょ」
「若作りだって言いたいの?」
「本人の前で言うなよ、それ」
呆れたようにキュアドレインが言う。
「なんかのクスリか呪いなんかじゃないの」
つるぎこは答える。どちらもこの町では珍しいものではない。それもそうか、とキュアドレインは納得したように、酒を一口すする。
「それで、あんたはどうなんだい?」
「何が?」
「その力、薬なの? 呪いなの?」
「どちらかと言うと呪いかな。女神様にもらったの」
「女神様?」
「知らない? ドブヶ丘の女神」
キュアドレインは少しの間考えて、驚いたように言う。
「ハンターズの?」
「そう」
「あの人、そんなこともできるの?」
キュアドレインの驚きももっともだ。女神が目撃されるのはハンターズの代打の切り札として打席に立つときか、角打ちで呑んだくれているときだけだ。どちらの姿も神性とは程遠い
「どちらかと言うとそっちが本職らしいけど」
「人は見た目に寄らないんだなあ」
感心したようにキュアドレインが答える。
「そっか、じゃあその女神さまの力なんだ」
「うん」
「なんか、さっき使ってなかったけど?」
今度はつるぎこが目を逸らす番だった。
「どしたの?」
「私も最近調子が悪くて」
「うん」
つるぎこはしばし逡巡し、思い切ったように言う。下手に隠すよりも、明かした方が今後のためになる気がした。
「魔法が使えないんだ」
「使えないって」
「わかんない。でも、ボールとかバットに魔力をのせられなくなってて」
「なるほど」
そう言ってキュアドレインは頭頂部をさすった。先ほどつるぎこの投球が直撃した箇所だ。
「魔力が込められていたら、痛いじゃすまなかったのかな」
「たぶんね」
「それは助かったな」
「でも、なんで使えなくなったんだろう」
「心当たりは?」
「ない」
二人は考え込み、店内に沈黙が流れる。
『はい、ドブヶ丘ラジオ、これからの時間はあなたのやりたいを応援する、御馬ヶ時お宮がお送りします』
店内に流れるラジオにキュアドレインは眉をひそめた。
「あれ?」
キュアドレインはラジオを指差す。
「なに?」
「これ、録音かな?」
『いやー、この前ちょっと抗争に巻き込まれちゃったんですけどね』
ラジオから流れる声は滑らかに、ドブヶ丘の日常を語る。
「どうしたの?」
「御馬ヶ時お宮って、さっき死んだはずなのに」
「でも、ドブヶ丘ラジオに録音機材なんてないよ」
「え?」
二人は顔を見合わせる。確かにお宮の死体を確認したわけではない。しかし、廃工場は完全に崩壊していた。ただの少女があの崩壊から生き残れるはずがない。
「あいつ、何者だ?」
その時、酒場の扉が開いた。ドアに取り付けられたベルが鳴る。
「なんか面白そうなこと話してるね」
現れたのはドブヶ丘の女神だった。
「女神様!」
「ああ、つるぎこちゃん、久しぶり」
声を上げるつるぎこに女神は優しく声をかける。
「あなたが、女神さん?」
「ああ、初めまして、キュアドレインちゃんだね。話は聞いてるよ」
少し警戒したように挨拶するキュアドレインに、女神は手を差し出した。
「なんか、めんどくさそうなことになってたからさ」
女神の後ろから店主が姿を現した。
「なるほど」
キュアドレインとつるぎこから事情を聴いた女神はひと言つぶやくいた。目の前に置かれた酒瓶に手を付けず目をつむって黙り込む。
「あの」
沈黙に耐えきれず、つるぎこが声をかける。女神はそっと目を開いた。
「キュアドレインちゃんは、その御馬ヶ時ちゃんに近づいたときに暴走したんだよね?」
問いかけられ、キュアドレインはおずおずと答える。
「ええ」
「その時、御馬ヶ時ちゃん歌ってた?」
「どうだったかな」
「歌っていたと、思います」
光景を思い出しながら、つるぎこが答えた。
「なるほど、なるほど」
女神は納得したように頷き、さらに問いかける。
「キュアドレインちゃん、その右腕はドブ川に落ちてそうなったんだよね」
「はい、そうです」
「だとすると……」
再び、女神は考え込む。やがて、酒瓶を持ち上げると、一口口に含んだ。
「御馬ヶ時お宮を倒す」
女神は固い決意とともに口を開いた。
「御馬ヶ時お宮をですか?」
「そう」
「どうして?」
「おそらくあの子は邪神ドブヶ丘明神の加護を受けている。キュアドレインちゃんの右腕と同じね」
「これですか?」
キュアドレインは右腕を示しながら訪ねた。
「あいつはこの町のドブ川に邪神でね、ときどき良くない力を人に与えるんだ。多分御馬ヶ時ちゃんもそう」
「なんのために?」
「信仰心を得るため。それが、私たち神の力の源だから」
女神は苦々しそうに答える。
「こんな街だもの、神への想いなんてそんなにあるわけじゃない。でも、そのわずかなパイを奪い合って何とか生きてるのが私たちなんだよ」
「それじゃあ」
「そう、やつは御馬ヶ時ちゃんに力を与えた。あの子へのファンの想いが御馬ヶ時ちゃんを通じてあいつに流れてるんだと思う」
「だから女神さんの力が薄れてるんだ」
カウンターで話を聞いていた店主が口を挟んだ。女神は頷いて続ける。
「このままじゃ、良くない。あいつの力が変に増しちゃうと、この町がまずいことになっちゃう。今のうちに阻止しないと」
「御馬ヶ時お宮を仕留めれば、いいんですか?」
キュアドレインの質問に女神は答える。
「信仰の対象を失えば、やつへの信仰は消えるはず。そうすれば今までと同じくらいのバランスに戻るから」
「でも、どうするんです? 私たち顔見られちゃってますよ」
「そこなんだよね。警戒されてさすがに易々とは近づけないだろうし」
つるぎこが尋ねると、女神は考え込んだ。他の三人も考え込むがいい案は浮かばない。考えあぐねた店長は手癖でラジオをひねった。
『そうそう、私今度ライブするんだけどさ』
「あー」
流れ始めた御馬ヶ時お宮の声を聞いて、店長はラジオを切ろうとした。
「いや、待って」
女神が店長を止めた。
『対バンで来る予定だったバンドがこれなくなっちゃって。なんか強盗に会ったとかで。うん、殺人強盗』
「これだ」
女神はどう猛な顔でニヤリと笑った。
◆◆◆◆
三日間が過ぎた。キュアドレインがどこからともなく手に入れてきた楽器がアンディフィートに運び込まれた。以来、店の扉には準備中の看板が下げられている。閉め切られた店内で女神、店長、キュアドレイン、それにつるぎこはひたすらに楽器の練習に励んでいた。
「ちょっと一回休憩するか」
女神がそう言って立ち上がった。つるぎこはため息をつきながらギターを置いた。痛む指を揉みながら、ノートを開いて運指を確認する。最初の火にキュアドレインが渡してくれたノートだ。意外にも几帳面な字がわかりやすいイラストとともに並んでいる。
「ん」
目の前にジンジャーエールの瓶が差し出された。気が付くといつの間にか店長が隣に立っていた。
「ありがとうございます」
「うん。えーと、つるぎこちゃんだっけ」
「はい」
「音楽苦手?」
「ええ、まあ」
淡々と尋ねられて、つるぎこは気まずそうに頷いた。そっか、とつぶやくと店長は手に持っていたミネラルウォーターをひと口飲んだ。
「野球が好きなんだっけ?」
「はい」
「そっか」
そう言うと店長は黙り込む。つるぎこは机の角でジンジャーエールのふたを開けると一口飲んだ。生姜の辛みと炭酸が喉を通り抜けていく。
「外の野球の選手でさ」
「ふぁい」
突然店主が口を開く。げっぷを堪えながらつるぎこは答えた。
「ピアニストの野球選手がいたんだって」
「ピアニストですか?」
「うん。そっちでもかなり上手かったらしくて、どっちで生きるか悩んだんだけど、結局野球選手になったらしい」
「はあ」
とつとつと語る店主の話に、つるぎこは相槌を打つことしかできない。
「でも、野球選手になってもピアニストとしてのリズム感とか、感性とかそういうのは残ってるからさ、そういうので自由奔放な活躍をしたそうだよ」
「でも、私ピアノどころか音楽自体が」
「うん、でも、やってきたことがやることに繋がることもあるし、今やってることがいつかやることに繋がるかもしれないってこと」
「はあ」
「まあ、あんまり気負わずにやりな」
言って店長は立ち上がり、ドラムセットに向かった。
励まされたのだろうか? いまいちピンとは来なかったが。
つるぎこはジンジャーエールを飲み干すと、瓶を床に置き、改めて指使いを確認した。ジンジャーエールの炭酸の分だろうか、少しだけ胸が軽くなった気がした。
【続く】
書いた!
逆噴射小説大賞が終わっていろいろ燃え尽きかけてましたけど、習慣としてやることがあるのは良いことですね。
今回の話は物語の要請上こうなることが決まってからだいぶ迷いました。そういえば学園キノでも軽音回ありましたね。楽器は難しいです。オタマトーンは好きです。
以下、こそこそ話
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
