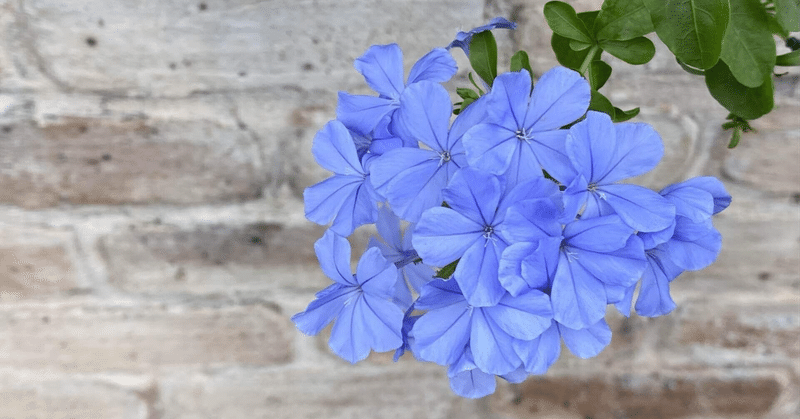
【連載小説】梅の湯となりの小町さん 5話
ふっと目を開けると、木目の知らない天井が見えた。私の家じゃ、ない。そこまで思って、はっと理解した。そうだ、私、東京の名村家に来たんだった。と同時に、自分が昨晩、ここの住人のひとりである花恵さんに対して「近々出て行きますから」と啖呵を切ってしまったことも同時に思い出し、胃がずんと重たくなった。
隣を見たが、花恵さんの姿も彼女の寝ていた布団ももうなかった。私が寝ている間に、押し入れにしまっていったのだろう。障子ごしの光は明るくて、スマホで時刻を確認すると七時四十分だった。
台所に行くと、一人分の朝食がラップをかけて置いてある。ご飯茶碗と汁物茶碗は伏せてあり、目玉焼きにハムサラダ、納豆パックがあった。私のかな、と思ってから居心地が悪くなる。用意したのは佳代さんかもしれないけれど、こういうことをしておくのは手間だろう。家のなかはしんとして、佳代さんや二朗おじさんの気配も感じない。
食べていいのか迷ったけれど、空腹には耐えかねた。ダイニングテーブル前の椅子を引いて腰かけ、ラップを剥がすと「いただきます」と手を合わせた。醤油をたらした半熟の目玉焼きに箸を差し入れ、炊飯器から盛りつけたごはんと一緒に口につめこんだそのとき――台所の入り口からぬっと男性が入って来たので、私は思わずむせそうになった。
短髪というには少し長めの髪をなでつけてワックスでかため、薄い眼鏡をかけた細身の二十代半ばほどの男性。ぱりっとスーツを着ている。彼はこっちを見て一瞬目を見開いた。私ははっとして、自分がもう箸をつけてしまった目玉焼きを見てあわてた。
「あ、あの! お兄さんの征一さんですよね? 私、昨日から居候させてもらっている、いとこの紘加です。もしかして、この朝食、私征一さんのぶんを食べちゃったんでしょうか⁉」
征一さんは「あー……」と言った。納得しているのか、それとも批難しているのか、わからない口ぶり。三秒置いてから「俺、朝いつもコーヒーだけだから」とぼそりという。
「だから、その朝飯、たぶんあんたのじゃないの」
「あ、そうでしたか……よかったぁ」
失態をしていなくてよかったと胸をなでおろす。そのまま征一さんは、私とはす向かいの席に座り棚から出したマグカップをテーブルに置く。そしてドリップバッグの封を開けはじめた。
電気ケトルで湯を沸かすと、征一さんは慣れた手つきで、ドリップバッグに注ぎ入れていく。ふわりと良い香りが立ったが、そのあいだ、ずっと無言。私は話しかけていいものか迷ったが、結局何も言えずに黙々と朝食を食べながら征一さんの横顔を盗み見た。征一さんを評した昌太くんの言葉を思い出す。
(兄貴は、わが道を行くし他人に興味ないって言ったらいいのかな。あんまり余計なこと話すのは嫌いだし、マイペースを崩されるのも苦手)
ま、まさにそんな感じだな。言ってみれば、冷酷な貴公子って感じ? こういうタイプの人気キャラクターがいたアニメ、あったな。
結局征一さんは一言もそのあと喋らないまま、コーヒーを三杯飲むと、「じゃ」の一言すらなく、そのまま台所を出て行ってしまった。玄関のドアがバタンと閉まる音で、出勤したのだとわかった。私、まるで空気だった。いないことにされていた。
名村家の家族、二朗おじさんと昌太くん以外は難しい性格だ。そのことがわかって、胃がまたきりきりしはじめた。佳代さんは、基本的によくしてはくれているけど、あのちゃきちゃきしたもの言いにまだ慣れてないので、必要以上にキツく感じてしまう。
とりあえず朝食を全部腹に収め、シンクで食器を洗っていると、ひょこっと昌太くんが姿を現した。気の許せる彼が来たので、大げさでなくほっとしてしまう。いろいろ気持ちが追い詰められてきたこともあり、開口いちばんに私は聞いた。
「昌太くん、東京でアパート借りるときって、やっぱり両親に上京してきてもらわないとダメだと思う?」
昌太くんは目を丸くした。
「紘加さん、マジで言ってるの、それ? 姉貴と昨晩話したけど、姉貴は『迷惑なこともちょっとは考えて』って言っただけで『出ていけとは言ってない』って言ってたよ。だいたい、紘加さん頼りなさそうにしか見えないけど、いままでバイトのひとつもしたことあるの? 俺は近所のスーパーで、高校一年のときからレジやってるけど、家賃分や食費分、光熱費分を稼ぐのとか、相当大変だよ? そういう苦労をしないために、うちに来たんじゃないの?」
昌太くんの口調から、世間知らずの箱入り娘だと呆れられているのがよくわかって、私は小さくなった。その通りだ、私は何も考えられていない。現実逃避をしているだけだ。
「ごめんなさい。出て行きたいなんて、本当は思ってないけど、なんだか花恵さんや征一さんに、あまりに歓迎されてないみたいで」
「姉貴も兄貴も、たしかにひとくせある人間ではあるけど、そこまで紘加さんのこと邪魔だとは思ってないはずだよ。気にしなければいい」
心のなかで、昌太くんは私よりもずっと大人だと思った。そりゃあ勉強は真面目にしてきた私ではあるけれど、これまでぜんぜん世の中のことや、お金を稼ぐことや、知らない人ばかりの中に放り込まれたときの対処法など、学んでこなかった。だったら、これから何をしていったらいいんだろう?
昌太くんが「それより、紘加さん」と口火を切った。
「駅から梅の湯まで来るときさ、父さんと一緒に来たんでしょ。ここまでの道、結構入り組んでなかった? 路地も曲り道も多いじゃん。紘加さんは、もうすぐ大学一人で通うんでしょ? この家から一人で駅まで歩いていけそうなの?」
ニヤニヤしながらずばっと言われてしまって、私は頭を抱えた。一人で戻るだなんて、そんな芸当ができるだろうか、私に。無理だ。
「僕、今日はまだ春休みだから案内できるよ?」
天から助けの糸が降りてきた、と感激した。昌太くん、やっぱりこの一家のなかでは天使……!
「ありがとう、お願いしていいかな?」
カレンダーはまだ三月終わりで、四月初旬の入学式までまだ余裕がある。この時期に、このあたりの道に詳しくなれたとしたら、助かる。一人で気晴らしに外出だってできる。手を取らんばかりにしてそう伝えると、昌太くんは細い目をさらに細くして笑顔をつくると、容赦なく言った。
「道すがら、美味しいおやつを買える店がいくつかあって。買い食いしながら散歩しようよ。もちろん、紘加さんのおごりでね。お昼前には、店も開くから出かけよ」
そ、それはタカリですか? ――昌太くん、やっぱり悪魔。私はがっくり肩を落としたが、いまは彼を頼りにするしかないのだった。
時計が午前十一時を回ったころ、私と昌太くんは連れ立って名村家の玄関を出た。今年は暖かくなるのが早く、桜がもう八分咲きと、見ごろに差し掛かっている。
「紘加さん、駅までの道しっかり覚えてね? 僕、もちろん次回もおやつおごってくれたら何回でも教えるけど、紘加さんとしては一回で済ませたいよねえ」
「一回で覚えます……」
鼻歌を歌いながら先に歩く昌太くんの大きな体を追いかけながら、私は何度も名村家と梅の湯のほうを振り返り、位置関係を確認した。目印となる個人クリーニング店の緑のひさしや、小さな川に渡された石橋の名前まで見て、確認を繰り返す。
「あ、ここ、ここ。紘加さん、どら焼き買おう」
「さっそく?」
昌太くんが足を止めたのは「しらとり堂」と古い木でできた看板をかかげてある和菓子店だった。ぺたぺたと、ガラス戸にいろいろなポスターが貼ってある。地元の高校の吹奏楽コンサートのポスターが一番新しく、昨年の夏のお祭りと花火大会のポスターや、ずいぶん色褪せている「豆大福、あります」とマジックで書かれた案内紙なども掲示してあった。
「こんちはー」
一秒も迷わずガラス戸を引いた昌太くんの後ろから、おずおず少し薄暗い店内に入る。ショーケースの中には、どら焼きのほかにも桜餅や豆大福など、五、六種類ほどの和菓子が並んでいた。
「おー、昌太じゃないか。なんだ、年上の女の子連れて。まさか、姉さん女房か?」
遠慮のない物言いが店内から聞こえて、びくっとしたら、白い割烹着を着ている小柄なおばあさんが出てきた。ひどく、腰が曲がっている。それでも、ひょこひょことこちらに向かってきて、にかっと大口を開けて笑った。おばあさんの歯はところどころ銀歯だったり抜けている。
「まさか。こちら石川県から来た、僕のいとこの紘加さん。こっちの大学に合格して、うちに居候することになったんだ」
おばあさんは目をかっと見開くようにして、驚きの表情をつくった。
「へーっ! あの広くもない家に、もう一人ねえ。昌太んち、まだ征一のやつも花恵のやつも、片付いてないっていうのに、もう一人とは」
そこまで誇張して言われると、身の置き所がなくなってくる。
「ばあちゃん、どら焼きふたつね。あんこたっぷり入ったやつ」
昌太くんがおばあさんに注文したので、あわててかばんから財布を探った。と思ったら、昌太くんが先に自分の財布を出して私のぶんまで支払っていた。
「え、あの、あれ? だって私が……」
どういうことだかわからなくなった私を、昌太くんが店の外に引っ張り出した。こらえきれない、というように笑いだしながら、私にどら焼きを渡してくる。
いつも温かい応援をありがとうございます。記事がお気に召したらサポートいただけますと大変嬉しいです。いただいたサポ―トで資料本やほしかった本を買わせていただきます。
