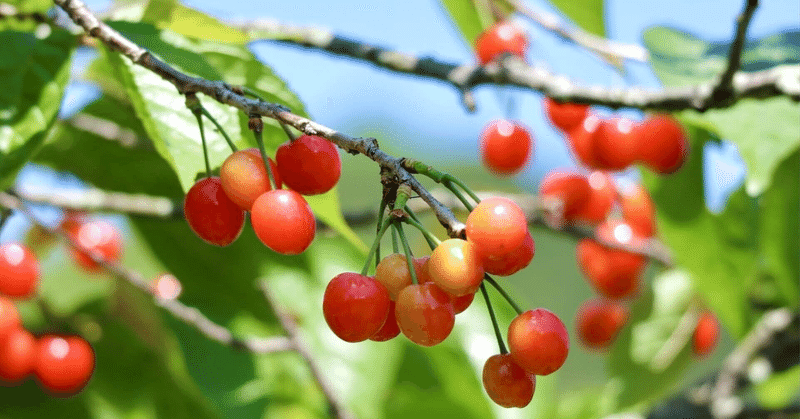
【連載小説】梅の湯となりの小町さん 6話
「紘加さん、ピュアすぎ! ほんとうに僕がおごらせると思った? そもそも紘加さん、お金節約したくてうちに来たんでしょ。ちょっとからかいたくなっただけ」
「なにそれ、もう!」
すっかり騙されてしまった。昌太くん、もしかして三きょうだいのなかでは、一番食えないタイプなのかもしれない。ちょっとぷんすかしながら先を歩いていると、昌太くんが「ごめんごめん」と追いかけてきた。
「ま、僕との今日のおやつ巡りイベントは、この先も続くから、次の店では紘加さん、よろしくね」
そうにこにこ顔で言われてしまうと、なんだか憎めない。得する性格だなあ、と半ばあきれ、半ば感心しながらどら焼きをかじってみる。卵の風味のほっくり甘い皮に、滋味深く糖度の高い餡が包まれていて、優しい味わいがハーモニーとして感じられた。
「――美味しい」
ちょっと悔しいが、機嫌も少し治ってしまった。「でしょう?」と昌太くんはとても満足気だ。お腹に収まってしまうまであっという間の、どこか懐かしくなる味わいが、名村家に来てからふくれあがった不安やストレスを和らげてくれるように思えた。
この日は結局、昌太くんと駅まで行く道のあいだ、しらとり堂のほかに三軒も買い食いをしてしまった。昌太くんが二軒分、私が二軒分の支払いをしたが、財布のなかのお金はたいして減らなかったのでほっとした。
「紘加さん、大学始まったらもちろん勉強もがんばるだろうけど、バイトも楽しいと思うよ。自分で働いた金で、甘いもの食べ歩くのが、僕にとっては最高の日々の愉しみ」
そんなアドバイスまでされて、もうどっちが年上かわからない。田舎で勉強しかしてこなかった、ふわふわしている自分とは違って、昌太くんは高校生なのに地に足がついている感じがする。昌太くんと出かけた帰り道は、少しだけ気分が軽くなっていた。
帰ったあとは、花恵さんがいない部屋に戻り、夕方までじっくり持ってきた本を読み返した。大学が始まることを、また以前のようにわくわくしながら待つ気持ちが戻って来た。というより、二畳分のスペースにも慣れてきたのかもしれない。
ところが、私の新生活への期待は、夕方またしぼんでしまうことになった。夕飯の席に、昌太くんが今夜はいなかったのだった。
「あー、昌太? いないのはたぶんバイトじゃないの。夜まで帰らないんじゃない」
台所で鉢合わせた花恵さんは淡々と告げる。「あいつの分は残しておけば大丈夫だから」と面倒そうに言いながら、佳代さんお手製の作り置きをレンチンしはじめたので、私も部屋に戻るに戻れなくなってしまった。気まずいけど、花恵さんと夕食をとる流れになった。続いて廊下から足音がしたかと思うと、今度は征一さんが台所に入って来た。
「――征兄、やたら早いね。そっか、水曜日だっけ」
「そう、ノー残業デーだから」
征一さんはネルシャツにチノパンという私服に着替えていて、花恵さんと言葉を交わしている。距離感を感じる征一さんと花恵さんとともに夕食をとることになるようだ。私の胃がきゅっと緊張に縮んだ。
今夜の晩ごはんは牛肉とトマト炒めに、切り干し大根ときゅうりの和え物、厚揚げとこんにゃくの煮物に、豆腐とわかめのお味噌汁だった。自分の分のごはんとお味噌汁を盛り、いただきますと小声で言って食べ始める。
食卓では、三人がものを口に運ぶ最小限の音しか聞こえない。そのことがひどく落ち着かず、美味しいはずの味もよくわからないが、二人は私のことなんか気にせず、黙々と食べている。私は汁椀をテーブルに置いたあと、思い切って口を開いた。
「せ、征一さんは会社でどのようなことをされているのですか?」
はじかれたように征一さんは顔を一瞬上げたが、すぐに目を伏せた。
「その質問に答えることで、俺になんのメリットが?」
「え、あ……」
言葉につまってしまった。そんな、メリットうんぬんじゃなくただの世間話のつもりだし、これからひとつ屋根の下で暮らすのだから、お互いのことを知って行ってもいいのでは……というようなことを言い訳がましく思ったが、もちろん何も言えなかった。
征一さんは飯椀を置くと、私に釘を刺す。
「たんに君がひとつ新しいことを知って、満足するだけだろう。俺のほうは別に得しない。だから答えない。以上」
変な質問をしてしまったのだ、と後悔した。というか、損得で考える問題じゃなくないか? と腹の底では憤慨した。凍った場の空気を持たせようと、今度は花恵さんに話しかける。
「花恵さんの、今日のネイル可愛いですよね。ご自身で塗られたんですか?」
びくりと、花恵さんが夕食を食べる手をとめる。今日、花恵さんの指先は紫がかったショッキングピンクに、白い水玉が散っていた。台所で会ったときから素敵だと思っていた。
「――紘加さん、さあ」
花恵さんが、うんざりとでもいったような調子で、私に言葉を放つ。
「名村家はごはんを食べるとき、だいたいみんな喋らないの。紘加さんのご実家では違ったのかもしれないけど、食べながら話すのって、行儀悪いじゃない。あたしも、征兄も、食事のときに話しかけられるのは嫌い。覚えておいて」
「すみませんでした」
しおしおと、そのあとは無言で食べた。何も味がしなかった。昌太くんがこの席にいれば、きっとなぐさめてくれただろうけど、とまで思ってはっとした。昌太くんにも、甘えすぎちゃいけない。
征一さんと花恵さんは、私よりも先に食べ終えると、それぞれにシンク台に立ち自分たちが食べた分の皿洗いをして、さっさとお互いの部屋に引っ込んでしまった。
私はやっとのことで喉に食事をつめこみ、昌太くんのためにラップをかけて、料理の残る皿を冷蔵庫にしまう。
スポンジに洗剤をつけて、自分の皿を洗い始めたとき、ぽろりと涙がこぼれた。いやだ、もう、この家やっぱりつらい――。でも、ほかに行ける場所なんてない。
涙で視界が見えなくなった、と思ったはずみに、小皿が一枚手からすべり落ちた。あ、と思う間もなく、泡のついたままの小皿が床でこなごなに砕ける。
「――最悪」
人様の家の食器を割ってしまった、という事実は、いまの私をさらに打ちのめした。涙を手の甲でがしがしとぬぐいながら、割れた小皿のあとしまつをする。かけらを拾い集め、チラシの上にまとめると佳代さんにわかるように「ごめんなさい。割りました。紘加」とメモ書きを残した。
そのあとは、花恵さんがいる部屋でゆっくりする気にはなれず、梅の湯に行くことにした。佳代さんが受付にいたので、一言小皿のことを報告し謝りたかったが、ちょうど馴染みのお客さんと楽しく談笑している最中のようだったのであきらめた。
脱衣所のロッカーキーを受け取り、涙目なのを悟られないようにそそくさと女湯のほうへ向かった。夜の銭湯は、比較的混んでいて、金髪の若い女性や、小さい子連れのお母さんや、おばあさんがたなど、さまざまな年齢層の人たちが思い思いに汗を流していた。
髪を束ね、熱い湯に体を沈めてしまうと、とたんにどっと泣けてきた。泣いているのをわからないようにしたくて、うつむいた。
帰りたい、と突き上げるように思った。受験をがんばり、やっとの思いでつかんだ山原先生の研究室がある学部の合格通知。何もかもこれからなのに、もうめげそうになっている。自分が、情けない。
上京するまでの自分は、お父さんとお母さんに庇護されて、本当に何も知らなかったのだと痛感した。四月は授業があるとして、ゴールデンウィークはすぐに実家に帰ろう。でもそれを待ちきれないくらい、いまは逃げ帰ってしまいたかった。これは、世にいうホームシックというやつなのだろう。誰も咎める人がいないのをいいことに、そのまま私は、ぽろぽろと湯のなかで泣き続けた。
銭湯から戻って、汚れ物がたまっていることに気が付いた。明日、佳代さんにどうやって洗濯すればいいか聞いてみよう。そう思って花恵さんとの部屋に入った。彼女はもう、自分の分の布団を敷いて、すこやかな寝息をたてていた。私と似たパーツをした素顔の寝顔を眺めて、ひとつため息をつくとバスタオルで髪を押さえた。
いつも温かい応援をありがとうございます。記事がお気に召したらサポートいただけますと大変嬉しいです。いただいたサポ―トで資料本やほしかった本を買わせていただきます。
