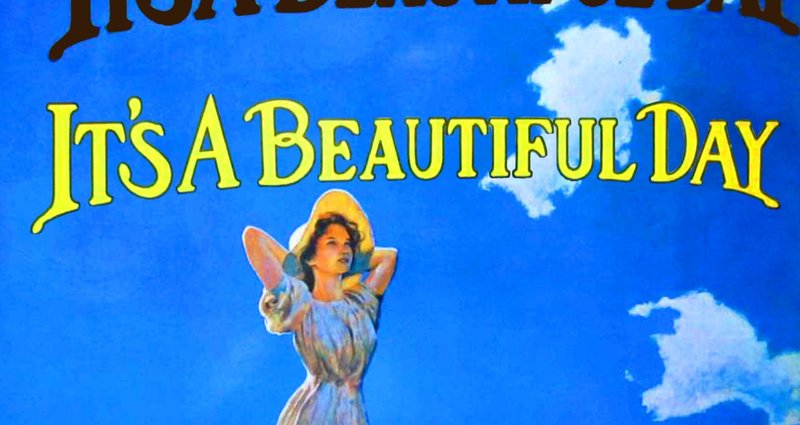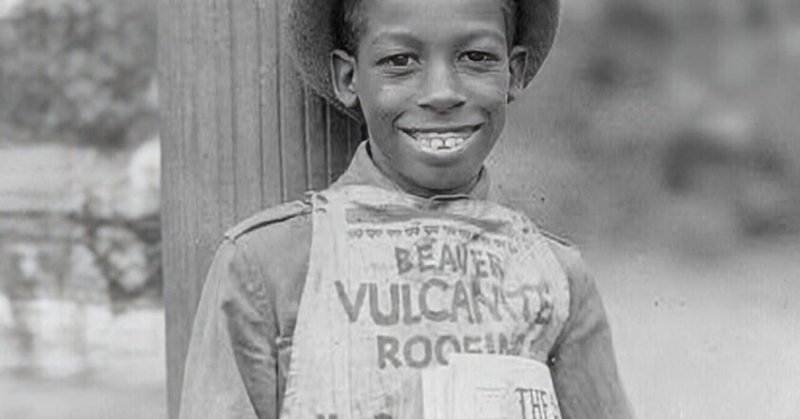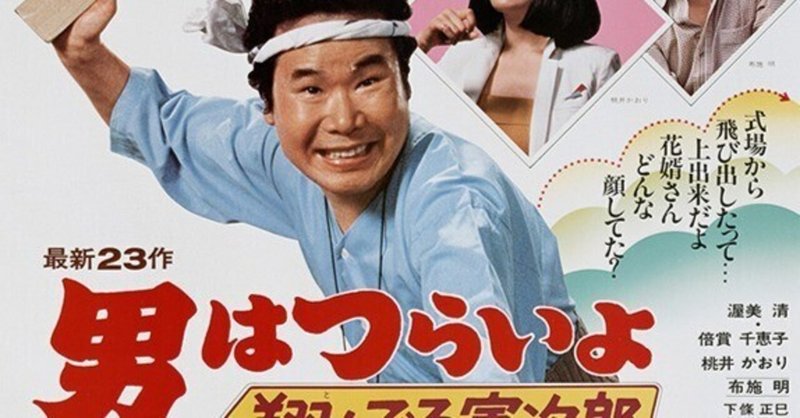#経営学

誰もが、新商品開発、品質改良、販路拡大、販売システムの構築等に躍起となっているが、何故もっと「宣伝方法」に心血を注がないのか?
TVの電源を入れると、深夜から早朝までショップ・チャンネルのような番組が流されています。 ブラウザを開くと、広告が矢継ぎ早に表示されてきます。 民法ラジオもそうです。 郵便もそう。 新聞もそう。 投函チラシもそう。 その中でアピールしていることは、ほぼ全てが、「商品」や「サービス」の宣伝です。 この世界的な不況の中、物やサービスを売り込むことは、本当に大変で、上記のように、起きて寝るまでの間に出会う情報に、かくも山のような商材宣伝が入ってきている状況は、十分に理解できます。