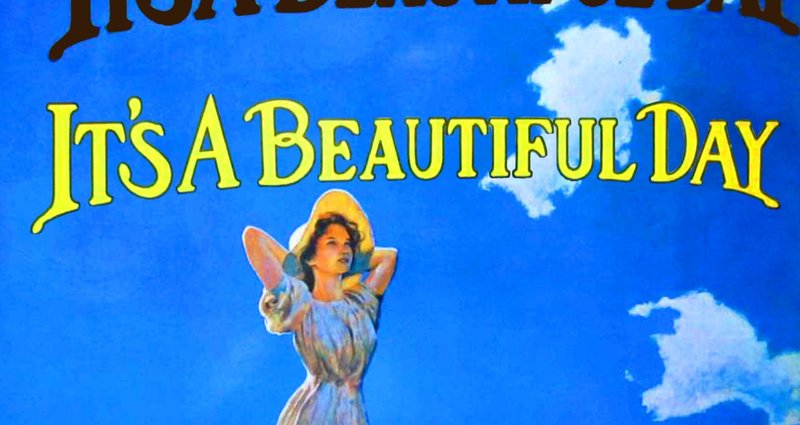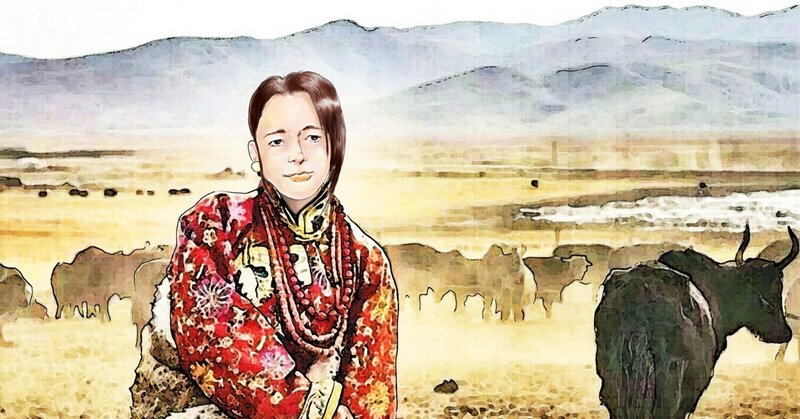#問題解決

「いじめ問題」は、「いじめをする方の問題」であり、「される方の問題」ではない。「不登校問題」は、「学校の問題」であり、「不登校をする生徒の問題」ではない
しかし、大抵の場合、問題を持っていない方の問題とされてしまうので、解決することは並大抵ではない。 解決するには、問題とされてしまう側の児童、生徒を「問題児(生徒)扱い」せず、一個の人格を持つ人間として接するだけでよい。 それなのに、多くの保護者や教師がそれを台無しにしてしまう。 つまり学校の教師は問題の当事者としての自覚が全くないので、解決の糸口を見つけられるはずがない。 保護者は、心配という「子ども扱い」により、知らない内に「いじめ」や「不登校」を悪化させる側に加担さ