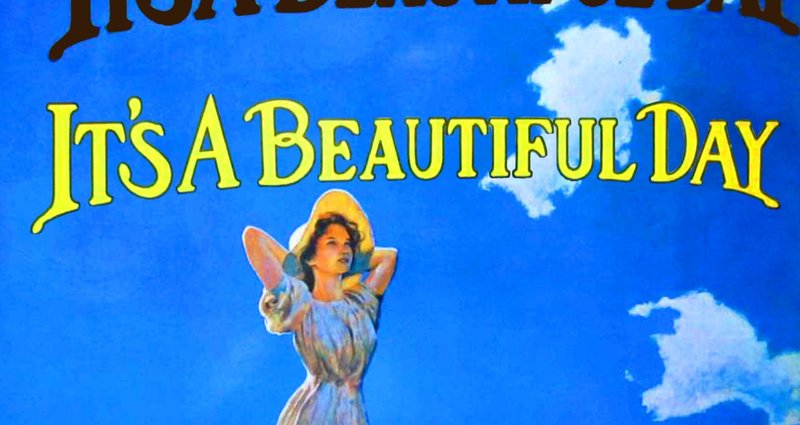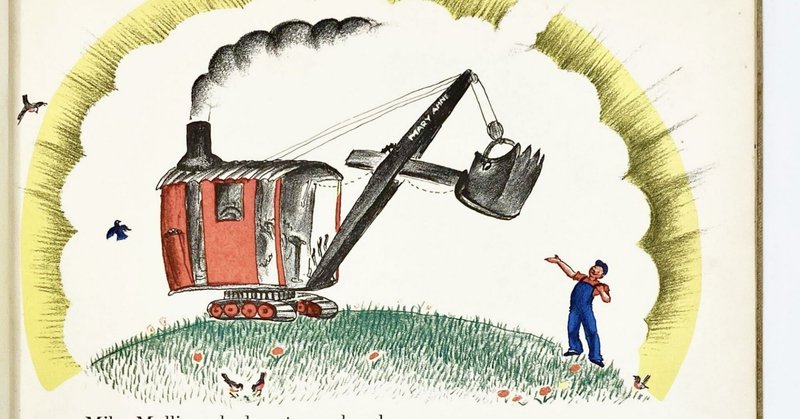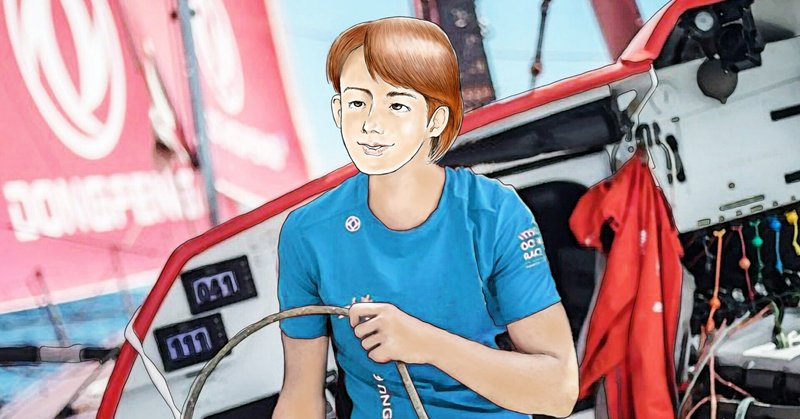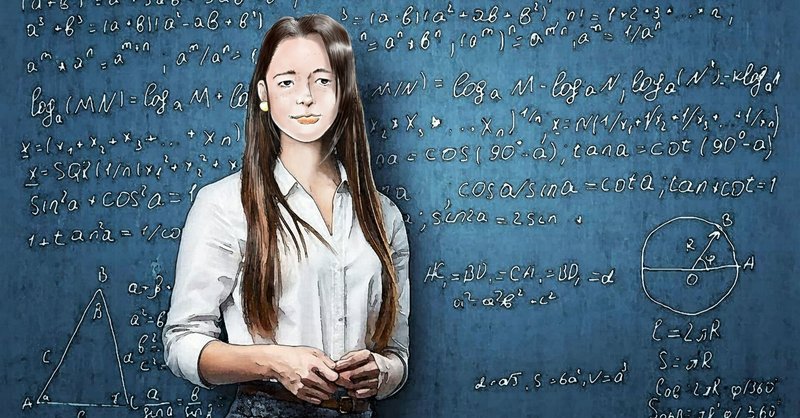#ソリューション

「働く」の原点は、「自分に向いている仕事(会社等)を探すこと」ではなく、「物事を解決に導くソリューション力を発揮すること」 ②いかにソリューション力を養成するか?
映画「カールじいさんの空飛ぶ家(原題:UP!)」をご存じだろうか? ディズニー・ピクサー社のアニメで、子どもに大変人気のある映画なのだが、その映画の最初の方に、このようなシーンがある。 妻に先立たれ、一人暮らしをするカールの家に、ボーイ・スカウトの少年ラッセルがやってきて、お決まりのセリフを述べる。 『 Can I cut your trees? ・・・・・ (お庭の木を切りましょうか?)』云々と。 自分が人の役に立てる(他人の問題をソリューションできる)ことがらを尋ねてい

「働く」の原点は、「自分に向いている仕事(会社等)を探すこと」ではなく、「物事を解決に導くソリューション力を発揮すること」 ①なぜソリューション力なのか?
もう少し言い換えると、「働く」の原点は、「自分に向いている仕事や職業を見つけること」ではなく、「社会に溢れている大小様々な問題などを解決に導くソリューション力を発揮すること」だが、残念ながら、こういった力は現在までの学校では、ほぼ養成されることは無い。 もっと端的に言うならば、子どもは物心ついて、数年のうちに、「なりたい職業」なんて、なれるわけがないし、そんなのがやっていける程あまくないということを悟ってしまうのだ。 保育園の年中さんで「花屋さんになりたい!」と言っていた