
『定年前と定年後の働き方』
はじめに
定年前と定年後の働き方は、個人の思考ひとつで大きく変わる。
幸福感と年齢の関係について「U型カーブ」や「エイジング•パラドックス」について、書かれています。
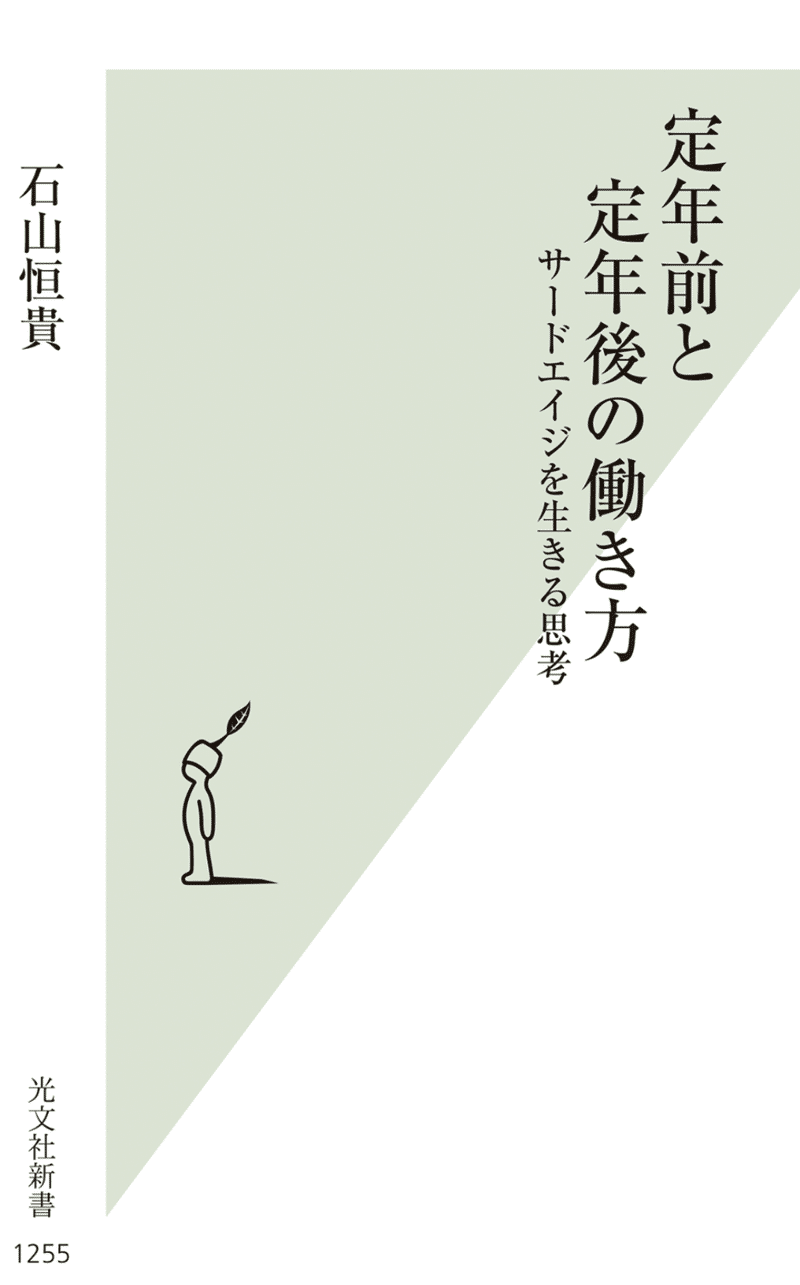
光文社新書 (2023.05.30.)
エイジズムとは何か
エイジズム:年齢に依る差別
若い時に、シニアに対する偏見を持つと、自身がシニアになった時に自身の内面にあるステレオタイプ(固定観念や思い込み)に影響を与えてしまう。
しかも、厄介なことに偏見は無意識に醸成され、本人は それが偏見と気づいていない。
無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)
世代論で捉える誤解
新人類 就職氷河期世代 ゆとり世代 ミレニアム世代 Z世代
団塊世代も同様に「イマドキの○○世代」として一括りにしてしまうと、誤解を生む危険性がある。
幸福感とは
ハピネス:happiness
サティスファクション:satisfaction
ウエルビーイング:well-being
エウダイモニア:eudaimonia
3つの要素
サティスファクション:日常生活への満足
ハピネス:喜びや楽しみなど快楽を示す心の状態
エウダイモニア:人生における意義や目的意識
エウダイモニアな生き方(実現)
シニアの働き方思考法
シニアになり加齢していくと、さまざまな喪失感や衰えがあるはずなのに、幸福感は高まっていくと云う矛盾(パラドックス)と受け取られる。p.50
働き方を考える
役職定年と定年再雇用
一般的にメディアは、役職定年や定年再雇用を切っ掛けにモチベーションが低下すると捉える。
しかし、関係の調査を見る限り48歳を底として、幸福感のU字型カーブを描く。
しかも、年代層を一律に捉えることは、好ましくない。
役職定年前の人達の3割強の人が「やる気の低下や喪失感」を感じ、他方3割の人達は「プラス思考」を回答し、受け取り方は、様々です。
pp.48〜51.
主体的な職務開発(設計)
タスク:具体的な業務
認知:仕事の意味づけ
関係:仕事で接する人々との関係性
pp.91〜93.
シニア労働者の働き方
命題:シニアは働くべきか? p.148
仕事 ボランティア 地域活動
雇用契約 業務委託契約 フリーランス
人生の4つのフレームワーク
就労 家庭 社会学習 地域(社会)活動
自走する力をつける
P:Proactiv まずやってみる
E:Explorer 仕事を意味づける
D:Diversity 年下とうまくやる
A:Associate 居場所をつくる
L:Learn 学び活かす
pp.192〜214.
おわりに
シニアの能力は、一方的には衰えない。
シニアの働き方と幸福感については、個人差がある。
第3のライフステージ「サードエイジ」と捉える。
多世代かつ多様な人々と対話し、年齢や、これまでの地位•役職の上下にこだわらないコミュニケーションの習得を心がける。
感謝の気持ちを表す
人間関係を育てる
親しい人を大切にする
自身の専門性とスキルを棚卸しする。
pp.218〜225.
【光文社/公式サイト】
【光文社/Note】①
【光文社/Note】②
【石山恒貴研究室】
【追記】
2023.05.22.
2023.05.26. 追記
