
【読書百遍】『知の編集術』
はじめに、この本が出版された2000年の日本を見てみる。
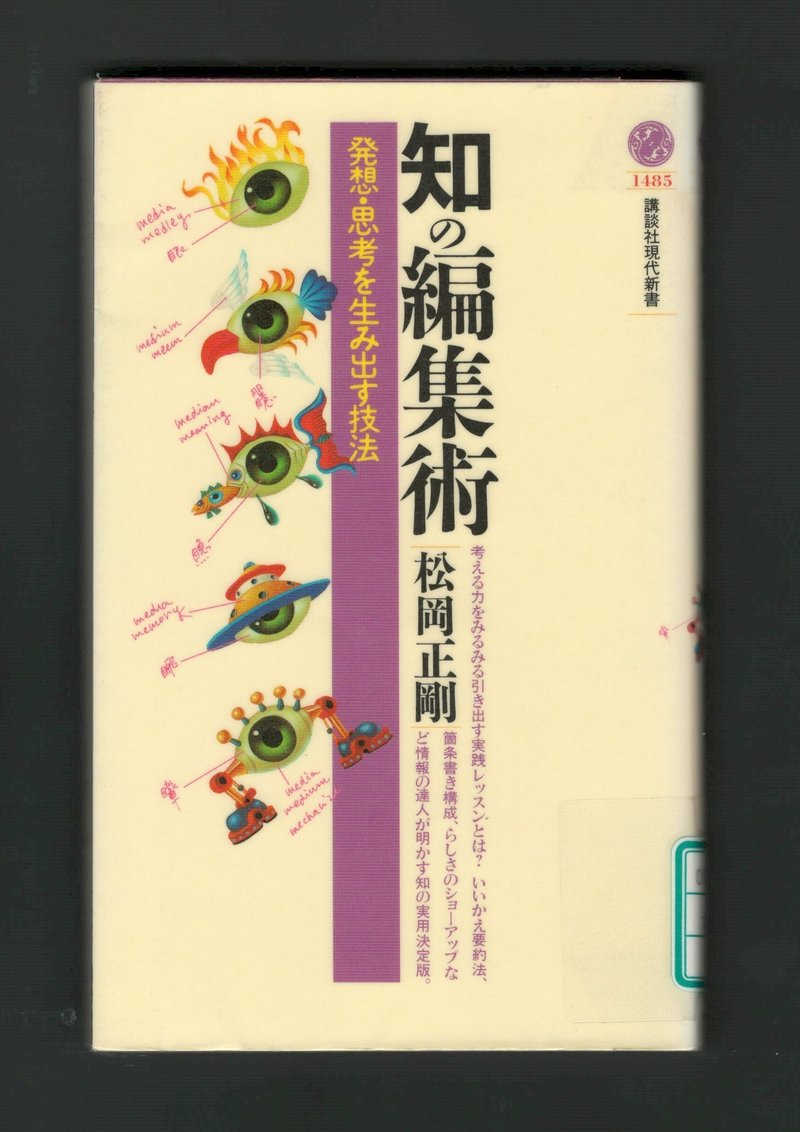
講談社現代新書 (2000.01.20.)
【編集とは】
この本で「編集」とは、新聞や雑誌・映像の編集より幅広い意味で使われています。
人々が言葉や動作を覚え、それらを使って意味を組み立て、人々とコミュニケーションすること。その全てを意味しています。p.4
【第1章】 編集は誰にでもできる
① 通訳名人と編集名人
② 文化と文脈を編集する
③ 句読点を動かしてみる
【編集稽古01】
どこかに、こんな文章が掲げられていたとする。これに句読点を打って、二つの意味をもつ文脈にしてほしい。
A ) ここではきものをぬいでください
「ここで、はきものを、ぬいでください。」
「ここでは、きものを、ぬいでください。」
B) いやよして
「いや、よして。」
「いやよ、して。」
④「情報の様子」に目をつける
【編集稽古02】
「すみません」の3つの意味
a) 失敗したりした時の謝罪
b) 相手が自分のために何かしてくれた時に感謝の気持ち
c) 迷惑をかけてしまうけれどもお願いをする時に依頼の意味
⑤ 会話の中にあらわれている編集術
おなかが空いたので、何か食べに行く内容。一方的に決める会話と、相互に話し合いながら決める会話。
「○○を食べに行く?」
「お昼、何が良い?」
⑥ 小説の中の会話
⑦ 乱世をどう編集していくか
⑧ 関係を発見するために迷惑をかけたり
【第1章の要約】
21世紀は方法の時代である。
主題の時代から方法の時代への転換が高らかに宣言される。
その「方法」とは「編集」「編集術」「編集工学」である。
まずは、文化や文脈のなかの情報の様子に、いかに注意深くなるかが、会話の事例を中心に開示されていく。
pp.13〜46.
【第2章】 編集は遊びから生まれる
① 子供の遊びにひそむ編集
② 子供の極意=「ごっこ」「しりとり」「宝さがし」
③ よく遊び・よく学び・よく編集せよ
④ カイヨワの「遊び」の四分類
⑤ スポーツ・ルールの編集術
【編集稽古03】
サッカーやラグビーにはオフサイドというルールがある。このルールはスポーツ史上きわめて画期的なルールで、ずる(安易な得点)ができないようになっている。また、それによって守備側の戦略もしだいに精巧になってきた。(オフサイド・トラップなど)
では、このようなオフサイドに似たルールは、スポーツ以外の社会や慣習のなかにもあるだろうか。考えてみてほしい。
⑥ 法という編集の世界
⑦ 堅い法律、柔らかい法律
⑧ コンパイルとエディットのちがい
⑨ 編集的連続性に注目する
【第2章の要約】
日本の子どもの遊びから、スポーツのルールまで。遊びとは編集そのものであって、編集のない遊びはなく遊びのない編集もない。
遊びのなかで動く「自己編集性」と「相互編集性」、日常の編集的連続性に着目して、「編集する自己」を浮かび上がらせるコツを示す。
pp.47〜84.
【第3章】 要約編集と連想編集
① 映画編集を体験する
② 要約と連想の魔法
③ キーノート・エディティング入門
④「箇条書き」という方法
⑤ 編集にもモードやファッションがある
⑥「らしさ」のショーアップ
⑦ 略図的原型をみつける
⑧ 情報の分母と分子
⑨ 要約編集のための多様な技法
【第3章の要約】
要約と連想の二つはいろいろなジャンルにつかわれる編集術の基本である。
文章や映像の編集だけではなく、会話にも読書にもアクションにも要約と連想は連動して駆動する。
その手法として要約ではキーノートなどの多彩なモード、連想では情報の分母と分子を動かすことに言及する。
pp.85〜126.
【第4章】 編集技法のパレード
① 剣道と「鳴らぬ先の鐘」
② 連想ゲームにひそむもの
③ 情報はひとりでいられない
④「いいかえ」が思想をかたどっていく
⑤ 十二の編集用法にとりくむ
A) 情報を収集して分類する
B) 情報を系統樹やネットワークにする
C) 情報郡をモデル化やシュミレーション化する
D) 情報の流れに入れ替えを起こす
E) 情報に多様性が生まれるようにする
F) 情報を年表や地図、図表にする
G) 情報郡に引用や注釈を加える
H) 演劇や音楽、舞踏、芸能などを加える
I ) デザインや装飾を施す
J) 異文化交流を可能にする
K) スポーツを加える
L) ゲームや遊びを編集に加える

編集術とは:気が付かなかった方法に気づく
pp.139〜155.
⑥ めくるめく六十四編集技法の世界
編集(compile)と編纂(edit)
データを扱う基本
pp.159〜163.
【第4章の要約】
情報はつねに乗りかえている。
情報はつねに着がえている。
情報はつねに持ちかえている。
メディア、モード、アナロジーが動きつづけていることをまとめていえば、「情報はひとりでいられない」ということだ。第四章ではイシス編集学校の編集稽古でも取り組む十二の編集用法、六十四の編集技法が紹介されている。
pp.127〜164.
【第5章】 編集を彩る人々
① 武満徹のエディターシップ
② 編集名人たちの職人芸
③ そこに「方法の魂」はあるか
④ 知のテイストと情報コンディション
⑤ 私の好きな読書法
⑥ 文字のクセが表現を変える
⑦ 注意のカーソルをハイパーリンクさせる
⑧ 情報のライフサイクル
⑨「編集八段錦」
a) 情報を区別する
b) 情報を相互に比較する
c) 情報を系列化する
d) 情報の解釈
f ) 情報のネットワーク化
g) 情報の相互の関係を見つける
h) ほぼ出来上がった情報に比喩性や連想を与え、新しい息吹きを与える
i ) 情報に物語性を
【特徴】
情報を集めて特色を発見する
もう一度 情報の背景を考える
そこに含まれる意味を考える
【第5章の要約】
作曲家の武満徹、デザイナーの田中一光、建築家の磯崎新。雑誌編集者、演劇演出家、落語家やお笑い芸人、実況中継のアナウンサー。
そこには編集名人たちの編集技法が光っている。彼らの方法を取り出しながら、松岡自身の読書法、編集手順としての十二段階の活用方法、編集の完成にいたるまでを分節化した八段錦を詳述する。
pp.165〜208.
【第6章】 編集指南・編集稽古
① 一日の出来事を書き出してみる
② コピーライターになってみる
③ ジョージ・ルーカスの定番プロット
④ 俳句マスキング・エクササイズ
⑤ 速読術に王道はあるか
⑥ 情報を推理してみる
⑦ 記号上手はノート上手
⑧ 手話にひそむ編集力
⑨ これからの編集文化
【第6章の要約】
編集力はどのようにして鍛錬、錬磨できるのか。
物語技法、俳句手法、ノーティングを検証し、松岡流編集エクササイズが連打されていく。
個別の実践、トレーニングが心許ない諸兄には、イシス編集学校のめっぽう面白い編集稽古で発想、思考を生み出す技法に磨きをかけてもらいたい。
pp.209〜253.
【読後感】

初めて『情報の歴史』見た時は、情報量とレイアウトに衝撃的でした。
今回「8章 情報の文明 1990〜2029」が追加されましたが、あらためて『知の編集術』を読み返し、年表の完成に至るまでの【十二の編集用法】と【編集八段錦】の意味(過程)が、おぼろげながら理解出来た。
2023.03.24.
