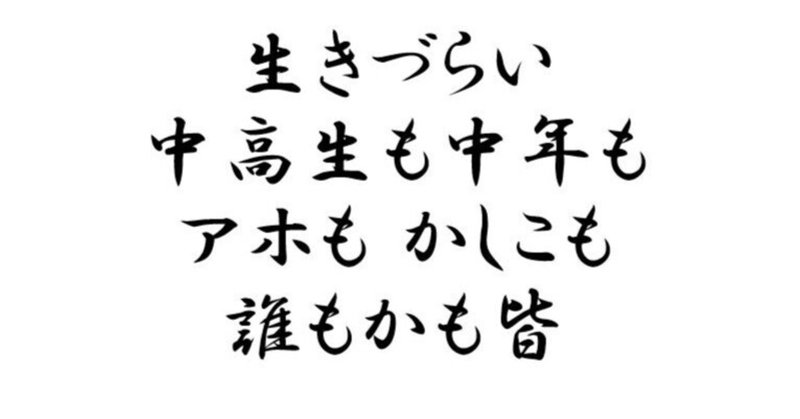
【入学式】大学に 夢と希望を 持つ君へ(その1)
「『石の上にも三年』って言うけど、同じ肩書で無事4年目を迎えることが出来た春なんて、結局小学生のときと大学生のときだけよ。」・・・春代は春がキライだ。私は春代も春も好きだったのだけど。
4月からの京都転勤が決まって、3月下旬の土日に引っ越し先の独身寮で荷解きをしていると、小鳥の囀りにカラスの声が入り混じる。意外にもカラスを邪魔に感じないどころか、小鳥のソプラノにカラスのアルトが加わった混声合唱に思わず耳を澄ましてしまう。それを遮ったのは、隣の部屋の目覚まし時計であった。私と同じタイミングで本社異動となった先輩の四畳半で電子的な囀りが鳴り止まない。「あー、かなわんなー、こんなんやったら電池抜いときゃよかったわー。どの段ボールに仕舞ったか分っからへん。引越って疲れるなあ。もうええやろ。なあ、昼飯でも食いに行こうや。」先輩に誘われるまま、少し自転車を走らせると、秀吉の時代に築かれたという水路に出るのだが、その土手を埋め尽くす鮮やかな菜の花色と、七分咲きの淡い桜色が、晴朗な青空の下でキラキラしている。何もかもが初々しく映って、新入社員に戻ったかのような心緒に身を包み込まれていたけれど、すでに入社4年目を終えようとしている春だった。洛中からはやや離れていたが、遠方の視界にハッキリと存在感を出している京都タワーの方角から市街地の喧騒がささやかに伝わってくる。微かな地鳴りのような都会音が、この場所の静けさを却って際立たせる。先輩の目覚まし時計は結局電池が切れるまで鳴り続けていた。・・・この幸せな春を迎える4年前まで、私はそれなりに悩める大学生であったのだ。
「私って、勉強したくて大学に来た珍しい人なの。だって、そうじゃない。殆どの人にとって、大学って、学問しに来る所じゃなくて、卒業証書を貰いに来る所でしょ。しかもね、哲学をしたかったのに、親に命じられるまま法学部に入ったでしょ。う~ん、もともと根っからの勉強好きだから、どんな科目でも楽しいんだけどね。でも、春が来ても心からはワクワクしない。」春代ですらこんな哀憐を胸に秘めて学生生活を送っているのだ。いわんや無能な私をや、である。
私が大学を卒業するまで学費を援助してくれた血縁は、私が弁護士にでもなるものと信じていた。今にして思うと、私が合格した時の喜び方も、いつも太々しい血縁の態度からは想像もつかないものだった。ところが、フタを開けてみると、私という若者はどうしても法律それ自体をがむしゃらに学ぶ事が性に合っていなかった。基礎法学や憲法、せいぜい刑法までは面白がって講義に臨んだが、民法や商法、訴訟法といった実用法学に興味が持てなかったのである。社会に出てから役立つのはこちらのほうだと脳では十分に理解しているのに、関心が脳に付いていかない。入学してからたったの数ヶ月で、私は法律を学ぶために法学部を選んだにもかかわらず、法律がさほど好きなわけではない事に気付いた、否、早めに気付くことが出来たのである。さすがに人間、人並み以上に好きな物事でなければ、なかなか忍耐を伴う努力というものが継続できないことは心得ていた。もちろん講義やレポートや単位取得だけが大学生活の全てではないのだから、法学部の勉強がそれほど好きではないという自覚が、私の大学生活に致命的な傷を与えるわけでは無いと判っていた。判っては居たけれど、卒業までの多くの時間を興味関心の対象外となるものに消耗せねばならない事実を1年生の数ヶ月で悟ってしまったあのショックは想定外に大きく、まずその鬱屈から立ち直るのに時間を費やしてしまった。しかし、あの悩みにじっくりと時間をかけて、しっかりと向き合ったおかげで、その後の人生に悔いを残さない心理状況で、そして――ここが肝心だが――傷を最小限に止める形で社会に飛び立つことが出来たのだった。
私は酒の力を借りて懊悩を紛らわしながら、少しずつでも気持ちを切り替えていった。昔から酒ばっかり飲んでいる。あの偉大なる父の英才教育が奏功したのか、飲酒の頻度だけは特待生だった。周囲の友人にも私と同じような“不本意法学部生”が居て、彼らの存在にも救われた。大人になった今では口にする気にもなれない合成清酒の熱燗を徳利ごと一気に呑み干し、半ば気を失って激安の縄暖簾を出るや否や、駅前の違法駐輪の群れに近づき、自転車と共に倒れ込んだと思ったら、好きな子の縦笛でも舐めているつもりなのか、いきなり誰が座っていたのかも分からないサドルに舌を這わせている。私の親友はそんな酔っ払いばかりだった。
留学生とも仲良くなれた。小中高を通じて叩き込まれたという流暢な日本語には、ただただ嘆賞するばかりだった。「酒の肴になるような話は1つも御座らん」と、誰に習ったのか「御座らん」という言葉の響きが気に入っているようで、彼のあだ名は「ゴザラン」に決定した。「世界共通の法則として、女の会話には一貫性がゴザラン」「青春とは昔を懐かしんで『あの頃は良かった』と振り返られるほど甘いものではゴザラン」「目に見えるモノしか信用しない人には、酒という微生物の神秘の賜物を楽しむ資格はゴザラン」・・・彼の名言の数々が私の乾いた大学1年目に潤いをもたらしたことは言うまでもない。そんなゴザランが展開した最も衝撃的な持論が何と「環境問題」だった。
「世界中の人が二酸化炭素を減らそうと心底本気で考えているっていうのはウソだよ。そんな偽善者はオレの国では天然記念物だヨ。ゴミの分別とかペットボトルや紙のリサイクルが削減に効果的だってことも、実は誰もが納得するような証明って今の科学の力じゃ無理らしいじゃん。オレ達、騙されて面倒なことに付き合わされているだけかもしれネーゼ。人間なんて生きているだけで二酸化炭素を増やしちゃう病気なんだからサア、減らしながら生きるなんて究極的には超越できない矛盾なんだってば。
だいたい温暖化ってダメなのかな?寒い北国では不可能だった葡萄栽培が盛んになって、新しい品種で美味しいワインが出来たり、今まで縁の無かった南の海の魚を新鮮なまま味わえたり、メリットもあるんだぜ。別に灼熱地獄でカラダが溶けちゃうわけじゃないんだし、それくらい地球が熱くなる頃になれば、きっとオレ達の子孫もその熱さに耐えられる機能が進化していると思うよ。
温暖化で海面上昇が進んだらサア、陸地の減少に比例して地球の総人口も減少するからサア、いつかは二酸化炭素の排出量にも歯止めが掛かるんじゃネーノ?オレのおばあちゃん、もうすぐ水没して人が住めなくなるって言われている島の出身なんだけど、何も気にしてネーヨ。『ニホン人なんて会社からしょっちゅう転勤を命じられるんだろ?ワタシだって、この島がダメなら、あの島へ引っ越すだけのことヨ』って嗤ってたぜ。それどころか、色んな先進国の環境活動家らしき不審者が次々と土足で上がり込んできて、急に地元の政治家が金持ちになったり、街に騒々しいモノが溢れたり、とにかく怪しいことだらけで、昔の暮らしのほうが良かったってハッキリ言ってるわ。却って海洋ゴミも増えちゃったらしいゼ。そりゃ、海洋ゴミはダメだよ。でも、アレはゴミを海じゃなくてゴミ箱に捨てればイイって話で、温暖化とは全く関係がゴザラン。
清く正しく美しそうに見える理屈ほど、疑ってかかったほうがイイヨ。海に沈む自分を救済してくれそうに思える理屈ほど、疑ってかかったほうがイイヨ。人間って追い込まれると耳障りの良い巷説を信じやすくなっちゃうから。藁にも縋る思いで、掴んでみたらホントに藁だったとき、溺れてしまっても後の祭り。誰にも文句は言えネーゼ。大学って、そういう精神を体得するってか、常識を多面的に判断する力量を養う場所なんじゃネーノ?効き目のある薬かどうかって、飲んでみないと分からないんだから、とりあえず『みんながイイって評価している薬』じゃなくて『自分の体に合いそうな薬』を試してみたら?」
私は留学生に背中を押される形で、「みんながイイって評価している薬」が自分の体には合いそうにないことを直ぐさま確認した。先ず、司法試験や公務員試験を目指すような人生は似合わないし、さっさと選択肢から捨てることに自信を持った。法曹界で生きるということは、司法試験を突破するための猛勉強が不可欠なのは勿論のこと、やはり「世の中の正義を実現したい」とか「社会において法の下の平等を守りたい」とか、そういう“信念”を備えてこそ、法を司る事を生業とする人生に納得するということである。また、“先生”と呼ばれるステイタスの割には裕福な生活をしていける保障が何処にも無いのだから、中途半端な動機付けでは、挫折するために机に向かうようなものである。公務員も同様だ。必要なのは公務員試験を突破するための猛勉強のみならず、それなりに「霞が関から国家を支えたい」といった“信念”を持ち合わせていないと、“ただ役所で働きたかっただけの人”として「これで良かったのだろうか」という疑念に一生向き合うこととなる。それに、私が大学生の頃には、すでに公務員に対する風当たりは強く、平和を維持し、国民の健康で文化的な生活を守るために流す汗の割には、長時間労働で、私自身が幸福な生活をしていける保障は何処にも無いといった想像が容易だった。
次に、私は「自分の体に合いそうな薬」を直ぐさま試してみることとした。法学部のカリキュラムの中でも、興味を持った科目だけでいいから、講義をサボらず、ノートをきちんと取り、そこで得た「知識」を自分の人生に役立つ「知恵」に繋げていこうという試みだった。大学というのは、必須科目が決められているものの、それ以外の範囲では自由に受講科目を選べる仕組みになっている。御飯と味噌汁と漬物は皆同じでも、例えばおかずを魚にするか肉にするか、魚だとしたら焼くか煮るか、小鉢は何にするか、といった程度のメニューは選べる定食なのだ。そして合計の摂取カロリーすなわち取得単位が要件を満たせば、卒業証書が授与されるというわけだ。入学して早々にあまり予備知識もないまま選んだとはいえ、本当に苦手な食べ物は極力外しているはずである。科目を限定すれば、集中して講義を聴くことくらいは無理なく続けられたし、続けていくに連れて、自ずと好きな科目が分かってきて、前向きになれた。殊更、1年生の時期は一般教養科目が私の狭い視野をこじ開けてくれたことに嬉々とする場面も少なくなかった。
まあ、そもそも自分で選んだ科目なのに、講義がつまらないからといって教室を抜け出してしまう行為そのものが、自分で選んでもいない授業をマジメに受けていた高校までの生活を踏まえると、とんでもない怠惰なのだが、大学生というのはそれが出来てしまう環境にあった。毎日がまるで自由の恐ろしさを試されているかのような自由に溢れている。そして、教授には大変失礼ながら、愕然とする程つまらなく無意味にすら思えてしまう講義があったのも事実であった。それはもう高校までとは比べ物にならない次元のつまらなさである。辛抱できない程つまらないと、居眠りが抑えられなくなってくる。しかし、居眠りは私のポリシーが拒否した。たとえ内容がつまらなくても、私に何かを伝えようとしている相手に対して失礼だし、私が勝手につまらないと感じているこの講義を面白いと思って真剣に聴いている学生が居るとしたら、その仲間に対しても失礼で迷惑を掛けていることになる。居眠りをするくらいなら、教室を出るのが通すべき筋だ。このポリシーは大学の数年間こそサボる言い訳と化してしまったが、私には昔からこのような弁えがあって、授業中や会議中は絶対に寝ないという誓い事だけは、誰に教え込まれたわけでもなく、頑なに守り通している。
・・・ここまでが大学1年生という「有用な無駄」の中で私の得たものだ。ゴザランみたいな奴に出会えただけでも学生時代の収穫だった。「このご時世、地球環境を守ろうっていう掛け声に真っ向から反論をぶつけると、それこそ生ゴミを見るような眼つきで罵声を浴びちゃうけどサア、オレは反論すら許さないってタイプの暴力がキライでね、それで暴力以外の課題解決方法を深掘りしたくなって、法学部に入ったんだ。」・・・そんなゴザランは1年だけでアメリカへと更に旅立っていった。
この男、酔うと、かなり適当にイタリアっぽい歌詞を即興で作って、気持ちよくテノールを披露する。出鱈目もここまで達すると感心して聴き惚れてしまう。「昔からいい加減なガキだったのかもナア。先生や親に怒られるのを恐れずに、その場では何とか調子良く乗り切っちゃう。ああ、何でイタリアかって?そりゃ、日本に来たときに初めて食べたパスタやピザが旨かったからナ。でも、本場のほうが絶対に旨いなんて疑わしいからサア、とりあえず今は日本で食べながらイタリアっぽい気分を演出するのが一番手っ取り早いなって思っただけ。」ゴザランの思考回路には日本人の風呂敷では収まりきれないものがあった。外国人だから当然なのだけど・・・つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
