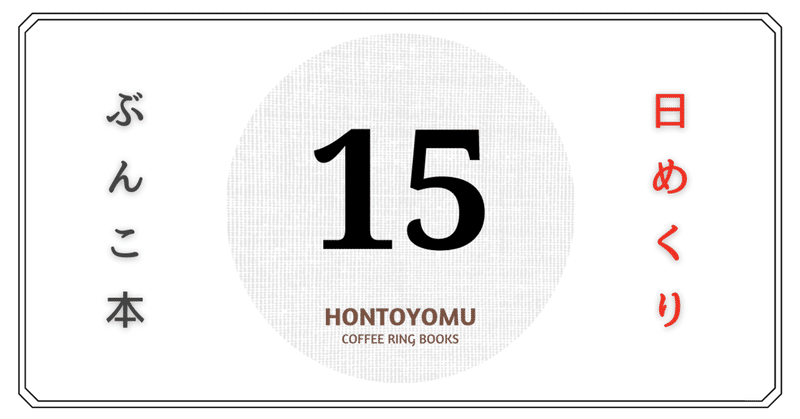
『小説論 読まれなくなった小説のために』 – 日めくり文庫本【4月】
【4月15日】
「音」については、ナボコフが『ボヴァリー夫人』について〝音と声のシンフォニー〟という言い方をしますが、音と声のシンフォニーのような、そういうさまざまな楽器が混じり合った音をオーケストラが立てるといった大きな音とはちがって、日本の小説はオーケストラの奏でる音ではなく、独奏とか合奏に近い音なのかもしれないというちがいがあります。
私は開高健の小説は、とりあえず、オーケストレーションされた私小説とでも言っておきましょうか。そこでなにも音とか耳とかいうことを、事新しく言い立てる必要なまったくないと思います。
それこそフローベールの小説に出てくる音は実に様々です。自然のなかに含まれている音が象徴的に使われる場合もあれば、現実の田舎道を走る馬車の音とか、田舎の町の教会の鐘の音、あるいは町をフラフラしている乞食のの歌う歌、エンマのピアノ、ダンス・パーティーの音楽、オペラのアリア、おしゃべりの声、花火の音、小さな叫び声、風の音、心臓の音、血液の流れる音、など実に多様で豊かなものです。エンマがロドルフに会う田舎の共進会のシーンがあります。それは農業共進会で町長や町のお偉方が農民のつくった農作物などを町の広場で表彰するのですが、集った人々のざわめき、音楽、鐘の音、町長の演説をバックに、ロドルフとエンマが町の広場を見下ろす建物のなかからそれを見ながら、エンマを口説く有名なシーンがあります。
そこでロドルフとエンマが二階から見ている町の広場の様子は、まるでカメラが移動して広場の情景を映していくという感じで広場の色彩、音、動いている人間を一望のもとに見渡して、それと同時にそこで語られている会話、共進会に出ている動物の鳴き声や何やかと、ロドルフがエンマを口説く、陳腐ではありますが、甘い恋の瞬きに、エンマが溜息をつきながら答える言葉が重なりあうのです。ここを読むたびに、映画はフローベールが発明したのではないかと思ってしまいます。
「物語と大衆」より
——金井美恵子『小説論 読まれなくなった小説のために』(朝日文庫,2008年)126 – 128ページ

出典:Édition des manuscrits de Madame Bovary de Flaubert > Plans et scénarios - folio 26v より
1857年4月15日にようやく出版された『ボヴァリー夫人』の自筆原稿は公開されており、有名な農業共進会の場面は「下書き」に先立つ「シリナリオ」段階からその「交響曲の効果」が練られていることがわかります。大きなバツ印に格闘の後が見てとれますね。
/三郎左
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
