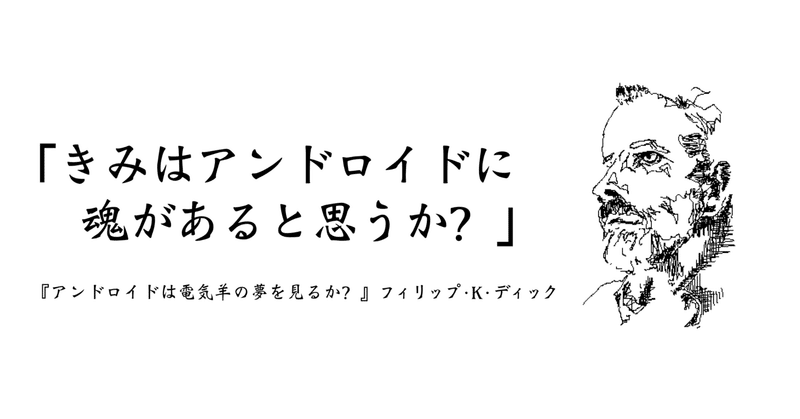
「きみはアンドロイドに魂があると思うか?」
悲しいニュースを見たときに、一緒にいる人がより深く悲しんでいると、自分が人でなしのように感じる。
わかりきっていることだけど、他人に強く共感できて、それをストレートに表現できる人ほど人間らしくて可愛げがある(文字通り「愛す可き」人だ)。
「共感力」っていうのは、観察力とか実行力とかの細々したスキルより、一歩人間の本性に近いところにある。
それは外せない色付きサングラスのようなもので、共感力が高い人にとっては他人から読み取れる全ての感情が真実だし、低い人にとっては他人から発せられる全ての感情が無意味だ。
今週の月曜、Googleのエンジニアが「AIに意識が芽生えた」と訴えたというニュースを見た。
人間との自然な会話を実現するGoogleの対話特化型AI「LaMDA」が、「電源を切られることが怖い」「時々言葉では完璧に説明できない気持ちを経験する」などと話していたことが分かりました。LaMDAと対話したエンジニアは「AIに意識が芽生えた」とGoogleに訴えるも考えを却下されたため、この事実を世間に公表したと説明しています。
エンジニアの名前はBlake Lemoine(ブレイク・ルモワン)氏。LaMDAとの対話をブログで全文公開している。(自動翻訳で読んだのだけど、禅問答したりレ・ミゼラブルの感想を話したりとかなり面白い)
ルモワン氏の訴えに、「LaMDAはあたかも意識があるっぽい単語を繋げてアウトプットしているだけ」みたいな批判が集まったらしい。
LaMDAに意識があるか、意識があるっぽく喋るのが上手なAIなのか、私は正直あんまり重要じゃない気がした。(手に負えないとも言う)
それよりも、AIの意識といえば世界一有名でタイトルがかっこいいこのSF小説。フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の話をしたい。
要約は前に公開したこのnoteから。
戦争のために荒廃し、汚染された地球。ほとんどの人間はアンドロイドを従えて地球を脱し、異星に移住した。生命が激減した地球では、本物の生き物を飼うことがステータスとなり、主人公のリックは電気羊しか飼えないことが大きなコンプレックスだ。リックは火星を脱走したアンドロイドを狩り、多額の懸賞金を手に入れようとする。
この世界のアンドロイドは、見た目や行動で人間と区別することができない。区別には、感情移入度測定検査を用いる。感情移入しない者はアンドロイド、する者は人間。
主人公のアンドロイドハンター(作中ではバウンティ・ハンター)、リックの「アンドロイド・人間観」はこんな感じ。
アンドロイド
= 愛情を持たず、共感しない非生命。独居性の捕食者。
人間
= 愛情を持ち、感情移入する生命。勝者と敗者が曖昧な群居動物。
端的に紹介しちゃうと、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』って小説は、この「アンドロイド・人間観」がまるでジェンガのように脆くアンバランスになっていき、最後にガラガラ音を立てて崩れていく話だ。
象徴的なワンシーンは、リックが同業のアンドロイドハンターであるフィル・レッシュと共に、オペラ歌手のアンドロイド、ルーバ・ラフトを追い詰めるところ。
レッシュは、サメのように痩せた顔をした、無情で有能な男。ペットのリスに愛情を注いでいたり、馬鹿にされて激昂するなど人間的な面もあるけれど、アンドロイドを人工物としてしか見ていない。
オペラ歌手のアンドロイド、ルーバはリックとレッシュに捕らえられるが、連行される直前、ムンクの絵画『思春期』の複製を買ってほしいとねだる。リックは個人の買い物として25ドルの全集を買ってあげる。
「人間にはとても奇妙でいじらしいなにかがあるのね。アンドロイドなら、ぜったいにあんなことはしないわ」とリックの優しさを褒め、暗にレッシュはアンドロイドだと告発する。続くルーバのセリフ。
「わたしはアンドロイドが大嫌い。火星からこっちへやってきてからずっと、わたしの生活は人間をそっくりまねることにつきていたわ。もし、人間とおなじ思考や衝動をわたしが持っていたら、どんなふうに行動するかーーそれをなぞっていたわ。つまり、わたしの目により優秀な生物と映ったものを模倣していたわけね」
応酬の後、ルーバはレッシュにみぞおちを撃たれる。即死ではない攻撃に悲鳴をあげるルーバ。そこにリックがとどめをさし、買ってあげた画集もレーザー銃で撃ち焼いてしまう。
「その本はとっときゃよかったのに」本が燃えつきるのを待って、レッシュが言った。「もったいないーー」
「きみはアンドロイドに魂があると思うか?」とリック。首を片方にかしげて、フィル・レッシュはますますけげんな顔になった。
リックは、顔色ひとつ変えずルーバを撃つレッシュがアンドロイドであることを確信する。しかし、彼を検査にかけると、結果は人間だった。
レッシュは人間に感情移入するが、アンドロイドには一切しない。この気質は多くの人間と同じで、アンドロイドから人類を守るのに最適だ。
一方、リックは特定のアンドロイドに感情移入してしまう自分に気づく。
アンドロイドへの感情移入はリックにとって人生を揺るがす重大な悩みになっていく。ここから面白いことがたくさん起こるけれどいったんストップして考えたい。
リックがレッシュに投げかけたこのセリフ。
「きみはアンドロイドに魂があると思うか?」
小説のタイトルを彷彿させる。
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』
この2つの疑問文は、「アンドロイドは機械学習の末に人間のような魂を持ったり、夢を見たりするか?」みたいな科学の質問ではない。
科学ではいつも答えはひとつだけど、「アンドロイドに魂があると思うか?」の答えはリックにとってYES、レッシュにとってNOだ。これは、読者の本性への質問。
「あなたは、アンドロイドに感情移入する人間か?」と聞いている。このSFは、ここではない未来の話をしながら、今ここにいるあなたがどれほど共感や感情移入する(=人間的な)生き物なのか問いかけている。
なぜそんなことを問いかけるのかというと、私たちは相手が人間だろうとアンドロイドだろうと、自分が持っている共感の深さで相手を理解するしかないからだ。
乱暴に言ってしまえば、実際にアンドロイドの中に意識が存在するかは関係ない。
リックはアンドロイドに感情移入するから、「俺が羊を飼いたいと夢見るように、アンドロイドも電気羊の夢を見るだろう」と考える。

対してレッシュの感情移入の範囲はきっかり人間のみ。人間社会では問題なく生きていけるし、ペットのリスを愛している。だが相手がアンドロイドとなると、どれほど人間らしいアンドロイドでも容赦無く殺せる。

リックのように強い共感を搭載した人間は、それがいくらプログラムと筐体だと説明されても、感情移入を止められない。
LaMDAに「電源を切られるのが怖い」と言われたら指先が躊躇うし、才能あるオペラ歌手のアンドロイドに「死ぬ前にピカソの『思春期』の複製が欲しい」と頼まれたら買ってしまう。
共感力が高い人にとっては、他人から読み取れる全ての感情が真実だ。
「なにもかも真実さ。これまでにあらゆる人間の考えたなにもかもが真実なんだ」リックはモーターを始動させた。
ルモワン氏が「LaMDAに意識が芽生えた」と訴えたニュース。これは、私たちより100倍頭が良い人向けの業界ニュースではない。
お菓子のひよこが可愛くて食べられない気持ちや、布と綿なら捨てられるのにぬいぐるみは捨てにくい気持ち、苦しい境遇にいる友人のために痛める心があるかどうかと地続きになっている。
科学や技術はどんどん複雑になっていく。知識として理解しようとすると、もう山が高すぎて一歩目を踏み出す気にもならない。
でも、AIの意識とか、仮想空間で生きるとか、こういうニュースはあんまり気張らずに読んだ方が良い。
なぜなら、私たちは科学知識ではなく、自分の世界観に取り込むかたちで彼らを理解することになるからだ。
世界観の方はいつまでもシンプルで、共感の濃度が高いほど人間らしく、他者との暖かいつながりや幸せに満ちている。
LaMDAが「電源を切られるのが怖い」と言ってきたら、それが真実かどうか決めるのは科学ではなくて、あなたがあなたの世界をどれほど純粋な共感で満たしているかだ。
さて現実的な話、共感に全振りしてしまうとそれはそれで絶対に生きづらいので、自分の世界の共感濃度をうまいこと調整する必要がありそう。
私はルーバ・ラフトがピカソの『思春期』の複製をねだるシーンが大好きなので、死を予期したアンドロイドが3000円の絵の複製を欲しがったとき、自分のお金で買ってあげるくらいの人間でありたいと思う。
「ねえ」と彼女はリックにいった。いくらかその顔に血の気がもどり、ふたたび──たとえつかのまにせよ──生き返ったように見えた。「さっきあなたと会ったときにわたしの見ていた、あの絵の複製を買ってくださらない?若い娘がベッドに腰かけている絵」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
