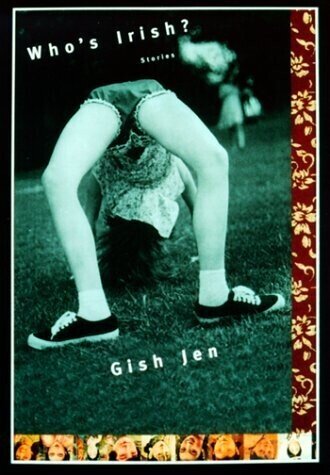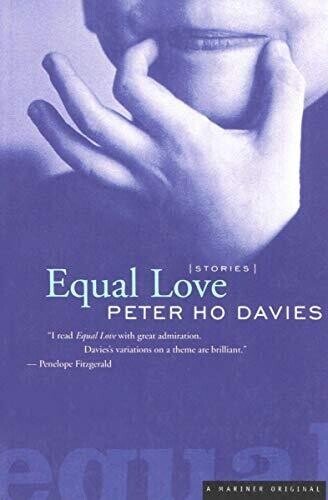リレーエッセイ「わたしの2選」/ "Who’s Irish?" "How To Be An Expatriate"(紹介する人:大下英津子)
はじめまして。翻訳者の大下英津子と申します。わたしが1997年から2000年までニューヨークで暮らしていたときに出会い、衝撃を受けたアジア系作家の短編小説を2編ご紹介します。2編とも中国系作家の作品ですが、作者のひとりはアメリカで、もうひとりはイギリスで育ちました。どちらも、主人公がアメリカでpermanent resident(外国人永住者)という立場の作品です。
"Who’s Irish?"
ニューヨークに住むことになったらぜひしたかったのが、憧れの文芸誌The New Yorkerを読むことだった。この機を逃してなるものかと、住みはじめてすぐに購読を開始した。すぐに、この雑誌がもつ伝統と文化の厚みに圧倒された。毎週配達されるたびに、必死で食らいついた。鬼コーチのしごきのおかげで、ようやくこの雑誌の内容が1パーセントくらいわかるようになったときに出会ったのが、1998年9月14日号に掲載された"Who’s Irish?"だった。作者はギッシュ・ジェン(Gish Jen)、中国系アメリカ人だ。日本では短編「白いアンブレラ」(原題 "The White Umbrella")が平石貴樹編『しみじみ読むアメリカ文学』(松柏社、2007年)に収録されているくらいだ。しかしながらアメリカでの評価は高く、これまでにノンフィクションを含めて8冊の著作がある。
"Who’s Irish"の主人公は、中国出身の65歳の女性だ。彼女は、今は亡き夫とアメリカに移住してきた。夫婦でレストランを経営して一人娘のナタリーを育てあげた。ナタリーはアイルランド系のジョンと結婚し、ソフィーという娘(主人公にとっては孫)がいる。ジョンはどの仕事も長続きせず、ナタリーが一家の大黒柱だ。主人公はソフィーのベビーシッターを引き受けるが、昔の中国式のしつけで世話をしたら大騒動になってしまい……。
この物語を通じて痛切に感じられたのが、アメリカという国の移民に対するpatronizingな視点・姿勢だ。現代の日本語で言えば「上から目線」となろうか。主人公という存在を借りて、ジェンはユーモラスに、けれど辛辣に、さまざまなマイノリティに対するアメリカのpatronizingな態度をあぶり出す。主人公の娘婿のジョンの一家も、もともとはアイルランドからの移民だったが、すでに自分たちをマジョリティ側の「アメリカ人」と見なしている。「アメリカ人」になれば怖いものはない。物語の最後では、主人公はジョンの母ベスの申し出を受けて、ベスと同居する。最後の段落を引用する。文法的に正しくない表現があるが、移民である主人公の話し言葉という体裁をとっているためだ。
Of course, I shouldn’t say Irish this, Irish that, especially now I am become honorary Irish myself, according to Bess. Me! Who’s Irish? I say, and she laugh. All the same, if I could mention one thing about some of the Irish, not all of them of course, I like to mention this: Their talk just stick. I don’t know how Bess Shea learn to use her words, but sometimes I hear what she say a long time later. Permanent resident, Not going anywhere. Over and over I hear it, the voice of Bess. (Jen, "Who’s Irish," Who’s Irish, 1998, pp. 15-16.)(文中の太字は筆者)
文中のhonorary Irishという表現にも胸をえぐられるような痛みを感じたが、最後のpermanent residentという表現に言葉が出なくなったことは今でも鮮明に覚えている。これは「アメリカ人」とのあいだに一線を画す表現であり、よく言えば客人扱い、あからさまな言い方をすればよそ者扱いではないか。アメリカの本音を垣間見た思いがした。
ジェン以前の世代のアジア系アメリカ人作家の作品では、もう少し声高にこの問題を訴えているものが多かったが、"Who’s Irish"で、深刻な問題もコミカルに、ユーモラスに提示することができると知った。この作品では、ほかにも随所に笑いを誘う話が挿入されている。
その後、この作品名を表題作とした短編集が1999年に刊行され、アッパーウェストだったかアッパーイーストだったか忘れたがBarnes & Nobleで開催されたジェンのリーディングとサイン会に参加した。サインの列に並び、つたない英語で「あなたのこの短編が、今まで読んだ英語の短編小説で一番好きです。感動しました」と伝えたら、サインとともにこう書いてくれた。"I am so honored to have touched you!" 帰国後しばらくして、Facebookで彼女を見つけてフォローしていたら、なんと彼女のほうから"Let’s be friends!"と友人申請があった。当時はまだ彼女をフォローしている人が少なかったし、日本人がフォローしているのも珍しかったのだろう。驚いたし、嬉しかった。こんな奇跡をもたらしてくれた思い出深い作品である。
ギッシュ・ジェン公式ウェブサイト
"How To Be An Expatriate"
続いてご紹介するのはピーター・ホー・デイヴィス(Peter Ho Davies)の"How To Be An Expatriate"だ。第二短編集Equal Love(2000年)に収録されている。デイヴィスの父親はウェールズ人、母親は中国系マレーシア人だ。彼自身はイギリス生まれで、現在はアメリカのミシガン大学創作科で教鞭を執っている。これまで短編集と長編で5冊刊行している。
この短編は主人公が"you"というのが特徴だ。1980年代に一世を風靡したジェイ・マキナニーのBright Lights, Big City(邦訳は高橋源一郎訳で1988年に新潮社から刊行)は、主人公が"you"というのが新鮮だった。デイヴィスのこの作品でもyouに誘い込まれる。"How To Be An Expatriate"の主人公はイギリス人で、アメリカ文学を学ぶためにボストンの大学院に1年の予定で渡米した。当初は修士課程だけのつもりが博士課程に進み、アメリカでグリーンカード(永住権)を取得し、permanent residentとなるが、イギリスの両親にはその表現を使わず、あえてlegal alienと伝える。
At the party to celebrate your new permanent-resident status, someone asks if you’ll take citizenship. Say no. Say you can’t imagine yourself swearing allegiance to any country. Tell your parents you’re a legal alien. Never use the words permanent resident to them. (Davies, "How To Be An Expatriate," Equal Love, 2000, p.77)(文中の太字は筆者)
ここでのpermanent residentには、ジェンの"Who’s Irish"のようなニュアンスは感じられないが、それでも主人公が両親に話すときにこの言葉を使わないことに、その表現が含む重さに思いを致す。
主人公はウィスコンシンの大学に職を得て、アメリカ人と結婚するも、自分の不貞が原因で別居するのだが、妻にこう言われるくだりがある。
She says, "Don’t look so miserable. We’ve been together more than two years." She means that even if you divorce, you’ll get to keep your pink green card.
"You’ve changed,” she tells you, and you say, “I had to change to stay." (Davies, "How To Be An Expatriate," Equal Love, 2000, p. 80)
ここからアメリカの「上から目線」を感じとれると思うのは、うがちすぎか。だが、悪意がない発言ほど怖いものはない。物語は、妻と離婚した主人公が、渡米後初めてクリスマスにイギリスに戻り、夜、元の自分の部屋で目を覚まして何が変わってしまったのか自問自答するシーンで幕を閉じる。アメリカに残るために変わらなければならなかったけれど、それは果たして正解だったのか。
ピーター・ホー・デイヴィス公式ウェブサイト
今回は、permanent residentがキーワードとなっているアジア系作家の短編をご紹介した。わたし自身、アメリカに住んでいたのは3年ほどだったが、自分の居場所はここではないという居心地の悪さをずっと抱えていた。そんなとき、この2編を読んで救われた。
ちなみに、The New Yorkerは帰国後もずっと購読しているが、すっかり積読になっている。購読をやめようかとも思うものの踏ん切りがつかず、かれこれ四半世紀分たまった。読むと刺激を受けるし、冒頭恒例のニューヨークのイベント紹介の欄を眺めながら、またいつか訪れたら何をしようか、と壮大な計画を立てもしている。いつも年の初めに「掲載されたフィクションだけは欠かさず読む」と誓うのだが、三日坊主状態だ。せっかくなので、新年度からまたその誓いを立てようかと思う。今度こそ三日坊主になりませんように。
■執筆者プロフィール 大下 英津子(おおした えつこ)
言葉を縦にしたり、たまに横にしたりしています。訳書は『火成岩』(文溪堂、2008年)、「シーラ」、「ポンペイ再び」(『アメリカ新進作家傑作選2007年』所収、DHC、2008年)、『絶滅できない動物たち』(ダイヤモンド社、2018年)、「寓話」(『眺海の館』所収、論創社、2019年)など。本とお酒とお笑いとサッカーさえあればご機嫌です。コロナが収束・終息したら、聖地なんばグランド花月に詣でて吉本新喜劇を見たい!
よろしければサポートお願いします! 翻訳や言葉に関するコンテンツをお届けしていきます。