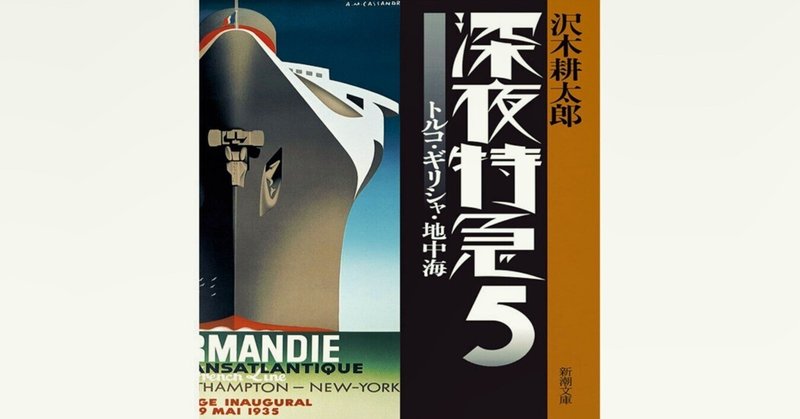
『虐待児の詩』 新潮文庫の一冊
「深夜特急(5) トルコ・ギリシャ・地中海」
生きていくということは、常に何かの代償と引き換えに、別のもの、行きぬくための糧のようなものを得ている。
著者の言いたいことは痛いほど分かるような気がしてならない。
彼も、きっとこの旅で得たモノの大きさに気付いたのではないだろうか。
旅も人生も、何かを無くさずに前に進むことなど出来ないが、その代償から得られるものは、計り知れないほど大きなものなのではないだろうか。
人は皆、何処か見知らぬ土地へ旅に出るとき、一度も見たことがないはずのその目的地に対して、勝手に創り上げたイメージの中でその土地を体験し、既に知っているような錯覚に陥っているのではないだろうか。
そしてその想像より劣っていると落胆し、勝っていると感激する。
何も旅に限ったことではない。
この人種はこんな風だと勝手に想像し、決めてかかる。
そんな先入観念が差別を生んだりもするのだろうが、人間とは不思議なもので、決めてかかられる側も自身で決めたわけでもないのにそれがあたりまえのように思い始める。
いじめっ子は自分がいじめっ子だと意識すればするほど自分のイメージするいじめっ子になり、いじめられっ子は自分がいじめられっ子だと意識すればするほど自分のイメージするいじめられっ子になっていく。
そして、それは自分自身を全く別の自分だと思い直さない限り永久に変わらない。
なんだか道が横にそれてしまったが、私が言いたかったことは、二つある。
ひとつは生きて来た過程で蓄積された体験からの先入観念、もうひとつは何故かイメージを現実化しようとする神秘的な力のことである。
この二つが相互に作用し合って、旅、そして人生を創り上げていっているのではないだろうか。
「先入観念も想像するものなのだから、イメージを現実化するような力があるとすれば、先入観念どおりに実現して落胆するようなことはないはずだ」と言いたくなるかもしれないが、これは一見、正当なパラドックスのようだがそうではない。
想像した本人は意識してないかも知れないが、先入観念による想像が落胆するイメージであった可能性は否定できないからである。
不思議なもので、「こうあって欲しい」と「こうならないで欲しい」とは、願っていることは相反することであるにもかかわらず、イメージした状態の実現へと向かっていくのがわかる。
思い描いたイメージの良し悪しに関係なく、良いことをイメージすれば良いことが、悪いことをイメージすれば悪いことが、何故か現実のこととなっていることが多いものなのである。
目的地に着いて落胆したときというのは、多分、「こんな所であって欲しい」という良いイメージが鮮明でなく、「こんな所じゃない方が良いな」というイメージの方が鮮明だったということはないだろうか。
これは勝手な持論だが、初めての土地、いや何度も訪れたことのある土地ほど、訪れる前に、そこはきっと私にとって最高のところに変貌しているはずだという、良い先入観念と「こんな所であって欲しい」という良いイメージを鮮明に描いてから出かければ、期待を裏切られることなど絶対ないと思っている。
騙されたと思って一度試してみて欲しい、きっと良い旅が体験できるはずである。
もちろん旅先でトラブルが起こるなどとは思わない方が良いが、仮に起こったとしても、このトラブルは単に旅を面白くするためのスパイスを誰かが与えてくれたのだと思い直せば、「災い転じて、福となす」こと請け合いである。
但し、私の場合には、すべてがこれで上手くまわってきたので、あなたも一度試してみればどうかとお勧めしただけのこと、災いが生じても転じなかったり、目的地に落胆するようなことがあったとしても、悪しからず!
話を、戻そう。
彼らに「イメージを現実化しようとする神秘的な力」が作用したかどうかは知らないが、ビリー・ヘイズ(「ミッドナイト・エクスプレス」の著者)は、トルコで投獄され、「深夜特急」の著者(沢木耕太郎)は、無事トルコを通過した。
ビリー・ヘイズは投獄されたが、これも「人間万事塞翁が馬」とでも云うべきだろうか、脱獄後、「ミッドナイト・エクスプレス」はベストセラー(ミリオンセラーかも?)となり、同名で映画化されることとなった。
投獄されなければ、小説の存在も無いのだから、何とも形容しがたいことではある。
ちなみに、この映画の脚本はオリバー・ストーンだったが、現小説に無い酷い脚色もあったようで、トルコに訴訟で負けたらしい。
また、蓄積された体験は人格を形成する。
二人の人が全く同時に、同じ街を見て、二人とも感動し、たとえ共感したとしても、そのふたりの感動は同じではないということなのだ。
要するに、人間とはすべての新しい体験をそれまでの体験、つまり経験からしか判断できないということだ。
当然のことながら、同じ街を二度目に訪れたときは最初に街を訪れたときのような感動は味わえない。
体験は蓄積はされるが取り除かれることがない。
しかし、「想像」はちょっと違う、体験がなくても人の体験を読んだり聞いたりすることで、膨らませることができるからだ。
そしてもうひとつ、どんなところへ旅しても、その場所がどんなところなのかを感じているのは、あくまで心なのだ。
ということは、同じ場所であっても心の感じ方ひとつで良くもなり悪くもなるってことだ。
つまり、心の持ち方を変えることができる人に成れたら、どんなところに着いたとしても良い感動が味わえるんじゃあないだろうか。
そんな人にすぐ成れるかどうかは別にして・・・。
だがもし、「イメージを現実化しようとする神秘的な力」が存在するなら、成りたい自分を思い描くだけでいいはずだ。
だめで元々なら、成りたい自分を思い描いた方が絶対得なのだ。
これまた失敬、私の持論などどうでもいいだろうから、著書から少々離れてしまった道を元に戻るとしよう。
人は常に群れようとする。
そして一旦、群れると、今度はその逆に、人はなぜか孤独を求めようともする。しかし、この孤独は孤立無援のものではなく、知った顔がないことを望んでいるだけで、人が一人もいないことを望んではいないのである。
要するに、必要以上に構われたくないだけのことなのだ。
そう、著者も旅は一人旅を好んで実行しているが、出会い、ふれあいを求めて放浪している。
この旅の目的地には無人島などありえないのだ。
やはり人は一人では生きていけないものなのだろう。
「ペロポソネス半島」、著者が一人旅を好んでするようになったきっかけ、つまりこの旅の原点となるものは、ギリシャの田舎、ペロポソネス半島にあった。
やはり体験、即ち、生きていく環境、周囲の人、場所、時代、などが一人の人間を形成していたのだ。
ふと自分を振り返ってみると、多くの人から受けた影響が思い出されてくる。
食う、寝る、歩く、自分を形成してきたのは自分だ・・と、つい思っていることも多いが、なんと多くの他人の要素を吸収していることだろうか。
良いこともあれば、悪いこともある。まったく、実に多くの要素を他人から受けているものだ。
親兄弟も別の人格、他人として考えたなら、現在の自分自身は他人で構成されていると言っても過言ではないのかもしれない。
「地中海からの手紙」と称する第五章では突然文体がですます調に変わっている。
私には、これがただ手紙の文体だからそうしたのだとは思えなかった。
旅の終盤に差し掛かった著者が、ここまでに過ぎ去ってきた様々なモノのすべてに敬意を表している、そんなふうに感じてなんとなくしんみりとした気分になってきた。
幼い頃、春もうららの心地よい日に縁側でうつぶせで日向ぼっこをしていたら、足の裏を生暖かい風がすり抜けていった。
その涼しくも暖かくもない微妙な感触がやけに気持ちよくて、そのまま永遠に縁側で寝そべっていたいと思ったものだ。
著者のからだを船上ですり抜けて行った地中海の風とは似ても似つかないはずなのに、何故かそんな懐かしい風の感触が突然よみがえって来た。
そして「ブリーズ・イズ・ナイス!」、思わず心の中でそう呟いている自分がいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
