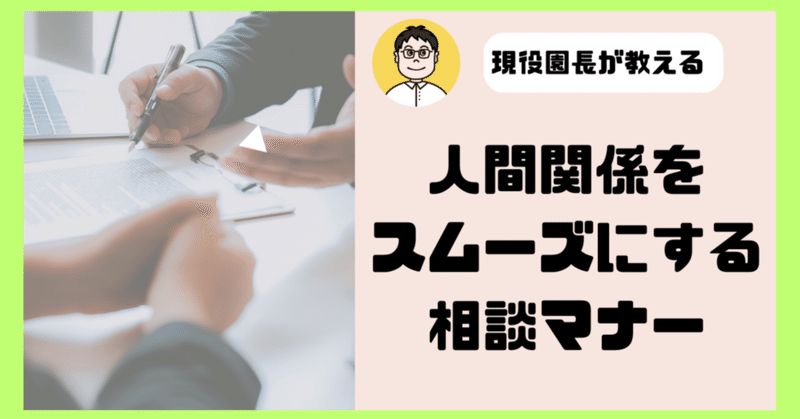
人間関係をスムーズにする相談マナー
皆さんは、上司や同僚に仕事の相談をするときにギクシャクしたり、トラブルになった事はありますか?仕事をする上で、相談は必要不可欠な行為です。相談をしないで勝手に進めると、問題が起きた時に重大なトラブルに発展するケースがあります。何か物事を進めるうえで、周りの人に確認したり、相談することはとても大事なことです。
しかし、相談をする時に、マナーを守っていないと、相談をした相手とのトラブルに繋がる事もあります。どのような方法で相談をするのが良いか、知識として知っているだけで、人間関係のトラブルを回避することができるでしょう。また、相談をよくされる側の人は、マナーを伝える事で自分の仕事の負担やストレスが軽減します。
4つのポイントを押さえておくだけで、人間関係トラブルを回避しやすくなります。ぜひ、最後までご覧ください!

園長コマツ
とある私立認可保育所の園長です。 子どもや保護者、職員みんなが活き活きと暮らせる保育園へ向けて悩みながら改革中。 自分の取り組みや学びをNoteを通して発信します。 プライベートでは二児の父。 好物はハンバーグ。


①相談する相手は直属の上司or仕事を依頼された人へする。
仕事の事で相談をする場合、誰に相談するのか?という事を意識しましょう。場の中はそれぞれ立場があり、立場によって権限が違います。クラスの簡単な決め事はクラス担任や主任、園全体の運営に係る決め事は園長や理事長、などそれぞれ仕事の範囲が違います。
クラスの細かい決定を園長に相談すると、どういう事になるでしょう?きっと「それはクラスの先生や主任に確認して」と言われ、イラッとされるでしょう。それは扱ってる業務内容が違うからです。
また、相談事をリーダーや主任を飛び越えて、いきなり園長にいってしまうと、リーダーや主任は園長に相談した内容を把握していないことになってしまいます。基本的に相談事は自分と立場が近い、クラスリーダーに相談するようにしましょう。クラスリーダーと相談し、更に上へ相談する必要があれば、主任に相談しましょう。

園長もクラスの細かい事までは全部把握しきれません。相談されても困ってしまうケースもあります。基本的に仕事を任された場合の相談は、仕事を任せた人にするようにしましょう。


②相談するタイミングを適切にする。
相談の基本的な考え方は「自分の力量では判断・処理ができないから、他の人へ意見をもらう」ということです。人はそれぞれのペース配分で仕事をしています。いくら仕事の内容の相談とは言え、相談される側は自分の仕事ではない、プラスの仕事を持ちかけられ、時間を奪われるわけです。この認識はしっかり持っておくようにしておきましょう。
相手の時間を奪うという認識がちゃんと持てていれば、どのようなタイミングで相談を持ち掛けるのがよいか、配慮ができるようになるでしょう。

もちろん後輩の仕事のカバーをするのは先輩の役目。しかし、マナーは守りましょう。例えば、園長コマツは保護者会が始まる10分前に「来月のお誕生日会について」相談を持ち掛けられたことがありました。答えるには答えましたが…こっちにはこれから挨拶や資料説明など重大な仕事があるから、できれば後回しにしてほしい…。と思いました。

相手の都合を考えなければ、「この人は自分の事しか考えられていない」という風に思われてしまいます。そこからトラブルに発展してしまうケースもあります。相談する前に、相談相手がどのような状況であるか、一度確認してから相談を持ち掛けましょう。
「〇〇について相談したいのですが、いつ頃が都合よいでしょうか?」と聞くだけでOKです。
その際に期限ギリギリに相談するのは避けましょう。例えば、明日提出の書類について「いつ頃、相談できますか?」と聞かれたとします。
相談される側としては「明日提出する書類の相談なんて……今答えるしかないじゃん……」と半強制的に相談に乗らなくてはなりません。相手の立場を考えた相談とは言えませんよね。

③相談をする時は「自分の意見」を持ってくる。
皆さんが相談を受ける立場の人だったと仮定して、次のどちらが相談を受けやすいですか?
・クラスの食事で子どもが落ち着いて食べてくれません。どうしたらいいですか?
・クラスの食事で子どもが落ち着いて食べてくれません。人数をもっと少人数で食べられるように、机を購入しようかと思っているのですが、どうでしょうか?
おそらくは後者の質問の方が考えやすいと思います。この2つの質問は同じ食事に関しての質問ですが、大きな違いがあります。それは、自分の意見を持ってきているかどうかです。相談を持ち掛ける場合は必ず、自分なりの意見を考えて、相談するようにしましょう。自分なりの解決策を持たないと、問題を相手にそのまま丸投げすることになってしまいます。
先ほどの質問で言えば、前者の質問に、回答者は1から10まで説明しなければなりません。しかし、後者の質問の場合は「いいよ」と回答を省略できるのです。
また、自分の意見を持っていくことで、自分なりに業務をちゃんとやろうと努力している姿勢も伝わります。自分の意見を伝えるのには勇気がいりますが、必ず伝えるようにしましょう。

私は相談を受ける際に自分の意見を伝えてこない職員がいたら、「〇〇さんはどう思いますか?」と必ず訊くようにしています。それを繰り返しているると、自然と相談と共に自分の意見を伝えてくれるようになりました。


④相談相手が判断ができるデータを用意しておく
相談を持ち掛けるときには、相手が判断できるデータを用意することが大切です。例えば、このようなやり取りがあったとします。
相談者「子どもの折り紙が全然足りないので、いっぱい買ってもいいですか?」
回答者「1日何枚くらい使ってるいるのですか?」
相談者「わかりません…」
これでは相談として成り立っていません。
「園には在庫が〇〇枚あり、一日〇〇枚使用しています。こども達の中で折り紙がとても流行になっていて、遊びが発展しているので購入してもよいでしょうか?」
このような相談の方法だと「買ってよい」「使い過ぎなのでは?」など、相談される側も判断ができます。相手が判断できるだけのデータを揃えて、相談に行くことを心がけましょう。
まとめ
相談をする際は、以下のことに気をつけましょう。
相談する相手は直属の上司or仕事を依頼された人へする。
相談するタイミングを適切にする。
相談をする時は「自分の意見」を持ってくる。
相談相手が判断ができるデータを用意しておく
働いている環境の中で、少しでも人間関係トラブルが減ることを願っています。ぜひ、試してみてください!
コチラもオススメです!
保育園や幼稚園で充実した園内研修をするためのネタが充実しています。
知っているようで、なかなか知らない……子どもについての話をわかりやすく解説しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
