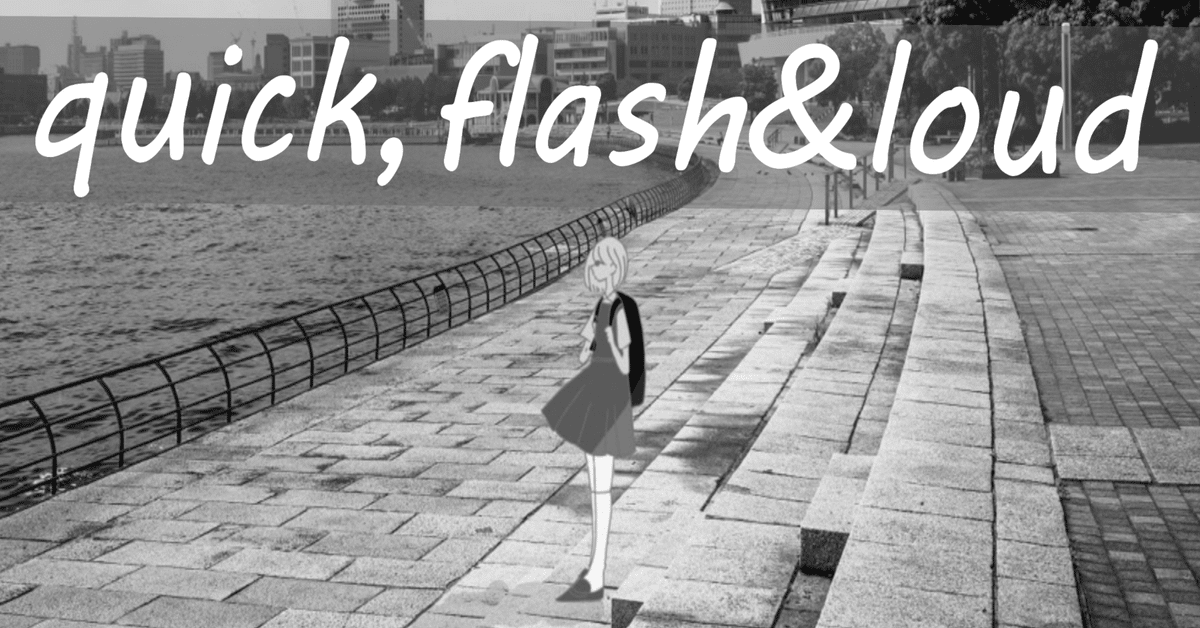
長編小説:クイック、フラッシュ&ラウド 第3章 ウェイストランドボーイズVS小太りズ_3
我がウェイストランドボーイズの音楽性は、七十年代のパンクやネオモッズ、六十年代のモッズ、ビートバンド辺りが主体である。
また、ゆくゆくはスタックスやモータウンなどの六十年代のブラックミュージックも視野に入れて行きたい。と思っているのは僕と橋本だけだった。
吉川にモテたいがためだけに、ドラムを始めた高田
甲子園の夢破れた後の、心の隙間を埋める何かが欲しい山内
特に強い主義主張は無く、ただ付き合ってくれている人の良い青山
の三人はそんな勝手な方向性に困惑した。だが、その都度僕と橋本によってなだめすかされ、だまくらかされ、啓蒙され、結局はなんだかんだでバンドは精力的に活動を続けていた。
まずは簡単なパンクのカバーを足掛かりに、初期のザフーやスモールフェイセスなどソウル寄りのビートバンドにも取り掛かり始め、十一月の文化祭のライブを目指して日々練習に明け暮れていた。
小さい頃にピアノを習っていて、元々音楽的素養のあった青山と、馬鹿正直にひたすら練習し、完コピを目指す山内。二人はみるみる成長している。
そして最初はか細かった僕の声も、毎日血を吐く様にして叫んでるいるうちに、良い具合に嗄れて太くなって来た。
サムクックのライブ盤の様に、声の限りに叫びながらも音程を自在にコントロールできる様になりたい。元々ボーカルなどやるつもりは無かったが、自分の理想の形を朧げながらイメージする様になっていた。
ただし高田だけは相変わらず下手糞で、しかも自己肯定感だけは強いので全く成長しない。音だけはでかい出鱈目なドラムだった。
夏休みに入っても僕らは再三集まり練習を繰り返していた。初期衝動が云々と橋本が面倒臭い事を言っていたが、今のところ幾らやっても飽き足らず楽しくてしょうがない。
そんなある日、いつもの様にスタジオで練習を終え、一息ついていると、青山が急に「あ」と小さく声を漏らし、僕の背中越しを見つめた。皆が青山の目線に促され振り向くと、意外な人物の姿があった。
「あれ、お前こんなとこで何してんだ」
と高田が素っ頓狂な声を上げた。休憩スペースの奥にある円卓に、バレー部キャプテンだった桜井の姿があった。当の桜井は表情を歪め俯いており、なんとなくバツの悪そうな顔をしている。
「なんだお前も音楽やってんの?一人で?」
無神経な高田が席を立ち近づこうとした時、円卓の奥にあるスタジオの扉が開いた。そこから北山、黒田、細川と言う電子音楽研究会の連中がどやどやと出て来たので僕らはさらに驚いた。
電子音楽研究会
それはこの学校では異端視されている異形の集団であった。
ただでさえ軽視されている文化系の部活の中でも、謎の存在とされていおり、その活動は殆ど明らかになっていない。
電子音楽などと言いながら、パソコンでアダルトゲームを行っているだけの変態集団であろうと皆思っていた。
因みに部員は三名。全員小太りの眼鏡である。その電研の面々と、バレーボール一筋、ゴリゴリの体育会系である桜井の取り合わせだけで妙である。
彫りの深い、昭和の二枚目俳優の様な桜井と、眼鏡小太りの電研メンバーが並び立つだけて相当な違和感を覚えた。
「あ、佐山君達もバンド始めたんだってね」
電研の一人、北山がサラサラの中わけをかき上げながら微笑みかけて来た。
その言い方に含まれた挑発的な響きを皆も感じ取っただろうか。少なくとも僕は感じ、不快感を覚えた。君達も、と北山は言ったが僕らは誰も電研のバンドの事など知らないし興味もない。
加えて、北山が手に持っているおぞましい物体が僕の神経を逆撫でした。
彼の手にはピンクのペイズリー柄のギターが握られていたのだ。これは殆どホラーと言って良かった。僕もバンドマンの端くれであるからして、楽器が大好きだし、ジャンルの違いから来る様々な趣味嗜好もリスペクトしたいと思っていた。しかしこのギターはあまんまりだ。誰が何のために作ったのか皆目検討もつかなかった。
「今度の文化祭で初ライブしようと思って練習してるんだ」
青山が屈託無く答えると、そうなんだ、と意味有り気に笑い北山はまた髪をかき上げた。電研の残り二人、黒田と細川も続いて笑った。ちなみに電研の面々は単体だと殆ど判別がつかない。見分けるための違いは
北山はサラサラ中わけの小太り(銀縁眼鏡)
黒田は色黒で癖毛の小太り(黒縁眼鏡)
細川は長髪でキムタクヘアの小太り(縁なし眼鏡)
となっている。
「桜井は電研の連中とバンドやってんのか?」
高田が問いかけると桜井は
「いや…バンドって言うかまぁ…」
と苦虫を噛み潰したような表情で曖昧な返事を返した。
「お前がバンドやるなんて意外だな」山内が笑いながら語りかけると
「俺がやったら悪いのか?」と桜井はなぜか僕を睨みながら返した。
実を言うと僕と桜井は部活を引退して以来話していない。桜井は僕を引退試合の戦犯だと思っている。と言うか事実僕は戦犯であろう。
ただしあれは投げやりな山岸采配が悪いのであって僕のせいではない。僕はあの引退試合の後、早々に気持ちを切り替えバンド活動に傾倒して行った。
そんな姿を桜井が快く思っていないのかも知れない。部活をやっていた頃はそれなりに仲が良かったのだが今は廊下ですれ違っても目も合わせなくなっていた。
「いや何も悪いなんて言ってないだろ。」
予想外の桜井の剣幕に山内は慌てて取り繕う様に付け加えた。険悪な空気が場に漂う。
「桜井君はボーカルとして僕らがスカウトしてバンドに入ったんだよ。彼、高音ならA#迄出せるからね」
小太り②の黒田が桜井の肩に手を置いた。当の本人である桜井はなんだか迷惑そうにその手を視界の隅で一瞥したが、何も言わなかった。
「佐山君はこのバンドのボーカルなの?」
小太り①サラサラヘアの北山がニヤニヤ笑いながら聞いて来た。
「そうだよ」何がおかしいのだろうか。僕は一切表情を出さないように努めながら答えた。
「佐山君は因みにどのくらいまで出せるの?」
小太り達は先程から一貫して挑発的に見えた。何故か僕と桜井の声の声域がバンドを代表した代理戦争となるべく、話を展開させたい様だ。
「俺?わかんない。考えた事もない」
その手には乗らない。別に高音の金切声を出せたり、ギターの速弾きができれば偉い訳ではない。スポーツがやりたければ勝手にやればいい。俺達はアートをやっているのだ。数値やデータでは測れない価値観でやっている。根本的に考え方が違う。
「そうか君達はパンクだもんね。そんなの関係ないよね」
パンクのステレオタイプなイメージを引き合いに出し、知った風な口を利く北山。
「君たちはどんな音楽をやっているの?」
橋本が柔らかな口調で口を挟んだ。とっくに電研の挑発的な態度に気付いている様だが、敢えて友好的な姿勢で応対しているのだろう。
「いやぁ本当はプログレかフュージョンをやりたいんだけどさ、まだマニアックなのは桜井君にも荷が重いかなと思って。」
「だから結局何をやってんだよ」
北山の遠回しな言い草に高田も明らかに苛ついている
「まぁJPOPかな。今のところは」
北山の代わりに小太り③細川がメガネを神経質そうに触りながら答えた。
「今度の文化祭で対バンできるのが楽しみだね」青山はこの期に及んでまだ無邪気に笑いかけた。うちのメンバーの中で青山だけは本当に腹が立っていないようだった。大した人物だ。
「じゃあこれからリハだから」
と言って北山達は再びルームFへ入って行った。たかだか素人の練習を「リハ」と言う感覚ひとつ取ってみても、僕とは永遠に相容れない断絶を感じさせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
