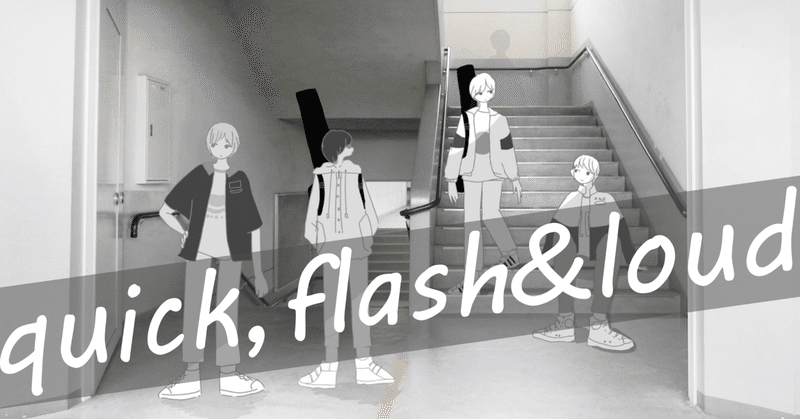
長編小説:クイック、フラッシュ&ラウド 第1章 十代の荒野_3
それから僕らは色々な音楽を聴いた。刺激的なもの、美しいもの、素晴らしいもの、格好いいもの、馬鹿馬鹿しいもの、そしてゴミみたいなものでさえ、それはそれで魅力的だった。
幸いな事に九十年代中頃は、僕らの前に過去の遺跡が次々と発掘されていった時代だった。オアシスやブラーやストーンローゼスの新譜が発売される一方で、過去の名作がリマスターされて次々とCDで再発されて行く。
HMVやタワーレコードと言うミュージアムを訪れれば、国宝級の名盤から最新のトレンド迄がアルファベット順に整然と並べられ僕らを待ち構えていた。
ザフーを知り、スモールフェイセスを聴き、そこからポールウェラーを知る。ジャムを聴き、ロンドンパンクを聴き、ジャムがカバーしたモータウンを聴けばスタックスへつながり、スタックスからサムクックを聴き、チェスを辿りシカゴブルースを聴きハウリンウルフへ至る。また現代に戻りジョンスペを聴き、そこからJBを聴いて、スライを聴いた。かと思えばやっぱりビートルズとストーンズを聴き、キンクスやゾンビーズも聴き、再発されたバズコックスやマガジンを聴く。でもまだニールヤングもザバンドもバーズもビーチボーイズも代表曲しか聴いていなかった。ディランだってベスト盤しか聴いていない。スペシャルズやマッドネスは聴いたが、もっとオーセンティックなスカやレゲエも辿りたいし、ソウルをもっと掘ればヒップホップにも道は続いているだろう。そして底無し沼であるジャズにはまだ爪先も踏み入れていないのだ。
気が遠くなるような膨大なアーカイブは際限なく広がり、聴いても聴いても焦燥感と飢餓感が増した。そして自分の懐を鑑みるとその寒さに絶望的な気分になった。残りの人生でいったいどれ程の音楽を聴ける金と時間が残っているのだろうかと。冗談では無く人生の全てをかけてもいいと思った。
そうして貪る様に音楽を聴き漁る中でも、ザフーだけは僕と橋本の中では特別な存在として常に心の神棚に飾り手を合わせていた。ザフーは、あの日に狩り場で初めて聴いた衝撃の何倍もの体験をその後の僕らにもたらした。
リーズ大学でのヤングマンブルース。ストーンズを完全に打ちのめした、ロックンロールサーカスでのクイックワン。ワイト島のビデオで見た深夜のサマータイムブルース。どれも尋常な体験では無かった。その度に僕らは何度も熱狂し、その素晴らしさを放課後何時間でも夢中になって語り合った。
ザフーによって世界が二つに割れた。格好良いものと格好悪いもの。その世界を分かつ分水嶺にザフーが存在した。ザフーの様に轟音で鳴っているか。ザフーのように高く跳躍しているか。ザフーのようにイカれているか。ザフーの様に繊細であるか。ザフーの様に美しいか。どんな音楽を聴いてもザフーからの距離で判断を下した。
音楽ばかりで無く立ち振る舞いや考え方にも影響を及ぼした。僕らは世の中の人間も「聴いている奴」と「聴いていない奴」の二種類に分けた。僕と橋本が前者で残りが後者。そして後者と深く交わる事をやめた。
二人だけにしかわからない暗号の様な単語で囁き合うように会話をして、流行りのJPOPをこき下ろして笑った。
興味を引くイントロがあって、心を掴むAメロがあって、徐々に盛り上がるBメロがあって、胸が締め付けられる切ないサビと、共感できる歌詞があるミリオンヒット。そんなものは糞喰らえだった。
僕も橋本も表向きはヘラヘラと掴み所の無い人間を学校で演じながら、その実、内心は同世代に対して唾棄していた。子供向けの砂糖菓子を与えられて喜んでいる馬鹿な連中。僕らはもっとハードコアな表現を欲していた。
益々部活に打ち込まなくなり、時には怪我を理由にサボる様になって行った。それまで仲の良かった部活のメンバーとも少しずつ疎遠になって行った。しかしそんな事は問題では無かった。目の前に広がるミュージアムを前にして最早スポーツの事など頭に無くなった。
スポーツは僕に答えをくれなかった。音楽もくれなかったが、少なくとも聴いている間は自我をかき消し、脳が痺れる様な快感をもたらしてくれた。「音楽は僕を高みへと引き上げた」と言いたいところだが、実際の所は「僕の中での音楽以外の序列を下げた」だけだったと思う。
ついでに言うと周りからの僕に対する評価も著しく下げたかもしれない。でもそれもどうでも良かった。どんなに人生の先行きが暗くても、学校がつまらなくても、生きる意味が見出せなくても、そんな事全然問題では無かった。あのピートタウンゼントの跳躍、キースムーンのチャーミングな狂気を思い出せば、僕らは間違っていない、それは奴らのほうだ。といつも思えた。
そして僕らは決意した。自分達で音楽をやる。素早い閃光と、そして轟音で頭の中を塗りつぶしてしまえば、「自分を意識している自分」と言う醜悪な十代の自我を跡形なく打ち消す程の快楽を得られる。そう信じてバンドを作る事にしたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
