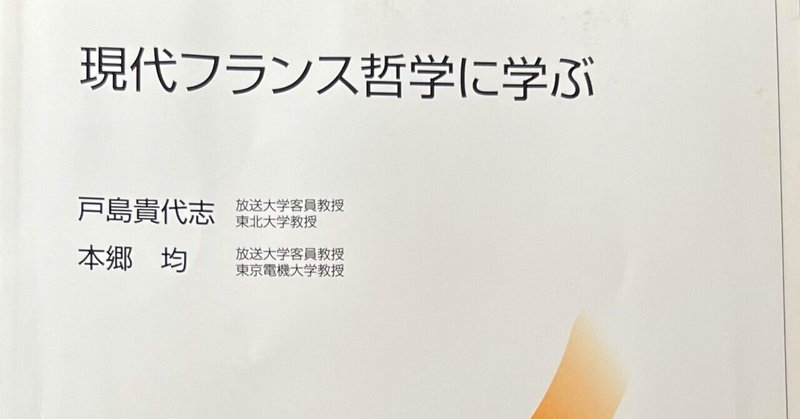
ベルクソンの哲学について
戸島喜代志共著『現代フランス哲学に学ぶ』に基づいて、ベルクソンについて勉強します。
行動の効率
無機質から直接に有機養分を合成できる植物と違って、ヒトを含めた動物は有機栄養分を植物や他の動物に依存し、そのために動くことを本質としている。
ヒトの認知・認識能力も原理的にこの動くことつまり行動のためという実践的関心を基盤として成り立っており、その意味でヒトの行動も本性上おのずと効率的な行動へと向かっていく。
それは、意識が行動をみずからの道具としているということになる。
そして、このことは、当の意識そのものは行動の要求の外にあるということでもある。
このように、実践的関心をはみ出るこの意識(純粋意識)を行動の要求ではなくて創造の要求と呼んで、これをもって「生命の根源」とベルクソンはみなしている。
物質の多義性
知性にとって生命進化の必要条件は外的物質環境への適用である。
しかし、これに対し、その外的物質環境を生き抜くために生が自分が自分を物質化する。したがってみずからを解体する傾向としても、ベルクソンは物質の概念を用いている。
ならば、このみずからを解体する傾向としての物質性に対置して、生みずから本来の生たらんとする傾向もあるとベルクソンは主張する。
確かに、自己を振り返ってみると、「もうどうでもよいや」という投げやりな気持ちと、「いや何とか頑張って乗り越えてみよう」と内面で常に葛藤していた。
生がみずからを解体する傾向つまり弛緩としての物質化と、生がみずからの本来の生たらんとする傾向つまり「緊張・集中・飛躍」は、事象としての生そのものの存在の二傾向として、ともにこの生を内側から形成する。
緊張していたがそれが解かれると、直ちに弛緩してしまうのは、良く経験していたことであった。
知性と直観
この知性にとって『創造的進化』では、これまでの「直観」との構造的対比ーー知性:外側からの固定的・空間的把握、直観:内側からの動的・時間的把握ーーとは若干異なった、一種の発生的視点からあらためてこういわれている。
生命、すなわち 「物質の制約を纏った意識」 が 「自分の通り過ぎる物質に注意を固定」 すれば知性が、「自分本来の 運動に注意を固定」 すれば直観が、それぞれ生じる、と
〈物質の制約 のない意識〉 つまり純粋意識から見るならば、もともと知性も直観も、前者は「物質の制約を纏った意識」 が自分の外に出て物質に集中する場 合に、後者はこの意識が自分自身の中にいて生命に集中する場合に、そ れぞれ生じた生の相補的根源様式と映る、ということである。
ベルクソ ンは、さらにこの相補関係をより深めるかのように、直観の本質である 〈事物の中に入り込むこと〉 のもつ反面の性質 ーーかえってそこに 「釘付け」 されてしまうことーーが 知性の性質である 〈事象から身 が、を離すこと〉 あるいは 〈事物に外から適応すること〉 によって打ち消さ れる、と考えた。
してみると、対象と一体化する直観と、対象から距離をとる知性との 連繋、 これら相補的二側面の連携は、 みずからがそれの部分である生の 全体を引き受け、それによって生をより自由にし、生をより拡張すると いう、その一点で繋がる連繋であるといえよう。
この連繋をはかるも の、それが行動をみずからの道具とするあの 「意識」、 すなわち 「行動 の要求」 を超えた 「創造の要求」 としての純粋意識なのである。
この意 識にとっては、もはや直観と知性はいわば共通の地 (=生命あるいは意 識)から成っている。 ある種の凝縮によってできあがった固い核つまり 知性は、自分を包む流体 (生命や意識) と根本的に異なっているわけで はなく、むしろそれと同じ実質から出来ているのである。
「直観」は事物の中に入り込んでしまうことが本性であるがゆえに、「ミイラ取りがミイラとなる」危険性があるが、一方「知性」の方は、外から自分を見るという冷静さがあるので、双方が相補的に連携し合っているというわけである。
ベルクソンには、生を支えるものは、創造性を発揮して努力するしかないのだという前向きさがある。
ハイデガーの「計算的思惟」
ハイデガーは『形而上学とは何か』序論で大地と根に譬えて、形而上学と本質との関係を述べている。
「大地は根にとっての大地である。根は、大地の内で、樹木のために、己を忘れる。・・・根は、己の在処(つまり土壌)から得るもの(たとえば養分)と、己自身とを、樹木のために、消費する。・・・根がその在処に編み入れられることなしには在処も在処ではない。」
ハイデガーによれば「根」が「形而上学」であり、「大地」が「本質」を示している。
「根」は「大地」に根差すとともに「大地」から生い立ち、その「大地」からみずからを切り分けている。同様に、「形而上学」はみずからの「本質」から根差すとともに「本質」から生い立つが、生い立つと同時にその「本質」から離れ、「本質」を忘却する、とハイデガーは考えている。
形而上学におけるこの忘却とは、形而上学が「存在するもの」のみを思考し、己の「本質」である「存在そのもの」には向かわない、ということである。
ここでの「形而上学」、すなわち「存在」を忘却した「存在者の思惟」は、存在者全体として「前に立て(表象し)」、前に立てる仕方で「計算する」思惟である。
ここで、ハイデガーは、「前に立てる」思惟の「本質」それ自体は原理的に前に立てることができず、一切を計算する思惟の「本質」は計算することができない、と考える。
だが、「存在の思惟」と「形而上学的思惟」は対立するものではないとも考えている。対立物にしてしまうと、「形而上学的思惟」そのものを、「存在の思惟」みずからが遂行することになるからである。
つまり、「存在者の思惟」と「存在の思惟」は断絶しているのではなくて、繋がっているということになる。
「計算的思惟」(形而上学的思惟)を離れるには、「計算的思惟の根底」(存在の思惟)に戻るしかないのである。
一方、ベルグソンは計算する思惟を、哲学的思惟としての「形而上学思惟」と対立させている。ベルグソンとハイデガーでは「形而上学的思惟」の意味が相違していることに注意が必要です。
計算と希望
ベルクソンはいう、反省のあるところには予見があり、予見のあるところには不安があり、不安のあるところにはかならず生への密着の瞬間的な弛緩がある、と。
このような弛緩を補填するのが防御策としての宗教である。しかし、この宗教も防御策としての役目を果たすことができずに、ニヒリズムが蔓延する。
ハイデガーは技術世界を形成する新種のニヒリズムを見出した。しかし、現在を眺めれば分かるように、計算からくる幾多の障害ーー戦争、飢餓、格差、差別、貧困、地球破壊などーーが立ちはだかっている。
計算を凌駕する「希望」の計算なき行動や、動かすべき山を見ない「開いた魂」の「躍動」は、時代的計算の根底へとみずから入り込む「存在の思惟」にも、一つの風穴を開けることはできるのだろうか、と戸島氏は問うている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
