
【累積的抑圧経験】
2019年12月、東北学院大学准教授の【社会学】者・小宮友根が、フェミニストによる表現への集団クレーム攻撃を持ち出すため炎上繰り返すポスター、CM…「性的な女性表象」の何が問題なのか(2019年12月)の中で持ち出した概念。
特に私が重要だと思うのは、ある表象が差別的な女性観を前提に作られているとき、日頃からその女性観に苦しめられている人にとって、表象はその抑圧の経験との繋がりの中で理解されるだろうということです。たとえば「家事育児は女性がすべき」と言われてその負担に苦しんでいる女性にとっては、女性があたりまえのように家事育児をしている表象は、「ここにも同じ女性観がある」というように自らの抑圧経験と意味的に繋がったものとして経験されるでしょう。
差別的な女性観による抑圧の経験(あるいはそうした経験を多くの女性が持つという知識)は、その女性観を前提にした表象を理解する際の文脈を形成するということです。同じ女性観を前提にした抑圧経験との意味連関のもとで特定の表象がより「悪く」感じられることを、「累積的な抑圧経験」と呼んでおきましょう。「炎上」の繰り返しを引き起こす、表象作成者と批判者の間の齟齬の一端は、この累積性に対する理解が両者で異なることに由来すると私は考えています。
要するに「イヤなことを思い出させたのだから、そのイヤなことの原因でもなんでもない相手であっても、フェミニストは八つ当たりで攻撃し炎上させてよい」と言う主張である。実際に、この箇所で小宮氏が正当化しようとした炎上事件は、エロティックでもなんでもないばかりか「固定的ジェンダーロール」すら冤罪だった【人工知能学会誌表紙事件】であった。
当然ながら、これは「イヤな思い出を刺激する表現」全てについて言えることであって、話を「差別」にも「女性」にも限る必要はない。運動が苦手なのを馬鹿にされてきた人、親から虐待を受けて育った人など……は、それぞれ、スポーツを賛美する広告、理想の家族を描いた漫画や写真……などなどに「累積的な抑圧経験」を思い出すであろう。
極端な話、純粋な科学的事実の記述でさえ「それを知らなかったことでバカにされたことがある人」の苦い記憶を刺戟するかもしれないのである。
しかし、だからといって「私のイヤな思い出を甦らせるからそんな広告は出すな」などということは、常識のある人は言いはしない。そんなことをすれば、自分たち自身も誰かのイヤな思い出を刺激しないように何も言えなくなることは分かり切っているからだ。【人工知能学会誌表紙事件】で持ち出された「家事を負担に感じている女性」なんかより遥かに不幸な人であっても、である。
当然ながら、この概念は逆用することもできてしまう。
フェミニズムが繰り返し「萌え絵」などの表現を攻撃して燃やしている以上、当然そのような排除を被ったファン――いわゆる「オタク」の側には「累積的抑圧経験」が発生することになるので、反撃が正当化されてしまうわけである。しかも本来のフェミニズムの攻撃が、その表現には何の責任もない累積的抑圧経験からの八つ当たりである以上、オタクからの反撃範囲も一切コントロールする必要がないことになってしまう。
「累積的抑圧経験」概念のこのような弱点が露わになったのは、下記の高橋幸(フェミニズム研究者・大学講師)の発言である。
みんな、ごめんごめん。Twitterでの人の動き方がよく分かってなくて。「規制」の言葉だけで累積的な抑圧経験が刺激されてしまうんだ。傷ついてきてるんだよね。
— 高橋幸 Yuki Takahashi『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど』3刷!(感謝) (@Schnee05) November 26, 2020
前述のブログ記事でも書いたように、私はもちろん児ポ法改正に反対だったし単純所持で検挙できる論理的な根拠が分からないという立場だよ
ここで高橋がやらかしているのは、自身の「表現の自主規制論」に批判が集中した際、反論に窮した彼女はつい、この「累積的抑圧経験」を「相手方の心理として」煽りに使ってしまったということである。
すなわち、累積的抑圧経験などというものは女性やフェミニストの声を特別に優遇できる概念でもなんでもないことを、自ら認める破目になってしまったのだ。
【最善の相】発言などに見られるように、小宮友根という人物はどうも「浅い考えで一般的過ぎる反撃方法を考案しては、敵側に逆用されてしまう」という失態を繰り返しているようだ。
筒井康隆が1977年に発表した小説『エディプスの恋人』は、小宮・高橋両氏などよりはるかに先立ち、このような累積的抑圧経験の原因となった本人ではなく、「それを思い出させた者」への攻撃へと転化する心理の醜さについてありありと描いている。
読心能力を持つヒロインの火田七瀬は、ある少年の過去について調べるため、彼の故郷にいた男に接触する。その男は少年に危害を加えようとしたことが原因で負傷し、それ以降足が不自由になっていた。そのことを思い出させられた男は、それを「思い出させた」七瀬に対して逆上し、強姦しようとするのである。
ひと通りの回想を終えた郵便局員の中では「彼」への恨みがいつの間にか七瀬への攻撃衝動に変化していた。幼年時代、少年時代の、彼の身勝手さ、我儘、兇暴性がふたたび燃えさかりはじめていた、この女子大生が自分に昔のいちばん厭なことを思い出させたが故に、自分はこの女子大生を犯して当然である、と、彼は考えていた。胸についたやり場のない怒りの炎を消し、屈辱感を柔らげるために、自分は早急に女を犯す必要があり、この女子大生はその犠牲になるべきである、と思っていた。自分にはそれだけの力がある。この女を力ずくで犯し、責め苛むことのできる力が、まだ自分にはある。おれはそれをただちに、自分に対して証明しなければならない。
滅茶苦茶な理屈であったが七瀬はそういった醜悪な自我には馴れていた。
この心理はまさに小宮氏の言う「累積的抑圧経験」からの攻撃行動であり、よりにもよって、それがフェミニストが憎悪してやまないはずの「強姦魔」の心理としてなのは最高の皮肉になっている。
そして「滅茶苦茶な理屈であったが」「そういった醜悪な自我には馴れていた」――この一言は、まさに表現の自由派がフェミニストの発言を見るたびに思うことなのである。
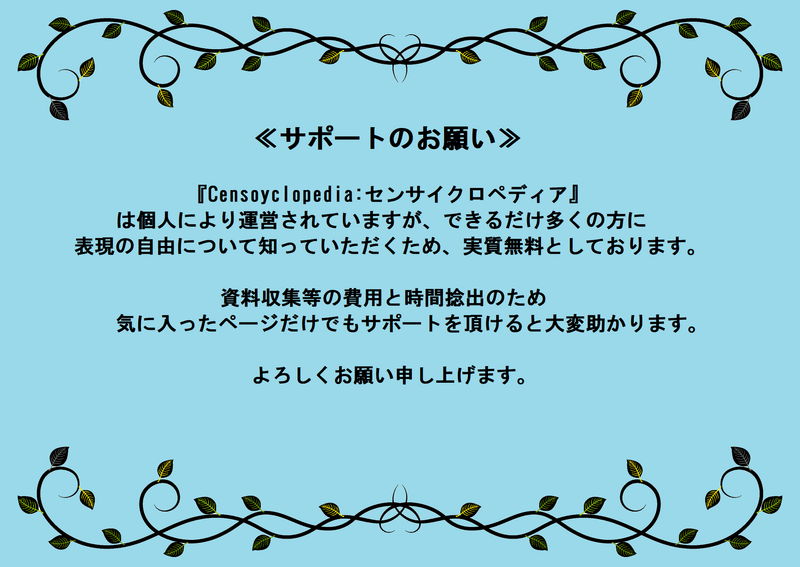
参考リンク・資料:
資料収集等、編纂費用捻出のための投げ銭をお願いします!↓
ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。

