
【短編】消極的自分探し
「あなたはインドに行ってもなにも得られないよ」
君はぶっきらぼうにそんなことを言った。
分かっている。別に分かっているんだ。
でも、そんなこと言われたらムキになっちゃうじゃないか。
ただ言ってみただけだった。
「あなたはどこに行ったってもっと素敵になって帰ってくるよ」
こんなことを言って欲しかったんだ。
もはや、インドに行くことは自分探しのためではなく、君が間違っていたのだと突きつけてやるための材料探しになった。
そしてインドに着いて3か月目の夜。
壁の薄い部屋の硬いベッドの上で泣いた。
辛かったからじゃない。
楽しくも、苦しくもなかったからだ。
自分の中身のなさに涙が出た。涙が出てしまったせいで本当に体の中は空っぽになった。涙しか入っていなかったのだ。
油断したらまた余計なものが注がれてしまうから、ずっと部屋中を舞う埃を数えていた。
人知れず帰国した。誰にも連絡を取らなかった。
それから、廃人のように毎日を過ごした。喧騒が嫌いになった。会話が苦手になった。自分以外の何かに触れると自分が侵食されるように感じるようになった。ポジティブな人に出会うと責められていると感じるようになった。
「嘆いてもしょうがないよ!がんばろ」
「やれることは全部やったの?」
そんなことは言われなくてもわかっていた。うるさいから黙っていて欲しいとだけ思っていた。
それは態度に出ていたのだろう。どこに行っても敵を作ってしまった。
僕は家を出なくなった。
三ヶ月は閉じこもっただろうか。時間の感覚なんてとっくに捨て去ったから大体しかわからないけど、多分そのくらいだったと思う。
きっかけは些細だ。窓を開けてみたらいつもより涼しかったから。
僕は外に出た。バイクを借りて気が済むまで走り続けた。
給油をして二時間ほど走ったあと、「絹の町 冨野」という看板を通り過ぎた。
知らない名前だった。
その看板を通り過ぎてすぐに道の駅らしきものがある。
スタイリッシュな雰囲気ではなく、何の変哲もない普通の道の駅だ。
僕はバイクを停め、建物の中に入った。
中には小さめの食堂と野菜の販売所があった。
せっかくだからと思い、小さめの食堂で豚汁定食の食券を買って手渡しに行った。
「あら、お兄さんどこからきたの。」
「東京からです。」
「1人?」
「はい。」
「外のバイクお兄さんのかしら。かっこいいわね!」
「ありがとうございます。借り物ですけど。」
「そうなのね。豚汁定食すぐ作るから待っててね。」
気さくなおばちゃんだった。食堂で働いているのはそのおばちゃん1人のようだ。同じようにお客さんも僕1人だった。
5分も経たないうちに呼ばれて取りに行くと豚汁の他にコロッケがお盆に乗せられていた。
「僕頼んでないですけど。」
「いいのいいの、ちょっと疲れているように見えたからね。揚げ物でも食べて!」
「お金払います。」
「いいから!貰えるもんは貰っときな。」
僕はお礼を言って席に戻った。そのコロッケは
母がたまに作ってくれたコロッケと同じ味がした。
食堂を出て、野菜売り場も少しのぞいて見た。野菜売り場の端に一箇所だけお土産を売っている場所があった。
その中にキーホルダーがあるのを見つけた。小さい木彫りのクマにチェーンがつけられていた。決して上手ではないが、味のあるクマだった。なんだかそれを気に入ってしまった僕はレジに持っていった。
そこでは1人のおじちゃんが難しい顔をしながら新聞を読んでいた。僕に気がつくと、ゆっくりと退屈そうにレジの前にたった。
僕は木彫りのクマを渡した。
するとそのおじちゃんが
「これ、私が作ったんだよ。素人にしてはよくできているだろう。」
と言って、笑顔になった。
「そうなんですね、顔が可愛いなと思って。」
「昔、近所に住みついていた熊の子供をイメージして作ったんだよ。親は獰猛だったが、子供はおとなしくて可愛かった。そんなことを言ったら私が親に怒られちまったけどね」
そう言っておじちゃんはまた笑った。
僕は買ったキーホルダーを携帯につけた。少し渋い感じになったけど、意外と合っているなと思った。
外に出ると少し気温が高くなっていたので、自販機でアイスを買って、近くにあったベンチで食べることにした。座ってアイスをほおばっていると、さっきのおばちゃんとおじちゃんが外に出てくるのが見えた。そして、僕を見つけるとおばちゃんが走ってきて
「まだいた!よかったわ、あなたお財布忘れているわよ。」
と僕に財布を差し出した。
どうやらレジに財布を置き忘れてしまっていたらしい。
「あっ、すみません。ありがとうございます。」
「もー、気をつけなさいよ、免許とか入っているんでしょ。捕まっちゃうわよ!」
「はい、助かりました。」
おばちゃんはふぅと大きなため息をついて僕の隣にどっこいしょと座った。
「今日のお客さんはお兄さんだけなのよ。まぁ、平日だからかしらね。昔は平日にもたくさんお客さんが来てくれてね」
そう言っておばちゃんは昔話を話し始めた。
そこで、ようやくおじちゃんが僕たちのいる場所にたどり着いた。
「昔話なんか聞かせたって兄ちゃんにはなんも面白くないがや」
「いいの!聞いてくれているんだから。余計なこと言わないで頂戴。」
そういいながらおばちゃんはおじちゃんの膝をパンッとはたいた。
「怒られちゃったわ。」
おじちゃんはそう言いながら僕の方を向いてガハハと笑った。それを見て僕も少し笑った。
爆笑とか、苦笑いとかではない。心の底からの笑いだった。
「お兄さん、今年の祭りの季節にまたおいで。毎年9月にやっているから。」
「そやそや、町中の若い姉ちゃんもようけ集まるから兄ちゃんも楽しめる。」
「またふざけたこと言って。」
「わかりました。ぜひ。」
僕はそういってからバイクにまたがった。おばちゃんとおじちゃんは地元の名産品だというビワを僕のリュックいっぱいに持たせてくれた。
僕はバイクのエンジンをかけ走り出した。二人はバックミラーに移らなくなるまで僕に手を振ってくれた。
そして、行きに見た「絹の町 冨野」の看板を通り過ぎたとき、僕はふいに彼女が言っていた言葉の続きを思い出した。
「あなたはインドに行っても何も得られないよ。あなたの居場所はここなんだから。」
やさしさに満たされた僕の体からは余った水分が涙となってあふれ出した。
その涙はモーター音と共に森に広がり、ゆっくりと溶けていった。
縦書き版




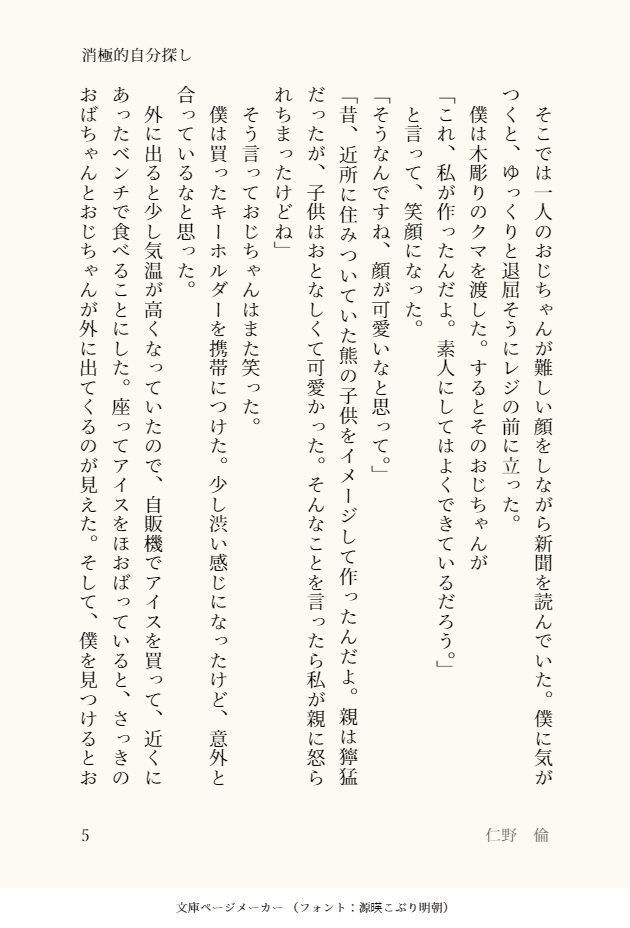



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
