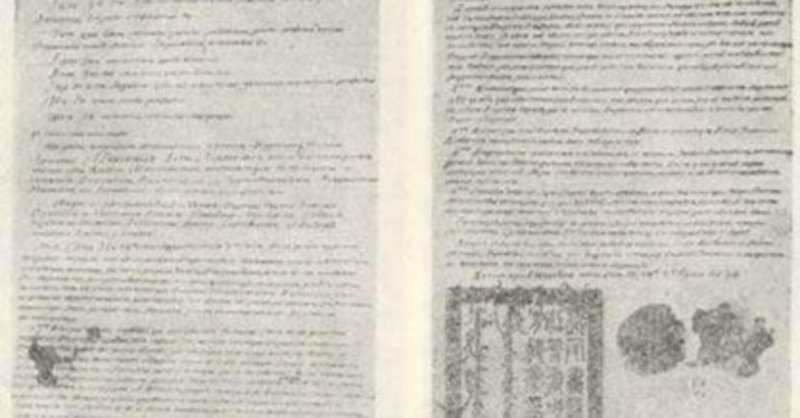
ネルチンスク条約ラテン語版を和訳してみた(第5回)
De his autem post uniuscuiusque Imperii legatorum in proprium regnum reditum rité examinatis et clare cognitis vel per legatos vel per litteras postea determinabitur. Item fluvius nomine Ergon qui etiam supra dictum fluvium Sagalien Vla influit, limites ita constituet, ut omnes terrae quae sunt ex parte meridionali ad Sinicum, quae vero sunt ex parte boreali, ad Ruthenicum Imperium pertineant : et omnes aedes quae ex parte dicti fluminis meridionali in faucibus fluvii nomine Meyrelke extructae sunt ad littus boreale transferentur.
これもまた、短い一文と長い一文の計2文です。分けて説明します。
De his autem post uniuscuiusque Imperii legatorum in proprium regnum reditum rité examinatis et clare cognitis vel per legatos vel per litteras postea determinabitur.
分割してみます。
「De his autem」は「これについては」。「his(これ)」とは、先述に上がった、未確定として残ったウダ川と山脈の間にある川・土地のことです。
「post uniuscuiusque Imperii legatorum in proprium regnum reditum」は、「両帝国の各使節がそれぞれの国に帰還した後」となります。ラテン語の前置詞「in」には「〜へ」という意味があります。
「rité examinatis et clare cognitis」は「正式に調査して明確に認識する」。吉田氏の和訳では「rité」を「入念に」と訳しています。これは直訳ではなく、ニュアンスを優先した訳だと思われます。
「vel per legatos vel per litteras postea determinabitur.」は「特使または書簡によって後日決定される」。
以上、まとめると「これについては、両帝国の使節がそれぞれの国へ帰還した後、正式に調査して明確に認識し、特使または書簡によって後日決定される。」となります。
Item fluvius nomine Ergon qui etiam supra dictum fluvium Sagalien Vla influit, limites ita constituet, ut omnes terrae quae sunt ex parte meridionali ad Sinicum, quae vero sunt ex parte boreali, ad Ruthenicum Imperium pertineant : et omnes aedes quae ex parte dicti fluminis meridionali in faucibus fluvii nomine Meyrelke extructae sunt ad littus boreale transferentur.
長いので分けて説明します。
なお、ロシア語版ではここから第2条に移っています。
「Item」は「〜もまた」。
「fluvius nomine Ergon」は「エルゴンと呼ばれる川」。ロシア語版だと「реченная Аргун(アルグン川)」となっています。よって、エルゴン川=アルグン川だと推定できます。
「qui etiam supra dictum fluvium Sagalien Vla influit,」は「上に述べたサハリャン=ウラ川に流れ込む」。ロシア語版の説明だと、「アムール川に流れ込む」川となっています。中国語版でも同様に、「黒龍江に流れる」川と説明されています。ここからも、「Sagalien Vla」=「黒龍江」であると断定できます。
「qui」は関係代名詞なので、先程のフレーズと合わせて「上に述べたサハリャン=ウラ川に流れ込むエルゴン川と呼ばれる川」となります。
「limites ita constituet」は「境界をこのように設定する」です。
「ut omnes terrae quae sunt ex parte meridionali ad Sinicum」は「南部以降の全土は清へ、」。「南部以降」だと日本語がおかしいので、「南部全土は清へ」でいいでしょう。
「quae vero sunt ex parte boreali,」は「しかし、北部にあるものは」となります。先述の「meridionali」と「boreali」は対称の関係にあるのでしょう。
「ad Ruthenicum Imperium pertineant :」は「ロシアが所有する」となります。先述の文と組み合わせると、「北部にあるものはロシアが所有する」となります。
「et omnes aedes」は「そしてすべての建物は」。
「ex parte dicti fluminis meridionali in faucibus fluvii nomine Meyrelke extructae」は、「先述の川の南にあるメィレルケと呼ばれる川の河口に建てられた」となります。長いですが、この部分が「omnes aedes」の説明になります。
また新しい川が出てきました。ロシア語版には記述がありませんでした。中国語版だと「墨勒克河」と表記されていました。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/239450/1/shirin_080_5_714.pdf
上記の論説によると、黒龍江将軍サプスが「メリルケン川」へ調査に行ったという記述があります。おそらく、これが「メィレルケと呼ばれる川」なのではないでしょうか。
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA81808064
こちらがサプスの一次史料らしいので、機会があれば読んでみようと思います。
「sunt ad littus boreale transferentur.」は「それらは北側の沿岸に移される」。
動詞の語尾に「ntur」が付いているものは三人称複数の受動態です。
全部繋げてみます。
「これについては、両帝国の使節がそれぞれの国へ帰還した後、正式に調査して明確に認識し、特使または書簡によって後日決定される。上に述べたサハリャン=ウラ川に流れ込むエルゴン川と呼ばれる川を国境として設定し、南部全土は清へ、北側はロシアが所有する。また、先述の川の南にあるメィレルケと呼ばれる川の河口に建てられたすべての建物は北側の沿岸に移される。」
要するに、ネルチンスク条約で中露国境はすべて確定しなかったということです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
