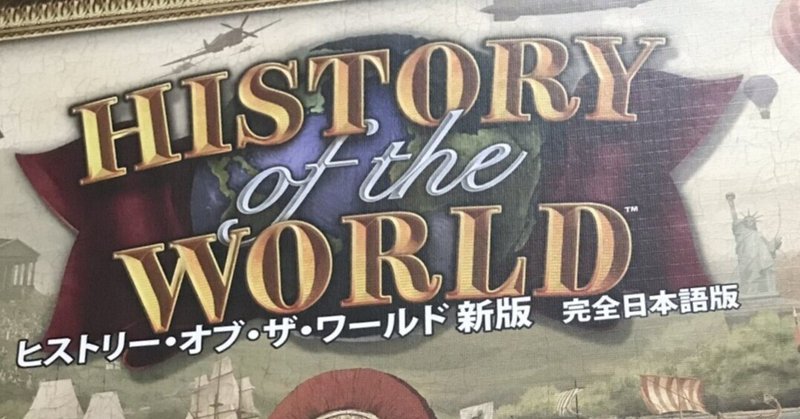
【ヒストリー・オブ・ザ・ワールド】10月29日の自分のプレイを世界史的観点で見てみた
はじめに
今回プレイしたボードゲームはこちらです。

「ヒストリー・オブ・ザ・ワールド」です。
今回は、こちらのボドゲにおける自分のプレイから、世界史との比較をしてみたいと思います。
なお、プレイに夢中で最後の写真しか撮っていませんでした……。文章ばかりになりますが、お付き合いいただけると幸いです。
どんなゲームなの?
箱に書いてあるとおり、「3~6人でできる世界征服ゲーム」です。
ざっくり言うと、古代~近代に実在した国家・民族を操作して、合計でできるだけ多くの陣地を得ることを目的としたゲームです。世界地図を舞台にした陣取りゲームって感じです。
目安のプレイ時間は2~3時間とのことでしたが、6人でプレイしたところ、全然終わりませんでした!5時間かけて4/5しかプレイできませんでした……。初プレイの方は参考にしてみてください!
アクション自体はとてもシンプルなのですが、考えることが非常に多く、頭を捻らせながらプレイしました。しかし、その場にいた全員が「面白い!」「もっとやりたい!」と言ってくれました!
現在は市場にあまり出回っていないようです。私はヤフオクで8000円ほどで競り落としました。
このボドゲにおける「時代」と「帝国」
このボドゲは、ラウンド(以降、時代と呼びます)ごとに自分が担当する国家・民族(以降、「帝国」と呼びます。なお、ゲーム上の用語であって実際の帝国ではないことをご了承ください)をドラフト式に選択します。
よって、各人がゲーム内で合計5つの「帝国」をプレイすることになります。
この時代からとても練られていて面白いです。どの「帝国」を選んだかによってプレイ順とスタート位置が決まるのですが、これがおおよそ現実の時代順になっているのです。
以下に、時代ごとの「帝国」を紹介します。
時代Ⅰ
シュメール文明
エジプト文明
ミノア文明
ヒッタイト帝国
アッシリア帝国
殷
十六大国
ギリシア文明
時代Ⅱ
スキタイ王国
アケメネス朝
カルタゴ
ケルトの女王国
マケドニア帝国
マウリヤ朝
漢
ローマ帝国
時代Ⅲ
ササン朝
グプタ朝
東西ゴート王国
フン帝国
唐
イスラム帝国
フランク王国
時代Ⅳ
ヴァイキング
セルジューク朝
モンゴル帝国
明
メソアメリカ文明
オスマン帝国
ポルトガル海上帝国
スペイン帝国
時代Ⅴ
ムガル帝国
清
ロシア帝国
フランス帝国
大英帝国
アメリカ合衆国
ドイツ帝国
大日本帝国
以上、ルール上ランダムでゲームから除外される「帝国」はあるものの、おおよそ上から下まで順番に「帝国」が建国し、侵略や領土拡大を行っていきます。これにより、A国が侵略した後にB国が攻めてきて……という関係が非常に上手く再現されています。
また、メインとなる「帝国」以外にも、属国となる「王国」をプレイすることもあります。そちらも史実に沿っていて面白いです。
では、ここからは本日の私のプレイから、実際の世界史との比較をしてみたいと思います。
時代Ⅰ
とりあえず、一番マイナー(?)そうな「アッシリア帝国」を選んでみました。
バビロンの空中庭園で有名ですね。世界の七不思議にも出てきます。もちろん、ボドゲの「世界の七不思議」にも登場します。
まず、「王国」として「ハラッパー文明」を使い、インダス区域を獲得しました。
史実ではインダス川上流、現在のパキスタンあたりに存在した遺跡の名称です。インダス文明の中の一つです。都市遺跡の名称なので、この中に色々な遺跡があります。有名なモエンジョ=ダロもこの一つです。
さて、ゲームの話に戻ります。
アッシリアはメソポタミア区域からスタートしました。しかし、既にシュメール文明などができていたため、中東は激戦区でした。
しかし、戦争をしかけて他の区域も獲得し、見事中東の覇者となりました!
史実では100年も持たずにアケメネス朝ペルシアに滅ぼされてしまいますが、どうなるでしょうか……?
時代Ⅱ
時代Ⅱではスキタイ王国を選択しました。
スキタイは、現在の南ロシア・ウクライナ周辺の広範囲で活躍した騎馬遊牧民族です。
ボドゲ「インペリウム:帝国の時代」にも登場します。こちらの記事はまだ書けていません……いずれ!
取り敢えず属国となる「王国」を獲得するのが強いかな?と思い、「マヤ文明」を選択することにしました。
この時代では北アメリカの区域を獲得しても点数になりませんが、いずれアメリカが発展した時に使えるかなと思って使いました。
「マヤ文明」は、特殊効果「チチェン・イッツァ」で得点となる「記念碑」を置くことができます。
「チチェン・イッツァ」とは、ユカタン半島にあるマヤ文明の遺跡のことです。

ククルカン(ケツァルコアトル)を祀るピラミッドが有名です。
FGOでも出てきましたね。
話を「スキタイ王国」に移します。
彼らは特殊効果「カタフラクト」を持っています。簡単に言うと、戦闘を行うと普段より多くの区域に侵攻できるスキルです。
「カタフラクト」とは、古代に存在した重騎兵のことです。調べてみると、これが実在したのは古代末期、ローマ帝国や東ローマ帝国などの時代のようですが……。
「アーマード・コア6」の強敵の名前としても使われているようです。
「カタフラクト」を使いながら、再び中東をひた走りました。世界市場では、騎馬遊牧民族は急に現れて略奪をしていくイメージが強いので、そのイメージが再現されていて感動しました。
中東だけでは得点が増えないので、他の地域にも足を伸ばしたり他のプレイヤーの邪魔をしたりしました。
史実と比べると、ちょっとスキタイ人暴れすぎですね笑 こうした史実と違う展開が見られるのもこのゲームの醍醐味です。
時代Ⅱの後半で、他プレイヤーが「ローマ帝国」の多数の軍を率いて各地域を蹂躙していきました。
特に、「カルタゴ」が制圧していた北アフリカの区域を「ローマ帝国」が侵略するシーンは、ポエニ戦争におけるカルタゴの敗北の再現を目の当たりにしているようでした。
時代Ⅲ
いわゆる、中世と呼ばれる時代です。
私が担当した「帝国」は、「東西ゴート王国」です。
史実では、ローマ帝国を滅亡させる一因となった出来事「ゲルマン人大移動」の「ゲルマン人」の一つです。東ゴート人と西ゴート人とに分かれており、彼らがまとまったことはなかったはずですが、このゲームでは便宜上か一つの国とされています。
ちなみに、ローマ帝国をゲルマン人大移動から防衛するボドゲとして「パンデミック:ローマの落日」があります。もちろん、東ゴート人と西ゴート人も登場します。
お馴染みの「王国」も使いました。今回は「ムーア文化」です。
ムーア人とは、中世の北アフリカやイベリア半島、シチリア島、マルタ島などに住んでいたイスラーム教徒のことです。
イスラームがアフリカに伝わるのは7~8世紀、つまりウマイヤ朝の頃です。
時代Ⅲの中には含まれますが、ゲルマン人大移動が起こった4~6世紀には当てはまりません。まあ、どの「王国」をどのプレイヤーが使うかはそのゲーム次第なので、この辺は誤差です。
さて、このムーア人ですが、血筋や語族、文化などを同一にする明確な民族ではありません。あくまで、キリスト教徒が違う文化圏の人々の総称として用いていただけです。よって、「ムーア文化」とは何かはなんとも言いがたいです。ムーア人はアフリカから来たので、スタートがマウレタニア(北アフリカのムーア人の居住地域)なのは納得です。そこからあと3コマ他の区域に歩を進めるができるので、そこでムーア人がヨーロッパに広がることを表現したかったのかなあ、と思いました。
さて、これでカルタゴやローマの区域をムーア人が獲得してしまいました。実際、中世では既にローマ帝国もそれに属していたカルタゴも滅亡しいるので、史実通りに動いていますね。
メインの「帝国」、「東西ゴート王国」に移ります。
多くの手数で周りの国を蹂躙するプレイスタイルです。
特殊効果に「遊牧民」とありますが、ゲルマン人は遊牧民ではないですね……。遊牧民族フン人に追われてきたのがゲルマン人です。なぜここだけずれている……?
もちろん、史実通りローマ帝国が保有する区域をたくさん獲得しました。史実通りでにっこりです。
ただ、そんなゴート人たちの国は東ローマ帝国やイスラーム帝国により滅ぼされるのが史実です。その通り、東ローマ帝国にボコボコにされました。スキタイとゴート人たちと一緒に広げてきた我が領土は、あっという間に無くなってしまいました。
時代Ⅳ
時間の都合上、これが最後の時代になりました。
私が担当した「帝国」は「ポルトガル海上帝国」です。
世は大航海時代。スペインとポルトガルは香辛料などを求めてインドへ至るルートを探すため、国の威信をかけて航海士たちに冒険させていました。その中で見つけた新大陸を占領し、アメリカ大陸と名付けたのであった……。というのは有名な話でしょうか?この時代の航海士としてはコロンブスなどが有名です。
ひとまず、「王国」カードを使いました。インドの「チョーラ王朝」です。
大学受験のために世界史を受験していたときは、南インド史が苦手でした。どの国も影が薄いので……。しかし、改めて勉強してみると、チョーラ朝はローマとも交易するなど交易で栄えた国であることを知りました。始まりは紀元前3世紀、一度3世紀に滅びるものの9世紀に再興され、13世紀まで続きました。合計すると、かなり長く栄えた国と言うことになります。
さて、いよいよ「ポルトガル海上帝国」の出番です。
ここまででかつて私が獲得した区域はほとんど失われているので、大航海時代らしく多くの地域に少しずつ進出して得点を稼ぐ作戦にしました。
ゲーム上、普通は海の上を移動できません。しかし、「ポルトガル海上帝国」は例外で、東太平洋以外はほぼ全ての海を渡ることができます。すごい!
北米、南米、ユーラシア、中東に進出してみました。まさに大航海時代の再現です!
ちなみに、各「帝国」カードの上部には、その「帝国」で有名な君主の名前が書かれています。「ポルトガル海上帝国」はマヌエル1世が消化されています。彼の名前を聞いて思い出すのは、ボドゲ「アズール」です。「アズール」は、プレイヤーがマヌエル1世に頼まれて宮殿の壁を飾る……というストーリーになっています。
おわりに
プレイに関しては、ほぼ記憶だけで書いています。矛盾などあったらすみません!!
「ヒストリー・オブ・ザ・ワールド」は世界史を知らない方でも陣取りゲームとして楽しむことができますが、世界史を知っていると目の前で世界史が再現されているような気分になり、楽しさが倍増します。
時間があれば、区域名や他の「帝国」についても説明する記事をつくってみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
