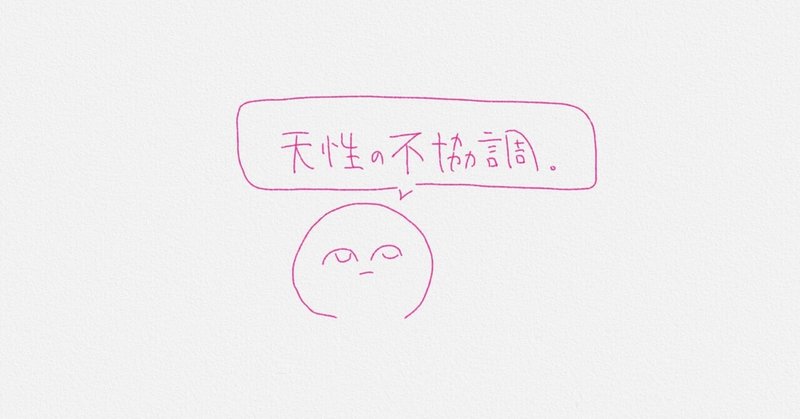
二 不登園児は語らない(けど水鉄砲は好き)
私は幼稚園が好きではなかった。
というか、家が好きすぎるあまり、外に出るのが嫌いだった。
少しずつ自他境界が見え始めた頃の私にとって、家というのは、自分をこの世界の全ての不安から守ってくれる唯一の場所だった。
家に居れば、何の心配もない。
その一方で、ひとたび家の外に出ると、いいようもない不安の霧が私をとりかこんだ。
家は私の母国だった。
家の外に一歩踏み出せば、そこはもうよその国だった。
私はこの母国に永住するつもりでいた。
ずっとここにいれば、衣食住が保証されるし、身の安全は守られるし、こわい人に怒られることもない。
けれども私は、幼稚園という装置によって外へと引き摺り出された。
そこはとても奇妙な場所だった。
私と同じような背の高さをした人間たちが、みな同じように言葉を発したり、歌をうたったり、絵を描いたり、縄を飛んだりしている。
普通に考えて、各々にはそれぞれのタイミングでそれぞれのやりたいことがあるはずなのに、けれどそこにいる人たちはみんなで、同じ時間に、同じ行為をしていた。
私には、それができなかった。
馬鹿らしかったからとか、納得できなかったからとかではない。
ただ自分が見知らぬ世界にいるという恐怖だけで、体が動かなくなってしまったのだ。
その世界では、見知らぬ大人が指示をして、見知らぬ子どもたちが一斉にそれに従っていた。
それが何のためであるのか、誰のためであるのか、私には何もわからなかった。
常に自分のしたいことをしていた私にとって、その世界は全くルールのわからない異郷の地で、私はそこを訪れるたびに路頭に迷った。
例えるならそれは、『千と千尋の神隠し』の、神々の世界に迷い込んで慌てふためきつづけて結局最後までどうにもならなかった世界線の千尋のようだった。
私には、慌てずにハクの言うことを聞く冷静さも、「ここで働かせてください」と声を発する度胸もなかった。
幸い私は、もとの世界(家)へは容易に帰ってくることができたから、名前も両親も奪われずに済んだのだが。
とはいえ、じゃあまたあの世界へ行こうかという気には当然ならないわけで。
異世界たる幼稚園を支配していた命令と服従という奇妙な秩序、そして私と同じ立場であるとされた小さな人間たちが漂わせていた妙に活発で躍動的な空気感に馴染めぬまま、私は幼稚園に通いつづけた。
否、あんまり通わなかった。
まあ当たり前かもしれないが、ほとんど記憶がない。
みんながプールに入っているのを椅子に座って眺めていた記憶、
みんなが縄跳びの試験をしているのを庭に突っ立って見ていた記憶、
みんながなにかを歌っているのを後ろで聴いていた記憶、
ああ、こんなのばっかりだな。
それからよく覚えているのは、年長の頃の担任が不登園気味の私を気遣ってくれて、登園するたびに列車の写真のシールをくれたことだ。
私は列車が好きだった。
同居する祖父の部屋で鉄道模型を走らせるなどという随分とブルジョワな趣味も持っているくらいには好きだった。
私は先生からもらったシールを、専用の小さなノートに貼っていった。
先生は卒園の日に、竹を模した見た目の水鉄砲をくれた。周りに内緒で。
なぜそのチョイスだったのかはわからないが、ともかく嬉しかった。
だって水鉄砲だぞ。
しかも竹だぞ。竹の柄だぞ。
ぜんぜん意味はわからないけど、竹なんだぞ。あの硬い竹だぞ。すごいぞ。硬いぞ。
棒を押し込んだ圧力で竹筒から水を放つタイプの水鉄砲なんだぞ。
ところてんと同じ仕組みなんだぞ。
ところてんを作る用のやつなのかもしれなかったんだぞ。
そう考えるとなかなかいいチョイスだなあ。
しかしあいにく、ところてんを作る機会はその後一切訪れず、竹水鉄砲はしばらくのあいだ、風呂場で水を放ち続けた。
だんだんガタがきて、竹筒の上部に長いヒビが入ったりした。
そのヒビから水が放たれたりした。
正面から出る量よりもヒビから出る量のほうが多かったりした。
その様があんまり不格好なので、もうそれを見るために水を放ったりしていた。
それ用のおもちゃだった。
水ぶちまけマシーンだった。
やがてとうとう使い物にならなくなったその装置は、ひっそりとどこかのタンスに仕舞われた。
ああ、愛しきあの装置。
私の幼きころの思い出。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
