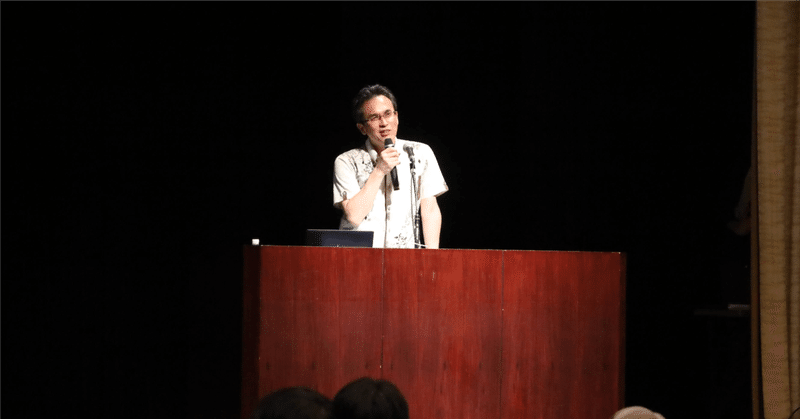
【オンライン哲学講座】 「普通」ってなんだろう。 【服部奨学生レポート】
イベントについて
第15期奨学生、静岡大学教育学研究科修士2年の竹下琴里です。2023年6月17日(土曜日)に、愛知県碧南市「哲学たんけん村無我庵」で、服部財団選考委員の梶谷真司先生(東京大学大学院総合文化研究科教授)をお招きした哲学講座が開催されると聞き、オンラインで参加してきました。講座のテーマは「普通ってなんだろう?」です。

哲学講座(以下、哲学対話)とは、その名の通り哲学的なテーマについてグループディスカッションをすることです。教育現場で使われることも増えていて、私が教員を目指していることもあり、この機会に参加することにしました。学校では、円を描くように座り、コミュニティボールと呼ばれる毛糸の丸いボールを回しながら進めていきます。今回はオンライン開催だったので、ZOOMの挙手やリアクション機能を使うことで対話をしていきました。

発話者の膝に置かれた毛糸玉がコミュニティボール
哲学対話のルール
哲学対話は、ただの議論とは異なり、以下のルールに則って行われます。
・ 何を言ってもいい
・ 否定的な態度をとらない
・ 発言せず、ただ聞いているだけでもいい
・ お互いに問いかけるようにする
・ 知識ではなく、自分の経験にそくして話す
・ 話がまとまらなくてもいい
・ 意見が変わってもいい
・ 分からなくなってもいい
これらのルールによって、参加者は自分自身の経験や意見、考えた事を何を言っても受け入れてもらえる安心した環境の中で共有することができます。

哲学対話スタート! : 普通についてあなたは何を考えますか?
哲学対話がはじまり、私たち参加者は「普通とは何か」について共有しました。大学生からお年寄りまで、さまざまな年代の方がいらっしゃることで「普通」への考え方が、経験や普段の環境によって大きく違っていることに驚き、新たな発見も多く充実した時間となりました。
さて、この記事を読んでいる方は「普通」をどう考えますか? 我々が、日常生活で頻繁に使うこの言葉には、どのような意味が込められているのでしょうか? また、我々はどのような意味を込めて使っているのでしょうか?
私たちのグループでは、まず「普通」の使われ方に注目して対話しました。以下、参加者の言葉をご紹介します。
犯罪が起きると、メディアが近所の人々を取材します。彼らはよく『あの人は普通の人でした』と使いますね
ここで言う「普通」っていうのは、〈そんな事をするようには見えなかったけど、普通の範疇から逸脱してしまった〉という意味を込めた、対比として使われているんじゃないでしょうか
「普通」って、自分の価値観で測った ”ものさし” で、必ずしも世間一般を指す言葉じゃないのでは
「普通」とはこうであるべきだ!という、ある種の期待を込めて使ってしまっているんじゃない?
あと「普通に可愛い」「普通に美味しい」のように副詞としても使われていますよね
普通に美味しいって言うけど、あれって結局のところ、美味しいの? 美味しくないの?(笑)
お笑いの世界でも「普通」って使われてますよね。例えば、お笑い芸人の永野のネタ「ゴッホより普通にラッセンが好き~」なんて。
このネタは「普通に」という言葉があることによって面白みが増す使われ方ですよね。進化を促すキーワードなんじゃないですか?
このように「普通」について考えた事を、一人一人共有していきましたが、誰一人として同じ意見の人はいませんでした。それぞれが経験だけを頼りに話しても、何でも受け入れてもらえる環境だからこそ、ここまで多様な意見が出たように思えます。
対話の後半では、「普通」という言葉はポジティブに使われているのか、それともネガティブに使われているのか?「普通」は「常識」と同義なのか?もし「常識」と同じなら、常識は「ある」もしくは「ない」で表現されますが、「普通」にはそれが適用されるのか…? と、どんどん対話は進んで行きました。
時間をかけて繰り返し問うことで、何気なく用いている言葉の一つに、深い意味があるということを知りました。一つの問いに皆で向き合うことで、一体感も生まれました。無数の答えがでる哲学対話は、議論を深めていけばいくほど、意見と意見が足し合わせされて、新たな考えが出来上がっていきます。この様子はまるで錬金術のようでした。繰り返し問うことの必要性や、時間をかけて考えることで、ぼやけていたものがクリアになっていく。そんな感覚はなかなか味わえません。参加者一人一人の考えからバトンがつながっていき、「普通」という言葉が持つ可能性、意味の広がっていく様子を体験することができたように思います。
イベントに参加して
やっぱり人と話すのは楽しい!この一言に尽きます。「普通」について一人で考えていたとしたら、今回の対話で出てきたような意見は到底考えつかなかったと思います。私たち一人一人は、自身の経験、価値観に基づいて「普通」を理解し、普段から使いこなしています。しかし、それは必ずしも全体像を捉えているわけではなく、一部分でしかありません。対話の中で、他の参加者の持つ視点を取り入れることにより、「普通」という単語の意味の広がりや相関をより理解することができました。
また、普段は言葉の意味をここまで考えているわけではないことにも気付かされました。私たちは、「普通に可愛い」「普通の人」など、日常的に「普通」という言葉を使いますが、その背後にある意味や、その言葉を使った時に、他の人がどう考えるか、どのように影響を与えるかについては、ほとんど考えていないように思えます。ひょっとすると、「普通」以外にも「常識」のように、無意識に自分の物差しで定義して使っている言葉があるのかもしれません。この哲学対話イベントでは、私たちが無意識に使っている言葉について、その意味を再考するきっかけにもなりました。
そして、何よりも哲学対話を経験し、哲学対話がとる形式に魅力を感じました。年齢も環境も様々な人々が一堂に会し、一つのテーマについて、自由に、かつ深く考えて意見を交換していく。そして、そこから新たな視点や洞察が生まれ、自分自身の理解が深まっていく。これは、たとえ同じ人が集まって同じ事をしても、二度と再現することはできないでしょう。偶然居合わせた人々と、一緒に議論を重ねて、新たな視点を得ることの面白さ、その対話が生み出していく数々の考えは、哲学対話ならではのお土産のようなものです。
碧南市でのこのオンライン哲学講座は、言葉に対する新たな理解と、対話の持つ力を再認識させてくれる、大変貴重な機会となりました。
その後の「座談会」を通して
服部国際奨学財団から参加した、14期服部奨学生の樋廻さん(学部2年)と、西山さん(学部1年)、事務局の鹿島さんの4人で、講座後に座談会を実施しました。

哲学対話では、さまざまな年代や環境の方と話し合えることの面白さを知りました。その後の座談会では同じ奨学生の樋廻さん、西山さん、事務局の鹿島さんと、少人数で「普通」について考えたことを共有する、非常に濃密な時間でした。境遇が違う人たちだからこそ、多様な意見が生まれるので、留学生も多い財団で実施すれば、国際性豊な面白いイベントになりそうです。座談会の詳しい内容は、後日公開されるそうなので、楽しみにしています。
(文責:竹下琴里 第15期奨学生)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
