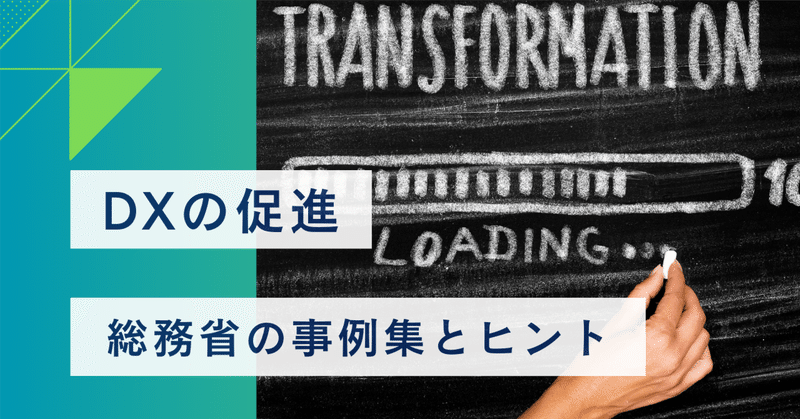
【DXの促進】総務省の事例集とヒント
夜でもヒルタです。
私、晝田浩一郎はデジタル人材育成やDX(デジタル・トランスフォーメーション)の分野でも様々な支援をしています。
京都府等が主催するエキスポでも講演させていただいたり、様々な自治体で研修講師も担っております。アーカイブ動画があるので以下のリンク参照ください。
【「京都スマートシティエキスポ2022」での登壇】
「自治体職員向け企画 デジタル人材育成に向けて〜今求められる公務員とは〜」(2022年10月7日登壇)
いつでもお声がけくださいね!(宣伝)
それはさておき、総務省が『自治体DX推進参考事例集』を2023年4月28日に策定した旨の報道発表がありました。様々な自治体の取り組みが掲載されているので、自治体の方も民間企業の方も参考になりそう。弊社、株式会社官民連携事業研究所でコーディネータ・サポートさせてもらった事例もありました。ありがとうございます。
せっかく良い事例を共有しているんだから、資料作成にももうちょっとお金かけて見やすく・わかりやすい資料にしてくれれば良いのにもったいないなーーーーーーー、と感じました。総務省の職員ががんばってまとめたんだろうなっていう気概は伝わるけども。もうちょっと見せ方あるじゃんーーー、って。せっかくなんだから、せっかく広めていきたい事例なんだからデザインやみやすさについてもお金かけてほしいな、って強く思いました。頼むぜ、総務省。
近年、DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進が自治体のあらゆるところで必要とされ、様々な政策が実施されています。デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタル・トランスフォーメーションがあるんですが、このあたりは愛知県の資料『あいちDX推進プラン2025~デジタルで生まれ変わる愛知~』がわかりやすい。

DXを「業務効率化」と捉えている方もいますが、もちろん、間違っちゃいないです。間違っちゃいないけども、それだけじゃない。単なる業務効率化だったら、デジタイゼーションやデジタライゼーションくらいのお話。トランスフォーメーション…変革です。そもそも「ルール変えちゃおうぜ!」「当たり前を変えようぜ!」「これからの当たり前のつくろうぜ!」っていうことです。
「ルールなんか変えちゃえばいい!」っていうと、「ルールは守るべきものだ!頑なに何が何でも守るべきもの、それがルールだ!」っていう生真面目な人がいます。その考え方もいいんですけど、否定はしないけど。そういう考え方だからヨーロッパ等の欧州のルールづくりが得意な人たちにやられっぱなしになっているわけで……。時代も世の中も変わるんだから、それに合わせてルールも変えていけばいい。2040年にガソリン車新規販売禁止、とかなるわけです。
あらためて、DXの本質とはなにか。DXとは、単なる業務効率化を超えたデジタル技術の活用を通じて、組織や社会全体を「変革」すること。「トランスフォーメーション・Transformation」なんです。自治体においては、市民サービスの質や効率を向上させるだけでなく、経済発展や地域コミュニティの強化にも貢献することができる。利用者の方にもっと意識を向けて考えることができる。
様々な自治体がいろんな取り組みを実施しています。総務省の『自治体DX推進参考事例集』等の「事例」などを通じて、成功したDX推進の取り組みが共有されています。これらの事例を参考に、自治体はどんどん取り入れるべきです。 ただし、そのまま取り入れるのではなく、地域の特性やニーズに適応させることが重要です。同じ課題でも地域によって細部が微妙に異なるってことはよくある話。海外でキレイに咲いている花を日本にそのまま持ってきてもキレイに咲かないのと一緒。土壌も気候も違うんだから。しっかりと調整していくことが必要です。
色々と考えて、計画つくって、っていうのももちろんめちゃくちゃ大事なんですけど、まずは「やってみる」姿勢が大事。 DX推進には、まずは試行錯誤を繰り返しながら進める「やってみる」姿勢が欠かせません。自治体は、新しい技術やアプローチに対して柔軟な姿勢を持ち、失敗を恐れずに挑戦すべき。どんどん挑戦して、どんどん失敗すればいい。失敗からしか学べない。最悪なのは、失敗を恐れて何もしないこと。座して死を待つのみ、ってなっちゃうわけです。そういった自治体は市民に対して失礼。
もちろん、これは自治体に限らず民間企業やNPO等でも必要な取り組みです。デジタルツールをいれましょう、っていうわけじゃなくて!でも、便利な道具はどんどんと使えばいい。デジタルツールなんかただの便利な道具なんだから。
令和にもなってメールでコミュニケーションするんじゃなくて、チャットでコミュニケーションしましょうよ!ってことですよ。いつまでメール使っているのかと。市川博之さんの記事読んでほしい、ほんっと参考になるので。
「DX」は怖いものではありません。だって、家ではその恩恵を受けているじゃないですか。家では令和の家電や生活をしていながら、役所へはタイムマシンに乗って昭和に出勤、だなんていう笑い話があるほどです。住民や企業を含め、庁内の自治体職員の皆さんにも、「タイムマシンに乗って過去に行かせる」なんてのを、そろそろやめませんか?
DX推進は、単なる業務効率化ではなく、地域全体の活性化に寄与する取り組みです。各自治体は、事例を参考にしながら、地域に適応させたDX推進策を考え、積極的に取り組むことが求められます。これにより、地域社会の発展や市民サービスの向上が実現されていきます。自治体だけでがんばるのではなく、民間企業との連携・共創をしてはじめてできることもたくさんあります。自分たちだけでがんばろうとするのではなく、お互いの得意をかけあわせて取り組んでいきましょう!
さぁ、共創だ!
サポートありがとうございます! プレッシャーいただけたと感じてがんばっていきます!!
