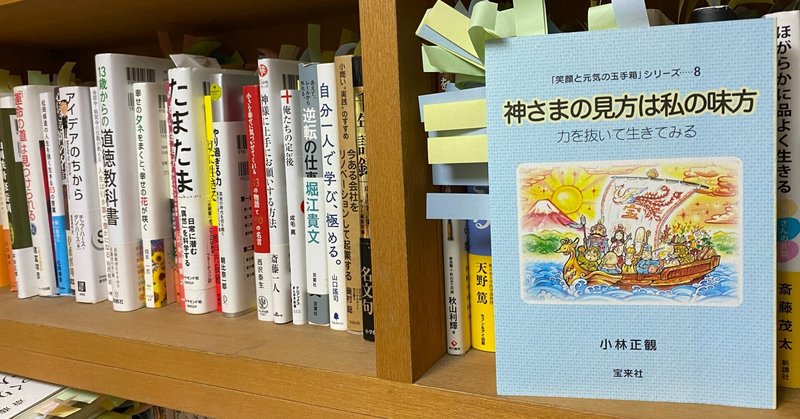
許容度180度の「ボーッとした人」
今日のおすすめの一冊は、小林正観さんの『神さまの見方は私の味方』(宝来社)です。その中から「自分がいかに恵まれているか」という題でブログを書きました。
本書の中にこんな興味深い話がありました。
ある学者、ガンになった人に対して、その食生活を調べてみたそうです。その結果食生活よりも精神的な原因の方が大きい、という結論になりました。なぜ、臓器がきちんとした解毒作用をしなくなるかというと、人間がストレスを感じたことにより臓器を痛めるのでしょう。ストレスとは、自分の思いどおりにならない、ということ。
ところが、宇宙にはストレスという現象は存在していません。「私」がストレスを感じた瞬間に、初めて宇宙にストレスが生まれるのです。例えば、ある人が目の前を通りすぎて行きました。その人に対して「私」が何も感じなかったら、この人は単に通り過ぎるだけの人。次の人が来たとき、その人に対して「私」がイライラを感じた瞬間に、この人は「私」をイライラさせる人になりました。
平均的な人間の許容度、許容量を扇子に例えて90度とすると、イライラしてストレスを感じる人は、心の広さが20度、30度、40度というように狭いのかもしれません。そして、自分の価値観の外にいる人を、自分の価値観の中に連れてこようとする。しかし、その人たちをコントロールできないときイライラを感じます。
そのとき、もう一つの解決方法があります。そこにいる人を、「私」が認めてしまう。すなわち、受け入れるということ。「私」の心が広くなってしまったら何も問題がない。今、心の広さが60度くらいの状態で、まだ許せない人や自分の価値観の外にいる人が現れたとします。そういう人がいてくれたお陰で、「私」は許容度・許容量を広げることができて嬉しい、有り難い、と思うと心が広がります。
さらに、自分の価値観の外にいる人を全部受けれ入れてしまったら、心の広さが180度になるでしょう。このように180度に広がった人を「ボーッとした人」、「あるいは「ボート部の人と呼ぶことにします。
逆に30度、40度の狭い寛容度・許容量の中で生きている人は「ピリピリした人」。「ピリピリした人」は、自分の価値観や自分の思い込んでいる正義感、使命感が非常に先鋭的なので、自分の思いどおりにしようとする。例えば、毎日ジョギングをしているところに石があったりすると、かけ声を出しながら、この石を持ち上げて自分の道を確保しようとします。「あら、よっと」。「ヨット部」の人です。
それに対して「ボート部」の人は「オールあり」。「ヨット部」の人は、「オールなし」で、マストマストで生きています。「こうでなければならない」「ああでなければならない」という、そのマストに凝り固まっていて、自分も縛り他人に対しても厳しい。そして、「ヨット部」の人は、航海(後悔)ばかりしている。
九州の大分県に「咸宜園(かんぎえん)」という私塾がありました。儒学者である広瀬淡窓が設立し5000人という当時の日本で最大の塾生をかかえていたといいます。咸宜の意味は、「ことごとくよろしい」で、身分や階級にうるさい時代にあって、学歴、年齢、身分、性別を問わず、勉強の意欲があれば、誰でも入塾できるシステムだったそうです。
「ことごとくよろしい」という絶対肯定ですね。つまり、許容度が180度あるということです。すると、咸宜園のように全国から多くの人が集まって来るのですね。
許容度180度の「ボーッとした人」には限りない魅力があります。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
