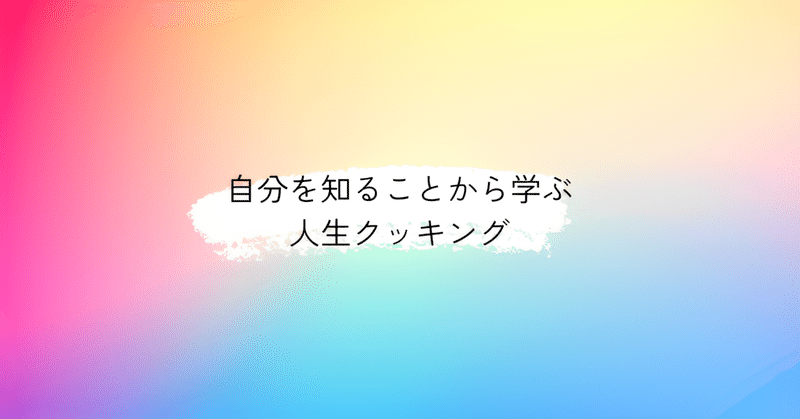
【人生クッキング #002】共感は自我の喪失に誘う
こんにちは!ひろげとんです。
前回の記事は上から飛べます。
今日は何を語ろうかなとトピック探しをしてはいたんですが、僕の内面を見る機会があってそこで自分には「共感力」に関しての能力が人一倍高いことを思い出し、じゃあそのことについて書こうと決めました。
タイトルを見るだけだと恐怖感漂う話に感じるかもしれませんが、決してそのような話だけではないということを分かっていただければと思います。
1. 第一の障壁

共感力というのは「他社の考えや意見にその通りだと感じたり、喜怒哀楽といった豊かな感情表現に寄り添うことができる力」の事です。
近年注目されているリーダーシップの在り方を書いた著書『サーバント・リーダーシップ』でも共感と傾聴が重視されています。
本記事では共感力がある話というよりは、共感することによる障壁とそれを打開するための施策について共有できればと思います。
「共感力が高い」の同義に「感受性が豊か」という言葉があります。
僕は小さい頃から感受性が高く、人の感情の機微を敏感に感じ取る性格でした。もちろんその性格による弊害もあり、とにかく疲れてしまうというのが一番でした。
人の顔色ばかり窺い、自分の意見を押し殺し、さらに引っ込み思案な性格も相まって悪い意味で靡いて生きてきました。この一連の性格や感情を当時は嘆いていました。
2. 共感力の中に感受性が内包されている

僕は大学生に入って「共感力」に対して3度考え方が変わっています。
1回目 : 大学2年生
「共感力と感受性は辞書ベースだと同義だが、実際問題に視点を向けると全く違う認識」
このことに関しては現在もそう思っている節はあります。
感受性の上位に共感力があると思っていて、感受性は人に共感するために必要なステータスであり、共感力は感受性がある前提での話で、共感することは一方的に相槌を打って相手の言葉を集中して聴きに徹することではないと思っていました。
もちろん聴きに徹することは大切ですが、それはスキルという要素でしかなくて相手の言葉に間違いがあるなら意見をしてみるのも大切であると考えていました。
この時代は共感力というのは一方通行の伝達ではなく相互補助の関係、つまり双方で成長するようにベクトルを上げていく作業が「共感力が高い」という表現だと定義していました。
僕もそう行動するように意識していました。
3. 第二の障壁

2回目 : 大学4年生~現在「共感は自我の喪失に誘うことであり、正義にも悪魔にもなり得る」
タイトルの通り、自我の喪失に誘われます。
何を言っているんだという話かもしれませんが、僕は相手に共感し続ける人生で1度自身のアイデンティティを失い、死にかけたことがあります。
「自己とは何者なのか分からなくなった状態」になり(自我同一の拡散とも言います)、単純に言えば頭がおかしくなってしまったのです。
まるで悪魔にでも身体を乗っ取られた状態のように性格まで歪みました。
正当に「共感すること」を評価できれば上記の状態にはならなかったとは思いますが、当時の僕にはそこまでの耐久力がありませんでした。
共感というのは相手の感情を繊細に読み取り、自分ごとのように受け取って咀嚼することで、ときにはお互いに成長するために議論を交わすことが正義だと思い込んでいましたので非常に疲れ果ててしまいました。
4. 学習結果

3度目
そこから禅問答のように繰り返し自己との対話を行い、その結果「共感するというのは相手の感情の質量や質感まで感じ取ることではなく、基本的に少しでも触れることができればいい」という考えに変わりました。
もっと解像度を上げると・・・
①相手が今どういう気持ちなのかに触れている感覚を育てる
②深堀りはしない
③感情の柔らかさや匂いや雰囲気を感じ取りたい場合は、そう感じとるに相応しい相手なのか見極める
この3つに集約されると思います。
5. まとめ : 共感力は鋭利でなく柔和であってもいい
僕は共感力は基本的にだれにでも備わっている能力で発揮させているかいないかの違いであると思っています。
そして共感力を発揮していると疲れる方は相手の感情を鋭く捉えないで欲しいです。一度立ち止まって穏やかに自分に優しく負担にならない程度に受け取ってみることが大切であり、真意であると僕は考えています。
最近はHSPなどという言葉も生まれていますが、言葉で片づけられるほど簡単な問題ではない壁に真剣に向き合ったからこそ言語化できる内容です。
皆さんは「共感力」はありますか?
生きづらい環境から脱却するためにも自分の意見をはっきりと述べられるようなコミュニティを探したり作ったりすることがこれからの時代では必要であると考えます。
「ライフ3.0」。結論は思い詰めないことです!
皆さん、どうでしたでしょうか?
何か意見などあればコメントいただけると大変嬉しいです!
では次回のNoteもお楽しみいただければと思います!
今後とも応援よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
