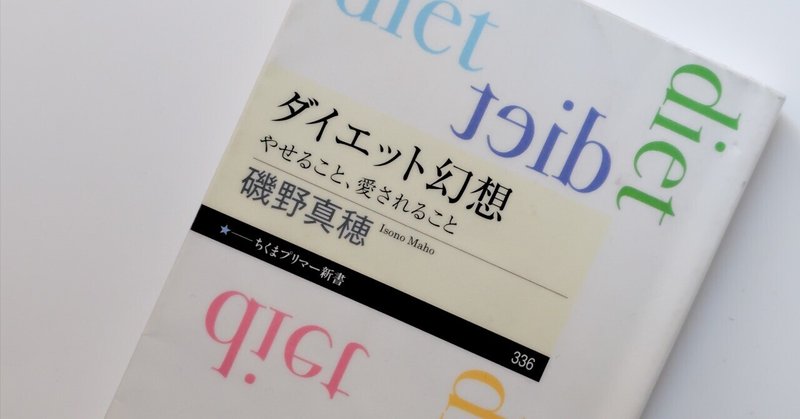
『ダイエット幻想/磯野 真穂』読了
新しい視点を得たような、ちょっと不思議な読了感。
食関連でつい最近知った磯野真穂さんは、文化人類学の研究者。
ダイエット。もとは単に「生活習慣」という程度の幅広い意味だったのに、いつの間にかそれが「痩せるための食事」に置き換わっている現代。なぜやせようとするのか、もっというと、「やせたいと思わされているのか」というそのロジックについて、人類学の観点からアプローチしているのがこちらの本。
端的に言って、とても面白かった。
開催したワークショップの中でのアンケートや、様々なインタビューをした結果の、それぞれの人の実体験をベースに検討・論考を深めていく手法。そして、自分ではなかなか気づかない視点からのアプローチ。考える手法がとても参考になって、そして得られる結論も示唆に富んでいた。
ここで内容を要約するつもりはないし、要約だけ読んでもたぶん詳細に理解することはできないと思うので、気になる人にはもう読んでもらうしかない。でも、もし「やせればもっと理想の自分になれる」というような意識があって、それが負担に感じてしまう部分がちょっとでもあるのなら、この本を読んで見る価値があると思う。
本屋で何気なく雑誌を眺めていたとき、女性向け雑誌コーナーでふと目に入ってきた言葉、「愛され◯◯」。自分もこの言葉を見て、なんだかとても違和感があったことは、確かに憶えている。
この本の中でも、ダイエットに走るこころの動きの理由を、この言葉の意味を読み解くことで明らかにしている。ここが一番面白かった(興味深かった)。
他には、シンデレラ体重。
そういう言葉があるとは知らなかったのだけど、結果的に自分はいま、このゾーンに入ってしまっている。やせたいと思っているわけではなく、むしろ体重増やさないといけないと焦っているくらいの心持ちなのだけれど。
でも、毎食けっこうな満腹感まで食べているつもり、それでも太らない。たぶん、やせたい人から見たら夢のような状況に見えるのだと理解はするのだけど、当人としてはこれはこれで困っている。病気の一種かどうか、とくに糖尿病かどうか等で病院にかかりもした。結果的にそうではなかったのだけど、予備軍ではある。
というのが自分の自分に対する理解で、だから、ダイエットに苦心している人たちとは心持ちは違うだろう、と思っていたのだけど。でもこの本にかかれていることは、自分にも当てはまっているものばかりのように思えた。
体重を毎日測って、数字で管理するのはなぜなのか?
そこに、増えすぎていたら困る、という心理はないのか? 自分にもあるはず。
食事を用意しているときから、あるいは外食であれば食事が出てきた瞬間から、これくらいの量だけ食べようと意識的に制限していないか? 自分もしているはず。
美味しそうなものがあっても、頭で考えて排除していないか?
栄養素として、何をどれくらいの割合でとらなければいけない。ファストフードは身体に悪いからやめておこう。清涼飲料水も、ポテトチップスも、ドーナツも、身体に悪い食べ物は極力避けておこう。そういう思考にとらわれていないか?
いちおう自分としては、自分の身体性を重視するように意識する、ということをやっているつもり。満腹感が出てきたところで食べるのをやめる、逆にそこまではしっかり食べる、とか。むやみに脂身を避けない、でも、最近は年齢のせいか脂のとりすぎは胃がもたれる感覚があるのでほどほどにする、とか。
最初に頭で考えて決めている、というよりは、身体に入れてみてどういう結果になったかを観察して、その次のアプローチを決める、というような意識を持つようにしている。
はずなのだけど、上に書いた通りで頭から決めている部分もあるなあ、と。
頭で考えて食べる食べないを決める、特に数字を重視して数字で管理してしまうことは、結果的に世界と関わる文脈や世界の彩りを消し去ってしまいかねない危険性がある。その逆として、身体で感じる美味しさを重視し、世界の彩り、仲間との関係性の中で生まれる美味しさや楽しさを重視する。
本の中ではこのようなことも述べられているのだけど、これを見たときに思ったのは、なんとなく、思考による理性で制御しようとする西洋的なアプローチと、身体性や感覚をもとに世界を理解しようとする東洋的というか仏教的なアプローチ、という対比構造と似ているように思えた。
このふたつは、本来どちらが良い悪いは無い。数字で理解することもある意味では必要で有効な面もあるし、身体性を重視して「今、ここ」を楽しむことの大事さもある。
それぞれをどう捉えて、自分の中でどういう風に使っていくかが重要で、そこには他者による評価は本来要らないはずで。
本当は、自分はどう在りたいのか。他者から規定される在り方ではなくて、本当にどう自分自身が思っているのか。その考えは本当に「当たり前」か。疑いながら、考えながら、常に自分のこころとからだに問いながら、微調整していくことが大切なのかな、と。
明確な答えが得られるわけではなく、新たな課題を感じながらも、でもなにか答えの芽のようなものが見え始める感覚。新しい視点を獲得したような、ちょっと世界がすこし開けたような感覚。
不思議な読了感を残す一冊だった。
P.S.
読了後、磯野真穂さんの記事などを探していたら、このような記事があった。
このような形で人間の食の多様性とその社会的役割を見てゆくと、サイエンスの旗を掲げて人間の食のあるべき姿を語ることは不可能であることがわかるだろう。日本人にとってのベスト、人類にとっての健康食という形で、ある食事法が一般化され始めたとき、その食事法は「科学」ではなく、「思想」になるのだ。
その思想に伸るか反るかは自由である。
ああ、本当にそうだ。
これだ、これなんだ。
自分も以前から似たようなことを考えていて。前にこのnoteでも書いたこともあった。
同じようなことが、もっと洗練された言葉で表されていて、ああなるほどそういうことかと妙に納得。
このあたりのこと、もっといろいろと知りたいというか、いろいろな人と議論とかしてみたら面白そうなのだけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
