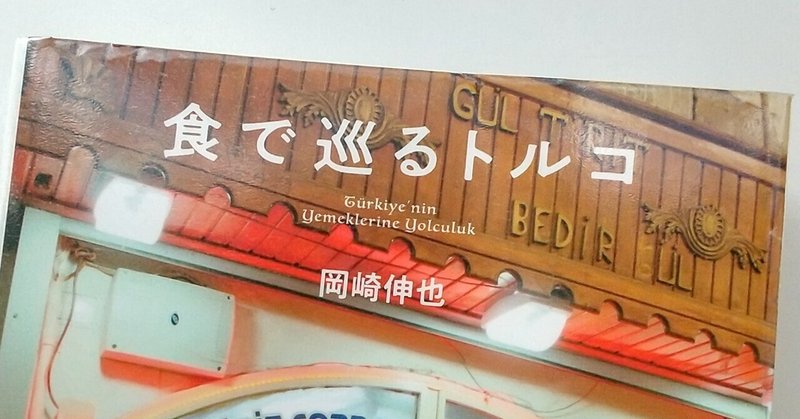
『食で巡るトルコ/岡崎伸也』読了
料理と共に、ぐるりとトルコを一周したような気分。
著者の岡崎氏は、バックパッカーとして訪れたトルコの料理に魅了され、帰国後しばらくの後に再びトルコを訪れて「食をテーマにトルコ全土を旅する」ことを目指す。本書は、まさにその通りに、トルコ全土81県それぞれの食を紹介する。
と同時に、多民族国家であるトルコで出会う様々な人との交流についても書き記されていて、その背景や民族の意識などもあぶり出している。民俗学のような側面ももった一冊になっている。
とりあえずボリュームが凄い。81県のそれぞれについて、名物だったり普段食べられている料理についてあれこれ紹介していくものだから、最初の10県くらいを読んだ時点で「これ、この後もずっとこのくらいの細かさで行くのか…」と軽くめまいがしたほど。
注意なのは、レシピが載っているわけではないこと。あくまでどう作られているのかの概要と、それにまつわるストーリーやどんなときにどうやって食べられているのか、という生活面に着目している。
紹介されている料理は、もちろん共通していてほんの少しの差異があるくらいのものも多いのだけれど、海に近いところや内陸部などその土地々々で何が採れているのか、といったことで左右されるローカルフードがたくさんあって興味深い。トルコはかなり広いこともあって、本当に多種多様。
途中で挟まれるコラムを読めば、より彼らの生活面のことがわかり、それが食事にどう影響しているのかも考えることができる。次々と現れる人々との交流を経て、それぞれを考えながら一緒に旅をしていうような気分になれるような、そんな不思議な本。
この本に載っている料理を見て、日本のトルコ料理店で食べられるものは本当にごく一部なんだということに改めて気付く。
利益を考えなければならない飲食店では、それは仕方のないことでもあるのだけれど、やはりどうしたって分かりやすくて、誰もが「トルコらしい」と思うような定番の料理に収斂していってしまう。いわゆるサイテキカイのような。なんとなく地味で見た目がパッとしなかったり、知名度がなかったり、分かりやすい美味しさがじゃない料理は、なかなかメニューに上がりにくい。
あとは、食材が手に入りにくかったりコストが高かったり。味つけが普通の日本人には受けないようなものだったり。塩味のきいたヨーグルトを餃子っぽいものにかけて食べる、というのは、普通の日本人からすると美味しいとはなかんか想像できない。(食べてみれば美味しく感じる人も多い、と思う)
この本に載っている料理の中でも、特にローカルフードだったり目立たない野菜料理だったりが面白くて仕方がない。どんな味がするのか、想像できないものが多くて食べてみたい。「ケールとお米やブルグルを煮てペースト状にしてから、黒胡椒・唐辛子・塩・バターで味を整えたもの。そこに合わせるのは必ずとうもろこしの粉で作った、ぎっしり詰まった硬いパン。パンは料理の上にほぐして、指で混ぜ合わせて食べる」とか、もうこんなのやってみたくてたまらない。
他にも、料理ができる過程のことを載せていることが多くて面白い。野菜売りから野菜を買って、肉屋に行ってひき肉とともに野菜を刻んで肉に混ぜてもらって、それをパン屋に持って行ってパンの上に載せて焼いてもらう、とか。単に料理がでてきて、その味はこうです、以上終わり、ではなくて、その背景にどんな生活があるのかといったことがわかる。
このnoteでも、少し前から「世界各国の食を巡る」ということであちこちの料理店に行っているわけだけど、なかなかこういうローカル仕様のものに出会うことが難しい。上で書いたような理由で仕方のないことなのだけれど、やっぱりどちらかというとこういう家庭料理というか、その土地で普通に食べられているアレコレをもっと紐解いてみたくなる。フランス料理やイタリア料理のようにメジャーなところから離れれば離れるほど、それは難しくなってしまう。
こうなってくるともう、日本に住んでいる現地の人の台所に伺うのが一番良いのだろうな、という気がしてくる。実際、そういう風にして紹介をしていたりされていたりする人たちのことは、ネット記事などでよく見るわけだし。ただ、そこまでの人脈と行動力は、自分にはないな、と思ってしまう。
その点では、著者の岡崎氏もすごい行動力と人脈。あちこちへ出かけ、現地の人と仲良くなり、その土地の家庭料理を見せてもらってこうして本にまとめている。それも400ページ近く。
その行動力と好奇心は、本当に尊敬の念しかない。
ああ、トルコへ行ってみたくなってきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
