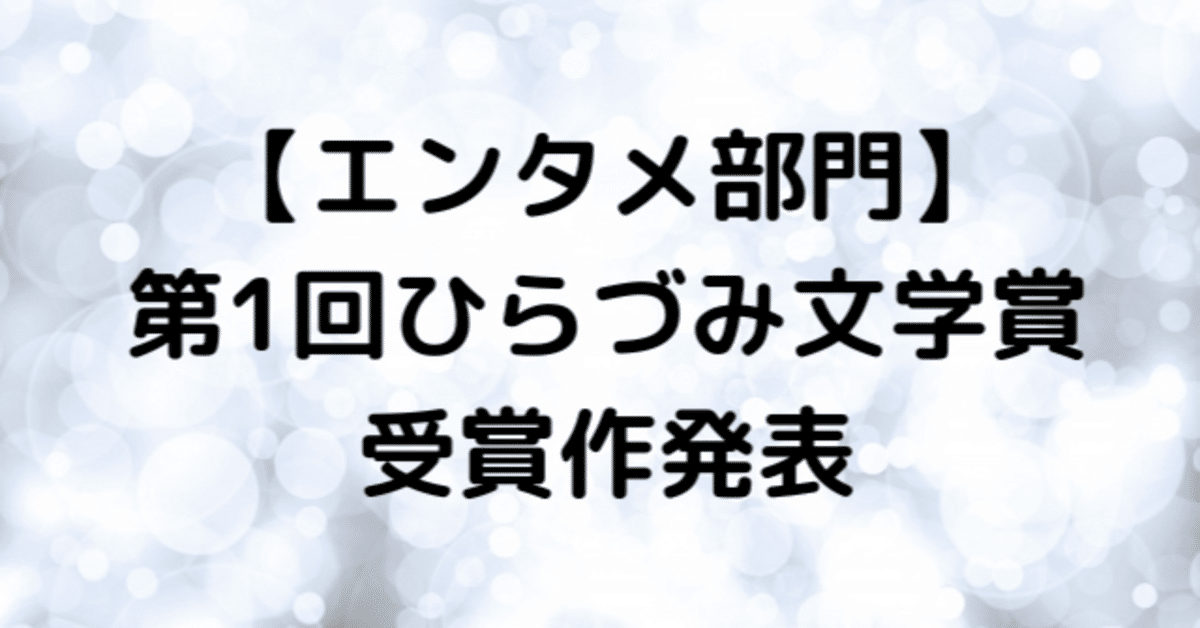
【受賞作発表】第1回ひらづみ文学賞/エンタメ部門
※当初は「大賞」1本、「優秀賞」3本を選出させていただく予定でしたが、審査の結果、急きょ「佳作」を設けさせていただいたことをご了承ください
【大賞】あいぞめ(田面類)
一
「し、失礼します。ゆずです。弟子の、渡井(わたらい)ゆずです」
月に二回は来ているのに、先生のお部屋に通されるときはいつだって緊張でいっぱいです。
埃のひとつもないぴかぴか障子に手をかけて開くとき、わたしの腕には見えない力がかかります。きっとそれは、『この先生に俳句のご指導を受けること』の重さで。高校の先生とは違う緊張感。放課後、わたしだけの俳句の先生。
でも、今日の緊張のわけはそれだけではなくて。
ここまで案内してくれた、先生の屋敷のお手伝いさんは、お庭に出ていかれました。わたしひとりです。それでも勇気を出して、わたしは障子をすうっと横に開きました。
「来たか」
右手に筆ペンを持ち、俳句用の短冊を見つめておられた先生。
しゃがれ気味のお返事。筆ペンのキャップが閉まる、カチッという音が鳴ったあと。トレードマークの藍染め浴衣と羽織を、ひょろりとした体格の関係でぶわりとはためかせながら、先生はわたしのほうへ向き直りました。浴衣も羽織も夜の海のように深い藍色で、染まり方も均一ではないので、はためくとまるで本物の波が立っているみたい。
角ばったべっこう眼鏡の奥で光るするどい目。突き出した鼻。とがった顔の輪郭。『猛禽類みたいね』ってうわさされていたのを聞いたことがあります。
そんな先生が、わたしのことをじいっと見ています。こわいとはもう思いません。なんてったってわたしは、弟子三年目になりました。それに――顔を合わせるたび、わたしを正面から見つめてこられる理由は、もう充分知っているので。
「こんにちは。離水先生」
「……ああ。ごきげんよう、ゆず君。今日はずいぶんと表情が硬いようだが。なにか気がかりか、それとも体調か?」
花山(はなやま)離水(りすい)先生。いかにも怖そうに、気難しそうに見える、高名な俳人の先生。でも本当の姿は、とてもお優しいのでした。
……それはそれとして。図星も図星で。
「それは」
思わず自分の左手を見てしまうわたしです。ぎゅっと握った、ベージュの手提げかばん。ふだん中に入れているのは、俳句用のメモ帳と筆記用具、あとはクリアファイルだけ。でも今日はそれ以外に、『俳(はい)星(せい)』という俳句の専門誌が入っています。学校からの帰り道、本屋さんで買ったもの。この中に、大事な賞の結果が載っているのでした。
離水先生も察されたようで、
「あー……とりあえず、その話はあとにしよう。座ってくれ」
「は、はい」
木目がきれいな座卓の、離水先生と向かい合う位置。先生はそこに敷いてある座布団を指さしました。
「まずは前回の課題だ」
「そうでした。ちょっと待ってください、取り出すので」
クリアファイルから短冊を一枚取り出します。前回の稽古で出た課題は、『季語「秋晴(あきばれ)」を上五に置いて一句』。季語――季節を感じさせるものや風景などの言葉――の指定に加えて、もうひとつ小さな縛りを入れたお題が、離水先生の課題の基本です。今回の縛りは季語の位置。
最初、俳句の五・七・五のそれぞれを上五(かみご)・中七(なかしち)・下(しも)五(ご)と呼ぶことすら知らなかったわたしは、この課題でたくさん鍛えられてきました。
「俳句ではことさらに語順が重要だ。十七音の短さの中で、どの順に情景・具象物を出していくのか。まず大きな光景を出し、そこからだんだん小さな光景にピントを合わせていく方法。反対に、小さなものにピントを当て、そこから大きなものへと情景を広げていく方法。大きな光景と小さな光景を対比するように、すっぱりと切り替える方法。やり方はさまざまある」
弟子になってすぐのお稽古で言われたことです。今回はきっと、秋晴という大きな情景・気候の季語を最初に出したあとで、どう展開するか。それを問われています。
短冊を出すときはいつも、自分でもびっくりするくらい腕が震えます。でも、この短冊が今のわたしの答えだから。弟子として恥ずかしくないように、先生の目をまっすぐ見るのです。
「これです」
作った句と、わたしが俳句を詠むときの名前――俳号を書いた短冊を差し出します。
「……なるほど。いつもの通り、自分で読み上げなさい」
「はいっ」
ひとつ、息を吸います。
秋晴に伸び上がりゆくクレーン車 四ツ国(よつくに)ゆず
人前に立つのは苦手です。授業で発表するのもやっぱり苦手。でも、わたしの句を披露するのはわたしの声じゃなきゃいけないので。ぼわぼわした声にならないように、大きく口を動かし、しっかりと読み上げます。
読み上げる間(あいだ)、背の高い離水先生のそっと見下ろすような視線は、絶対にわたしの顔から離れません。眉間にほんの少し寄ったしわ。ひと言も聞き逃さないという強い気持ちを感じます。
離水先生は、聞き終えてからしばらく目を閉じておられました。やがて――ごくり、と。先生の大きく突き出たのどぼとけが、小さく鳴ります。
緊張。緊張です。だけど――先生のくちびるがほんの少しゆるむのが、たしかに見えました。
「……いい句だ、ゆず君。腕を上げている」
「ほんとう、ですか」
「ああ。明快な光景を明快に詠んでいるが、ひとつ大きな工夫を感じる。『伸び』『上がり』『ゆく』と動詞を三つ重ねたことだ。本来なら『伸びる」だけでもいいところを。これは意識したか?」
「意識しました。動詞を積み上げたら、きれいな秋晴にどんどん伸びていくクレーン車を想像してもらえるかなあって」
「その狙いは成功している。情景も、クレーン車が伸びていく間のささやかな時間経過も見える。ただ、ひとつだけいいだろうか」
「はい。あの、どこですか?」
「秋晴『に』だ。僕なら秋晴『へ』にする。きみが表現したいのは広い秋晴に高く高く伸びていくクレーンだろう? それなら『に』より『へ』のほうがより遠く、より広大な場所を目指すイメージが出るはずだ。もちろん、秋晴『に』でも良句には違いないが」
「……ほんとだ。たしかにそうです」
「文章というのは、短ければ短いほど一文字、一語の重みが増していく。ゆえに十七文字の俳句では、一文字としておろそかにできない。その心意気で作るんだ」
繰り返し伝えていることだが、と断って、先生は噛みしめるようにおっしゃいました。
「はいっ。大事なことですから、何度でも教えてください」
「そうか。俳句を詠むとき、僕が一番大事にしていることだからな。きみもそうありたいというのなら嬉しく思う。俳句は、」
「『芸術の最小単位』」
「覚えていてくれたのか。そーなんだよ、僕はこの表現が俳壇や多くの詠み人に広がればいいと思っているのだが……どうしてか、ちっとも流行ってくれないんだ。俳句は誰でも気軽に始められるすそ野の広さを持つ一方で、一文字・一語を緻密に組み上げて作る、もっとも小さな芸術でもある。割合芯を食った表現だと思うのになあ……」
うなだれています。あの離水先生が、珍しく表情を崩してうなだれています。もにょもにょした声で不満そうにされています。
先生はときどき、こういう無邪気な姿を見せるのでした。
「わたしはその言葉、すきです。ちいさくて、複雑で、きれい。俳句にはそういうところもあるなあって最近思うようになってきたので。ちいさな芸術、そうだと思います」
本心です。なぐさめなんかじゃないです。
わたしの言葉を聞いた離水先生は、かすかに笑ってくださいました。
「ありがとう、ゆず君。恥ずかしいところを見せてしまったな。僕のキャラクターというのか、人格というのか。そのあたりは後世に残らずともよいと思うのだが。花山離水の作品と、俳句に対する考え方。このふたつだけは残せるようにしたい。すべては僕自身の努力にかかっている」
べっこう眼鏡をかけ直しながら、まっすぐな目でおっしゃる先生。でもすぐに、少しだけ表情をふわりとさせて。
「真面目な話に戻ってきたところで、だ。そろそろその雑誌を見ようじゃないか。僕だって楽しみにしているんだよ」
「は……はいっ。見ましょう、か」
正直に言って、覚悟はできてないです。俳句の大きな賞に応募するのははじめてだったから。
それでも、逃げているわけにはいきません。わたしは手提げかばんから俳句誌を抜き取りました。あとで全部読みますけど、今は結果発表のページだけ確認です。目次、もくじ……えーっと。
『第十七回綺羅(きら)星(ぼし)新人賞 結果発表』
これだ。四十三ページ。狙いを定めたら、ぱらっ、ぱらっとめくります。ぱらぱら、はできないです。やっぱりまだこわいので。
当季雑詠――応募時の季節の季語さえ使えば、あとはなにをどう詠んでもいいという形式――で五十句。それが綺羅星新人賞の応募要項でした。
当季雑詠はいいとして、問題は五十句詠むことです。それだけの数詠むのもわたしにはまだ一苦労だし、五十句をどういうまとまりにするかも応募者に任されています。なにかテーマを決め、それについて五十句詠んでもいいし、ストーリー仕立ての連作にしたっていいそうです。もちろんばらばらに五十句詠んでもいい。ただ、どれにしたってすごく大変なことでした。
でも、わたしは考えて考えて、今できることを全部しました。もちろん離水先生のお力は借りずに。だからどんな結果でも悔いはないはずですけど――やっぱりこわくて。
でも、ページをめくるのは止めません。いつのまにかわたしの隣に座っていた離水先生が、じっと見ておられますから。先生の両手はどこか祈るように重ねられていました。
えっと……ここだ。
『第十七回綺羅星新人賞 結果発表』
『応募者三八九名 受賞八名』
『満場一致の大賞、現る!』
どん、どどんっ、と大きな文字が座っています。わたしの名前、あるかな――
「……あ、」
離水先生の息を呑む音が、はっきりと聞こえました。
先生の骨ばった指が示す先には。
『奨励賞「わたしの青」 四ツ国ゆず(十五)兵庫県伊丹(いたみ)市』
そう、書いてありました。
「……ほんとう?」
そんな言葉しか出てきません。誌面を見て、先生の見開かれたお顔を見て、また誌面に戻る。ちゃんと確認してみても、本当のようでした。
奨励賞はあまり大きな賞ではなかったはずです。でも、賞をいただけたこと自体がとーってもうれしくて。
「ゆず君、おめでとう。ご両親にも、ご友人にも、胸を張って報告するといい。きっと喜ばれるだろう」
「は、はいっ。ありがとうございます、離水先生! 先生といっしょに歩けたおかげで、ここまで来られました」
離水先生のお声はいつも通り落ち着いているようで、うれしそうな色がほんのり見えていて。べっこう眼鏡の奥の目も細められていました。
「そうか。僕もうれしく思うよ。この歳で初めて弟子をとるという決断をしたのは、間違いではなかったようだ」
「えへへっ。……そういえば先生、どうして弟子を取ろうと?」
わたしが俳句を始めるずうっと前から先生はご活躍されています。わたしが一番弟子なのは前から不思議に思っていて、でもなかなか訊けなかったのですけど。今なら、もしかして。
急なわたしの質問にも先生は答えてくださいました。ゆっくり、ゆっくりと。お庭をまぶしそうに眺めながら。
「僕ももう四十八だ。だというのに未だに若手と呼ばれる俳壇が不安になってな。ひとつ、新しい風が吹いてほしくなった」
わたしのほうに戻ってきた、先生の視線。それは、はじめて見るような優しいほほえみで。どくん。心臓の音がひとつ、大きく聞こえた気がしました。
――新しい風。わたしが、それになれる?
少しだけ、ぼうっと浸ってから。講評があるのでそれも読みます。
奨励賞はいちばん小さな賞のようで、賞品は賞状と三千円ぶんの商品券。だけどその割に、わたしの作品の講評は大賞と同じくらいの長さです。……どうして? しかもわたしの作品の講評、安仁屋(あにや)露(ろ)山(ざん)先生です。本屋さんの俳句コーナーをのぞけばいくつもご著書を見つけられるほどの、高名な先生。
とにかく、読み進めなきゃ。
審査員講評(安仁屋露山先生)
十五歳。当新人賞の応募可能年齢、その下限である。だが年齢をいちいち取沙汰せずとも、鮮烈な才能であるのは明らかだ。ひらがなと漢字、カタカナの使い分け、明快な描写、「胃薬のやう(よう)ににがくて蝉時雨」の句に代表される巧みな比喩と、素直な感情の切り取り。加えてリズム感とさりげない音韻。どれも一定以上の水準であり、「古き良き」と今どきの青少年らしい「新しき」を兼ね備えている。そのうえ、俳句の柱ともいえる『季語』をいかにして引き立てるかへの意識もうかがえる。受賞に推すことにためらいはない。
しかし、である。この五十句はいささか、俳人・花山離水氏の影響を受けすぎてはいまいか。加えて、離水氏の域にはまだ遠い(年齢を考えれば至極当然とも言えるが)。この作者が離水氏に師事している事実を勘案してもなお、見過ごせはしなかった。金賞や銀賞ではなく奨励賞に落ち着いたのはそれゆえである。
たった十七字の中に無限の可能性を秘めているのが俳句である。どのような表現もできうる。どれほどの尊敬や感銘がその背後にあろうとも、特定人物の句風の模倣に身を落ち着けるのはあまりに勿体ない行為であると、私(わたくし)自身は思うのであるが。貴女は今一度、リスペクトとただの模倣・二番煎じの差を理解し、その境界を踏み越えることがないよう留意すべきであろう。
離水氏は私から見ても当代きっての名俳人であり、柔軟性と平明さを備えたうえで己の句風を確立しておられる。それゆえに「自分も離水先生のような句を詠みたい」と思う者が後を絶たず、さりとて真似は難しい。
余談かつ個人的な感情にはなるが、ひとつ。五年前に早逝された、離水氏のご夫人・香(か)鳥(とり)風月(ふづき)女史の晩年の句風が離水氏に寄っていったことは、いまだに口惜しく思っている。であるからこそ、貴女には自分だけの句風をひとつ確(しか)りと持ち、それを掲げ続けていただきたい。
師の背中を追うだけが道ではない。幸いにも、貴女はまだ若い。吸収がしやすい今の間に多くの句風に触れ、多くの俳人と関わるのがよいのでは。それらからわずかずつ取り込み、離水氏の句風と混ぜ合わせて自分の句風、自分の色を確立し、貴女がその俳句世界を広げていくことを、切に願う。厳しい言葉となり申し訳ない。
「なんだろう、これ」
ひとりでに、そんな言葉が出ていました。わたしの目も口も、言うことをきいてくれません。さっきまでのほわほわはとこかへ飛んでって。今はじわっ、と、熱い涙がにじみ出してしまいます。
この講評に書かれていることはたぶん正しくて、参考にしなきゃいけないのに。『わたしの俳句、もしかして離水先生の真似をしているだけ?」と自分を疑ったこと、何度もあるのに。どうして胸が苦しいんだろう。
「先生。わたしは、どうすればいいんですか」
ずりずりと畳の上を動いて、わたしは先生のほうに身体ひとつぶん寄りました。
そのするどいお顔を見上げても、先生は言葉を返してはくれません。歯を食いしばりうつむいて、なにかに耐えておられるようでした。先生も、これを見て感じるところがおありなのでしょうか。
と、思っていると。
「……風月を侮辱するな」
普段の先生の声よりさらに低い、火山が噴火する直前の地鳴りのような声を、たしかに聞きました。
わたしに言っているんじゃない。きっと露山先生に向けているんだ。それがわかっても、やっぱり肝が冷えてしまう。そんな、聞いたこともないくらいのこわい声でした。
ざんばら髪の間から、先生の目線がご自身の左手の指に向かっているのが見えます。先生は亡くなられた奥様のことをほとんどお話しになりませんけど。その薬指には今も、銀の指輪か光っているのです。
ああ、と思いました。
先生がなにかを呑みこむまでじいっと待っていよう。心に決めました。わたしのことはそれからです。それからで、いいのです。
「……ああ、すまない。見苦しかったろう」
少し経って、離水先生は勢いよく顔を上げました。髪の毛をわしゃわしゃ掻いて、申し訳なさそうにされています。
「あの、気にしないでください、先生。わたしは失望なんて絶対にしませんから」
「……ありがとう。だが、本当にすまない。苦しいのはゆず君のほうだろうに、僕は自分のことでいっぱいになってしまった。露山先生の余計なことまで素直に話しすぎる点は、どうも好かなくてな。今度お会いしたときには小言をくれてやろう。それで手打ちだ」
ぱんっ。先生は薄く笑いながら、柏手(かしわで)をひとつ打ちました。その音で話題を区切るみたいに。全部許すみたいに。でも、先生のお顔にこわばりが残っているのが、はっきりとわかってしまって。ぎゅうっと、身体が締めつけられるような感覚です。
わたしはそれがいやで、
「せんせ――」
「今はゆず君のことだな」
先生は、明らかにわたしを遮(さえぎ)りました。
「率直に言って申し訳ない。露山先生の言うことは、おおむね間違ってはいないだろう。今までも一緒に他の句会へ足を運ぶなどして、ゆず君を様々な俳句のかたちに触れさせようとはしてきた。だが、足りなかったようだ。『僕だけが俳句ではない』とは何度か言ってきたが、今後はいっそう外の世界も見せられるようにしたい」
「……はい。でも、さみしいです。わたしの原点は、いつだって離水先生なので」
「大丈夫だ。原点をここに置いてくれるのなら、僕はそれでいい。ゆず君の俳句はゆず君だけのものなのだから、特定のものに染まりすぎるのはたしかに考え物だ。だが、ひとつ主役となる色を持っておくことは悪くない」
ひと言ずつ刻むように、先生はおっしゃいます。他の何色を差し込んでも、主役は離水先生から教わった色。それでいいのかな。もやもやがまだ少し残っているような気はしますが。
「はいっ。先生といっしょにいろんな世界を見るのはきっと楽しいですし、これからもがんばりたいです」
わたしはそうやって、笑顔を浮かべてみるのでした。
「ああ。……そういえば、肝心のゆず君の俳句を見ていなかったな」
結果発表のページには、受賞者の俳句が載っています。先生ははじめて見るはずです。
第三者の露山先生が見ても、わたしの句は離水先生の影響が強すぎるとお感じのようだから、先生ご自身が見たらどう思われるんだろう。そっくりすぎて笑うのかな。むすっとお怒りになるのかな。それとも、『これはゆず君の句だ』と言ってくださるのかな。
――答えは、そのどれとも違いました。
俳句誌をのぞき込む先生。その顔がみるみる青ざめていくのがわかります。露山先生にお怒りだった先ほどと同じくらい、動揺しておられるような。
どうされましたか、先生。ねえ先生。その細い首筋に流れる、冷や汗のようなものは。
「ゆず君、ひとつ答えてほしい」
「……はい」
「これらの句は、『あれ』を見て詠んだのか?」
まっ白になったお顔で、かすれ気味につぶやく先生。その視線が縁側の突き当たり――書斎に向きました。先生が『僕の心臓』と呼ぶ場所。
「ゆず君ならいつでも入っていいからな」とおっしゃるけど、恐れ多くてまだ入ったことのない場所。そこにある先生の句集などを見て詠んだのか、と聞いておられるのでしょう。
先生はきっと、本気で疑っているわけではないと思うんです。なにか別のお気持ちがあるはず。だからわたしは、正直に答えました。
「それはないです。わたしはちゃんと、まっさらです」
「すまない。疑うつもりはないんだ。だが、」
口に出したくない、と言いたげにくちびるを噛んだ先生は、
「『あれ』を見ずに詠んだというのなら、なおさらまずい。だが悪いのは僕だ。きみに責任はないんだ」
そう言って立ち上がり、部屋の壁に手をつきました。
「今日は賞の結果をもとに振り返りの予定だったが……すまない、また次回に回してもいいだろうか。今日のぶんは金をとらない。稽古代はまた払い戻すから、安心してくれ」
どこか苦しそうな声。
先生、どうされましたか。わたしの句がなにか問題あったのかな。なんで――
そんな気持ちは当然、ありますけど。
「しばらく旅に出る。頭を冷やしたい。次回の稽古までには戻ってくる上に、請け負っている仕事も進めるゆえ、そこも安心してくれ……先に失礼する」
屋敷の奥へ弱々しく去っていく背の高いはずのうしろ姿が、なぜだかとっても小さく見えたこと。消えてしまいそうだったこと。それのほうがずうっと、わたしの心をちくちくさせるのでした。
その日の夜です。学校の課題をぜんぶ片づけたわたしは、眠くなるまで俳句用の手帳と向き合うことにしました。
みかづきが昇りきるまで参考書 四ツ国ゆず
季語としての『三日月』は、陰暦八月――今の暦でいう十月ごろに昇る三日月を指します。早く昇って、早く沈む。
受験勉強は大変だけど、この月が頂上に昇るまでの短い時間だけでも机に向かわなきゃ。そんな気持ちで作ってみました、けど。
「ううーっ……こうじゃない。しかも、やっぱり先生の句風と近いもん……」
そんな声ばかり出ちゃいます。わたしの部屋はため息だらけです。
俳句では、百年くらい前まで日本で使われていた言葉遣い――文語体がよく使われます。でも、今使われている言葉遣い――口語体で詠まれた俳句もたくさんあります。わたしも離水先生もふだん文語体で詠んでいるから、口語体で詠んだら離水先生とちがう感じになれるかなって、浅はかな考え。
案の定、口語体で詠んだって、根っこのところ――先生の句風の影響が、なんにも変わりません。それに先生と比べたらいろいろ足りない。露山先生の厳しいお言葉は、間違ってはいないのだと思います。わたしの句と誠実に向き合ってくださったからこその講評だということ、痛いほどわかっています。わかってはいるのです。
目先を変えたって意味がない。次のお稽古は二週間後。そこまでに付け焼刃で他の俳人さんの句風を取り入れ、自分の作風に活かそうとしたって、きっと無理があります。
わたしの俳句から離水先生を引いたら、なにも残らないのかなあ。
……だめだめ、自信を持たなきゃ! わたしの俳句の真ん中にはやっぱり離水先生がいるから。それはきっと、いつまでも変わらないから。
『離水先生の弟子』
部屋の壁に貼った半紙がでかでかと主張しています。高校の授業の一環で、市の俳句コンテストに出した句。それがたまたま、審査員をされていた離水先生の目に留まったこと。授賞式で少しだけお話ししたときの、ちょっとした話の流れ。そんな幸運のおかげで、とても素敵な句を詠む先生がわたしの師匠でいてくださる。その事実をずっと心に刻んでいたら、少しは自信を持てる気がして。丁寧に丁寧に、筆で書きました。……友達からの評判はさっぱりですけど。
「異物」とか。「秩序がない」とか。「理由はわかったけど」とか。
部屋がピンク色と薄い藍色でいっぱいなのが悪いのでしょうか。でもどう言われたって、この半紙は大事なものなので。
前を向くのです、わたし。これからどうするか、どうしたいか、自分で考えなきゃ。
……そうだ。やりたいことと、そのために必要な準備がひとつずつ思い浮かびました。その準備をするため、明日は絶対、先生のお屋敷に電話するのです。先生はもうおられないかもですけど。きっと、屋敷のお手伝いさん――絵(え)梨子(りこ)さんが出てくださるはずです。
がんばります。わたしの進む先には、離水先生がいてほしいから。
二
この土日、珍しいことにアルバイトがお休みなので。この機会を逃さないように、土曜日、わたしは先生のお屋敷を訪れました。
しっかりと手入れのされたお庭を通り抜けて、呼び鈴を鳴らします。
すぐに引き戸が開きました。からからからから、軽やかな音です。
「はーい! ゆずちゃんやね?」
縦にも横にも大きな身体。ショートヘアをうしろでざっくりとお団子にした髪型。屋敷のお庭によく響く、関西の人だなあって話し方の声。絵梨子さんです。
「絵梨子さん、こんにちは。昨日電話で事情はお話しましたが、その……お邪魔して本当にかまいませんか?」
「かまへんで! せんせは『一、二週間ほど旅に出る。悪いが屋敷の管理を頼む。仕事はする』言うてどっか行ってもたけど。さ、上がって上がって」
「失礼しますっ」
先生のいないお屋敷に入るのは、いつもとちがう緊張がありました。玄関で靴を丁寧にそろえ、絵梨子さんについていきます。
「書斎に用があるんやったかいな」
「そうです。……あの」
「ん? どうしたんや、ゆずちゃん」
「ここまできて訊くことじゃないんですけど。「ゆず君なら、いつでも書斎を見ていっていい」というお言葉、先生がいらっしゃらなくても有効でしょうか……』
「有効でしょ。せんせ、絶対怒りゃせんよお」
「だと信じます」
離水先生。次にお会いできたら、ごめんなさいを伝えます。
……あっ。思わず足取りがとぼとぼしてしまって、すたすた歩きの絵梨子さんに置いて行かれそう――と思ったら、止まってくださいました。頭を下げてから、追いつきます。
「しっかしゆずちゃんも大変やねえ。せんせ、結局なんでそないうろたえたんかも言わんで、ゆずちゃんを家ぇ帰したんやろう?」
「……はい。事実はそうです。でも、よほどのことがあったんだと思います」
「まあ……せやろなあ。せんせ、めっちゃ偏屈みたいな見た目やけど、勝手なことはめったにせんもんな」
顔は見えませんけど。今の絵梨子さん、優しい顔をされているんだろうなあ。
「はい、着いた。鍵は開けとくさかい、終わったら呼んでなあ」
「ありがとうございます」
長い縁側の突き当たり。古びた木の扉が、書斎の入り口でした。結局まだ入ったことのない場所です。この中に離水先生の言う『あれ』はあるのでしょうか。新人賞に出したわたしの作品に動揺されていた先生は、いったいどの句に引っかかったのでしょうか。
「……あっ、せや」
立ち去りかけていた絵梨子さんが、なにかを思い出したようにこちらを振り返ります。
「なんでしょうか」
「この中にはなあ、せんせだけやなくて、藍(あい)ちゃん……本名じゃわからへんか。風月ちゃんの残した作品やらメモやらもぎょうさんあるんよ。あたしは風月ちゃんとはちいちゃいころから仲良かったからなあ、大事に読んだげてな」
「はい。もちろん、落としたり破れたりしないように気をつけますっ」
「アハハハハッ。そこは心配しとらへんよお。……ほな、またあとで。あたしは『あれ』がなにかまでは知らんけど、たぶんボツにした句とかそんなんや思うから、がんばりよー」
……そっか。『あれ』の正体が『世に出なかったボツ句を集めたもの』の可能性はありそうです。
軽い足取りで遠ざかっていく絵梨子さんのうしろ姿に、「ありがとうございます」と声をかけました。
先生の言う『あれ』の正体。さっそく探し始めます。
本棚、本棚、戸棚、本棚。たまに飾り棚。そんな書斎のどこから手を……入り口近くからにしようかな。目についた戸棚の引き出しに、『没・メモ用 其(そ)の六』という表紙のメモ帳が。
でも……其の六を全部見ても、わたしが綺羅星新人賞に応募した句たちと似たものは見つかりません。其の三十二も其の一も違いました。どうしよう、手がかりがありません。
わかったことはふたつだけ。ひとつは、お若いころの先生はいろいろな句風に挑戦していたということです。中には、自由律俳句――五・七・五の定型のリズムに縛られない、自由な俳句まで。明治時代の有名な俳人さんそっくりの句も、いくつかありました。特に、先生やわたしと同じ、伊丹出身の俳諧師――『西の芭蕉』上島(うえじま)鬼(おに)貫(つら)先生に近い句風のものが多く見えます。離水先生の『自然体で素直な読み口だけど、いろんな想像のできる深みのある俳句』は、もしかして鬼貫先生の影響がおありなのかな。そんなことを思いました。
ただ、もしそうだとしても、先生が今の句風を形作られるまでには、鬼貫先生以外にもたくさんの俳句を通ってきているのでしょう。このメモ帳たちからは、離水先生の足跡が見えるようです。
「あれも違う」
「これも違う」
自分だけの色を見つけたくて、あっちこっちの句風をたずね歩く。そんなお若いころの先生の声が聞こえてきます。
今はご自身の句風をしっかり持っておられる離水先生。いろんな句風をさまよってみたら、いつかわたしもどこかにたどり着けるのかな。そう思いながら読んでいると、かなり最近のものらしい『其の三十二』のメモ帳にたどり着きました。そこで詠まれていた句は、没だったり推敲途中のものだったりするとはいえ、初期のものより好みで。
わかったことその二。それは、わたしはやっぱり、離水先生が長い時間をかけてたどり着いた今の句風がいちばん好きということでした。
自分の好きなものはわかったけど、また時間を使ってしまったわたしです。どうしようとなりながら、書斎のいちばん奥にあった歳時記――季語が『春・夏・秋・冬・新年』の五つに分類されて載っている、季語の辞典のようなもの――の棚を見ていました。その中のひとつをなんとなく取り上げます。すると、歳時記だと思ったものは外箱だけで、中身はどこかへ行っていて。でも、その割には重たいのです。
外箱の中をのぞくと――入っていたのは、重しと一冊の小さな日記。紙は少し黄ばんでいますが、表紙には傷ひとつありません。きっと、大事にしまわれていたのだと思います。
わざわざ外箱と重しまで用意して、隠すようにしまわれていたもの。これだ、と直感が働きました。中身は――やっぱり日記だけど、ふたり以上で書いている? 毎日の名前欄には『離水』と『風月』。一冊で交換日記をされていたみたいでした。お互いが一日交替で書き、いちばん下の行で一句詠む形式。
その日記は、六年前から五年前にかけて、風月さんが亡くなられる直前まで続いていたようでした。
読み進めます。闘病日記のような重たい内容もあって、だけど風月さんの筆致はずっと明るく、あたたかくて――あっ。
あっけないくらいすぐ、見つかりました。七月十九日の日記です。
胃薬のやうににがくて木下(こした)闇(やみ) 花山離水
胃薬のやうににがくて蝉時雨 四ツ国ゆず
ちがうのは下五だけ。その下五だってどっちも夏の季語で、樹木の周りで感じ取れるところまで一緒です。木下闇はたしか、樹木の葉っぱで光がさえぎられてできる影のこと、だったはずだから。
先生はこれを見て、近すぎると思ったのでしょう。だとしても、どうしてそこまで動揺されたのかはまだわかりません。でも本当にそっくりです。たまたまかもしれませんけど、先生と同じ目線で近いものを読めたのだから。どうしたって、うれしいと思ってしまい――
――取り消します。嘘でした。その日の日記をちゃんと読んだら、とてもそんなこと言えなかった。
六年前にはもう、風月さんは前からのご病気が進んでしまっていたようです。「今日から入院です」「風月が一時退院した」のような入院と退院の繰り返しが、たぶん三回くらい。七月十九日は、日記の中で二回目の入院の日でした。
『胃薬のやうににがくて木下闇』の句は、離水先生が風月さんのお見舞いに行った帰り道で詠んだ句のようです。びりり、と。ずしん、と。その背景を見ながら読むと、すり潰されるような痛みをより感じます。
かなしさで思わずうつむきながら歩く視線の先に入り込んでくる、塊(かたまり)のような木下闇。
ゆらゆらとざわめく、底のない闇。そんな情景さえ見えてきます。
わたしの句も、蝉時雨を実際に聴きながらたくさん考えて詠みましたけど。離水先生の句と比べたら、やっぱり実感のこもり方も、情景を呼び起こすパワーも足りない。わたしはまだまだ、離水先生のおられるところには遠いのです。
日記を外箱に戻し、そっと元の本棚にしまいました。絵梨子さんを呼びます。
「終わりました!」
「はいよーっ! よし、鍵かけた。玄関まで送るわあ」
「ありがとうございますっ」
「ゆずちゃん、なんか声明るいわねえ。ええもん見つかった?」
ふたりで元来た方向に戻りながら。絵梨子さんが楽しげな声で話しかけてきます。
「大事なものを見つけました。探し物をしたおかげで、先生に伝えたいことがまとまりました。だから――わたし、迎えに行きたいです。そうしなきゃ先生、ふわっと消えちゃいそうだったから」
「ほんまになあ。『しばらく旅に出る』ってあたしに言うたときのせんせの顔は、心細うしとるちいちゃい子みたいやった。一、二週間言うてたけど、あの調子じゃあもっとかかるか……下手したらな、もう帰ってこんかもしれん。本気でそう思たんよ。うん、行ってきい」
「はい!」
「で、肝心の、せんせのいる場所やけどな。間違いなく城崎(きのさき)やわ。先生がお休みとるときは、いつだって城崎よ。せんせと言えばあの句やろ?」
「たしかに! それに、先生から城崎温泉のお話を聞いたこと、何度かあります」
湯上がりて城崎の荒星を浴ぶ 花山離水
離水先生の代表句は、城崎の情景を詠んだものです。とてもお気に入りの場所なのでしょう。
「あと、泊まっとる場所もわかるで。ひいきのお宿があるんやわ。あとで電話番号と詳しい場所教えるさかい」
ちょっと、いや、かなり遠いですけど。同じ兵庫県でも、伊丹のほぼ真反対ですけど。行ったことのない場所ですけど。もう気持ちは決まっています。
「明日、城崎に行ってこようと思います」
「うん、うん。明日かあ。せんせはさあ、ちょっと気にしすぎなんよ。作風がどうとかの話やんね? 風月ちゃんの俳句はきっと、最期まで風月ちゃんだけのものやったし。ゆずちゃんの俳句も、きっと大丈夫よ。ゆずの木みたいによう育つって」
「だといいなあって、思います」
樹木みたいに背筋を正して、そう答えました。
すると、絵梨子さんのぽつり、ぽつりとした言葉。いつも明るいこの人の表情に少し影が差して見えるのは、夕方が近づいてきたからではないのかもしれません。
「あたしは俳句のことようわからんし。見てわかるやろけどテキトーに生きとる自覚はあるしなあ。そんなんでもせんせのやわっこいとこに寄り添おうとしてはみとるけど……正直、できてへんとこもあるのはわかってまうんや。せんせのとこに行くの、ほんまはあたしの役目やで。けどな、今のせんせにいちばん寄り添えるんはきっと、ゆずちゃんなんやと思う。ほんまに悪いんやけど、託してかまへん? ごめんなあ」
言い終えると。絵梨子さんは、深く深く頭を下げられました。
わたしの答えは決まっています。にっこりと、しっかりと。自信をもって言うのです。
「はいっ。託されました」
「……ありがとうなー!」
ゆっくりと頭を挙げながら、絵梨子さん。
「きっと天国の風月ちゃんも浮かばれるわあ」
「ふふっ。天国にいるなら浮かばれているじゃないですか」
「ほんまやなー! じゃ、気をつけて帰りよー」
お宿の電話番号などを教えていただきながら、玄関口まで。絵梨子さんはいつもの豪快な笑顔で、大きく手を振ってくださいました。
家に帰ったらすぐ、先生のごひいきのお宿に電話しようと思います。
三
許可さえ取れたらアルバイトができる高校でよかった。心からそう思います。往復六千円は、突然の出費にしては少し多いので。
伊丹から城崎温泉まで、電車で四時間。流れる景色を見ながらひたすら俳句を読んでいたら、思ったよりも早く時間が過ぎた気がします。離水先生がひいきにしてらっしゃるというお宿は、城崎温泉街の奥のほうにある、小さな建物だそうです。
十月も半分が終わりました。日本海のすぐそばに行くんですから、当然それなりに着こまないといけません。城崎温泉駅で降りたら、ねずみ色のダッフルコートに身体を埋めて、にぎわう温泉街を進みます。ここで会心の句を詠むくらい、先生が愛してらっしゃる温泉街。どんな場所なのか、ゆっくり歩いて感じたい――そんな気持ちはいつかに取っておいて。今はずんずん、ずんずん、お宿まで。円(まる)山川(やまがわ)に沿って続く、きれいな柳の並木道をちょっと疲れるくらい歩いたら、着きました。呼び鈴を鳴らして、出てきたおかみさんらしき女性に言います。
「お電話していました、渡井ゆずと申します。俳人の花山離水先生は今、いらっしゃいますでしょうか?」
「あんたがゆずちゃんね! 電話で聞いた通り、先生にはゆずちゃんが来ること伝えてないから安心してちょうだい。ええ、ええ。先生呼んでくるからねえ!」
おかみさんがばたばたと上がっていったあと、少しして。とたり、とたり、と。恐る恐る階段を下りてくるような音。
「……幻、ではない、よな」
藍染めの着流し姿の離水先生が、心底驚いたようなお顔で出てこられました。べっこう眼鏡の奥。何度もまばたきをしているその目に、今まではなかったはずのクマが見えるのが、とてもかなしくて。でも、顔には出さずに。
「幻ではないです。離水先生、言いたいことがあって来ました」
さすがに玄関口で話をするわけにはいかないので、先生が泊まっておられるお部屋へ。先生のお屋敷のものと同じくらい立派な長机に、向かい合って座ります。
離水先生は浮かない顔をして。それから、勢いよく頭を下げられました。
「まずは、ここまでさせるほどの心配をかけてしまい、誠に申し訳ない。何も説明せずに出ていってしまった僕が悪いのだ」
「わっ、あの、あやまらないでください! 大丈夫ですから。それより、ひとつお訊きしたいことがあります」
珍しく、大きな声が出てしまいました、でもすぐに落ち着きます。先生のお話を聞いて、わたしの気持ちをちゃんと伝えるのが、今はなにより優先です。
単刀直入に訊きました。
「離水先生。先生がどの俳句を見てうろたえたのか、見つけました。『胃薬の~』の句ですよね。風月さんとの日記に載っていた先生の句と、たしかにそっくりでした。おどろかれるのはわかります。でも、どうしてここに来たくなるくらいの気持ちになられたのか。それは直接お訊きしないとわからないので、ここまで来ました。それに――」
こんな子どもみたいなこと言っていいのかな。いや、言わないほうが後悔するかも。
いろんな気持ちがのどの奥で絡まって、うまく出てきません。
――それでも。
「今先生のところへ行かないと、もう二度と会えない気がして、いやだったから」
素直な想いを、伝えました。
先生はしばらく腕を組んで、目をつぶって、なにか考えておられる様子でしたが。
「……わかった。答える」
やがて、そうつぶやかれました。
「露山先生の講評にも書いてあったが。僕の亡き妻――風月の晩年の句風は、元の情緒的な口語体に比べて、たしかに僕のものへと寄っていた。ただそれは、『もう長くないから、生きている間にあなたの世界を深く知りたい』と、風月が自らの意思で寄せたんだ。僕らは俳人夫婦だったが、それまではできるだけお互いの作句には関わらないようにして、影響を受け合うのを避けてきた。出会ったときはお互い、芯となる句風を固めていく途中段階だったのでな。そのような背景があった。風月はなんとなく僕に影響され、絡めとられたわけではない」
先生の声には、先ほどまでとは違う、強い自信がこもっているようでした。
「端的に言えば、誤解だったんだ。僕の世界にできる限り触れようと俳句で歩み寄る風月を、彼女のファンや俳壇は『結婚して句風が変わった』『前のほうがよかった』と受け取った。事情を知らないのだから当然ではあろう。明るい姿を見せようと、風月は闘病の事実を死の間際まで隠したのだ」
「そんなことが……」
「僕のもとにも当然心ない言葉がきたよ。『お前が風月先生を染めやがった』『句風を汚した』とな。闘病を隠すという風月の意思は固く、事実を示すわけにもいかなかった。なにくそとは思ったよ。だがそれ以上に、自分を責める気持ちのほうが強かった」
「ご自身を責める必要なんて、なにひとつないです」
話を聞いたばかりで、まだまだ弟子三年目な私の言葉。そんなものにどれだけの力があるかわかりませんけど。思ったことを正直に言いました。
「ありがとう。だがな、今の僕は『他人の作風に、不用意に影響を与えてしまう』ことがとにかく怖いんだよ。だからゆず君の『胃薬の~』の句を見たとき、怖気(おぞけ)がした。前々から、僕の作風を忠実に吸収しているようには思っていたが。まさか、書斎の奥の奥にひっそりと保管している日記の句と、そっくりな句を詠むとは。日記を見て詠んだのではないと言われたとき、『ああ、また深く染めてしまったのか』と思った。しかもゆず君は、素質にあふれた若者だ。いくらでも可能性があるのに――」
――僕が、染めてしまった。
最後のほうは引きつったような声で、机に突っ伏して。それでも、先生はすべてを吐き出してくださいました。だからわたしは、
「離水先生」
先生のそばにそっと近づき、その骨ばった大きな肩に手のひらを添えました。
「……ゆず(・・)」
「だいじょうぶです。あのですね、先生」
藍に染まった木綿の着物のやわらかな感触越しに、ぶるぶるとした震えが伝わってくるので。その震えが早く止まることを願って、わたしは、そっと話をします。
「わたしは、先生のすうっと心に入ってくる、あったかい俳句が。単純明快で、簡単なようで、同じように作るのは簡単じゃない俳句が、大好きなんです。この人のいる場所に、見ている世界に、少しでも近づきたい。そう思ってここまできています。あなたのように世界を見て切り取れたなら、どんなに素敵なんだろう。いつだってそう思います。だから、だからわたしは」
熱いものをこらえて。
「あなたの色に、染まりたいです」
それだけが言いたかったのでした。
先生はかすかにうなずかれているようでしたので、続けます。
「誰になにを言われたって――『リスペクトとただの模倣の境界を意識しろ』なんて言われたって。絶対に、ぜーったいに折れません。そんな境界なんて、尊敬で突き進めたらいつか壊せると思うんです。だいじょうぶです、先生のうしろ姿を追い続けていたらきっと、先生とはちょっぴりちがう藍色に染まります。藍の染物はひとつとして同じようには染まらないですよね。だから、先生のお召し物とはちがう藍色に染まります。風月さんだって絶対、そうだったと思うんです」
みんなみんな、ちがう人間だから。
「ゆっくりでいいですから、お屋敷に帰りませんか。絵梨子さんも待っておられますよ」
「……そうか。わかった、ふたりで帰ろう。だからな、もう少しだけ、待ってはくれないか」
「はいっ」
少しずつ体を起こしながら、先生はそう答えてくださいました。
「ゆず君。ありがとう。この礼は必ずする」
涙でぐしゃぐしゃの顔で、ぎこちなくも笑う先生の姿に。
――この人の弟子でよかった。
そう、思いました。
【優秀賞】該当なし
【佳作】ガーデンフィーバー(四条葵)
古いなあ。
初めてその家を見たとき、後藤(ごとう)涼子(りょうこ)は感じた。
京都市中京区六角町。かつては呉服問屋が軒を連ね、京都経済の中心地として栄えたこの地に、その家はあった。
通称「鴻池屋(こうのいけや)」。明治の昔に、京都の呉服王と言われた資産家が建てた家らしい。
「お嬢さん、この机はどこに?」
引っ越し屋さんの青年が、マホガニーのライティングビューローを二人がかりで運びながらそう訊くと、母が、ああ、それはこの子の部屋に、と玄関に向けて指さした。
「あなたの部屋は一階よ。ここを入ってすぐ左」
犬矢来が並んだ家の通り沿い。通りに面して、呉服問屋特有の糸屋格子と呼ばれる窓がある。その並んだ窓と窓の間に玄関がある。引き違い戸になったそこを開けると、敷石で整えられた歩道が続き、入り口の格子戸にたどり着く。
「お母さん、ここが私の部屋?」
「そうよ。六畳の和室。これからは東京の家みたくベッドじゃなしに、畳にお布団を敷いて寝ることになるけどね」
「じゃあ、そこにこれを」
その六畳間の襖を開けて部屋を初めて見た。入口に相対して四枚の障子が並んでいる。下の部分が硝子窓になっている雪見障子だ。壁はいわゆる京壁というやつで、くすんだ茶色だ。右手に次の部屋との襖がもう一つあり、欄間には鴨居に掛けられた古そうな書が飾られていた。
「これなんて読むんだろう?」
そう思っていると、引っ越し屋さんがライティングビューローを置きながら、この場所でいですか? と尋ねた。はい。そこで結構です。
天井からは西洋風の二灯式のシャンデリアが下がっていた。乳白色のガラスシェードで、ロカイユ文様が施された本体は真鍮製だ。
「和洋折衷ってやつね」
「どう? 気に入った?」
母がそう訊いたので、涼子は悪くないと思う、と答えた。
「障子開けていい?」
「好きにして」
ひんやりした部屋に入り、そっと障子をひいた。
「うわあ……」
それは京町家特有の空間だった。向かいには古そうな蔵があり、両側は茶色の杉皮を張った塀になっていた。いわゆる中庭というやつだ。残念だったのは、そこが緑溢れる美しい庭園ではなく、冬枯れた雑草と薄の繁茂した荒地だったことだ。
「このお庭はね、前の所有者が作らせたお庭らしいんだけど、手放してから一切手が入ってないそうよ」
「そうなんだ……」
すぐ下を見ると、いわゆる沓(くつ)脱石(ぬぎいし)と呼ばれる四角い石があって、これこれ、と言って母がサンダルを持ってきた。それを履き、庭に降りる。
庭は十二畳程の敷地で、四方を建築物が取り囲んでいる。上を見ると四角い早春の青空が見える。薄にかくれてよく見えなかったが、涼子の背丈程の石灯籠が一基、置かれている。足元を見ると、碁盤よりももう少し大きい六角形の石がある。真ん中が丸くくり抜かれていて、枯葉が数枚、重なっていた。
「ああ、それはね、六角(ろっかく)蹲踞(つくばい)っていって、前の所有者さんがこの家と一緒に手放したそうよ」
「これ、古いの?」
「どうかしら、明治四十二年のこのお家の完成時には既にあったらしい、とは聞いてるけど……」
涼子はそこにしゃがんで、その六角蹲踞を見た。一見すると御影石に見える。灰色のざらついた表面を、そっと触ってみた。
―水が、欲しい―
「え!?」
どこからか、そんな声が聞こえた気がした。
「お母さん、今なんか言った?」
振り返ると、既に母の姿はなかった。
もう一度、蹲踞を眺めた。さあっと風が吹いて、枯葉がすうっと舞い上がった。
「気のせいだよね……」
「涼子ちゃん、ちょっと手伝って!」
「はあい!」
涼子は元の沓脱石にサンダルを戻し、母の声がしたほうに向かった。
その夜は、両親と三人揃って、引っ越しそばならぬ、うどんを食べた。そばがなかったのは、ああ、やはり関西に来たからだなあと涼子は思った。
「どう、京都大学? お父さんやっていけそう?」
きつねうどんをすすりながら、涼子が訊くと、まあまあかな、と父は答えた。
「なんといっても、京都は本場だからなあ、やはり設備は素晴らしいし、なによりも蓄積が違うよ。お父さんの専攻する近代日本庭園史にはまたとない環境だ」
涼子の父は、長いこと東大で園芸学を教えていた研究者だ。そんな父にとって京都は聖地らしい。確かに京都には有名な寺社の庭が多く、園芸を生業にする者にとっては最高の環境だろう。
「お父さんの京都贔屓は異常だから……」
「いやいや、こんな素敵な街があったら誰でも憧れるさ。世界遺産は沢山あるし、国宝建築物だって、重要文化財だって本当に多い。それに……」
父は油揚げをかじった。
「なんといっても、国指定名勝が素晴らしい。天龍寺なんか特別名勝だぞ」
「でもねえ。だからって京町家一軒まるまる買うなんて。物好きよ、お父さん」
「いいじゃないか。いろいろ新鮮だろ? お母さん」
「まあ、台所がシステムキッチンなのは良かったけど。今時お釜でご飯炊けなんてなったらどうしようかと思ったわ」
涼子は昼間見たこの家の竈を思い出した。もちろん今は使われていないが、京都では「おくどさん」と呼ばれているのだそうだ。
「関東式ダイドコ、だっけかな。手を入れるとこにはしっかり手が入ってる。いい家じゃないか」
母は半ば呆れてうどんをすすった。
「涼子も、高校、馴染めるといいな。府立に行けたのはよかったけどな」
「うん……。まあ、明日入学式だけど……」
東京で成績の良かった涼子は、ここ京都の府立上賀茂高校に進学出来ることになっていた。
「青春しろよ。お父さんもお母さんも、遊ぶ時にしっかり遊んで、勉強する時にちゃんと勉強したからなあ。まあ、悔いの無いようにな」
「そうだねえ……」
実際、涼子は不安だった。自分のような東京人がやっていけるだろうか、と思っていた。京都は余所者に冷たいと言うし。
「彼氏出来たら、連れて来なさいね。お母さんに見せにくるのよ」
「おいおい、それは早いだろ」
「あら、何言ってんの。お父さんとお母さんだって、出会ったのは高校時代なんだから」
両親のそんなやりとりを聞いて、ああ、この二人は大丈夫だ、と思っていた。
その夜は、初めて和室で布団に入った。まだ家具や荷物が運ばれたばかりでなにかと落ち着かないが、午前零時半頃には、すうっと眠気が降りてきた。
翌日の朝、少し早めに家を出た。御池通を歩きながら、涼子は果たして新しい高校でやっていけるかどうかと、内心不安に思っていた。
「東京人だもんなあ……。あたし」
春の京都は、こんな朝早くから、早くも観光客らしき人たちがあちこちに見えた。
市バスに乗って、一番近い停留所で降りた。辺りを見ると、同じ制服らしい人達が沢山いた。
「これがカモ高かあ……」
府立上賀茂高校。通称カモ高は、明治時代の府立農学校が母体になっている。京都府内でも有数の進学校で、毎年京大合格者数では、同じく府立の膳(ぜ)所(ぜ)高校としのぎを削っていた。
同志社大学と並んで、市内最古の西洋建築と言われる講堂で入学式が行われた。
校長先生の京都弁の式辞がなんとも味があった。最後に、吹奏楽部による校歌の演奏があった。なんかかっこいい、と思った。
渡り廊下横の中庭に掲示された教室割り当て表を見て、自分のクラスを確認した。涼子は一年C組だった。長い廊下を歩いて、教室に着いた。
黒板に貼られていた座席表を確認して席に着いた。周囲を見ると、パラパラとあった空席が少しずつ埋まっていった。その時、後ろからツンツンと背中を突かれた。振り返ると、髪を肩で切り揃え、黒縁の丸い眼鏡をかけた女子が、心配そうな顔でこちらを見ている。
「ウチ、重森(しげもり)玲(れい)。よろしく」
どうやら悪い子ではないらしい。涼子は二言三言、自己紹介をした。
「ふうん、東京から来はったん。なあ、部活とか、どこ入るか決めた?」
「まだ決めてないの」
すると、玲は左右を見回し、何かとても大切な秘密を告げるように、こう言った。
「園芸部入らへん?」
それから新しい担任の先生が入ってきて、クラスの皆の自己紹介やら、先生の簡単な生い立ちやら、カモ高の歴史やら、自分が顧問を務める剣道部のインターハイでの活躍ぶりなど、一通りのことを話して、その日は解散となった。その後、涼子は玲と一緒に、構内のはずれ、園芸部の部室があるという場所に向かっていた。
「お父さんなにしたはるん?」
「大学教授なの」
「ふうん、東大で教えはって、今度は京大で教えはるん、えらいお人やねえ」
玲がそう言ったので、涼子は父の研究の専攻とか、内容を具体的に教えた。そして、近代日本庭園史という言葉を出した時、玲の瞳が煌めいた。
「日本庭園? ほな京都は聖地やんなあ? いろんなお庭とか行ったことあるんとちゃう? どこが好き? 龍安寺? 建仁寺?」
「詳しいのね」
玲はフフッと眼を輝かせると、涼子の顔をじっと見た。
「このカモ高の園芸部はなあ、府立農学校時代からある、学内最古の同好会やの」
気がつくと、辺りは鬱蒼とした木々が生い茂り、見上げると頭上に交錯した梢があった。
「涼子はん、あれわかる?」
玲が指さした所には、古風な洋館が建っていた。茶色のスクラッチタイルで飾られた、これも校舎なのだろうか。
「旧京都府立農学校一番教場や。あそこに園芸部が入っとるん」
「へえ……」
ネオゴシック様式のその一番教場は、国の登録有形文化財になっているらしい。
入り口を入ると、目の前にホールがあって、玲について行きながら、中を歩いた。迷宮のような一番教場のどこをどう歩いたか、黒地に白で「園芸部」と書かれた札の下がった教室の前に着いた。
「こんにちは。新入生二人です」
玲は扉を開けると、少し離れて立っていた涼子を手招きした。
「あら、玲ちゃん、こんにちは。お友達?」
「さっきから、やんなあ」
そこは十畳程の広さの洋室で、高い天井からは、ミルクガラスのシェードの照明がさがっている。奥に細長い部屋で、中央にはオーク材とおぼしきテーブルに、木製の椅子が五客。右の壁には古そうな書架が置かれていて、見たところ園芸関係の書籍が入っているようだ。壁には都合四枚の、金色の額縁に入ったボタニカルアートが飾られていて、奥には大きな窓があり、臙脂色のカーテンが垂れていた。
「私は上賀茂高校園芸部部長の加賀理沙子(かがりさこ)。今年で二年生になるの」
長い黒髪をヘアバンドで留め、制服をきちんと着こなし、少し神経質そうな二重の眼をしている。見たところ風紀委員長といった趣の、真面目そうな人だった。
「早速だけど、後藤さんは京都のお庭はどこが好き?」
そう訊かれて、言葉に窮した。父親こそ日本庭園の研究者だが、涼子には日本庭園の知識はあまり無い。
「ええと……、金閣寺とか……、平安神宮とか……」
「そう、じゃあ、京町家のお庭はどこが好き?」
踏み込んだ質問をされて、答えられなかった。
「フフ、初心者さんね」
加賀先輩はそう言って少し悪戯っぽい眼で涼子を見た。
「ねえ、加賀先輩、さっき話したんやけど、後藤はんの今のお家、本物の京町家なんやって。ね、お庭もあるんとちゃう?」
「え……、ええ……、まあ……」
「こんど部員みんなで見に行こ? なあ、ええやろ? 涼子はん?」
「ええ!?」
「あら、本当?」
急な話に、涼子は思わず部室の天井やら床やらを眺めて、視線をドギマギさせてしまった。
「で……、でも、お庭はほとんど手入れしないで放ってあったっていうか……。その、前の所有者が手放して以来、放ってあるっていうか……」
「でも蔵とか、あるんやろ? ええやん、な、見せて?」
「え、ええ……」
加賀先輩はテーブルに座りながら、そんな二人のやり取りを聴いていた。
「ねえ、涼子さんはお庭とか、園芸とか、あまり興味はないの?」
「え、えと、全くない訳ではないんですけど……」
「じゃあ、ここに入ったら目覚めるかもしれないわね」
「せやんなあ、涼子はん、な、皆でお庭見に行くさかい、見せて!」
「まあ、無理にとは言わないけど……」
加賀先輩はスマホを取り出すと、涼子に見せた。
「これ、去年秋の部の研修会で行った無名舎(むみょうしゃ)の写真なの」
「無名舎……?」
そこには、涼子の家と同じような京町家の中庭が写っていた。左右に開いた障子があって、中央に見たこともない植物が植わっている。笹をうんと大きくしたような、背の高い木で、扇形の葉が繁っている。どことなくヤシの木を思わせる植物だった。
「これは、一体……?」
加賀先輩はスマホをいじりながら、これはシュロチクという木だ、と教えてくれた。
「シュロチク?」
「涼子はん、シュロチクいうのはなあ、チクってついとるけど竹やのうて、ヤシ科の植物でなあ、京町家のお庭には欠かせない木やで」
そうなのか。でも枯れ木が繁茂した家の庭に、こんな木があっただろか。
「後藤さん、今、あなたのお家のお庭が荒れ放題なのは残念だけど、京都の人間にとって、お庭ってなくてはならない存在なのよ。あなたも京都の人間になったからには、お庭を大事にしないとね」
「お庭を大事に……」
「なあ、加賀先輩。皆で涼子はんのお家のお庭、復活させたらどうやろ?」
「え!?」
加賀先輩はスマホを見せながら、確かにそれもいいかもね、と乗り気とも乗り気ではないともつかない返事をした。加賀先輩がいじるスマホには、次々と京都の名庭の写真が現れた。
「これは富田屋(とんだや)、これは十四(とし)春(はる)……」
それは確かに、園芸にとりたてて興味の無い涼子にとっても、素直に美しいと思えるものだった。どうやら京町家という物には、美しい庭が付き物らしい。
「ここ、他に部員の方は?」
ふと涼子が訊くと、加賀先輩はああと言って、スマホをしまった。
「まだあと二人いるの。そうね、今度後藤さんのお庭を見に行くときに、全員揃うんじゃないかな」
「じゃ、今度の日曜日! ね、涼子はん?」
二
その日の日曜日、涼子は朝からそわそわしていた。
後藤家が京都に移って以来、初の客人だ。前日の土曜日に、居間と居室と玄関を片付けて、日曜日には朝、玄関先を掃き掃除した。
母はもうお友達が出来たのね、と上機嫌で、老舗の和菓子屋さんにお茶菓子を注文した。
午後一時すぎ。加賀先輩を筆頭に、カモ高園芸部の部員達が顔を揃えた。
「はじめまして。上賀茂高校園芸部部長の加賀理沙子です。この二人は同級生で……」
「小堀菜摘(こぼりなつみ)です」
「小川(おがわ)俊(とし)治(はる)です」
その二人は初めて見る顔だった。
小堀さんは栗色の長髪をうしろで纏めている。切れ長な目が印象的な女の子だ。
小川君はすっきりと刈り込んだ黒髪の青年で、一重の眼の、涼しい顔立ちの好青年だ。だが、どこか近寄りがたい印象があった。高校生というより、伝統工芸を作る職人の見習い、といった風情だ。そして玲がいる。
「ようこそ。さ、どうぞ、上がって」
母は一同を居間に招いた。
お客さん用にと、前日に老舗の茶店である一保堂で買ってきた煎茶を出し、同じく老舗の和菓子屋から取り寄せたお菓子を添えた。
「わあ、真(しん)盛(せい)豆(まめ)やん。お母さん、よう知ったはるなあ」
「それ真盛豆っていうの?」
玲が声を上げて喜び、それを口に入れるのを見て、涼子が訊いた。
「せや。豊臣秀吉公も食べた、言われとるお豆さんやで」
大き目のビー玉くらいの大きさで、全体に緑色の青のりの粉が塗してある。口に入れると、青のりの風味と、中の丹波産の小豆の甘さが絶妙に溶け合った。
「小川君、だっけ? 彼女とかいるの?」
「お、お母さん、いきなりそんな……」
緑茶を継ぎ終わった母がそんなことを言ったので、慌てて制した。
「あら、いいじゃない。ね、イケメンだし、ガールフレンドとかいるわよね? 家の子なんかどう?」
「お母さん、もういいからあっち行って」
悪戯っぽい笑みを浮かべて、じゃあごゆっくり、と母は席を外した。
「なかなかええ人やんなあ、おまはんのお母さん」
小川君が豆を頬張りながら、涼子に言った。
「ごめん、もう余計なことばっかり……」
「あら、ええやん、素敵なお母さんやで」
菜摘先輩が笑って三つ目の真盛豆を口に運んだ。
しばし、のどかなお茶の時間。
「ねえ、涼子ちゃん、お庭ってどこにあるの?」
菜摘先輩がお茶を飲み干して、湯飲みを受け皿に置いた。
「せやなあ、今日は皆、それ観に来たわけやし……」
小川君も続いてお茶を飲み終えた。
「ね、見せて、涼子はん家のお庭」
玲がお願いしたので、加賀先輩、こちらです、と涼子は自室に一同を案内した。
「ああ、靴、忘れないように」
玄関脇の涼子の部屋に入った。涼子は雪見障子を開けた。
「おー……」
玲が思わず感嘆したように声を上げた。
皆が来るから、せめて草取りだけでもしておこうかと思ったが、あえてそれはせず、ありのままを見せた。
「庭、入っていい?」
加賀先輩が頼んだので、もちろんです、と涼子は答えた。
銘々、靴を履いて中庭に入った。
加賀先輩も玲も菜摘先輩も小川君も、それぞれ思い思いの場所を見ている。
「ここは、借景が無いからごまかしがきかんなあ……」
小川君に言われてみると、確かに、この庭は四方に壁があるので、遠くは見えない。
「やっぱりシュロチク欲しいなあ……」
玲が眼で庭を検分しながら呟いた。
「ねえ、後藤さん、これ、気づいた?」
加賀先輩の指摘に、なんだろうと涼子は訊いた。
「この飛び石、沓脱石から始まって庭を一通り廻って、あの蔵の入り口と繋がってるの」
確かに、足元には所々に灰色だとか、茶色だとかの石が敷かれている。
「間の取り方が絶妙やな」
小川君が鋭い目つきで飛び石を見ていた。やはりこの人は違う。何か職人的な勘を持っている人なんだ。
静かな庭だった。ふと、ここが京都の町中であることを忘れてしまいそうになる。
「で、玲ちゃん、あなたはここを復活させたいのね?」
加賀先輩の言葉に、涼子はんが良ければ、と玲が言った。
「あの……、皆このお庭をなんとかしてくれるの?」
いつの間にか母が縁側にいて、一同を見ていた。
「あ、お母さん、それは玲ちゃんが言い出したことで……」
「あらそう。いいじゃない。お願いしたら? ねえ涼子ちゃん」
「でも、それは……」
なんといっても、天下のカモ高園芸部の人達だ。それを指図するようなことは出来ないだろう。涼子はそんな風に考えていた。
「お母さんと涼子さんが許して下さるなら、園芸部の総力を挙げて取り組みます。ね、菜摘ちゃん、小川君」
二人は無言だったが、加賀先輩の言葉はしっかりと心に届いたようだった。
さあっと春の風が吹いて、薄と雑草のそよぐ音がする。涼子はそれに耳を澄まし、しばし、春のひと時に身を委ねていた。
「俺は、ええよ」
小川君が、庭を眺めながら静かに言った。
「ウチも」
菜摘先輩が続けた。
「ウチらで造ろう、このお庭」
玲が眼鏡を指で押しながら、呼びかけた。
「それじゃあ、お母さんの許可も下りたようだし……」
加賀先輩は涼子を見た。
「あとは涼子さん次第ね」
涼子の胸に、初めて京町家の庭を見たときの想いが蘇った。
初めて部室へ行った時、加賀先輩のスマホで見た、あの緑豊かな庭園。それがこの家にも。
「そうそう、もちろん涼子さんにもお手伝いしてもらうわよ。これは立派な部活動だからね」
「あ、はい……」
涼子は決意した。
折角京都に住むことになったのだ。こうなったらお庭を造ろう。綺麗で、優しくて、うるおいに満ちた庭園を。
「わかりました……」
涼子は言い聞かせるように、一同に宣言した。
「造りましょう。お庭を。私たちの庭園を、ここに」
四人の意志が一つになったのがわかった。玲も、加賀先輩も、菜摘先輩も、小川君も、静かに、しかし力強く頷いた。
「それでは、宣言します」
加賀先輩は、やがて皆を一つにまとめるように、ゆっくりと四人の顔を見た。
「我が上賀茂高校園芸部の今年の活動。それは、後藤家庭園の復活です」
そして、その目に生き生きとした光を宿して、続けた。
「このお庭を甦らせましょう。私達全員の力を合わせて、上賀茂高校園芸部の部長、加賀理沙子が宣言します」
五人の見えない心の手が、力強く握手した気がした。
三
その夜のこと。
ふと、目を覚ました。枕もとの置時計は午前二時すぎを指していた。夜と夜の合間で、夢が途切れた、そんな感じだった。
なんか喉が渇いた。
そう思って、布団の上で半身を起こした。障子を見ると、豊かな月光が溢れている。
台所へ行って水を飲もう。そう考えたとき、月明かりを小刻みに揺らす影があった。
庭に誰かいる。まさか泥棒?
そっと硝子窓から外を覗くと、中庭に確かに人の気配がする。涼子は布団から出て、障子を引いた。
深夜の庭。そこには月光が満ちていた。全てが、様々な趣の青に染まっていた。
そこに、一人の少女がいた。
黒い振袖を着て、夜風に吹かれながら、手を後ろに組んで、まるで庭を散歩するかのように飛び石の上を歩いている。その髪は月明かりにもわかる黒髪で、背中の辺りまで長く伸びていた。
「おや、起こしてしまったかな?」
少女はこちらを向いた。翡翠のような瞳が、蛍のように灯っている。鼻は高く、唇は控えめに半ば開いている。
「あ、あなたは誰?」
咄嗟に我に返った涼子は、慌ててこの場に相応しい言葉を見つけて、半分放心したように訊くともなしに言った。
「ふう、それは私の言葉だな。またこの蹲踞に新しい持ち主がやってきたとはな……」
「え!?」
涼子は引っ越しの日に見た六角蹲踞に視線を落とした。相変わらず渇いた枯葉が、その上を覆っている。
「お主、喉が渇いたのだろう? 私もだ。あの時水が欲しいといったのに……」
「み、水って……」
少女は優雅に微笑みながら、飛び石を渡って涼子の傍に歩いてきた。
「あなたは、誰?」
「私は翠水。この六角蹲踞にやどっている付喪神だ」
「翠水……?」
状況を理解出来ない涼子は、その言葉を飴玉のように口の中で味わおうとしていた。
「あなた、こんな時間に、ご両親が心配するわ。早く家に……」
「フフフ、そんなもの、とうの昔に失った」
翠水と名乗った少女は渇いた笑みを浮かべた。
「あなたは、いつからここにいるの?」
「さて、いつからかなあ……」
少女はするっと反転すると、涼子に背中を見せて向かいの蔵を眺めた。
「初めてこの都にやって来たのは、室町時代の半ば……」
「え!?」
さらりと言われて、涼子は眼前の現実がますますわからなくなった。
「私の生まれたのはなあ……、尾張の国の岡崎だった」
「尾張……。愛知県のことね」
「ほう、今はそう呼ぶのか……」
翠水は再び飛び石を渡り、庭の中を歩いた。
「お主は知らぬだろうが、これは夏山石だ」
「夏山石……」
涼子は改めて六角蹲踞を眺めた。確かにそれは石で出来ている。
「腕のいい石工がな、私の依り代を造った。まだ岡崎にいた頃、都の豪商がこの蹲踞を買ったと聞いて、すぐに私はこの蹲踞に宿った。牛に引かれ、東海道を上り、この都にやってきた。その頃から、ここの景色も随分変わった。それから戦があって、平和があって、また戦があって、この都で私を所有する者は転々とした。江戸の終わりに、この都で最後の戦があった。それから三十年ばかり、最後に私を手にしたのは、この都の呉服問屋だった。明治の終わり頃だ。その時から私はここにいる」
「……」
ということは、この翠水は、人間ではないのだ。
「なあ、涼子よ。頼みがある」
「な、なにかしら……」
翠水はまた蹲踞の近くに歩み寄ってきた。
「この蹲踞に、また水を与えて欲しい」
「水を……?」
「そうだ。蹲踞は水あってのもの。明治の昔のように、またこの蹲踞に水を満たして欲しい」
一体これは夢なのだろうか。しかし涼子は、襟元に春の夜風を感じているから、これは夢ではないとわかっていた。
「安心しろ。私の姿はお主にしか見えぬ」
「え!?」
「この庭を、甦らせるのだろう?」
翠水はじっと涼子を見つめている。
「それ、この竹筒。ここから水を出せば、また私に豊かな水が溢れる。そうしてくれるだけで、私はお主らに幸運を与える」
「付喪神って……、いい神様なの?……」
「さあ、それはどうかな……」
翠水はまた涼子に背中を見せて、蔵のほうへ歩き出した。
「お主ら次第だ。お主が私を大事にしてくれるなら、私も相応の恩を返そう。私は水の神。水無くしては、あらゆる存在はありえない。全てを生んだ水。この都には、そんな尊い水の神が大勢いる。かつて、この都で頻発した大火を鎮めたのも水だ」
「そこに誰かいるの?」
母の声だ。
それを聞くと、翠水はまた涼子をじっと見た。
「今夜はこれでお仕舞だ。だが涼子よ、くれぐれも忘れるな。庭は水無くしてはあり得ない。水は尊いものだ。庭づくりに励む者の心得は、水を大切にすること。よいな?」
「あ、待って……」
ほんの一瞬で、翠水の姿は消えた。
「涼子ちゃん、どうしたの?」
「あ、ああ、ちょっと喉が渇いて……」
「早く寝なさいね。また明日も学校なんだから」
母の後姿を見送って、涼子は再び庭を見た。冬枯れた雑草が生い茂り、荒れた庭。ここをもとに戻すには、やはり水の力が必要なのだ。
翌日、登校した涼子は、真っ先に玲に質問した。授業が始まる前の、朝のことだった。
「ねえ玲ちゃん、蹲踞って、そもそも何?」
「ふうん、涼子はんからそんな質問が来るとは……」
玲は涼子を見つめると、すぐにいつもの笑顔になった。
「蹲踞っていうのはな、お茶室に入る人が、手と口を清めるために置かれた物でな、有名なのは龍安寺にある、この謎々……」
そう言って玲は、ノートにペンで円を描き、中央に四角形を描いて、その四隅になにやら漢字を書いた。
「これ、なんて読むかわかる?」
「えっと……、ああ、わかった。この四つの漢字に共通する一部分が真ん中の口なのね。すると、『、吾、唯、足るを、知る』これでいい?」
「正解!」
玲は笑顔で丸をつけた。
「神社にもあるやん、あの、お参りの前に口と手を清めるやつ、あれの一種やで。元々はお茶の世界のしきたりや。それを日本庭園が取り入れて、今はいろんなバリエーションがあるさかい、涼子はん家の六角蹲踞もその一種や。でな、蹲踞には大抵、筧っていってな、竹で出来た一種の水道があって、ここから水が落ちとるん」
玲はまた図を描いて示した。
「ふうん、そうなんだ」
「でも、どうしたん? 急に。蹲踞のこと訊くなんて」
「あ、いや、ちょっと……」
その日の放課後、涼子と玲はいつものように園芸部のある一番教場に行った。部室には加賀先輩と、菜摘先輩、小川君が揃っていた。
「丁度良かったわ。二人共。今三人で、涼子さんのお庭のこと、相談してたんだけど……」
加賀先輩が口火を切った。
「研修旅行?」
涼子が驚いた。
「いえ、旅行といっても、一日この京都を周るだけなんだけどね」
加賀先輩が二人に椅子を勧めた。
「カモ高園芸部の伝統行事なの。毎年春の五月に、京都のお庭を観てまわるの。二人は初参加だから、いろいろ戸惑うこともあると思うけど……」
「へえ、是非行きたいです」
涼子は一体どんな所に行くのだろうと興味津々だった。
「今年の研修旅行のテーマは、『石』にしたの」
「石!?」
思わず涼子は声に出した。
「石って……、あの、お庭の?……」
玲が尋ねると、加賀先輩は静かに頷いた。
「そうよ。日本庭園といえば、欠かせないわよね。今年は京都の色々な名庭を巡りながら、石について考えるのが目的よ」
「石ですか……」
涼子は不思議だった。
石って、思い切り地味だし、どれも同じに見える。
「ほなら、今度の五月三日、京都駅前に集合な」
菜摘先輩が告げた。
「歴とした部活動やさかい、時間厳守やで」
小川君が付け足した。
「それじゃ、楽しみにね」
涼子は玲がなんだか、急にソワソワし出したのを見て、不思議に思った。
「玲ちゃん、石は詳しいの?」
「言う程やないけどな、嫌いやないさかい」
「ふうん……」
涼子は不思議な感じで、この研修旅行の話を聞いていた。
四
快晴の木曜日だった。
京都駅のバスロータリーには観光客が長い列を成していた。聳え立つ京都タワーの展望台のガラスが陽光に煌めいている。
「おはようさん」
一番乗りで現れたのは玲だった。昨日スマホで相談した通り、制服姿だった。
「だって、部活動や、ゆうし」
「今日はどこ行くんだろうね」
「それは小堀はんが決めとるさかい」
「おはよう、二人共」
やはり制服姿の加賀先輩と、同じく制服の小堀さんと小川君がやってきた。
「じゃあ、行こうか」
市バスの五百円カードを買って、五人はバスの列に並び、乗り込んだ。
「今日は小川君ゆかりの地に行くから」
加賀先輩のその一言に、つり革につかまっていた涼子達は謎を与えられた子供の気分だった。当本人の小川君は端正な目元を緩めることなく窓外の景色を見ている。
東本願寺の巨大な甍と門構えを過ぎ、所々に瓦屋根の旧家のお屋敷と、寺院の混じる街並みを走って、ざっと三十分程。
「さあ、ここで降りましょう」
加賀先輩に続いて一同はバスを降りた。
数分歩くと、平安神宮の朱塗りの大鳥居が遠くに見えた。そして道は、南禅寺へと続く長い道路になった。
「ここを曲がったところにあるんやで」
さっきから高くて古そうな立派な塀が続いていたが、見ると道路に面して入り口があった。
「無鄰菴よ」
加賀先輩に先導されて、五人は中に入っていった。
「ここにお庭があるんですか?」
入り口で拝観料を払いながら涼子が訊くと、加賀先輩はその通りだと頷いた。
入り口を示す古い立て札を過ぎて一歩入ると、思わず涼子は息をのんだ。
左手にはこの家の主が済んだであろう古風な二階建ての日本家屋。その向こうには広大な芝生の庭園が広がっている。彼方に見える東山が借景になって、まるで庭はどこまでも続いているかに思われた。
「国名勝・無鄰菴庭園。小川君のご先祖が造ったお庭よ」
「ええっ!?」
涼子は思わず声を上げた。
時は明治二十七年。
内閣を二度にわたって組み、内務大臣や枢密院議長を歴任した明治政界の大御所、山県有朋。そんな彼が、ここ京都に作った別邸を無鄰菴という。
山県は庭好きとしても知られ、この無鄰菴庭園も、彼がお抱えの庭師と造り上げたものだ。
ある時、無鄰菴を訪れた山県は、庭を造っている職人達に、その石はこっちだ、その木はあちらではなくこっちだ、と指示していた。それを見た一人の庭師が、山県の前に出て、「閣下、あなたは百万の軍勢を動かすことにかけては上手な人かもしれないけれども、木石を動かすことについては素人なんだから、黙ってらっしゃい! 」と山県を𠮟りつけた。その庭師こそ、明治・大正の伝説の庭師・七代目小川治兵衛だった。その彼の末裔が小川君……。
「それ、ほんとなんですか?」
そう涼子に訊かれて、加賀先輩はにっこりと頷いた。
「俺は次男やから、跡は継がんけどな」
小川君は庭の彼方を見やりながら、相変わらず鋭い視線を向けていた。
「この庭が造られた頃は、まだ個人の家に川が流れているのは珍しいことだったの」
庭に入り、心地よい音で流れるせせらぎの上を、沢飛び石を渡りながら先頭に立つ加賀先輩が解説した。
「首都が東京に移って、国の中心ではなくなった京都は、明治に入って衰退していったの。そこで、京都の経済を活性化させようと起こされた明治の大土木事業が、琵琶湖疎水開通工事だったわけ。この工事の許可を与えたのは当時内務大臣を務めていた山県で、六年をかけて完成した時は総理大臣だったの。そんな山県は、ここ南禅寺界隈に初の別荘を築いて、京都の別荘地文化の草分けになったのね。でね、涼子さん、このお庭は当時、とても斬新だったんだけど、どうしてかわかる?」
涼子は庭を眺めてみた。
おおらかで開放的な庭だ。植物が存分に枝葉を伸ばし、水のせせらぎがなんとも心地よい。
だが、京都の庭でよくある作り方とはどこか違う。涼子にもそれは感じられた。
「芝生よ」
言われてみると、この庭は青々とした芝生の広がりが、どこまでも続いている。
「そして、この川」
水が滝になって落ちている。二段、三段となって、川に注いでいる。
「この川の水はね、山県が関わった琵琶湖疎水の水を引いているの。疎水の水が個人の家に引かれた初の例なのよ。それまでは、日本庭園の水と言えば、池が中心だったけど、山県は池よりも川のほうが好きだったのね」
確かにその通りだった。
芝生が一面に広がる庭は、京都の他の庭園とは空気が違う。
庭を見た後、五人は母屋の座敷に上がり、お抹茶と和菓子を食べた。
菓子は丁度今が旬の菖蒲を見立てて作られたもので、楊枝で切り分けて食べた。お抹茶の苦みが、なんとも心地よかった。
無鄰菴を後にして、一同はまた市バスに乗った。
「今度はどこに行くんです?」
「今日のテーマに深く関係するところ」
しばし、窓外の京都の街並みを眺めて、次の目的地についたらしかった。
「涼子はん、京都の禅寺はそれぞれ京都でしかわからん別名が付いとるんやけど、知ったはる?」
菜摘先輩にそう言われて、涼子はそんなものがあるのかと感じた。
「武家の崇敬を集めた南禅寺は、『武家づら』、立派なお堂が仰山ある東福寺は、『伽藍づら』、五山の学問僧が活躍した天龍寺は『学問づら』言うてなあ」
「へえ……」
「妙心寺は、でかい教団を組織したさかい、『算盤づら』言われとる」
小川君が付け足した。
「でな、これから行く大徳寺は、千利休が出入りしとって、お茶が栄えた寺やさかい、『茶づら』言うんやで」
菜摘先輩の話を聞きながら境内を歩いていると、壮麗な山門が見えてきた。「金毛閣」と呼ばれているらしい。
「ここでは、塔頭の大仙院を見ます」
広い境内に圧倒されつつ、大仙院の中に入った涼子は、その庭を見たとき、思わず声を上げた。
「こ、これが大徳寺大仙院庭園……」
決して広くはなかったのだが、隅々まで手入れが行き届いているのがわかった。
「これは一般に枯山水と言われている庭園で……」
加賀先輩が解説を始めた。
「左の奥、あそこに川を現した砂利があるの、わかるかしら?」
見ると、確かに灰色の砂利が敷かれている一画があった。
「あれが、水源の峡谷を現していて……」
加賀先輩の説明の通りに視線を動かしてゆく。
「お庭の真ん中、一面に砂利が敷かれている所は、川が海に注ぐ景色で……」
言われてみれば、丁度置かれている大きな石が、島に見える。
「あとは一面、大海原なの。このお庭では砂利が水で、石が島や山になっているのね」
涼子は思わずため息をついた。
砂利と石で水を、それも川から海まで表現するとは、信じられなかった。
「ちなみに、日本庭園には『亀石』っていうのがあって……」
加賀先輩は庭の左端に五人を誘った。
「これが、大仙院の亀石よ」
見ると、石がごろごろと並んでいる。
「あの……、どこが亀なんですか……」
「これが頭で」
一番端の石をそう説明し、次に真ん中の大きな石を、これが胴体で、と言って、その周りの小石を手足、一番右端の石を、これが尻尾、と言った。
「ああ、そう言われれば亀に見えるかも」
玲が笑っている。
「どう、涼子さん、石なんて、どれも同じだと思ってたでしょう?」
図星を突かれて、思わず涼子はぎょっとした。
「あ……。た、確かに……。でも」
涼子は威儀を正し、声を抑えた。
「今日の見学で、石のイメージ、変わりました」
それは本当だった。
今までは、石なんてどれも似たような物で、それを使って何かを表現するなんて、馬鹿馬鹿しいと思っていた。でも今は違う。加賀先輩の解説と、実際に石を見たことで、その表現の可能性の素晴らしさに感じ入ってしまった。
「石が分かればたいしたもんやで。なあ、涼子はん」
小川君が庭を眺めながら呟いた。
そして、ここでは時間の流れ方が違っていると感じた。
京都は不思議な街だ。
大都会なのに、少し横道や、奥に入ると、これだけ静かで、緑溢れる別天地にたどり着く。
東京にはこういう場所は無かった。
そして一日が終わった。
五人は再び朝の京都駅にやって来て、そこで解散となった。
「ねえ、玲ちゃん、今日の旅行、どうだった?」
「えらいおもろかったわあ」
五月の赤い夕焼けが、西の空を染めていた。
立った半日が、ずいぶん長く感じられた。
五
草の根に、全力を込めて引き抜く。
引き抜いてはまた引き抜き、また引き抜いては引き抜き、それをもう半日は繰り返している。
六月終わりの、ある日曜日。
空はどんよりと曇ったその日、涼子の家は朝から賑やかだった。
カモ高園芸部の部員達五人が揃って、後藤邸の庭の本格的な復興作業が始まったのだ。
まず、この雑草をなんとかしないと。
加賀先輩のその一言で、涼子達五人は庭園の草取りをしていた。
しゃがんで、手に力を込めて草を引き抜く、この作業が、想像以上にしんどいことだと涼子は思い知らされた。始めて三十分程で両腕と脚が痛くなってきた。ジャージを着ていたので、服の汚れを気にする必要こそなかったが、この猛烈な痛みはなんとかならないものか。
加賀先輩や菜摘先輩、小川君は涼しい顔でやっている。
玲と涼子は何度も上を見上げては、痛む首筋に悩まされた。
そんな作業を半日続けて、ようやく庭はその本来の姿が現れつつあった。
一抱え程もある雑草を、もう十回は運び出しただろうか。
「みんな、一息ついて。お茶がはいったから」
午後二時頃、母が紅茶を用意した。加賀先輩達はお礼を言いながら軍手を外し、縁側に座ってしばし休憩となった。
ここから見ると、随分と広い庭なんだなというのがわかった。正面の蔵の様子がここからはよくわかる。
「涼子さん、どう? お庭の手入れを初めてやった感想は?」
加賀先輩に訊かれて、想像以上に大変ですと答えた。
「でも、草を取るたびに今まで知らなかったお庭の姿が見えてきて、それが楽しいっていうか……」
「せやなあ、作業はめっちゃきついけど、庭がどんどん綺麗になっていくのを眺めるのは快感やね」
玲が続ける。
「加賀先輩達、平気な顔してますけど、きつくないんですか?」
「鍛え方が違うさかい」
小川君が紅茶を飲んだ。
「カモ高園芸部やったら、これくらい出来ひんと、なあ」
菜摘先輩がお茶菓子のマドレーヌをぱくりと口に入れた。
「草取りは園芸の一番の基本だから」
加賀先輩が二杯目の紅茶に角砂糖を入れた。
「でも、こういうことが、庭と生きていくってことだから」
そんな加賀先輩を眺めながら、涼子はマドレーヌを口に入れた。
「庭と生きていく、かあ……」
午後五時近くになって、ようやく草取りが終わった。
庭は昨日までとは全く違う姿になった。
隅々まで渇いた土が現れ、薄に埋もれていた石灯籠が全容を見せた。飛び石の並び方がわかった。正面の蔵と、その左右に見えるこの家の杉皮張りの塀がよく見えるようになった。
「まあ、随分眺めが変わったわねえ……」
五人が作業を終えた時、母が感心したように見ていた。
首と腕と両足が痛い。明日は筋肉痛で更に痛くなるだろう。
「結局、シュロチクとか、植栽は無かったなあ」
小川君の話によると、庭には本来色々な植物が植わっていたはずで、何種類かその残りがあるかもしれないと思っていたという。
「はい、涼子さん、これ」
帰り際に玄関で、一冊のスケッチブックを加賀先輩から手渡された。
「なんです? これ……」
「設計図、描いてみて!」
「設計図!?」
涼子が驚いていると、加賀先輩は今日の疲れを感じさせない活き活きとした眼をしていた。
「これに色々描いてみて。涼子さんが理想にしているお庭の絵。見取り図を描いて、ここにこんな木を植えたいとか、こんな花を植えたいとか、あると思うの。それを……」
「好きに描いたらええよ」
菜摘先輩が微笑んでいる。
「はあ……」
「大丈夫。草木の苗や株は園芸部が公式に用意するから。だってこれは立派な部活動だから」
「みんな今日はお疲れ様」
母が四人を見送った。
「それはあなたのお庭の設計図だから。自由に、ね……」
「設計図、かあ……」
なんの変哲もない一冊のスケッチブック。
でもその先には、なんだか楽しくて、とても大きな可能性がある、そんな気がした。
「ここに、私のお庭の理想を描くんだ……」
漠然とした夢に、加賀先輩が形を与える術をプレゼントしてくれた瞬間だった。
その夜のこと、涼子はスケッチブックと色鉛筆を手に、縁側で庭の設計図を描こうとしていた。
このお庭の理想……。それを形に。
だがそれは、予想を遥かに超える難問だった。
まず、理想の庭が、浮かんでこない。
一体どこから手を着ければいいのだろう。植物を植えると言ったが、果たして何を植えれば?
三十分程、手にした鉛筆が止まった時、ふと気配がして顔を上げると、あの少女がいた。
「あ、翠水さん……」
「なにやら面白そうな物を手にしたようだな」
涼子は相変わらず目の前の存在が信じられなかったが、それでも翠水に今日の出来事とこのスケッチブックの由来を話した。
「お主らが草を取ってくれたお陰で、私も久しぶりにせいせいした」
翠水はすっかり綺麗になった庭を見渡して、口元に笑みを湛えながら庭を見ている。
「ほう、『夢の庭』の設計図か」
「そうなの。でもなんにも浮かばなくて……」
翠水は悪戯っぽい眼で手を後ろに組みながら近寄ると、その隣に座った。
「好きな木を、好きに植えていいって言われて。本当はね、このお庭に少しでも木が残っていると思っていたの。でも庭を調べてみたら一本も残ってなくて」
「それはそうだ」
翠水はいとも簡単にその訳を教えた。
「この庭の木々は、既に全て枯死している。放って置かれた時間が長かったからな。それに前の持ち主が金に困って、目ぼしい木々は全て売り払っている」
「そうなんだ……」
初夏の趣を見せ始めた庭を、風が渡った。
「この庭の主題は、水だ……」
「主題?」
「ああ。そもそもこれに……」
翠水はあの六角蹲踞を指差した。
「これに満々と水が湛えられていた。筧から清らかな水が流れていて、それが水の流れと心地よいせせらぎを聞かせていた。いつしか水は止められ、枯れてしまったが、かつては水に満ちた庭だった。
「水が主題……」
その時、涼子の心の中で、何かが変わった。
それは丁度、播かれた種が発芽し、新しい根を伸ばし始めた瞬間のようだった。
「主題……。そうだ。テーマを決めればいいんだ」
翠水は急に様子が変わった涼子を不思議そうに眺めた。
「ねえ、翠水さん、このお庭、水が主題だって言ったわよね?」
「ああ……」
「それだわ!」
涼子はスケッチブックをもう一度開き、鉛筆を持ち直した。
「水をテーマにしたお庭を造ればいいのよ! 水に関わるお庭……。そう、翠水さん、聞かせて、水のあるお庭には何が植わっているかしら?」
「そうだな……。例えばセキショウだ」
「セキショウ?……」
「ああ。山村の川辺に行くとよく生えている。水辺にある草で、冬の終わりに花を咲かせる」
「じゃあ、それをこうして……」
涼子はまず、蔵へと至る飛び石の両側に星印を数か所付け、矢印を引いて「セキショウ」と書いた。
「岸辺をイメージしたの。あと川も。で、川が流れていくと、次第に里山に近づいて行くわよね? だから賑やかに花を植えて……。あ、そうだ、椿がいいわ」
次々と着想を得て描かれていく設計図を、翠水は半ば唖然として見ている。
「そうだ、玲ちゃんの言ってたシュロチクはここに……。あ、そうそう、翠水さんの蹲踞、この前蛇口を発見したの。だから水を流せるわ。で、蹲踞の周りに石を組んで……」
一時間程で、庭の大まかな見取り図が出来上がった。
「これ! 題して『水の庭』。あの日、加賀先輩が教えてくれた、大徳寺大仙院のお庭みたいに、山の渓谷から発した水が、森を流れて、里山に続いて、更に流れていく……。これでいいわ。ありがとう、翠水さん!」
翠水は完成した庭の設計図を見ている。
「これは、お主にこんな絵心があったとは……」
涼子はフフッと笑うと、スマホを取り出した。
玲と加賀先輩と菜摘先輩と小川君に、設計図が出来たとメールした。
「詳しくは明日お見せします。とにもかくにも、プランは出来ましたから」
「そう。明日見せてね。楽しみにしてる」
「よかったなあ、涼子はん。明日見せてや」
「楽しみにしとるで、なあ」
加賀先輩、菜摘先輩、小川君が返事をくれた。
「どうなるかと思うたけど、出来て良かったな」
玲が少しだけ遅れて返事をくれた。
六
七月のある放課後、園芸部部室には加賀先輩達五人が揃った。
「ほなシュロチクと、椿と、セキショウと、あとは?」
菜摘先輩がまとめると、加賀先輩は腕を組んで考え込んだ。その両目は涼子が描き上げたスケッチブックを見つめている。
涼子がこれを仕上げてからというもの、園芸部の五人は毎日のように部室に集まり、盛んに議論した。
特に話題になったのは、蹲踞周りの石組に使う石の種類と、この庭に新たに導入すべき要素があると言った菜摘先輩の指摘だった。
「京都のお庭やさかい、やはり『あれ』が必要やん」
菜摘先輩の指導は的確だ。
春の研修旅行で涼子の石の見方を変えた大仙院の庭園を訪問スポットに選んだのも菜摘先輩だし、ここ数日では庭に植える植物を選ぶにも、その咲く花の色まで細かく研究して選定してくれた。
「あれ」ってなんだろう。
涼子が不思議に思っていると、加賀先輩が意を決したように涼子に視線を向けた。
「涼子さん、このスケッチブックであなたが前よりも随分とお庭が好きになったのはわかるけど、お庭ってそれだけではないわ」
「はあ……」
涼子の反応に、フフッと笑みを浮かべた。
「涼子さんは、お庭の手入れを毎日出来る?」
「ま、毎日ですか?」
「そう、毎日」
日本庭園というのはなにかと手がかかるのもだとは思っていたが、毎日手入れをするという発想は無かった。
「今小堀さんが言った『あれ』って、なんのことかわかる?」
その答えは涼子には想像もつかなかった。
植える木は選んだ。あとは何があるのだろう。
「それってもしかして、『苔』ですか?」
玲が涼子に代わって訊いた。加賀先輩は目元を緩めた。
「その通り。苔のことよ。ねえ涼子さん、京都のお庭にはね、苔が重要な要素になるの」
「苔……、ですか……」
涼子は不思議だった。苔なんて、地面に生えてるあの苔?
それがお庭に欠かせない?
「涼子さんのお庭、苔を植えたらとても素敵だと思うの」
すると加賀先輩は椅子から立ち上がり、書棚を漁って一冊の本を取り出した。
「これ見て」
それは大型の本で、見開きのページ一杯にまるで緑の絨毯のような物が庭を覆っている。
それは瑞々しい緑色で、その美しさには息をのんだ。
「これは東福寺のお庭で、この通り見事な苔があるの。涼子さん、あなたの家のお庭もね、この苔を植えたら素晴らしいわ、きっと」
涼子は思わず自分の庭を想像した。
今、あの庭は渇いた土が広がっている。あれが全てグリーンに変わったら……。
「ただな、この苔っちゅうのはえらい手入れが大変でな」
菜摘先輩が始めた。
「真冬でも二日に一度は水を撒かんとあかんでなあ、春秋は毎日、夏は毎朝、毎夕水をやるんやで」
「はあ、それで……」
涼子は加賀先輩の言葉の意味がわかった。
毎日手入れするというのは、この苔のことだったのだ。
そしてその写真を見て、涼子の苔に対するイメージが変わった。
苔なんて、地面にただ生えてるだけのつまらない物だと思っていた。しかしこの写真の苔は違う。なんだかとても柔らかそうで、優しくて、潤いに満ちている。
関東出身で苔のある庭とは無縁だったので、その真価に気づくことが無かったのだ。
「とりあえず、出回ってるのだけでも五十種類はあるさかい、どれにする?」
菜摘先輩の問に、そんなに沢山、と驚いた。
「スギゴケ、ヒノキゴケ、ハイゴケ、ホソバオキナゴケとか、仰山あるで」
小川君に言われて、一体自分の好みにはどれが合うのだろうと考えた。
「西芳寺って知ってる?」
加賀先輩に訊かれて、名前だけは知っていると答えた。
通称「苔寺」。境内は一面様々な苔に覆われているらしい。
「ハイゴケがいいかもね」
加賀先輩はまた書棚を探り、本を手にしてテーブルの上に開いてみせた。
「これ、苔寺のお庭なんだけど、ここにあるのはハイゴケよ」
鏡のような水面の池の周りを木々が囲い、その足元には新緑色の苔が生えていた。それは関東の苔とは全然違う、本当に美しいものだった。
「手入れは覚悟せんとな」
小川君が添えた。
その翌日の土曜日。
梅雨も終わりに近づいたこの日、後藤邸の前には一台の軽トラックが停まっていた。
荷台には何本もの樹木や苗、それに幾つかの石が載っていた。
シャベルやスコップなどの農機具もある。
母は朝から現れた園芸部の五人を見て、今度は何かしらと言っていた。
いよいよ庭の本格的な工事が始まった。
「これは侘助さんやで」
菜摘先輩に言われて、それは何と訊いた。
「お茶の世界ではな、茶花の女王って呼ばれとる花や。花は一重でな、控えめに詫びるように咲くから侘助言うんや」
そうして荷台にある三本の苗木を示した。
「色は白、ピンク、赤と持ってきてもらったさかい」
「ありがとう。でも、これ一体誰が?……」
「家の兄貴やで」
小川君が運転席にいる青年を指した。
「おお、みんなお久しぶり。ああ、俊治、この子が前に言うとった……」
髪をこざっぱりと刈った、よく日に焼けた年は二十四、五歳といった青年だった。
「せや、新入部員の後藤はんと重森はん」
「弟をよろしく」
五人は力を合わせて庭と格闘した。
涼子の設計図通りに、まず穴を掘った。
涼子も大きなシャベルを手に、穴掘りに奮戦した。
「この木やったら、バケツ一杯程ほらんとあかんで」
小川君の指導通りにそう掘ろうとするのだが、土というのはある一定の深さを超えると、超絶的に掘るのが難儀になってくるのを知った。
土の密度が高いというか、目が詰まっていて凝縮されていて、中々シャベルの歯が立たないのだ。
すでに豆が出来そうな程痛い手を更に奮起させて、シャベルを地面に突き立てる。
軍手をしているがそれはほんのごまかし程度に思える程土が頑強だ。
シャベルに逆らう土に一心に力を籠めていると、大理石像を掘る時の彫刻家はきっとこんな気分なんだろうなと思う。
土と対話している気分になるのだ。
これが、大地なのだ。
これだけアスファルトが敷かれ、整えられた大都市でも、大地は厳しい。
滴り落ちた汗が穴の底に染みていく。
二時間程かけてようやくバケツ一杯の穴が掘れた。
菜摘先輩や加賀先輩や小川君は、苗木を植え始めている。
「穴、掘り終わりました」
「よし、ほならこれを」
小川君が片隅にあった植物を持ってきた。
これはシュロチクだ。
初めて部室に行った日に加賀先輩のスマホ写真で見たものだ。忘れない。
扇形の葉はとても美しく、「緑の宝石」と呼ばれているのも頷ける。
途中、昼食を摂った。
母がちらし寿司を作ってくれた。
縁側に五人並んで食べながら、出来かけの庭を眺めた。
ひたすら荒涼としていた庭に、命の息吹が込められているようだった。
真正面の蔵を背景に、シュロチク、侘助さん、そしてセキショウが植えられ、二三か所にシャベルが刺さっている。
五人とも無言でちらし寿司を食べた。
「あ、鳥……」
玲が声を上げた。
一羽のヒヨドリが、モミジの若木の枝にとまった。
午後は、石を運んだ。
小川君のお兄さんが言うには、これは鞍馬石といって今では採掘するのが難しい貴重な石だという。丸くなって寝ている猫程の大きさの石にまず縄をかけ、それを太い木の棒に吊るし、駕籠を運ぶように二人で運んだ。
玲とは背が同じ位だったので良かった。
それを、涼子の設計図通りに、掃除をして綺麗になった六角蹲踞の周りに置いた。
四つの石を組むのに二時間かかった。
その間何度も「ちょっと待った」と「ちょっと休憩」を涼子は繰り返した。
ようやく運び終え、石組が出来上がる頃には、時刻は午後五時を回っていた。
なんとか形になった庭を前に、五人の息遣いが聞こえた。涼子は肩で息をした。
手や首や腰や足が痛かった。しかし不思議な充足感があった。何かを生み出すということは、こういうことなのだろう。
「みんなお疲れ様! やっと基礎が出来たわね。後は……、あれね」
最後に、加賀先輩が一同をねぎらいつつ、視線を投げかけた。
そこには、あの翠水の依り代、六角蹲踞があった。
七
夏が終わった。
京都の夏は本当に暑かった。
東京育ちの涼子には堪えた。だが、庭の植物たちは夏を耐え抜いたようだった。
シュロチクは新芽が伸びて、新しい葉が二枚程育った。
侘助さんは葉の緑が深く、セキショウは夏の間に枯葉取りをした。紅葉は青々とした葉を湛え、今ではヒガンバナの新芽が数か所に吹いている。
夏の間は、とにかく草取りが大変だった。
陽光と暑熱で溶鉱炉となった庭の中で、涼子達五人はひたすら雑草の芽を摘んだ。
そして肝心の苔はといえば、夏を越してから植えたほうがいいと加賀先輩が言った。
今植えてもどうせ夏の暑さで痛むから、涼しくなってからにしましょう。大丈夫、秋からでも間に合うから。
九月も半ばを過ぎ、朝夕はわりと涼しくなり、猛烈な暑さがようやく収まりかけてきた時、涼子はふと、母と二人で庭を眺めることもあった。
冷えた麦茶を用意し、東京の実家から持ってきた江戸切子のグラスで飲んだ。
「でも、不思議な子ねえ。あの子」
「誰が?」
母はグラスを口元で傾けている。
「あの加賀さん、だっけ? 加賀理沙子さん。いつも来てくれるけど……」
「それがどうかした?」
涼子は麦茶を一口飲んだ。
「あんなに献身的に家のお庭を造ってくれて、なにか家に恩義でもあるのかしら……」
言われてみれば、確かに加賀先輩のこの家への愛情は深かった。
「性格がいいんじゃないの?」
「それだけかしら……」
母はグラスを右手に持って、微かに揺すっている。
「何か深い理由があるんじゃないの?」
「理由? どんな?」
「だから、何か決定的な理由よ。今時の子があんなに義理堅いなんて、なんか不思議だわ」
「考えすぎじゃないの?」
渇いた風が吹いた。木々の葉擦れの音が潮騒のように聞こえてくる。潮騒が海の予感なら、これは森や林の面影だ。
植えた時には鮮やかに照っていた新緑も落ち着き、木々の葉は秋色に沈んできた。
あのヒガンバナが咲けば秋だろう。
十月になって、すっかり涼しくなったある日曜日、後藤家にカモ高園芸部の五人が揃った。
「へえ、これが苔?……」
和菓子屋さん等でよく羊羹やお餅を入れてあるような一抱え程の大きさのプラスチックケースに、ビロード生地のような緑の苔が詰まっている。
「植えるのにはコツがあって」
加賀先輩は寿司飯を扱う職人のように手慣れた仕草で苔のシートを取り出すと、土の上に植えた。
「土の上に被せたら、馴染むように足で踏むの」
加賀先輩は実際にやってみせた。
「えーと……、こうして……」
やってみると、苔はとても崩れやすく、加賀先輩がやったようにはなかなかいかない。美しい緑は、指の間に崩れていく。豆腐のようだった。
玲も早速苔を植えていたが、やはり慣れるまでかなり難しい。
一時間程で全ての苔を植えた。植え付けが済むと、水を撒いた。
「大体三か月くらいだと思う」
加賀先輩の言葉に、苔というのはなんて気の長いものだろうと思った。
「根付いてくると、深い緑色になって、水を掛けるのが楽しみになるんやで」
菜摘先輩の言葉に、少し今後が楽しみになった。
上手く根付いてくれると良いのだが。
それから三か月。
後藤家の花暦は秋を歩んだ。
ヒガンバナが咲き、紅葉が真っ赤に色づいて、金木犀が咲いた。
そうして、涼子が上賀茂高校に入って最初の一年が終わろうとしていた。
そんな年の瀬の、十二月二十日のこと。
「加賀先輩、お誕生日おめでとうございます!」
カモ高園芸部の五人は、加賀先輩の誕生日を祝った。
場所は東山、円山公園のすぐ近く。
長楽館の一室を貸し切りにした。
長楽館は明治時代に建てられた洋館で、当時、「煙草王」と呼ばれた村井吉兵衛という人が建てたという。本邸は東京にあったらしいのだが、ここ京都にも別邸として建てられた。
まるでロンドンのリージェンシーストリートの一画のような門を入り、屋敷の中に入ると、そこは明治の昔がそのまま残っているような、古風なインテリアに触れられる。
高い天井からはクリスタルのシャンデリアが幾つも下がり、今日園芸部が借りた部屋はアフタヌーンティー用に使われる一室だった。
「みんな、ありがとう」
高校生には少し敷居が高いこのレストランで、菜摘先輩と小川君は春から始めたアルバイト代のほぼ三分の二をはたいたと言っていた。
この誕生日パーティーの話は十一月頃から、加賀先輩本人には内緒で準備されていた。
前日に、涼子と玲は二人で京都駅の伊勢丹にある花屋さんで、プレゼント用の花束をあつらえた。
「ご予算はどれくらいですか?」
若い女性の店員さんに言われて、二人は先輩達が大金を使うのだからと、奮発して七千円ぐらいかな、と説明した。
「お誕生日のプレゼントですと、華やかなほうがいいですね。こちらのバラですと、かすみ草と合わせたり、百合と一緒にしたり……」
「加賀先輩は、バラも近いけど、むしろこれかな?」
涼子は加賀先輩のイメージを思い浮かべて、清楚な白い蘭の花をリクエストした。
「胡蝶蘭ですと、こちらは?」
胡蝶蘭はいまいち違う気がした。
「むしろ、あれが……」
涼子はガラスケースの中にあった、白い大輪のカトレアを指差した。
「あれを一輪入れて下さい」
「それですと、七千円では収まりませんが……」
「いくらです?」
「カトレアは一輪二千円程……」
結局二人は九千円の花束を買うことになった。
だがその白い大輪のカトレアは本当に美しく、気高いものだった。
これなら加賀先輩のイメージにぴったりだ。本人も喜んでくれるだろう。
そのカトレアとクリーム色のジキタリスの花のブーケを、涼子が差し出した。
その時だった。
花束を受け取った加賀先輩は、その中に一際目立つカトレアを見るなり、ふと眉間に皺が寄った。
どうしたというのだろう。
蘭の花が嫌いという人はあまりいないと思うのだが。
「あ、ありがとう……」
すぐに笑顔に戻った加賀先輩は、ブーケを抱えて微笑んでいた。
しかし涼子は、加賀先輩のあの一瞬の、顔の曇りの理由がわからなかった。
一体どうしたというのだろう。
その後は四人からプレゼントの贈呈があった。
菜摘先輩はレースのハンカチ、小川君はミュシャの絵の銀の栞、涼子と玲は二人で革製の文庫本カバーを贈った。
それから皆はいつものペースで、冗談を言ったり、思い出話をして、運ばれてくる紅茶を飲み、洋菓子を食べた。
だが涼子には、カトレアの花を見たときのあの顔の翳りが、バラの棘のように気持ちに刺さり、どうにも気になるのだった。
ティーパーティーが終わり、そろそろ帰ろうかと一同がすっかり氷の解けた水を飲みだすと、加賀先輩はちょっとお手洗いにと言って、一人化粧室に向かった。
そのすぐあと、一応自分も済ませておこうと、涼子は部屋を出た。
すると、廊下の先に加賀先輩の後姿があった。
「先輩、もういいんですか?」
それを聞いたか聞かなかったか、加賀先輩はゆっくりと振り返った。
「ああ、涼子さん。なんでもないの」
「寒いから、コートきちんと着たほうがいいですよ」
「ありがとう」
ふと涼子は、先程の心の中の棘が異物のように感じられた。
「あの……」
「何か?」
務めて平静を保とうとする加賀先輩を見て、やはり気になった。
「カトレア、お嫌いでした?」
「え?」
「いや……、その……、さっき、お花差し上げた時に、ちょっと……」
「ああ……」
加賀先輩は、手札を読まれたカードゲームのプレイヤーのように、明らかに表情を濁らせた。その美しい二重の眼の煌めきが、一瞬失われた。
「別に、嫌いじゃないわ……」
「ああ、なら、いいんですけど……」
「今日はありがとう」
「いえ、いつもお世話になってますから……」
二人共口を噤んだ。
「理沙子ちゃん、そろそろ帰るよ」
菜摘先輩の声がした。
二人はそのまま、揃って廊下を後にした。
八
年が明け一月になった。
その日は朝からたいそう冷え込み、午後から雪が降りだした。京都の冬は厳しいと聞いていたが、これほど寒いものかと驚いた。
真夜中に、ふと目を覚ました。
中庭にはすっかり雪が積もり、清らかな雪明りが満ちていた。寒さを忘れて庭の雪景色を眺めた。すると、翠水が現れた。いつものように悪戯っぽい笑みをして、隣に座った。
「寒いけど、綺麗な雪ね」
「ああ」
相変わらずマイペースな翠水だったが、涼子はふと去年のお誕生会での加賀先輩の気になったことを話した。
「どういうわけか喜んでもらえなかったの」
「そうか……」
すると、翠水はいつになく真剣な表情に変わった。横顔からも、その眼差しの真っ直ぐなことがわかる。涼子はもしかして、と思った。
「ねえ、何か知ってるの?」
「知ってるって、何をだ?」
「だから、加賀先輩とこの家のこと。だってあんなに一生懸命にこの家のお庭を造ってくれて。なにか深い理由があるの?」
翠水は隣に腰かけたまま涼子の顔を見た。その翡翠の色をした瞳はいつになく真剣だ。
「ねえ、知ってるんでしょう? 何もかも。だって翠水、大昔からここにいるんでしょう?」
「どうしても聞きたいか?」
翠水の返事に、真実を知る覚悟は出来ているから、と答えた。すると翠水はまた庭に視線を戻して、おもむろに口を開いた。
「あれは、大正の半ば頃、まだこの国に子爵様や伯爵様がいた時代のことだ」
翠水は膝の上で両手を組み、続けた。
「かつて加賀正太郎という実業家がいた。大阪の船場の出で、家は江戸以来の両替商で、関西財界では絶大な威光を持つ名門の御曹司だった。その頃、日本には英国から伝わった蘭の栽培が盛んになっていた。しかし当時は、蘭は非常に高価で、貴族や大富豪しか手にすることは出来なかった。東京では池田家や福羽家や、島津家といった名だたる大貴族達が『帝国愛蘭会』を結成し、華族達を中心に本格的に蘭の栽培が行われていた。そんな矢先、胡蝶蘭やオンシジュームに混じって、カトレアも日本に入ってきた。あの頃はまだ蘭の交配種を作ることは揺籃期で、英国をはじめ、世界の国の有力者達が持てる富を注ぎ込んで、園芸家を雇い、自宅の大きな温室で品種改良を行っていた。加賀家も、そんな園芸家の品種改良を手伝う有力なパトロンだった。正太郎は京都の大山崎に山荘を建て、そこに壮大な温室を建築した。そこを拠点に、東京から呼んだ若手園芸家を雇い、日夜、カトレアの品種改良を行っていた。その園芸家の名を、藤堂兼吉という。弱冠二十六歳で、東京の新宿御苑の鏑木健次郎に師事し、蘭栽培の本場英国への留学経験もある逸材だった。その青年園芸家は、十七歳の時に、師の鏑木が新宿御苑の温室で栽培していたカトレアの美しさに惹かれて以来、熱狂的にこの花の品種改良をライフワークとするようになった。一方、師の鏑木健次郎にも有力なパトロンがいた。それが、ここ京都の呉服王、後藤吉三郎だった。今となっては失われた物だが、やはり宇治に山荘を築き、温室を建てて鏑木を援助していた。その頃は、ちょうど白い大輪のカトレアを作り出すことに誰もが夢中になっていて、また当時の社交界も、加賀正太郎と藤堂兼吉の支持者と、後藤吉三郎と鏑木健次郎を支持する二派に分かれ、関西財界を二分する大勢力になっていた。そんな矢先、京都で帝国愛蘭会主催の蘭のコンテストが行われた。この時は、誰もが師匠の鏑木がグランプリを獲ると思っていた。藤堂はまだ駆け出しの身だ。このコンテストは当時の政界の重鎮で、自らも蘭栽培を愛する大隈重信公も招かれた盛大なものだった。鏑木と藤堂。この二人はそれぞれ、十年をかけて作出した白の大輪のカトレアを出品した。誰もが、経験と実績で鏑木の勝利を疑わなかった。両者とも、パトロンだった加賀家と後藤家の家運と名誉を賭けた戦いに臨んだ。しかし結果は、弟子の藤堂がグランプリ、師匠の鏑木が銅賞という結果に終わった」
「そんなこと……」
涼子は信じられなかった。師匠が弟子に敗けるなんて。
「それは、ブラソレリオカトレア・ハクツルという品種だった。その名の通り、白い鶴が翼を広げたかのような華麗で、それでいて清楚な花だった。かくして、藤堂のパトロンだった加賀家は社会的な勝利を、鏑木を支援していた後藤家は敗北を得た。その後、加賀家は日の出の勢いで関西財界に名を成し、現在まで続く繁栄の礎となった。一方、鏑木を支援していた後藤家は大きな損害を被り、当時高島屋や三越に続いて行おうと計画されていた東京進出の計画も頓挫した。それから、家運傾き、没落して、表舞台からは姿を消した。その後、一族の末裔は満州へ渡ったとも、奈良に隠棲したとも聞いている。その加賀家の末裔が……」
「加賀理沙子先輩……」
翠水は静かに頷いた。
「彼女にしてみれば、呉服王後藤家は関西における強力なライバルであり、そしてこのコンテストでの勝利によってその存在を放逐することになってしまったわけだ。ただでさえ、師匠を弟子が破るということにもなってしまったわけだしな」
「そうだったんだ……」
涼子は雪明りに照らされた白い蔵を眺めた。
「それで、この家も引き払って……」
「その通り」
翠水はまた膝の上に視線を戻した。
「彼女、加賀理沙子にとって、この後藤家の敗北は一族の成功であり、同時に自らの出自に悲しみを感じる対象でもある。その白いカトレアも、理沙子にとってはどこか悲しみを感じるものなのだと思う……」
「だからあの時……」
涼子はあの日に加賀先輩が見せた顔の曇りが、他ならぬその白のカトレアにあるのだと知った。
「ねえ、翠水」
「なんだ?」
「あたし、どうしたらいいかな?」
翠水は涼子の顔を見た。その口元にはいつもの浮ついた微笑みは無い。
「加賀先輩、だから、あたし達が後藤の家の後を継いだから、それであたし達に尽くすことで、自分達の祖先の贖罪にしているんだと思う」
「それは、その通りだろうな」
それきり二人は黙り込んだ。
雪が降り止んだ空からは、北風が鳴る音がする。
その翌日、三十分程早く登校した涼子は、真っ先に園芸部の部室へと向かった。
だが部室にはその姿は無く、菜摘先輩と小川君がいるだけだった。
「ああ、理沙子なら付属庭園にいるよ」
菜摘先輩にそう聞いて、涼子はそこに向かった。
カモ高園芸部には、農学校時代に地元の素封家から寄贈された日本庭園があった。修学院離宮を小振りにしたようなもので、歴代の部員達が植えていった記念樹もある。庭園には大きな池があり、冬には白鳥がやってくるという。
見ると、彼方に加賀先輩の姿があった。
「加賀先輩!」
池の畔に佇んでいた加賀先輩は、涼子に気づくと軽く手を振った。
「寒いですね……」
駆け足でやって来たので、少し呼吸を乱しながら、先輩におはようございますを言った。
池には一面氷が張っている。
「あの……、先輩……」
「なにかしら?」
言うか言わざるべきか迷った挙句、涼子は加賀先輩の顔を見つめた。
「あれ、気にしなくていいんですよ」
「え!?」
涼子は加賀先輩の戸惑いを知って、出来る限りゆっくりと語気を整えた。
「だから、あれ。大正時代のあのコンテスト」
加賀先輩の眼が凍り付いた。
「だって、あたしは東京から来た別人だし、藤堂さんだって、正々堂々の勝負で勝ち取った栄冠でしょう? だからいいんです。加賀先輩のせいじゃないですよ」
「涼子さん……」
そこまで一息に言って、涼子は大きく深呼吸をした。冷たい冬の朝の空気が、ハッカのように清冽だった。
「いいのよ」
「え!?」
加賀先輩の返事に、涼子は一瞬返す言葉が無かった。
「本当はね、あなた達が入部したいって言ってきた時に、私本当に驚いたの。ほら、あの日、京都のご実家のこと、話したでしょう?」
「はい……」
加賀先輩はいつもの安らかな顔に戻った。
「あの時思ったの。ああ、これはもう運命なんだなって。私、ずっと高祖父のこと、加賀正太郎のこと、心の中にささくれみたいに残ってたから。だからこれは運命なんだって。神様が私に贖罪するための機会をくれたんだって……」
「先輩……」
加賀先輩は足元にあった小石を池に向かって投げた。渇いた音がして、厚い氷の面にはじかれた。
「でも私、わかったの。涼子さんを、あなた達を見てて。花に憧れるのは罪じゃないんだって。人間の自然な感情なんだって。だってあんなに一生懸命にお庭を造っていたんですもの。ね、楽しいでしょう? お庭造り」
「はい……」
その「はい」は純度百パーセントの「はい」だった。余計な打算や、ごまかしや、裏切りといった不純物は微塵もない「はい」だった。
「落ち込んでるのって、らしくないですよ」
涼子がそう言うと、加賀先輩はいつもの笑顔になった。
「そうね……。私らしくないわよね……」
空高く、鳥の声がした。灰色の空を真っ直ぐに飛んでいる。
「ありがとう。涼子さん」
涼子は意外な言葉に一瞬戸惑ったが、すぐにいつも通りになり、こう言った。
「こちらこそ、です。本当にありがとう。加賀先輩」
九
あった、これだ。
二月のある朝、涼子は庭の一隅に水門を見つけた。
これを開ければ、庭に……。
「お庭に川が?」
その日、園芸部の部室に行った涼子は、加賀先輩にその水門のことを話した。
「そうなんです。よく見たら庭の隅の、本当に隠れたところなんですけど、小さな水門があって、あれを開けたら、庭に水が引き入れられるんです」
「ほなら涼子はん、それで庭に川を流したい、言うんか?」
小川君がそう言うので、涼子ははいと答えた。
「素敵やなあ。お庭に川が流れたら、えらい風流やで」
菜摘先輩が続ける。
「じゃあ今度の土曜日に、皆で見に行きましょう」
その日、やって来た四人に、これなんです、と言ってその水門を見せた。
それは蔵の左脇、杉皮張りの塀の端にある物で、丸い取っ手があり、それを回すと開くようになっている
「瓢亭のお庭と同じね」
加賀先輩が水門を見ながら、その庭内に小川が流れているという老舗料亭のお庭の話をした。
「そういえば、これは川の痕跡ちゃうかな?」
玲が示した所には、この前の改修工事の時には手をつけなかった庭の中を蛇行する土の跡があった。
「うん、多分、そこが川だったんだと思う」
「ほなら、そこを掘って水路を造ればええな」
小川君が述べた。
ただし、と小川君が付け加えた。
「この水門から流れ出る所は、是非滝にしたいな」
「滝、ですか?」
涼子が訊くと、小川君が答えた。
「せや、石を組んで、その上から水が落ちるようにしたらええ。それが一番や。風情があるさかい」
「ほなら石が必要やんなあ」
菜摘先輩が言葉を継いだ。
「菜摘先輩、なにか良い石を得られるあてでもあるんですか?」
玲が訊くと、実はなあ、と教えてくれた。
「丹波石とか貴船石だったら、ウチの実家の店にあるさかい、それを持ってきたらええ」
「菜摘先輩のお家って、もしかして」
「せや、石材店やねん。せやから石はあるねんで」
「じゃあ、ここは一つ、小川君にやってもらいましょうか」
加賀先輩がにっこりと微笑んだ。
聞くところによると、小川君のご先祖の七代目小川治兵衛は、「石と水の魔術師」と呼ばれた程、水と石を扱うのに長けていたらしい。
小川君は水門と庭を見ながら、これから出来るという川の設計図を描いているようだった。
それから二週間。
冬休みも終わろうとしている頃、後藤邸の前にはまた軽トラックが停まった。
滝を造るために十個の石を用意したという。
石は貴船石と丹波石と、特別に珍しい浄土寺石があった。
「幻の石やからね。今はもう滅多に見つからんで、採掘どころか探し出すのも難しくなっとるねん」
灰褐色の石で、一目見ただけではそんなに貴重な石なのかと思ってしまう。
例によって石を運ぶのには苦労した。
縄をかけ、木の棒に吊るして運ぶという、夏の初めにやったあの方法だったのだが、昼食を挟んで午後四時頃までかかった。
その日は、石を運ぶだけで大ごとで、そのまま解散となった。
その夜、庭を眺めていた。
奥の蔵の左隣には、昼間運んだ十個の石がころがっている。ふと気配がして気がつくと、翠水がいた。いつものように隣に座る。
「いよいよこの庭に川が流れるのか」
「うん。皆のおかげでね」
「お主の言った『水の庭』が、いよいよ本当に実現するのだな」
「そうだよ」
「そうなれば、私の六角蹲踞にもとうとう水が?」
「そういうことだね」
「ふうん……」
翠水の横顔を見た。
この時ばかりは感慨深げに、庭を見つめている。
「あれは、浄土寺石ではないか?」
「よくわかるね」
「貴船石もあるのだろう?」
「そうだよ」
「どうやって手に入れた?」
「菜摘先輩が持ってきてくれたの」
翠水は立ち上がり、庭を歩いて石を見た。
「これは……。お主、この石の値段はわかるか?」
「さあ、どれくらい?」
翠水は人差し指を立てて見せた。
「一万円?」
「違う!」
翠水の顔がいつになくひきつっていた。
「十万円?」
まだ違うのか、翠水は首を縦に振らない。
「一千万円だ」
「ええっ!?」
石が一千万円とは。
しかし、菜摘先輩がこの浄土寺石は幻の石だと言っていた。
「これが高いのだ」
翠水はまた涼子の隣に来ると、座った。
「お主、いい友達に恵まれたな……」
「ああ……」
改めて言われてみると確かにそうだった。
いつも面倒を見てくれる加賀先輩。
隣にいて色々なことを教えてくれる玲。
優しくリードしてくれる菜摘先輩。
そしてここ一番で頼もしい味方になってくれる小川君。
「あなたもね、翠水」
翠水は、初めて外見の歳相応の気恥ずかしそうな顔で、頬を微かに紅潮させた。
「何を言うか」
「あら、ほんとにそう思ってるわ」
「お主らとは、生きた時間が桁外れだ」
「神様でも、嬉しい時はあるでしょう?」
「崇拝されたり、祀られれば、嬉しい時もある」
「じゃあ、身近に友達が出来た時は?」
「それはどうかな……」
翠水の横顔を見た。
いつもの飄々としたポーカーフェイスになっている。
「ねえ、ずっとずっと、ずーーーっと都にいて、一番楽しかったのはいつ?」
翠水は涼子のほうを見た。その澄んだ瞳は、こちらの心を映す鏡かと思われた。
翠水は立ち上がり、飛び石の上を歩いて、庭に出た。
「教えてよ。いつが一番楽しかった?」
それが聞こえたかどうか、翠水は後姿を見せて、後ろで手を組んでいる。
「今だ」
「え!?」
翠水は振り返り、悪戯っぽく微笑んだ。
上を見ると、満月が昇っていた。
月明かりを浴びて、涼子達の庭は平和に輝いていた。
その翌日、再び集まった五人は、石を組んだ。
水門からの流れに沿うように、石を組み合わせ、三段に組んだ。小川君の言うとおりに、角材で土を突きながら、目を詰め、土台を作りながら石を載せていく。
想像以上に根気のいる作業だった。
その作業に午前中一杯かかった。
母が昼食にミラノ風リゾットを作ってくれた。
午後、いよいよ水を流す時がやってきた。
「ほなら、開けるで」
小川君の言葉に、涼子達は緊張しながら答えた。
水門が開けられた。
水が石組の上に上ったかと思うと、次の瞬間、鮮やかに白い輪郭を描きながら、滴り落ちた。
庭に、水がやって来た瞬間だった。
耳を澄ますと、なんとも心地よいせせらぎが聞こえた。渇いた喉を潤すかのような、優しさに満ちた、そしてどこか不思議な音だった。
あの時植えた紅葉と、セキショウと、侘助さんと、シュロチクの傍らを過ぎて、川が流れる。
それは庭に潤いをもたらした。
描かれた庭園という壮大な龍の絵に、最後に瞳が描かれた瞬間だった。
「ありがとう、小川君……」
一同はお礼を言った。
普段滅多に笑わないこの青年が、笑みを湛えた。
涼子達の庭は完成した。
それはかけがえのない記憶として、この鴻池屋に新しい財産を築いた。
十
京都に春がやってきた。
加賀先輩達は三年生になり、いよいよ本格的に進路を決めることになった。
「加賀先輩、もう進路決めました?」
ある昼下がり、部室でお弁当を食べていた涼子と玲が訊くと、加賀先輩はにっこりと頷いた。
「私ね、大好きなお庭のこととか、園芸のこととか、植物のことを研究したいの、だから……」
そうして春風にそよぐ臙脂色のカーテンを見た。
「京都大学農学部!?」
涼子と玲は思わず声を上げた。
「そう。本当はね、同志社か京都女子大って親には言われたんだけど、でも私、やっぱりお庭のことを勉強したいの。一生懸命勉強して、庭園文化の研究者になるわ」
涼子と玲は顔を見合わせた。
まあでも、カモ高の実力ならやって出来ないことはないだろう。
「理沙子ちゃんは才女やさかい、きっと出来るで、なあ」
菜摘先輩が厚焼き玉子を口に入れた。
「あの、菜摘先輩はどうするんです?」
それを聞くと、菜摘先輩はほうじ茶を一口飲んだ。
「ウチは早稲田に行くつもりや」
涼子と玲はこれにも驚いた。
「と、東京の大学、行かはるんですか?」
玲が訊くと、菜摘先輩は頷いた。
「せや。ウチ、ずっと早稲田は憧れやったさかい、大隈さんの作った学校やでなあ。それに……」
お弁当の鯵の南蛮焼きをかじった。
「東京で一人暮らし、っちゅうのをやってみたい」
「そうなんですか……」
「学部は決めました?」
「ウチ、早稲田やったら、政経か文学部って決めとってなあ」
どちらも看板学部だ。
「何を勉強したいんです?」
涼子が訊くと、菜摘先輩は活き活きとした眼になった。
「政経行けたら日本近代政治史。文学部やtったらロシア文学。早稲田の露文科は名門やさかい」
菜摘先輩がロシア文学。
そう言われると、確かに菜摘先輩も少し文学少女かなと思う。
「アルバイトもしてみたいんやろ?」
小川君が話に入った。
「せや、ウチ、秋葉原のメイド喫茶のメイドさんになりたい!」
涼子と玲は顔を見合わせた。
「菜摘先輩が、メイドさん?……」
菜摘先輩は微笑んでいる。
でも、このバイタリティならやっていけるだろうなと思う。
「小川先輩は?」
涼子が訊くと、小川君は購買部で買ってきたサンドイッチを頬張りながら答えた。
「ウチは、一橋大学に行きたい」
「ひ、一橋……!」
「せや、将来はなあ、財務省か経産省に入りたいさかい」
小川君が官僚。
これには涼子と玲も驚いた。
「ああ、そうか、次男だから、お家の仕事は継がなくていいんですよね」
涼子が言うと、小川君は頷いた。
「せや。まあ、ウチは東京もんになる覚悟やさかいな」
「そら、ええなあ」
菜摘先輩が添えた。
「涼子さん達も、二年生だから、もう模試も受け始めるんじゃない?」
加賀先輩にそう言われて、二人はそういえば自分達もそろそろ将来を考えないといけない時期になったのだと感じた。
「なあ、涼子はんは大学どこ行きたい?」
「わ、私ですか? 私は……」
菜摘先輩に訊かれて、涼子は少し考えた後、意を決してこう答えた。
「私は、東京大学に行きたいです」
先輩達が驚いて顔を見合わせている。
玲も一瞬絶句した。
「父の母校だから……。私も父と同じように、日本庭園の研究者になりたいんです」
「それは初耳だわね」
加賀先輩がクリームパンの封を開けた。
「本当は、高校卒で京都の信用金庫に就職するか、行くとしても文系の学校だったんですけど、私、変わったんです」
その言葉に、一同が涼子を見つめた。
「京都に来て、この学校の、カモ高の園芸部に入って、みんなと出会って、ああ、お庭ってすばらしいなあって。この京都のお庭も、いろんなお庭が数えきれない程あるけど、いろんな時代の、いろんな人達が、一生懸命造って守ってきたものなんだって、そう思って……」
先輩達はじっと涼子を見つめている。
「だから、そんなお庭のことを、素晴らしさをきちんと勉強したいって。そう思いました」
開け放たれた窓から入る春風がカーテンを揺すっている。
「そうか……。じゃあ、行けるといいわね。東大」
加賀先輩がにっこりと微笑んだ。
菜摘先輩も、小川君も、玲も、平和になごんでいた。
「玲ちゃんは?」
その後皆に訊かれて、玲は一瞬戸惑いながら、それでも真っ直ぐな目で、こう言った。
「ウチは、東大法学部に行きます!」
一同が息をのんだ。
「ウチ、国連大使になりたいんです。涼子はんが言ったように、日本のお庭って素晴らしいから、その素晴らしさを世界中の人に知ってほしい、そう思って、ウチ決めたんです。外交官になって、日本の庭園文化を紹介したいって……」
しばし沈黙があった後、加賀先輩が驚きから親愛の表情に変わった。
「そう、それはいいんじゃない?」
涼子達は二人でとてつもない大仕事の段取りを打ち明けた気持ちになっていた。
「ほなら、勉強せえへんとなあ」
小川君が言った。
「せやなあ、お二人さん、応援するで」
菜摘先輩が続けた。
やがて先輩を代表するように、加賀先輩が言った。
「デュ・クラージュ! 」
終章
南禅寺の境内は、四月上旬ということもあって、大変な人出だった。
今年、新しく園芸部に入った二人の新入生がいた。
一人は松尾君。
実家は老舗の和菓子屋さんだ。
もう一人は鏑木さん。
お父さんは高校の国語の先生だ。
今年は先輩となって、この二人を連れて、玲と一緒に四人で園芸部の研修旅行を行っていた。
山門に登ると、京都の風景が一望出来た。
あちこちに、見事な満開の桜の木が見える。
「で、ここ南禅寺はこの山門から見える風景が素晴らしく、歌舞伎の『山門五三桐』では、大泥棒の石川五右衛門がここに登って、絶景かな、の名セリフを残しました」
新入生二人は、感慨深げに山門からの景色を眺めている。
涼子と玲は、かつての自分を見るような思いだった。
「涼子先輩、私達、お庭ってあんまりよくわからないんですけど……」
そういう二人に、涼子はふっと笑顔になった。
「じゃあ、一緒に勉強しましょう!」
「せやなあ、ウチらで、おおいに楽しんだらええよ!」
四人は揃って眼下の桜と、その向こうの京都市街を眺めていた。
涼子達の春が、新しい春が、また今年もやってきた。
終わらない青春、それこそは涼子の、そしてみんなの、ガーデンフィーバーだった。
【佳作】日曜日の桃ちゃん(西山ね子)
桃ちゃん人形になりたい。
常日頃、鉄男はそう思っている。
それはとてもとても強い願望で、天よりも高く、海底よりも深い。
可愛らしい桃ちゃん人形。
可憐な桃ちゃん人形。
もしも本当に桃ちゃん人形に成り代わることが出来たら、どんなにか素敵な人生になるだろう。どんなにか幸福な人生になるだろう。
が、そこまで夢想した後で、鉄男はふと我に返る。
いけない。
もしも本当に桃ちゃん人形になってしまったら、趣味のトランペットが吹けなくなってしまう。細い細い桃ちゃん人形は、きっと肺のサイズも小さいに違いないから、トランペットを吹きこなすだけの肺活量があるとは思えない。
それでもやはり、鉄男は夢想してしまう。
もしも桃ちゃん人形に成り代わることが出来たら、どんなにか素敵な人生になるだろう。どんなにか幸福な人生になるだろう。
*
「自らがどのような人間かを、たった一つの単語で表現しなさい」という問いがもしもあったとしたら、鉄男は迷わずこう答える。
ズバリ、「冴えない」
冴えないという言葉はまるで自分の為にあるような言葉だと鉄男は思うし、それは事実だ。
顔の造作は良くも悪くもなく、中肉中背。やや弱気。長所らしい長所も特に見当たらない。ちなみに鉄男は今年で三十歳を迎えるが、女性との交際歴はこれまでに一度もない。
カマボコ工場に就職して、鉄男は今年で勤続七年目を迎える。
カマボコ工場は、鉄男の二つ目の仕事だ。
新卒で入社したのは音響機器を扱う小さな会社で、営業担当だった鉄男は主にスピーカーを売り歩いていた。いや、正確に言えば、売り歩こうと努力していた。日々あらゆる店舗に飛び込んでは、名刺を差し出し、ペコペコと頭を下げて回った。相手が少しでも興味を示せば、自社のスピーカーの素晴らしさについて切々と説明した。
売り歩くのがなんであれ、飛び込み営業は厳しい仕事だ。ほとんどが門前払いで、話を聞いて貰えるのは一割にも満たない。名刺をその場で破り捨てられた事もあれば、定食屋で揚げたてのコロッケを投げつけられた事もある(それは壁が油染みていていて、手書きのメニューが薄汚れた鉄男同様冴えない定食屋だった上、壁の上部に小型テレビが据え付けられている店だったので、そんな定食屋に営業を掛けた鉄男も鉄男なのだが)。
結局、たったの一年で鉄男はその仕事を辞めてしまった。一年勤め上げ、鉄男が売ったスピーカーはたったの一台。職場に居づらくなったのも無理はなかったと思う。
そのたった一台のスピーカーを買ってくれたのは、時たま顔を出しているジャズサークルの知人(中学の同級生だった花輪という男が、現在社会人のジャズサークルに所属している)の叔母が経営しているというカラオケスナックだった。
そんな経歴を持つ鉄男だが、今のカマボコ製造会社に就職した事は幸いだった。従業員数約五十名という一見小規模な会社であるが、なんとこの国の約三十%のカマボコ供給率を誇っている。業績もそこそこの黒字を保っているから、今のところ会社が潰れる事はまずないだろうと思われる。それに、直属の上司(工場長)はいるが、音響機器の会社で働いていた時のように、鉄男をどやしつけたりするような事はない。
まだ二十四歳だったというのに、転職を試みた鉄男が採用を貰った会社は、とある鉄工所と、このカマボコ製造会社の二社だけだった。
鉄男は迷わずカマボコ工場を選んだ。鉄工所だと、体に余計な筋肉がついてしまいそうな気がしたからだ。桃ちゃん人形に、余計な筋肉はいらない。それでなくとも、鉄男の体は元来筋肉質で男らしい。例えば、ふくらはぎはまるで肥えたししゃものように膨らんでおり、その表面は岩のようにゴツゴツしている。
*
中学生の時、金管クラブに所属していた鉄男は、高校、大学を卒業してからもトランペットを吹き続けて現在に至る(内気な性格であるものだから、高校進学以降は、特にクラブやジャズ研に属していた訳ではないが)。
金管楽器の中でもトランペットを選んだことに、さしたる理由はない。
中学生の時、顧問だった教師から一方的にあてがわれた楽器を、現在まで吹き続けているだけのことだ。
が、トランペットの音色は、結構良い。特に高音が良い。パワフル且つ高らかに鳴り響くその音色を耳にすると、自分でもついうっとりしてしまう。
鉄男がトランペットを吹くのは、主にカラオケ店だ。
カラオケスナックを紹介してくれた花輪に誘われれば、ごく稀にセッションに参加する事もあるが、そのような機会は稀だ。鉄男はもちろん譜面は読めるし、トランペットを愛してはいるが、ジャズについて殊更詳しい訳ではない。花輪もその事をよく知っている。ただ、王道のマイルス・デイヴィスは結構好きだ。と言うより、他の有名なジャズトランペッターについて、鉄男は余りよく知らない。
だから、鉄男はカラオケ店で、一人孤独にトランペットを吹く。曜日は決まって、週の半ばの水曜日。仕事帰りにトランペットの入ったジュラルミンケースを抱えて、鉄男はカラオケ店を訪れる。
けれども実際のところ、一人トランペットを吹き鳴らす鉄男は全然孤独ではない。淋しくなんかない。
何故なら、カラオケ店で一人トランペットを吹くことは、エネルギーを得られるのと同時に、ストレス解消にもなるからだ。言ってみれば、一石二鳥という訳だ。
何故カラオケ店で吹くのかと言えば、察しがつくかもしれないが、今のアパートに引っ越して来た最初の日、引っ越し記念に部屋でトランペットを吹いたところ、隣人やご近所さんから早速苦情が殺到したからだ。
皆、何故理解してくれないのだろう。何故理解出来ないのだろう。こんなにも魅力的なこの音色を。
それは、人生の数十%を損していることだと鉄男は思うのだが、トランペットの魅力を理解できない一般の人々にとって、それはただの騒音にしか聞こえないらしい。
でもまあ、それも仕方のないことかもしれない。トランペットの音は、場合によっては100dB以上に達することもあるからだ。
最初は苦情など無視して(アパートの管理会社が、即刻苦情を伝えに来た)吹き続けてやりたいとも思ったが、鉄男にそんな度胸はなく、実際、二度目に恐る恐る音を鳴らしてみた所、今度はすかさず誰かが通報したらしく、玄関チャイムが鳴りドアを開けると、そこには制服を身につけた警察官が立っていた。
が、驚いたのは鉄男ではなく、警察官の方だった。何故ならその日、鉄男は桃ちゃん人形の扮装でトランペットを吹いていたからだ。
時刻は午後十時。朝剃ったばかりの髭も、再び濃くなって来た頃だった。厚化粧を施した肌に髭を浮かべたその顔は、さぞかし奇怪に見えたことだろう。
実際、警察官は一瞬ポカンと口を開けた後、「いやいや、用事があったのだ」と思い出したようにその表情を正し、けれども騒音について二言三言簡単に述べた後、まるで万引きを見つかりそうになった小学生のように、そそくさと帰って行った。
鉄男の顔は、一度見たら忘れられない幽霊の顔みたいに、さぞかしインパクトを与えたに違いない。その後、きっとその警察官は、桃ちゃん人形の扮装で髭を生やした鉄男のことを、幾度も幾度も思い出すに違いないだろう。
そう思うと、鉄男は少し気分がすっとした。
それにしても、例えば大太鼓とか小太鼓とかトライアングルとか、そういった打楽器に抜擢されなかったことは幸いだった。
何故なら、それらの楽器では、メロディーを奏でることが出来ないからだ。孤り大太鼓や小太鼓、トライアングルを鳴らすことほど退屈で虚しい行為など、この世にあるだろうか?ドンドン、トントン、チリーンチリーンと打ち鳴らすことで、一体何が得られるというのだろう?どんな喜びを与えてくれるのだろう?
そう思うと、鉄男をトランペットに抜擢してくれた顧問教師に、今では感謝したい。当時は他の生徒よりも人一倍厳しく指導されていたことを恨めしく思ったこともあったけれど、一人でもメロディーを奏でられるこの楽器を、今の鉄男はとても愛している。
*
鉄男の仕事は、毎週日曜が定休だ。
週に六日せっせと真面目にカマボコ作りに精を出し、待ち望んだ日曜日、鉄男は平日よりも早起きをする。起床時間は五時。五時半には洗面も朝食も済ませ、そしてミシンケースをぶら下げてカラオケ店へと出向く。
カラオケ店が二十四時間営業なのはラッキーな事だった。朝の六時から午前中いっぱいかけて、鉄男は桃ちゃん人形の衣装作りに精を出す。カマボコ作りをする時のように丹精を込めて、けれどもワクワクした気持ちを抑えきれずに、鼻歌など歌いながら。
そして正午を過ぎれば家に帰って昼食を済ませ、シャワーを浴びてから支度を整え(ムダ毛処理からメイクを終えるまでおよそ三時間も掛かる)、今度は桃ちゃん人形に姿を変えて家を出る。そして夕方、桃ちゃん人形となった鉄男はいよいよJ街の駅前にその姿を現す。
この事実を知る人物は一人もいない。今は離れて暮らしている家族は元より、花輪をはじめとするジャズサークルの知人たちも、鉄男がトランペットをすこぶる愛していることは知っているが、それよりも遥かに桃ちゃん人形を愛していることや、その上、桃ちゃん人形になりたいと夢想していることも、ましてや実際に桃ちゃん人形の扮装をして街をウロついていることも、勿論知らない。
桃ちゃん人形になりたい。
鉄男が密かに抱いているその強い願望を話せば、世間様が自分をどう見るか。それを判断出来るくらいには、鉄男は常識のある人間だった。
*
カマボコ社長が工場にやって来た。事前連絡は、常にない。まるで商店街を散策するようにふらりと、時々カマボコ社長はやって来る。
けれどもそれは、鉄男ら従業員の働きぶりを確認する為ではない。ウィンドウ越しに次々とカマボコが製造されていく工程を見学して、悦に浸っているのだ。社長なのだから当然と言えば当然の事かもしれないが、カマボコ社長は社の中の誰よりも、カマボコを愛している。
カマボコ社長は恰幅が良く、そしてお洒落だ。常にスーツ姿で、ジャケットの下にベストなど着て、常にパナマ帽を被っている。
性格は至って温厚。これまでカマボコ社長が大声を出したのを、この七年間鉄男は一度も聞いた事がない。
「よろしく頼むよ」が口癖で、いつもえびす様のような笑みを浮かべている。しかしながら笑い声だけは豪快で、おまけに声が通るものだから、「ワッハッハ」というその笑い声がすると、辺りの空気までビリビリと震えてしまいそうだ。
そんなカマボコ社長に、鉄男はとても好感を持っている。
工場を訪れる時、カマボコ社長は従業員への差し入れを欠かさない。カマボコ社長は太っ腹なのだ。
ちなみに今日、「相原さん、今日の差し入れ、にわな屋の最中らしいっすよ」と教えてくれたのは、同僚の藤堂だった(にわな屋は、この辺りでは有名な老舗和菓子店だ)。
この藤堂、年齢は鉄男より六歳年下で、金茶色の髪の毛とその言葉遣いから尋ねるまでもなく元ヤンキーなのだが、特にきっかけがあった訳でもないのに、入社以来何故か鉄男を慕ってくれている。
一旦機械を止めてしまうと効率が悪いので、機械を作動させたまま従業員は交代で昼食を取るのだが、藤堂は食堂で鉄男を見かければ必ず側に寄ってくるし、歓送迎会や忘年会の際などは、必ず鉄男の隣にピタリと座っては、若かりし頃の武勇伝(鉄男からしてみれば、二十四歳という藤堂の年齢は今でも十二分に若いが)を酔って据わった目で延々と鉄男に披露したりする。
引っ込み思案な鉄男は他の従業員とも世間話くらいはするが、「鉄男さん、今度キャバクラ行きましょうよ!」などと、プライベートでも交流を持とうとしてくれるのは、藤堂だけだ。
単に自分を慕ってくれているからという訳でもないのだが、カマボコ社長と同様に、鉄男は藤堂に対してもとても好感を持っている。裏表のない開けっ広げな性格を、鉄男は時々羨ましく思う事もある。
*
鉄男と桃ちゃん人形との出会いは、音響機器の会社に勤めていた頃まで遡る。
その日、鉄男は姪っ子の誕生日プレゼントを求めに、大型おもちゃ店をうろついていた。
ぬいぐるみやままごとセット。数々のおもちゃが並んだ女の子用の陳列棚を見ながら、ふと目に飛び込んできたのが、他でもない桃ちゃん人形だったのだ。
目に飛び込んできたその桃ちゃん人形に、鉄男は吸い寄せられるように近づいて行った。
なんて可愛い人形なんだろう。
この世にこんなにも可愛い人形が存在していたなんて。
鉄男はまるで一目惚れしたように、心を鷲掴みにされた。まるで、女児が生まれて初めて子猫をその腕に抱いた時のように。
桃ちゃん人形の入った箱を恐る恐る取り上げながら、鉄男はそれを凝視した。
クリリとした大きな大きな目。長い長いまつ毛。小ぶりの鼻と、やはり小ぶりの口。黄金色をした見るからにサラサラの長い髪。「可愛い」という言葉を具現化したら、きっとこんな感じになるのだろう。
なんて可愛い人形なんだろう。
この世にこんなにも可愛い人形が存在していたなんて。
結局、鉄男はその桃ちゃん人形を購入した。姪っ子の為にではなく、自らの為に(姪っ子にはキャラクター物のポシェットを選んだ)。
まるで自分がロリコンだか変態だかになったようで気が咎めなくもなかったが、それにも増して、鉄男の心は早くも桃ちゃん人形の虜になっていた。
が、自らが桃ちゃん人形を目指そうと即断したかと言えば、そうではない。実際にそうと決めたのは、もう少し後になってからの話だ。
大型おもちゃ店で桃ちゃん人形と出会って以来、新作が出る度に、鉄男は都度桃ちゃん人形を買い求めるようになった。今やそのコレクションは、二十体を優に超えており、テレビ台の上にズラリと並んだ桃ちゃん人形に「行ってきます」と「ただいま」の挨拶をするのが鉄男の慣わしだ。
*
それは、いつものように一つのスピーカーも売れないまま社に戻るため、駅で電車待ちをしている時の事だった。
今日も例によって手ぶらで戻った自分は、恐らくまた上司に怒鳴りつけられるのだろう。或いはネチネチと嫌味を並べられるだろうか。
そんな事を考え、憂鬱な思いで胸をいっぱいにしながら向かいのホームにふと目を向けると、全身をパープルカラーに包んだ女装姿の男が(パープルカラーのトップスにボトムス、タイツまでもがパープルカラーだったが、身長の高さと体つきで、男性なのだと容易に知れた)、ホームを行ったり来たりしている姿が見えた。
不思議な事に、何本の電車が到着しても発車しても、そのパープル男は一向に電車に乗り込む気配を見せず、いつまでもホームを行き来していた。
鉄男は思った。
ああ、あの男はきっと、人々の注目を浴びたいのだ。
最初は、単純にそう思っただけだった。
けれども、ようやくやって来た電車に自らが乗り込んだ瞬間、鉄男は突如思いついたのだった。閃いた、と言っても過言ではない。
そうだ、自らが桃ちゃん人形になってはいけない法などないのだ、と。
そして鉄男は、その足でデパートに向かった。桃ちゃん人形にふさわしい衣装を探す為に。
が、鉄男はすぐさま落胆した。
弱気な鉄男にしては珍しく、レディースファッションフロアをうろつく自分をジロジロと眺めてくる他のお客や店員の視線は気にならなかったが(気にならないくらい、兎にも角にも夢中だった)、次々と手に取った商品はどれもこれも、鉄男に着られそうなサイズの物は何一つとしてなかった。
大人向けのファッションフロアなのだから当然と言えば当然の事だが、桃ちゃん人形に似合いそうな衣服が、そこには一つとしてなかった。桃ちゃん人形が身につけているのは、例えばふりふりしたレースや大きなリボンがついた、可愛い可愛い洋服なのだ。
そして、鉄男はまたもや閃いた。
そうだ、店で手に入らないのなら自分で作ればいいのだ、と。
デパートを飛び出した鉄男は、その足で家電量販店へと出向き、ミシンを購入した。帰路についていたとはいえ、勤務中である事など頭の中からすっ飛んでいた。
ミシンを購入したその日から、鉄男は洋裁について熱心に勉強し始めた。自作の為には「型紙」なるものが必要らしい事。タックとギャザーの違いから、プリーツの種類についてまで。
当然と言うべきか、鉄男は試行錯誤を重ねた。「ふりふり ワンピース」だとか「ひらひら スカート」だとかいったキーワードでネット検索をかけ、ダウンロードした型紙を用いて取り組んではみるのだが、思ったようにふりふりしない。思ったようにひらひらしない。
結局、第一作目の衣装が完成するまでに三ヶ月もの期間を要した。三ヶ月かけて鉄男が作り上げたのは、「桃ちゃん」になぞらえた桃色のワンピースだった。裾がひらひらした(ふりふりに達する為には、もう少し腕前を上げなければいけなかった)、膝上のワンピースだ。
鉄男は歓喜した。これで桃ちゃんになれる。憧れの桃ちゃんになれる。余りの喜びに、めまいがした程だった。
*
土曜日の夕刻、いつも通り熱心にカマボコ造りに精を出した後、鉄男は自宅の最寄り駅から三駅先まで足を伸ばす。毎日ほぼ定時で帰宅出来るのも、カマボコ工場で働いていて良かった事の一つだ。
三駅先のその駅で下車した鉄男は、駅前にある手作り材料専門店へと足を向ける。三階建てのビルが丸ごと一軒専門店になっている大きな店だ。
鉄男にとって、そこは夢の国だ。
ピンクやスミレ色をした可愛らしい色の生地や、レースやリボン。星の形をした可愛いボタン。
最初にそれらを買い求めた時は、レジに立っていた中年女性たちから不審な目で見られたが、定期的に通う内に、レジおばさんたちも慣れたようで、今では微笑さえ浮かべて、商品の入ったビニール袋を手渡してくれる。
ミシンを扱う時、トランペットを吹く時同様、鉄男はカラオケ店を利用する。部屋でミシンを作動させた際、ご近所さんからの苦情は来なかったものの、トランペットを吹いた時同様、アパートの隣人からやはり苦情が来たからだ。
だから、ある時はトランペットのジュラルミンケースを携えて、またある時はミシンケースを持ち込み、鉄男はカラオケ店を訪れる。
店員が自分をどう見ているのかは知らないし、室内で何をしているのかはもちろん防犯カメラに映っているはずだが、これまでに苦情は勿論、質問を受けたこともない。法を犯したり、危険行為と見なされる事柄を除けば、何をしても良いということなのだろう。
だから鉄男は、個室の照明を最大限まで明るく点灯させ、スカートだのブラウスだのワンピースだのを縫う。
鼻歌交じりにミシンを作動させている時、それが少しずつ少しずつ桃ちゃん人形に近づいている過程だと思うと、鉄男は踊り狂いたいほどに嬉しくて、腰が抜けるほどに気持ち良い。
あまりに気持ちいいので、ミシンを作動させながら、鉄男は喜びを隠し切れず、生地を送りながらつい顔もニヤけてしまう。
そういう訳で、鉄男は現在の生活にとてもとても満足していた。
今年の年度始め、太っ腹のカマボコ社長が、創業五十周年記念に月給を一万円もアップしてくれたのもラッキーな事だった。給料がアップしたということは、桃ちゃん人形に掛ける製作費用も一万円アップするということだ。
次は、一体どんな服を作ろうか。
せっせとカマボコ造りに勤しみながらも、仕事中の鉄男の頭の中は桃ちゃん人形のことでいっぱいだ。
*
鉄男は、メイクについても酷く熱心に研究を重ねている。
それは衣装の第一作品目が完成した時の事だった。「桃ちゃん」になぞらえて作った桃色のワンピースを眺めて悦に入っていた鉄男だが、肝心な事を忘れていた事に気がついた。
そうだ、桃ちゃん人形になる為には、メイクも勉強もしなければ。
鉄男は広げていた生地だの糸だのボタンだの、とっ散らかっていたテーブルの上の裁縫道具を慌ててかき集めると、ミシンケースを右手に、ワンピースと小道具が入った紙袋を左手にぶら下げて、カラオケ店の個室を飛び出した。その足で、近所に一軒しかない本屋に飛んで行く。
それはしょぼくれた商店街にあるしょぼくれた本屋で、鉄男がそこを訪れたことは、それまでに一度もなかった。
小走りで本屋へと向かいながら「そのしょぼくれた本屋では、メイク雑誌など手に入らないかもしれない」と危惧していた鉄男だが、いざ足を踏み入れてみると、やはり整然と並んでいるのは小説やビジネス書の類ばかりで、雑誌は最も奥にある小さなコーナーに数種類並んでいるだけだった。予想通り、メイク本などは一冊も見当たらない。
が、こちらにもやはり足を踏み入れたことはなかったが、隣の駅から直結しているビルの中に、確か大型書店があったはずだ。
しょぼくれた本屋を後にした鉄男は、その足で駅へと向かい、今にもドアが閉まりそうな上り電車に駆け込んだ。
ハアハアと息を切らした鉄男を、すぐ目の前に席に座っている女が、不審そうな顔で見上げている。
電車が動き出し、スピードを上げた電車の車窓から、景色がぐんぐん流れていくのを眺めている内に、息切れしていた呼吸がようやく正常に戻ってくる。
が、ミシンケースを床に置いてつり革を掴んだその手は、まだじっとりと湿っていた。そのことで、鉄男は自分が酷く興奮していることに気がついて、思わず深呼吸した。
隣町の駅で下車すると、覚えの通り、ビルの中には大きな本屋があり、商品も充実しているようだった。
鉄男は店内をうろつきながら、雑誌類の棚を探した。
すると、二列目の中央あたりに「雑誌」と書かれたプレートがぶら下がっていた。
恐る恐る近づいてみると、ある物は棚の中に、またある物は平置きにされて、幾つもの雑誌が手に取られるのを待つように並んでいた。
まるでそうすることが儀式であるかのように、鉄男は周囲をキョロキョロと見回した。
が、数名いたのは全員男性客で、おまけに皆立ち読みすることに熱中しており、鉄男の姿を気にする者は誰もいない。
ようやく落ち着いた鉄男は、ミシンケースを床に下ろし、メイク雑誌に目を向けた。
まず、数々並んだメイク本の多さに、鉄男は驚いた。「シニアからの特選メイク」から「若返り美女」「ハーフ美女になるためのメイク二十選」等々。ありとあらゆるメイク本がずらりと並んでいる。が、「桃ちゃん人形になる為のメイク」など、まさかある筈もない。
数あるメイク本に次々と目を通した後で、結局鉄男が手にしたのは、「ハーフ美女になるためのメイク二十選」だった。
理由は勿論、「桃ちゃん人形は可愛らしいが、日本人にはとても見えないから」だ。
初めて手作り材料専門店に出向いた時とは違い、レジに立っていた店員は、機械作業のようにバーコードを読み取るだけで、鉄男に対して不審そうな目を向けてくることもなかった。そのことに、鉄男はホッとしながら店を後にした。
「これでまた、桃ちゃん人形に一歩近づいた」
鉄男の胸は、今にも天に昇っていきそうに喜びで満ち溢れた。
*
初めて桃ちゃん人形の扮装をして街へ出かけた日のことは、勿論よく覚えている。朝、ベッドの中で目覚めた瞬間、鉄男の胸は不安と喜びがちょうど五分五分だった。
鉄男は、念入りに髭を剃り、そして慣れない手つきで、しかしながらメイク本を片手に幾度も幾度も練習したメイクをその顔に施した。
顎の青い髭の剃り跡はコンシーラーで塗り潰し、その上からパウダーファンデーションを叩きつける。目にはもちろん付けまつ毛。鼻が小さく見えるよう小鼻は薄くシェーディング。唇はリップライナーで一回り小さな輪郭を。ちなみに、拗毛や腕や太もも、つまりは髪の毛と陰部以外のほぼ全身の毛は前日の晩に全て剃り落としていた。
そして手作りのワンピースを身につけ、いざ鉄男はアパートの部屋を出た。
淡い桃色ワンピースに、同じく淡い桃色のバッグ。出来れば髪の毛も桃ちゃんとお揃いの金髪ストレートロングにしたかったのが、まさかそんな髪型でカマボコ工場に出勤する訳にもいかない。仕事に直接差し障りがないとしても、何故そのような髪型にしたのかと同僚たちから間違いなく詰問される事は目に見えていたし、その質問に対する上手い言い訳も思いつけそうになかった。
だから鉄男は、ネットショッピングで金髪ストレートロングのウィッグを購入して被る事にした。
自ら製造する事が出来ない靴と、バッグ、下着類は同じくネットショッピングで手に入れた。世の中に、規格品のブラジャーを使用出来ないほどの巨乳や太った女性がいることは幸運なことだった。通信販売なら、鉄男の胸周りを悠々とカバーしてくれるブラジャーや(当然、複数枚のパッドを詰め込んで身につけた)、筋肉で包まれた鉄男の尻を包み込んでくれるパンティーが沢山あった。
インターネットで何でも手に入る時代に生まれて良かったと、鉄男は心の底から思った。
鉄男が目指した街は、上り電車で二時間ばかり行ったところにある都会の街、J街だった。
桃ちゃん人形に扮した姿を知り合いに見られる訳にはいかないから、最寄り駅はまずNG、勤務先の最寄り駅も勿論NG。
田舎町だと、通行人も少ないだろうから人々の注目を一斉に浴びてしまいそうだが、そんな注目を浴びる勇気はまだない。都会の街に立てば、少しは行き交う人々の波に紛れ混む事が出来るかもしれないと、鉄男は思ったのだった。
支度に膨大な時間を割かれたせいで、時刻は既に夕方に差し迫っていた。
電車に乗り込んだ瞬間は、さすがに酷く緊張した。J街に到着するまでの間、まるで奇天烈な物でも見るような視線で自分を見つめてくる乗客たちの視線にも、耐えられるかどうか不安だった。
だからJ街に辿り着くまでの間、電車の中で鉄男は寝たふりを決め込んだ。それでも、人々から向けられる矢のような視線を、瞼の裏に痛いほど感じた。
が、都会の街に立ったことは、結果的に「吉」と出た。
桃色のワンピースを身につけて夕方の駅前をウロつく鉄男に、人々は当然奇異な視線を向けては来たものの、立ち止まってまで鉄男を眺める者はいなかったし、ましてや話しかけてくる者は、誰一人としていなかった。まずはJ街の街角に立ってみる、という鉄男の目的は、見事果たされた事になる。
翌週の日曜も、そのまた次の日曜も、鉄男はやはり全身桃色の出立ちでJ街をうろついた。すると鉄男の中に新たな願望が生まれ始めた。
もっと色々な洋服を着てみたい。もっと色々な姿で街を歩いてみたい。
しかしながら、いつか見かけたパープルカラー男のように、「人々の注目を浴びたい」という願望は、まだ鉄男の中に存在してはいなかった。
*
花輪から久しぶりにセッションに誘われた。
久しぶりのセッションを、鉄男はそれなりに楽しみに感じた。が、セッション前に演奏予定曲の練習をしておかなければならない。
そういう訳で、とある月曜日の夜、ジュラルミンケースを携えて、鉄男はいつものカラオケ店を訪れた。本来であればトランペットを吹くのは水曜日なのだけれど、火曜の夜にセッションがあると花輪が連絡を寄越してきたのはつい先週の土曜の事だった。日曜日は桃ちゃんになるという絶対的なスケジュールがあるが、セッションも迫っている。それ故、鉄男は初めて月曜日の夜にカラオケ店を訪れた。が、ここで鉄男は雷に打たれたようなショックを受ける事になる。
入店手続きを済ませ、案内された部屋に向かおうとすると、カウンターの中にいた店員がヒソヒソと囁き合っているのが聞こえた。
「あれ、水曜日のおじさんじゃない?今日、月曜日だよね?」
鉄男は思わず振り返った。すると二人の店員は、バツの悪そうな顔をして、さっさとバックヤードへと引っ込んでしまう。
おじさん!?おじさん!?おじさん!?
店員たちの間で、「おじさん」呼ばわりされていた事に、鉄男は強いショックを受けた(姪っ子からは、鉄男くんと呼ばれている)。
鉄男は案内のあった個室を通り過ぎ、つきあたりにある男性用トイレのドアを開けた。手洗い場の正面に貼り付けられた大きな鏡に映る自分と目を合わせる。
「おじさん」と呼ばれるのは心外、と思ってはみたものの、よくよく見れば目尻には皺が出来つつあるし、顔を斜めに向けてみれば、うっすらとではあるがほうれい線もある。そこに着目すればするほど、うっすらとしか感じられなかったほうれい線が川の流れのようにくっきりと見えてくる。
十分ばかり鏡と向き合った後、案内された部屋に入った鉄男は、トランペットを取り出してマウスピースを嵌めるなり、ファンファーレを吹いてみた。が、気分は一向に高まらない。
かつてはエネルギーを得られるのと同時に、ストレス解消にもなっていたトランペットに、今の鉄男は何も感じる事が出来なかった。
おじさん、おじさん、おじさん。
そう。永遠の命など存在しないし、老いというものに逆らうことは出来ない。老いに逆らえないということはつまり、いつかは桃ちゃん人形の扮装を辞めなければならない日がくるということでもある。
シワシワになった肌で桃ちゃん人形の扮装をすることは、なんだか桃ちゃん人形を汚してしまうような気がするからだ。
一体どうすれば、自分は桃ちゃん人形であり続けることが出来るのか?
その疑問は、まるで追い払っても追い払っても付いてくる、昔遭遇した野良犬のように、がむしゃらにトランペットを吹き続ける鉄男の脳裏から離れなかった。
*
工場長が変わった。鉄男が入社以来世話になり続けた工場長が定年を迎えたせいだ。
新たにやって来たのは、鉄男とほぼ同年齢と見られる野田という男だった。聞けば、前職は鉄男の会社よりも大手、国内シェア五十%を誇るカマボコ製造会社の営業担当で、営業成績は常にナンバースリーを維持していたという。
確かに、従業員らの前で就任の挨拶を述べる野田新工場長はハキハキした口調で喋り、外見も爽やかで、また挨拶の内容もユーモアに富んでおり、常にナンバースリーの営業成績を保っていたのも頷けるような人物だった。
が、前職からの習慣からかポリシーからか、常にスーツ姿で出勤するその野田新工場長(工場長を始め、職務中は皆作業服に着替える為、スーツ姿で出勤する者はこれまでに誰一人としていなかった)の登場に、鉄男は少し緊張した。
「営業職」と言うその肩書きが、スピーカーを売り歩いていた頃の上司、鉄男に対して時に罵声を浴びせ、時にネチネチと嫌味を言ってきた上司の存在を思い出させたからだった。
野田新工場長に対して最初に違和感を持ったのは、食堂の同じテーブルに着いた時の事だった。
「お疲れ様です」と挨拶を述べた鉄男に、愛妻弁当らしい弁当箱を広げながら、野田新工場長は言ったのだった。
「君たちさ、よくこんなしみったれた工場でチマチマカマボコなんて作っていられるね」
「はい?」
意味が解せずに首を傾げた鉄男に、野田新工場長は更に言葉を続けた。
「全く、あの社長も社長だよ。工場勤務の従業員は社の業績を支える立派な人々だなんて言っちゃって。あのね、社の業績っていうのは営業の力で成り立ってるって言っても過言じゃないの。敏腕営業マンが多ければ多いほど、社の実績も上がっていくの。全く、君たちもあの社長も、俺は神経を疑うね。そもそも営業を希望して入社したのに、何で俺が工場なんかに配属されなきゃなんないんだよ」
「はあ・・・・・・」
「ねえ、相原さんっていったっけ?君だってそう思うでしょ?あんな手ぬるい社長の営業方針じゃ、今にこんなちっぽけな会社潰れるよ。全く、俺を営業に回せば業績だって間違いなく上がるっていうのに」
「はあ・・・・・・でも社長は従業員を大切にしてくれる立派な方だと思いますが・・・・・・」
従業員思いのカマボコ社長に好感を抱いていたのも手伝って、唾を飛ばしながら憤慨しているらしい野田新工場長の前で、鉄男は思わず社長を庇った。
が、次の瞬間それが失敗だったと悟った。鉄男の意見(野田新工場長からすれば、反論に聞こえたのかもしれないが)を耳にした野田新工場長の顔から、すっと表情が消えたからだ。
「君、相原っていう名前だったよね」
「はい。相原鉄男と申します」
「まあ、頑張ってよ。でも言っとくけど、俺はあの手ぬるい社長とは違うから」
鉄男の肩に手を置いた野田新工場長の目は、トカゲのように据わっていた。
立ち上がった野田新工場長は弁当を持って立ち上がり、席を移ってしまった。見れば、鉄男の席からは少し距離のあるテーブルで食事を取っていた従業員らと話し始めている。
自分にしたのと同じように、愚痴まじりの話を再び展開しているのだろうと推測した鉄男はしかしながら次の瞬間、「おや?」と思った。野田新工場長が席を移ったそのテーブルから、ドヤっとした笑い声が一斉に上がったからだ。従業員たちが野田新工場長の話に同意しているのか、或いは就任の挨拶で見せた話術を用いて、何か面白い話でもしているのか。
鉄男は嫌な予感がした。先ほど社長を庇うような発言をしてしまったことは、もしかすると鉄男が思っていたよりもずっと野田新工場長に取って面白くない出来事だったのかもしれない。
でもまあ、一従業員と工場長だ。工場長が自らカマボコ作りをする事はないし、確かに工場長は監査役ではあるけれど、真面目かつベテランの鉄男は仕事のミスも他の従業員と比べて極端に少ない。スピーカーを売り歩いていた頃のような目に遭う事はないだろう。
そんな事を思いながら食事の続きに戻った鉄男が、自らの予想が随分と甘い見通しだったのだと思い知らされるのは、もう少し後の話だ。
*
日曜の夕刻。J街の東口を徘徊していると、日曜だというのに塾帰りらしい小学生たちと行き合った。こういう状況は時たま発生する。
女の子は、鉄男を物珍しげに眺めはするものの、怖がって近づいて来ない。逆に男の子は、鉄男を指差し大声でからかってくる。
「あ、オカマだ!オカマがいる!」
そんな時、鉄男はドスを効かせてこう怒鳴りつける。
「うっせえガキ!とっとと失せろ!」
するとそこは小学生なのか、男の子らは一瞬ビクリとし、職員室で教師に叱られたみたいに、そそくさとその場を後にする。
桃ちゃん人形がドスの効いた声など出す筈もないのに、桃ちゃん人形になっている時、その外見とは裏腹に鉄男はなんだか強気になる事が出来るから不思議だ。
いつものように腹から声を出して男子小学生を追っ払うと、背中の方から今度はこう聞こえた。
「キャー!桃ちゃんさんだ!ね、写真写真!」
振り向けば、数人の女子中学生たちが、スマートフォンを片手に鉄男の周りに群がって来る。
桃ちゃんさん。
女子中高生たちは、鉄男をそう呼ぶ。
そして、「桃ちゃんさんと遭遇したり、一緒に写真を撮ることが出来れば、幸運が舞い降りてくる」というジンクスが、今や女子中高生たちの間で広がりつつあった。
鉄男自身予想もしていなかった事だが、この界隈で鉄男はいつの間にかラッキーチャームのような存在となりつつある。
鉄男にとって、それは悪くない気分だったが、今日は違った。
一体どうすれば、自分は桃ちゃん人形であり続けることが出来るのか?
先日カラオケ店で抱え込む羽目になったその疑問が、相変わらず寝ても覚めても頭の中でぐるぐると渦を巻いているせいだ。
スマートフォンを向けられても、今日はいつものような笑みを浮かべる事が出来ない。
「おじさん」の呼称にあれ程ショックを受けたにも関わらず、桃ちゃん人形に対する執着は募るばかりだった。
女子中学生と手を振り合って別れた後、ふと太ももの辺りに目をやった鉄男は、ミニドレスの裾に皺が寄っているのに気がついた。その皺を伸ばしながら、再び思案する。
そう。永遠に桃ちゃん人形であり続けることなど、出来る訳もない。
生き物たるもの、皆平等に必ず歳をとるのだ。
そんなことを延々と考えていると、いつの間にか夜の帷が降りていた。
が、今日はもうあちこち練り歩く気にもなれず、高架下のど真ん中で鉄男は立ち止まってしまう。
すると、背後から不意にトントンと肩を叩かれ、「幾ら?」と尋ねてくる男の声がした。
が、振り向いた鉄男の顔を見た途端、男はまるで異星人でも見たかのようにギョッとした顔をして、猛ダッシュで鉄男の側から離れて行ってしまった。
しばらくしてから、鉄男は気がついた。
恐らく自分は、立ちんぼと間違えられたのだ。
後ろ姿であるとは言え、女性と間違えられたその現実が、嬉しいのか悲しいのかわからなくなり、鉄男は混乱した。
その混乱した頭のままJ駅前のモニュメントを通過しようとしたその時、歓楽街へと続く小道から「ワッハッハ」と豪快な笑い声がした。
聞き覚えのあるその笑い声に思わず振り向くと、そこにいたのはカマボコ社長その人だった。見慣れたパナマ帽。どうやら、これからクラブで一杯やってこようとしているらしい。
鉄男はカマボコ社長に反射的に背を向け、その場を立ち去ろうとした。が、その瞬間、ロータリーのカーブの所に、客待ちのタクシーに紛れるようにして、光を放つ程ピカピカに磨きこまれた一台の黒い車が停車しているのが見えた。
嫌な予感がした。
鉄男はとっさに運転席に目をやった。遠目であるにも関わらず、運転手と目が合ったことがわかる。紛れもない、カマボコ社長の運転手だった。
桃ちゃん人形の扮装をした鉄男を運転手が認識出来るとは考えにくいが、かと言ってその運転手にぐんぐんと近づくのは憚られる。しかしながら後退すればカマボコ社長とかち合ってしまう。
どうしようかと迷っている内に、しかしこちらに近づいてきたカマボコ社長は鉄男の前をスッと通り過ぎ、行ってしまった。
けれども、安心したのもつかの間。モニュメントの陰に隠れようとすると、背後からポンポンと鉄男の肩を叩く者がある。
一瞬、鉄男の背筋は凍りついた。恐る恐る振り返ってみると、背筋を伸ばしたカマボコ社長が、えびす様のような笑みを浮かべて立っていた。
「やあ、相原鉄男君じゃないか。やあやあ、奇遇だねえ」
従業員思いのカマボコ社長は、全従業員の名をフルネームで覚えているのだ。
「こんばんは」とも「お疲れ様です」とも言えず俯いた鉄男に、「そんな顔をせんでも」と言いながら、カマボコ社長はまたもや鉄男の肩をポンポンと叩いた。
鉄男は意を決し、背筋を伸ばしてカマボコ社長の次の一句を待った。が、えびす様のような笑顔をピクリとも動かさず、カマボコ社長は言った。
「じゃあ、またその内に工場で。仕事の方、どうぞよろしく頼むよ」
そしてテクテクと歩いて行くと、歓楽街のネオンサインの中に紛れて行った。
鉄男はドシンとモニュメントに寄り掛かかると、そのままズルズルと地面にしゃがみ込んでしまった。
嗚呼、駄目だ。もしかすると、自分は仕事を失ってしまうかもしれない。今しがた目にしたえびす様のような笑顔はお愛想かもしれない。いくら太っ腹のカマボコ社長とはいえ、こんな姿を見られてしまったら、解雇されてしまうかもしれない。
それは困る。なんとしても困る。
鉄男は桃ちゃん人形になる為に、貯金はおろか、給料の殆どを毎月衣装作りに使い込んでいた。纏まった金らしい金はと言えば、まだ不出来な営業マンだった頃に定期預金に入れた三十万円があるのみだ。
当然のことながら、月々の収入がなければ、最小限の出費に抑えている生活費だって捻出する事は出来ないし、家賃や光熱費の事を考えれば、三十万円で暮らせる期間などたかが知れている。かと言って、そもそもカマボコ工場と鉄工所の二件しか内定を貰えなかった自分がスムーズに転職出来るとも思えない。
地面の上にしゃがみ込んだまま、鉄男は途方に暮れた。
「あー、オカマだ!オカマがパンツ見せてる!」
やはり塾帰りらしい小学生が、鉄男を指差して笑い転げているが、いつものようにドスの効いた声で追い払うことは出来なかった。
*
翌朝出勤すると、カマボコ社長の黒塗りの車が、既に工場の駐車場に止まっていた。
嗚呼、やっぱり駄目だ。やはり自分はリストラされるに違いない。
果たして、退職金は出るのだろうか?せめて今月の給料は日割りで支給されるだろうか?
不安、というよりは半ば諦めの面もちで「おはようございます」とロッカールームへと続く事務所のドアを開くと、カマボコ社長と野田新工場長が、揃って険しい表情で向かい合っていた。
嗚呼、やはりカマボコ社長は自分をリストラするつもりなのだ。そしてその理由を、ちょうど野田新工場長に話し終えた所なのだ。野田新工場長が鉄男を庇ってくれる可能性は万に一つもないだろう。野田新工場長は迷う事なく鉄男の解雇話を聞き入れるだろう。
今、一体自分はどんな言葉を発するべきなのだろう?
「すみませんでした」と謝るのもおかしいが、「あれは僕の趣味でして•••••••」と説明するのも、なんだか言い訳めいて聞こえる。
唯一言える言葉と言えば、「お世話になりました」の一言だろう。
「相原君」
カマボコ社長が呼び掛けてくる。
遂に来た。
遂にその瞬間がやって来る。
結局、退職金のことも給料のことも言い出せないまま、カマボコ社長が口を開くよりも先に、「これまで、大変お世話になりました」と、鉄男は深々一礼した。
「明日から出勤しなくて良い」という一言を聞くのが怖かったのだ。
けれども、俯きながら立ち去ろうとした鉄男の背を追い掛けるように発せられた言葉は、意外なものだった。
「どこに行くんだね?相原君。就業開始時刻が迫っているじゃないか」
「はい?」
事態が飲み込めないでいる鉄男に、カマボコ社長は打って変わってあのえびす様のような笑みを浮かべている。
カマボコ社長は、まだ険しい表情をしている野田新工場長に向かって言った。
「野田君、君の意見はよく分かった。しかし営業方針を決めるのは社長であるこの私だ。そこを履き違えないように」
そこで、鉄男はようやく合点がいった。二人は、鉄男の扮装やリストラについて話していた訳ではなく、単に営業方針で対立していただけのようだった。
安堵した鉄男は、空いていた椅子の座面に、崩れ落ちるように座り込んだ。余りの脱力感に、言葉も出なかった。
「じゃあ、よろしく頼むよ」
いつもの挨拶をして、カマボコ社長が席を立つ。
「お疲れ様です」と呟くような小声で言いながら、鉄男の心中は複雑だった。
これからも桃ちゃん人形でいられるという、踊り狂いたい程の喜び。何故カマボコ社長が鉄男の扮装に触れてこなかったのか、という疑問。それらが複雑に混じり合い、鉄男の脳内はまさにカオスのようだった。
鉄男はドアを出て行ったばかりのカマボコ社長の背を追った。事務所のドアがしっかりと閉まっている事を確認してから、黒塗りの車に乗り込もうとしていたカマボコ社長に「あの・・・・・・」と切り出してみる。
「ん?なんだね?」
「昨晩、J街の駅前でお会いしましたよね?」
「ああ、そうだね。あれ、桃ちゃん人形だろう?」
「はい?」
「桃ちゃん人形だろう?」
「はい•••••••あの、どうしてご存じなんですか?」
「孫が大好きなんだよ。そうだ、君、何だったら今度あの格好で孫に会ってみないかね?孫も喜ぶと思うよ」
「はあ•••••••でも、お孫さん驚きませんか?」
「ワッハッハ」
豪快な笑い声を発した後で、カマボコ社長は言った。
「大丈夫だ。『人を見た目で判断するな』と教育するよう、息子にはキツく言いつけてあるからね」
「はあ•••••••」
「それに、実際その桃ちゃん人形好きな私の孫も、男の子だからね」
「はあ•••••••そうですか。じゃあ僕は退職する必要はないんですね?」
「退職?一体どうしてまた?」
「いえ、あのような姿を見られたものですから」
「趣味は人それぞれだし、愛するものも人それぞれだ。私がカマボコをこよなく愛しているように、君は桃ちゃん人形を愛している。ただそれだけのことじゃないか」
「はあ•••••••」
「それじゃ、私はこれで失礼するよ」
「お疲れ様でございます」
妙にしゃっちょこばった口調とお辞儀でカマボコ社長を見送って、鉄男は今度こそ心の芯から安堵して、思わずため息が漏れた。
*
野田新工場長が就任してから一ヶ月が過ぎた頃、いつものように出勤してきた鉄男がロッカーの鍵を開けて扉を開くと、中にぶら下がっているはずの真っ白な作業服が見当たらなかった。おまけに鉄男が小学生の頃、給食の時間に被せられていたような、頭に被るとUFOみたいな形になる作業用の帽子も見当たらない。
まさか昨日仕事着で帰宅した筈もないので、鉄男は一人ロッカーの前で首を捻った。或いは、間違えて隣のロッカーにでも収納してしまったか。いや、それはあり得ない。そもそも、七年間一度も破られた事のない習慣が昨日突然乱れること自体が考えにくい事なのだ。
ロッカーの鍵には当然スペアキーが存在しており、それは工場長が管理している。
まさか・・・・・・と鉄男が工場長に疑いの目を向けた所で、当の工場長が出勤してきた。今日は上下茶のスーツに、黄色いネクタイを結んでいる。
「おはようございます」
「ああ相原さん、おはよう。どうしたの、棒みたいに突っ立って」
「あの、作業服が見当たらないのですが」
「は?」
「昨日ロッカーの中に収納した筈の作業服が無いんです」
「本当に?」と尋ねてきた野田新工場の瞳には、虫を潰して喜んでいる幼児のような、残酷な笑みが浮かんでいた(少なくとも、鉄男にはそう見えた)。
「はい、確かに収納して鍵を掛けた筈なんですが」
「でも、実際無いんでしょう?」
「ええ・・・・・・」
野田新工場長は鼻で笑った。
「だったら紛失したって事になるんじゃないの?まさか作業服に足が生えて逃げた訳でもあるまいし」
「でも・・・・・・作業服を紛失するなんて事があるでしょうか?」
「だけど、実際無いんでしょう!?」
突如声を荒げた野田新工場長の剣幕に鉄男は一瞬ビクリと体を震わせ、自らに落ち度はない筈だと確信しているのに、「はい、申し訳ありません」と思わず謝罪の言葉を口にしてしまう。
ロッカーの前で困り果てていた鉄男をよそに、ちゃっちゃと着替え始めていた他の同僚たちが、鉄男と野田新工場長のやりとりに目と耳をそばだてていた。
「全く仕方のない奴だなあ。就任早々に俺の手を煩わせるなよ」
言うと、工場長はデスクの引き出しを解錠して、中から小さな鍵束を取り出した。
「何番?」
「はい?」
「お前のロッカーナンバーだよ!」
「はい、あの、五番です」
不安と緊張で湿り始めていた両手の平を、鉄男はズボンで拭った。
野田新工場長は「ほら!」と再び大声を出し、何かを床に放った。鉄男が注視してみると、どうやらスペアキーであるらしい。
「何してんだよ!早く拾って着替えろよ!出勤してても開始時刻に間に合わなかったら遅刻扱いだからな!」
「はい、すみません」と、またもや悪くないのに鉄男は再び謝ってしまう。
その日一日中、手だけは忙しなく正確に動かしながらも、鉄男の胸は恐怖と憂鬱でいっぱいだった。自らも営業職に就いていた頃の数々の嫌な記憶が、水溜りに沸いたボウフラのように頭の中に浮かんでくる。
「俺はあの手ぬるい社長とは違うから」
以前、目の座った野田新工場長が言ったその一言が鉄男の脳裏をよぎった。
幸運だった事は、土曜日だった事だ。明日になれば、桃ちゃんになれる。桃ちゃんになれば怖いものなど何もないし、今日の嫌な出来事もきっと忘れられるだろう。そう考えるとようやく、鉄男は心の落ち着きを取り戻す事が出来た。
*
不運な事に、鉄男に対する工場長の嫌がらせめいた言動はその後も続いた。
例えば、これまで通り毎週水曜日にジュラルミンケースを携えて出勤していると、とある日ケース中身を尋ねれ、トランペットだと答えた所、「公私混同である上、仕事に集中していない証拠だ」と叱られた。
またとある別の日に珍しくミスを犯した鉄男は、同僚たちの前で徹底的に怒鳴り散らされた。
その内に、嫌がらせめいた言動は、実際の嫌がらせに変わった。野田新工場長が鉄男の事をまるで空気のように無視し始めたのだ。業務報告中の鉄男を置いて帰宅する。カマボコ社長の差し入れを鉄男にだけ配らない。
鉄男に対する同僚の接し方にも変化が現れた。鉄男と親しくして自分に害が及ぶのが嫌なのだろう、以前は世間話などする機会も度々あった同僚たちの多くはいつの間にか鉄男を避けるようになっており、堂々と鉄男に話しかけてくるのは、今や何故か鉄男に懐いている藤堂一人きりになっていた。
藤堂は言った。
「野田のヤツ、俺は工場長なんかに収まってるガラでも器でもないって調子乗ったこと言ってるらしいんすよ。んで、社長とも気が合わないし。そのストレスの矛先が相原さんに全部向けられてるんすよ、多分」
野田新工場長から嫌がらせを受ける度、鉄男は毎度桃ちゃん人形の事を思い浮かべ、以前よりも強く日曜日を待ち侘びるようになった。嫌がらせがエスカレートすればする程、それに比例して桃ちゃん人形に対する執着も強くなった。
これまで決して破られた事のない鉄男の生活サイクルも変化した。日曜日の午前中まで待ちきれず、鉄男は土曜日の夜からカラオケ店を訪れるようになった。土曜日の夜から日曜日の朝まで、徹夜で衣装制作に取り組むようになったのだ。目を血眼にして、仕事中よりも熱心に。鼻歌を歌うこともなく。どのような衣装を作ろうかとワクワクする事もなく。鉄男は頭に浮かんだ衣装を次々と完成させていった。
また、鉄男は散財もするようになった。平日の帰宅後、夜な夜なパソコンを立ち上げてはモニタをスクロールし、目に飛び込んできたバッグだの靴だのを、直感で選んでどんどん購入した。
スマートフォンに花輪から幾度か着信があったが、鉄男が応答する事はなかった。トランペットの事など、いつの間にかどうでもよくなっていた。
*
カマボコ社長がやって来た。例の如く、事前連絡はない。が、いつもと違った事は、業務にあたっている最中だというのに、カマボコ社長が鉄男を事務所に呼びつけた事だ。
不思議に思いながら事務所のドアを開けると、いつか見たような光景がそこにあった。カマボコ社長と野田新工場長が、まるで相撲取りの立ち合いのように、険しい表情で向かい合っている。
野田新工場長がチラリと鉄男を見た。その苦虫を噛み潰したような表情を目にした瞬間、鉄男は瞬時に悟った。野田新工場長は、遂に決定的とも言える手段に出ようとしているに違いない。恐らくある事ないことカマボコ社長にでっち上げ、自分を解雇させようとしているのだ。滅多に見る事の出来ないカマボコ社長の眉間の皺も、それを物語っているような気がする。
が、次の瞬間カマボコ社長はこう言った。
「野田君、相原君に何か言うべき事があるんじゃないのかね」
するとその険しい表情とは裏腹にもっそりとした動作で立ち上がった野田新工場長が言った。
「これまで申し訳なかった」
今度はまだ眉間に皺を寄せたままの表情をしたカマボコ社長が言う。
「野田君には辞めてもらうことにした。私とした事が気づいてやれなくて、すまなかったね」
ポカンとした表情を浮かべている鉄男に、カマボコ社長が言った。
「なあに、藤堂君が知らせてくれたんだよ。野田君の君に対する態度はパワハラ意外の何物でもないとね」
「はあ・・・・・・」
「それじゃあ相原君は仕事に戻りなさい」
「かしこまりました」
野田元工場長と二人きりで事務室に残されなかった事に安堵しながら、鉄男は作業場へ戻った。
*
昼休みの食堂。鉄男が一人コンビニ弁当をつついていると、いつの間にか隣に立っていたらしい藤堂が「隣、良いっすか?」と言い終えるよりも早く鉄男の隣にドッカリと腰を降ろしてきた。
唯一口をきいてくれる貴重な存在だった藤堂に、鉄男はテーブルの上のポットからグラスに麦茶を注いでやる。
「あ、どうもっす」
鳥が餌を啄むように小さな会釈をした藤堂は余程喉が渇いていたのか、注いだばかりの麦茶を一息に飲み干してしまう。
お代わりの麦茶を注いでやりながら、「この間は悪かったね」と鉄男は言った。
「この間?何のことっすか?」
「工場長のパワハラ、藤堂君が社長の耳に入れてくれたって」
「ああ、そのことっすか。別に相原さんが謝る事じゃないっすよ。それに俺、元々野田の事どうも虫がつかないヤツだと思ってましたし。みんな思ってましたよ、口に出さなかっただけで。でも自分が巻き込まれたくないから揃って無視を決め込むなんてガキ並みじゃないっすか。威張れる事じゃないっすけど、俺元ヤンなんで、そういう筋の通ってないの大っ嫌いなんっすよね」
「とにかく、どうもありがとう」
「いやいや、礼なんて良いっすよ。それより相原さん知ってます?」
「何を?」
「地元のダチ、あ、ダチって言っても、ポン引きやってるろくでなしなんすけど。そいつからちょっと面白い話聞いたんすよ」
「面白い話?」
「J街の駅周辺に、毎週日曜日になると決まって女装してウロつくが男が出没するらしいんすよ」
口から心臓が飛び出そうになるのを必死に堪えて、鉄男はオウム返しに言った。
「女装してウロつく男?」
「そうなんすよ、いつも長い金髪のヅラ被ってて、ちゃんと化粧もしてて女の格好してるけど、どこからどう見ても男なんですって」
早まっていく鼓動に思わず胸を手で抑えそうになりながら、鉄男は訊いた。
「僕は聞いた事ないなあ・・・・・・藤堂君の地元って、J街なんだ」
「ええ。J街って言っても、実家は外れの住宅街の方っすけどね」
「それで、その女装男、あ、なんか桃ちゃんって名乗ってるらしいんすけど、そいつに遭遇すると、なんか幸運が舞い降りてくるらしいんすよ」
「へえ・・・・・・」
喉がカラカラになってしまった鉄男は、自らの麦茶を一口飲んで、心を落ち着けようとしたが、グラスを持つその手はふるふると震えていた。
「まあ都市伝説みたいなもんかもしれないっすけどね。そのダチ、さっきも言いましたけどポン引きのろくでなしだし。幼稚園からの付き合いなんっすけど、昔から話がでかいっつーか盛りすぎっつーか、そういうヤツなんで。あ、電話、ちょっとすいません」
藤堂は唐突に椅子から立ち上がり、尻ポケットから取り出したスマートフォンを片手に、出入り口の方へと歩いていく。その姿が消えるのを見届けてから、鉄男は思わずテーブルの上に突っ伏した。食べかけのコンビニ弁当から鶏の唐揚げの匂いが漂ってくるが、先程まで確かに感じていた食欲は、綺麗さっぱり失せている。
嗚呼、もう駄目だ。
良い事と悪い事は順繰りにやってくるとよく言うが、それは本当だったのだ。
せっかく解雇を免れたというのに、まさか藤堂の地元がJ街だったとは。
もしも藤堂が好奇心からJ街に来てしまったら、一発で自分を見つけ出し、恐らく、いや絶対に正体まで知られてしまうだろう。いくらメイクを施していると言っても、職場でこうも毎日顔を合わせているのだから、正体を見破るのなんて屁にもならない事だ。
そもそも、地元がJ街だというのに、これまで藤堂と遭遇しなかったこと自体が、幸運だったのだ。
居ても立っても居られなくなった鉄男は、尿意も感じていないのに、トイレに行った。いつだかカラオケ店でそうしたように、鏡の中の自分と目を合わせてみる。そこに映っているのは、どこからどう見ても、一人の中年男だった。
おじさん、おじさん、おじさん。
カラオケ店で耳にしたその呼称が、再び鉄男の脳裏に浮かんだ。
声には出さず、しかしながら確固たる意思を持って、鉄男は自らに言い聞かせた。
僕はやれる。
僕なら出来る。
桃ちゃん人形から足を洗い、カマボコ工場に勤務するただの一人の中年男になるのだ。
今なら、まだ戻れる。
いや、戻るのだ。
しかしながら、確固たる筈であった鉄男の意思は何とも貧弱だった。自分に言い聞かせているそばから、まるで砂漠のど真ん中で水を希求するように、桃ちゃん人形に対する想いはもう止まらない。
午後の勤務にあたりながら、手先はだけはせっせとしっかり動かしながら、けれども鉄男は思い悩んだ。
自分は一体いつまで、桃ちゃん人形になり続けることが出来るのか。或いは、そんなことを考えている時点で、自分はカマボコ工場に勤務する一人の男になどなれないのか。
もしもそうだとして、では自分は一体どうすれば良いのか。
ハマのメリーさんのように、その体が許す限り桃ちゃん人形になり続ければ良いのか(メリーさんは女性であり、桃ちゃん人形は決して娼婦などではないけれど)。
或いは、やはりこの辺で桃ちゃん人形から足を洗うべきなのか。
どちらの選択肢も、鉄男は受け入れ難かった。ではどうすれば良いのか。いくら考えてみたところで、答えは出なかった。
*
翌週の日曜日、藤堂と鉢合わせするかもしれないと恐れを感じながらも、やはり鉄男はJ街へと足を運んでしまった。今やもう、坂道を転がり始めたの石のように、或いは一度覚醒剤を味わってしまった者のように、桃ちゃん人形から離れられない自分がいた。
コツコツとヒールを鳴らして夜の街を当て所なくぶらついた後、鉄男は終電に乗った。いつものことながら、自分に対して向けられる乗客たちからの奇異な視線を目一杯に浴びる。
つり革に捕まりながら、鉄男はふと暗い車窓に目を向けた。心は沈んでいるいうのに、鏡のように自分を映し出す黒い車窓には、どこかニンマリとした笑み浮かべる自分の顔が映っている。
違和感を感じた後、鉄男はハッとした。
桃ちゃん人形になれるだけで満足だと、人々の視線などどうでもいいと思っていたはずなのに、うんと昔に目撃したパープル男のように、いつの間にか人々の視線を浴びることに快感を覚えるようになっていたことに、今更ながら気がついたのだった。
このままではいけない。このままでは、ただの変態男になってしまう。
あれほど焦がれた桃ちゃん人形。
憧れの桃ちゃん人形。
これまで、金や生活の全てを桃ちゃん人形に捧げてきたというのに、今や自分のアイデンティティを覆そうとしているその桃ちゃん人形に、鉄男は初めて恐怖を感じた。
家路も中程までやって来た頃、日付も変わろうとしているこんな深夜に、とある駅で、隣のドアから一組の親子が車内に乗り込んで来るのが見えた。二人とも喪服に身を包んでいる所を見ると、どうやら通夜の帰りらしい。
シートは満席。今にも瞼を閉じそうな男児の手を取る母親は、明らかに疲れ切っている様子だ。
やがて、男児がくずつき始めた。
「眠い〜!座りたい〜!早くお家に帰りたい〜!」
けれども、乗客たちは迷惑そうな視線で男児と母親を睨みつけるだけで、誰一人として立ち上がる気配を見せない。
鉄男は親切にも立ちあがり、座席を確保しておく為、自らが腰を降ろしていた座席に、赤い小さなバッグを乗せた。ハイヒールを履いた足で、ガタゴト揺れる走行中の車内を転ばぬように注意しながら進んでいく。
その背を叩くより一瞬早く、母親の方が振り返った。鉄男の付けていたキツい香水に反応したものと思われる。
「もしよろしければ、代わりましょうか?」
赤いバッグを指しながら、鉄男は問うた。
母親は一瞬ギョッとした顔をして見せたものの、よほど息子を持て余していたらしく、素直に「ありがとうございます」と会釈をしてみせる。
「ほらカッちゃん、席、譲ってくれるって」
床の上で海老反りになっていた男児と目が合った。すると、先ほどまでくずついていた男児が、ぐずついていた時より更に大きな声で、言った。
「あ、化粧お化けだ!ママ、化粧お化けがいるよ!」
化粧お化け!?
鉄男はまるで銃で胸を撃ち抜かれたような気がした。
化粧お化け。化粧お化け。化粧お化け。
その言葉は鉄男を打ちのめした。奈落の底に落ちていくような気分だった。
電車の揺れにバランスを取りながらも棒立ちになった鉄男に追い打ちを掛けるように、カッちゃんと呼ばれた男児が、鉄男が身につけていたワンピースの裾をひらりと捲った。スカートに縫い付けたヒラヒラのレースが宙を舞い、スカートの中身が露わになる。
「あ、もっこりしてる!この人、女の格好してるのにもっこり星人だよママ!」
いい加減気まずさを覚えたらしい母親は「どうもすみません」と頭を下げた後、男児の手を引いて奥の車両へと行ってしまった。
もっこり星人。もっこり星人。もっこり星人。
*
帰宅した鉄男は土足のまま室内に上がり込むと、姿見の前に立ち、映し出された自分の姿を上から下までゆっくりと観察した。
真っ赤なワンピースに真っ赤なバッグ。真っ赤な口紅に、赤いリボンでツインテールに結んだ髪。
そして鉄男は、頭上から岩が落ちて来たような衝撃を受けた。
桃ちゃん人形は、全身を真っ赤にコーディネートしたりなんかしない。真っ赤な口紅なんて塗らないし、サラサラな髪の毛はいつも自然に垂らされていて、ツインテールに結んだりなんかしない。
これは桃ちゃん人形なんかじゃない。桃ちゃん人形とはかけ離れた、ただの女装男だ。藤堂の言っていた通り、ただの女装男だ。
鉄男はひどく混乱した。脳みそをミキサーでかき混ぜられているように思考が纏まらない。
やがて、鉄男の目にみるみる内に涙が浮かび始めた。それは次々と鉄男の頬を伝い、遂に嗚咽を零し始めると、涙はダムを放流したかのようにジャアジャアと頬を流れていく。
鉄男は再び鏡に目をやった。濃く施された化粧の上に薄っすらと生え始めている髭。涙で崩れたその化粧。そこにいるのは、紛れもない一人の「化粧お化け」だった。「化粧お化け」でしかなかった。
鉄男は焦った。取り敢えず玄関で靴を脱ぎ、メイク落としで化粧を落とし、伸びていた髭も化粧を施す前のように、念入りに剃り落とした。
鉄男はまるで熊のように、落ち着きなく室内をウロウロと歩き回った。そして、テレビ台の上に並べた桃ちゃん人形を、端から順繰りに眺めていった。
可愛らしい桃ちゃん人形。
可憐な桃ちゃん人形。
今や、それとかけ離れてしまった鉄男人形。
一度大きく深呼吸した後、思い立った鉄男は押入れから畳まれていた小ぶりのダンボール箱を取り出した。引越しの際、何かの役に立つかもしれないと、取っておいた物だ。
鉄男はダンボール箱を組み立て、テレビ台の上に並んだ桃ちゃん人形を一つずつ手に取り、眺めていった。
一体手に取る度に、鉄男は桃ちゃん人形と目を合わせ、「ごめんね」と呟く。
一体手に取る度に、一粒の涙がポロリと溢れる。
そしてその後で、後ろ髪を引かれる思いで、全ての桃ちゃん人形をダンボール箱の中に丁重に納めると、同じく引越しの際に利用したガムテープを取り出してきて、まるで小学生が缶の宝物箱に綺麗な石やセミの抜け殻を納めて蓋をするように、ダンボール箱の上部に念入りに蓋をした。
これでもか、これでもか、というくらいに、十文字型にガムテープを何重にも貼り付ける。
次に鉄男はノートパソコンの前にどっかりと腰を下ろすと、女装専門店のサイトに次々とアクセスし始めた。
世の中には、女装癖がある者も数多く存在することだろう。せっかく苦労して作り上げた数々のウエアーや買い求めた靴だのバッグだは、どこかの店舗に寄付してしまうつもりだった。
気がつくと、時刻はいつの間にか午前二時を回っていた。あと五時間ほどで出勤時刻になる。が、鉄男はベッドではなく、デスクの引き出しから取り出してきた鋏を右手にキッチンにある大きなゴミ箱の前に立った。
鉄男は金髪のウィッグををまじまじと眺めた後で、そのど真ん中にジャキリと鋏を入れた。そして続けざまにジョギジョギと音を鳴らしながら、まるでウィッグをみじん切りにしようとするかのように、一心不乱に鋏を動かした。
これでもう、おいそれと桃ちゃん人形になることは出来ない。
*
翌日、鉄男は午前半休を取得して、昨日念入りに封をした段ボール箱を抱えて本社を訪れた。本社は工場の隣街にあり、小さいながらも自社ビルで、駅から徒歩三分とアクセスも良い。
エレベーターを降り、鉄男は社長室の扉をノックした。「どうぞ」というカマボコ社長の返事を耳にしてから恐る恐るドアを開ける。
「相原君じゃないか。一体どうしたんだ、本社にやって来るなんて」
思わずなのだろう、座り心地の良さそうな大振りの椅子から立ち上がったカマボコ社長の前で、鉄男は口籠もった。
「いや、その・・・・・・」
「何かね?」
「いや、その・・・・・・」
「もしかするとまた誰かからハラスメントでも受けているのかね?」
「いいえ、決してそのような事は。あの、あの・・・・・・これ、もしよろしければお孫さんにと思いまして」
言いながら、鉄男は要塞のように頑丈に封をした段ボールを突き出した。
「ん?何だね、これは」
「桃ちゃん人形です。私のコレクションだったものなのですが・・・・・・」
「それじゃあ君にとっては宝物みたいなものじゃないか。一体どういう風の吹き回しかね?」
「いや、その・・・・・・実は桃ちゃん人形からは卒業しようと思いまして」
「そりゃまた一体どうしてだい?」
「いや、その・・・・・・」ともう一度口籠もってから、意を決したように鉄男は言った。
「僕は桃ちゃん人形に傾倒するあまり、自分を見失っていたようです」
すると、カマボコ社長は「ワッハッハ」と、いつもの豪快な笑い声を上げた。
「ようやく気がついたかね」
「はい?」
「いつだったかJ街で桃ちゃん人形の扮装をした君と行き合っただろう?」
「ええ」
「いやあ、君がそうと決心した今だから言うけれども、あれは酷かった」
「はい?」
「桃ちゃん人形だと推測する事は出来たけれども、実際の桃ちゃん人形とはかけ離れていたものなあ。無精髭を生やした桃ちゃん人形は、衝撃的だったよ。いやいや、桃ちゃん人形に対する君の愛情を否定したい訳じゃないんだ。ただ、桃ちゃん人形に扮した君は、明らかに何かに取り憑かれているようだったからね。いやあ目が覚めたようで良かった良かった。ワッハッハ」
「はあ、あの、お恥ずかしい限りです」
思わず下を向いた鉄男に、カマボコ社長は言った。
「君はまだ若い。桃ちゃん人形に代わる何かがきっと見つかるだろう」
「はあ・・・・・・まずはと言いますか当面はと言いますか、趣味だった筈のトランペットに、少し本腰を入れてみようかと思っています」
「そうかそうか、それは良い。仕事は続けるんだろう?」
「はい、もちろん」
いつものえびす様の笑顔を浮かべながら、カマボコ社長がお決まりの台詞を言った。
「それじゃあ、これからもよろしく頼むよ」
「はい。では失礼いたします」
鉄男は社長室を出た。エレベーターのボタンを押し、到着を待つ。
チンと音がしてエレベーターの扉が開く。乗り込んだ鉄男は、後ろ髪を引かれる思いで、今一度社長室に目を向けた。
「さようなら、桃ちゃん」と、心の中で呟いてみる。
ポロリとこぼれ落ちそうになった涙を慌てて袖口で拭うと、鉄男はスマートフォンで花輪の番号を呼び出した。
【佳作】スーサイドテスト(齊藤想)
こんな大雨の日に、君はよくこの田舎のモーテルにたどり着いたな。看板もなにもない廃墟としか思えないクソみたいな建物なのに。
さてと、君はジャーナリストだそうだな。そのふてぶてしい態度から察するに、若いながらも相応の経験を積んできたのだろう。幾多の修羅場も潜り抜けてきたのに違いない。その経歴には敬意を称しよう。
しかし、それとこれとは話は別だ。
私を訪ねてきた理由は君が口にしなくてもわかる。あの忌まわしきスーサイド・テストの顛末を知りたいのだね。推理の根拠など話す必要もないだろう。それ以外に、私を訪ねる理由などあろうはずがないからな。
君以外にもさまざまなジャーナリストが私を見つけ出し、あのテストのことを聞こうとした。もちろん、あのテストのことを思い出すのも語るのもゴメンだと全員まとめて拒否したさ。申し訳ないが、君にも同じ言葉を送らせてもらうよ。
それにしても、君が私を発見したせいで、また隠れ家を変えなくてはならない。本当に迷惑をしている。人と話すなど数年ぶりだが、もちろん喜んではいないぞ。私は心から落胆しているのだ。
もう話は終わりだ。帰ってくれたまえ。
いや、少し待った。君が右脇に抱えている木箱はなんだ。随分と大事そうにしているが、この場で開けてみる気はないかね。だいぶ古ぼけているが、アンティークだけが放つ古き良き時代の香りがする。
いまはこんな酢とゴキブリの臭いしかしない安モーテルに住んでいるが、私だって若いころは多種多様なワインをたしなんだものだ。ワインはアロマを楽しむ飲み物だから、自然と嗅覚が研ぎ澄まされたのだよ。
なになに、開くにはテーブルが必要だと。まあ、言われればその通りかもしれぬ。仕方がないから少し上がってくれたまえ。君を招き入れたのは、そのアンティークを鑑賞するためであり、あのテストについて話すと決めたわけではないからな。勘違いするなよ。
それでは開いてくれ。
おお、なんと素晴らしい。私の予想通りだ。いや、予想以上と言うべきか。こんなに気品溢れるチェスセットは見たことがない。
素材自体は平凡なヨーロッパオークで、デパートで販売している普及品と同じだ。しかし、駒のひとつひとつに染みこんだ使用者の油脂が何とも言えぬ芳香を放っており、それに職人による細かな手作業だけが醸し出せる古きよき時代の雰囲気がほとばしっている。
これは安物に見せかけた高級品だ。なんと奥ゆかしい。
ところで、君は人間がそれぞれ固有の体臭を持っていることを知っているかね。年頃の女性が父親を嫌うようになるのは、父親が自分と類似する体臭を放っているからだと言われている。これが近親相姦を防ぐ自然の摂理だ。嗅覚というのは、人間が持つ最高感度のセンサーなのだよ。
私ほど感覚が研ぎ澄まされていると、チェスセットを開けた瞬間の空気を嗅ぐだけで様々なことが伝わってくる。ワインで鍛えた嗅覚はいまだ衰えておらぬ。
少し手に取ってみてもいいかね。私はこう見えてもグランドマスターの称号を持つチェスプレイヤーだ。駒に触れれば、この駒を使ってきたプレイヤーのレベルがわかるのだよ。
ふむふむ、扱いは丁寧だ。対局が重ねられたものだけが持つ風合をまといながら、新品同様の美しさを保っている。これはかなりの名プレイヤー、しかもチャンピオンクラスの所有物と見た。
君、それは本当かね。
このチェスセットは、なんと、あの第十六代公式世界チャンピオンのガリル・カスパロフが幼少時代に使用していた物だというのか。それで、君はチェスができるのかね。もちろんできると、なるほど。しかも、このチェスセットを手に入れたのは、スーサイド・テストを取材するためだと。
なぜこれを君が持っているのかを聞くのは野暮というものだな。少し考えさせてくれ……まあ、それにしても偽名を使って世間から隠れ続けてきたこの私を発見するとはたいしたものだ。私の居場所を誰から聞いたのかね? ああそうか。情報源を守るのはジャーナリストとしての義務か。それならいい。もう聞かん。
念のために確認するが、君はスーサイド・テストのことを勉強してここに来たということでよいかね。そのテストは科学界ではアンタッチャブルな出来事として葬り去られ、いまや無かったものとされておる。言い換えれば、破廉恥かつ無道徳な実験であったため、永久に封印されたのだ。
君もご存知の通り、あの実験にかかわった科学者は、刑務所にぶちこまれることだけはなかったものの、社会的に抹殺された。それは完全かつ執拗なものだ。真相を知ろうとしたジャーナリストたちも同じ運命にあった。公表しようとした人間は、どこかに連れさられた。関係者は固い守秘義務を課せられ、いまではそのテストの名前を口にすることさえはばかられている。
君も秘密に触れたら、実験に関わった科学者やジャーナリストたちと同じ末路をたどることになる。下手をしたら社会的に抹殺されるだけではすまない。もちろん、喋った私も同罪だ。
しかし、私は老人だ。長年の飲酒で肝臓がやられてしまい、余命はいくばくもない。だから、君が自らの身を危険に晒しても良いというのなら、チェスを楽しみながらの余話として、この場で昔話をしてやってもよいがのう。
なあに、秘密は絶対に守るとか、情報提供者の保護だとか、そういった類の口約束は不要だ。誓詞もいらん。死に行く人間と約束して、何の意味があるかね。これから起こるすべての運命を受け入れるという君の決断だけで十分だ。
そうか。うん。それならよい。君はなかなかよい面構えをしておる。この事件に首を突っ込みさえしなければ、数年もすれば世界を代表するジャーナリストになるだろう。惜しいことだ。君のその向こう見ずな決心は、世間知らずの、青さに基づいている。実に青い、青すぎる。けど、その青さは、枯れ木となった私には眩しく、羨ましく感じるのだ。
私は人工知能開発の最前線から引退した寂しい老人だ。その寂しい老人の独り言として聞いてくれ。
僅かな期間とはいえヨーロッパを支配したナポレオンⅠ世は、「チェスはゲームであるには難しすぎるが、科学か芸術であるにはまじめさが足りない」と評した。言いえて妙だと思わないか。わずか六十四枡の盤上を、三十二個の駒が舞うだけなのに、可能性のある局面数が全宇宙の粒子数より多い。これほど単純なのに、その深さは無限大で、かつ真面目にも不真面目にも取り組むことができる。
チェスから得られる楽しみは、何よりにも変えがたい。
対局は一番勝負。元グランドマスターとして、君の先番で始めたまえ。宇宙がひっくり返ろうとも、チェスは先手有利が絶対的な真理だからな。
さあ、勝負だ。
妻のいない自宅など、ヤドカリが投げ捨てた貝殻のようなものだ。
窓際に積み重ねられた老妻の布団は、主を失ったまま六月の長雨を聞き続けている。一面にプリントされた妻が大好きだった赤い薔薇は、長いこと太陽の光を浴びていないせいか、寂しげにしぼんで見えた。小柄な妻に合わせて仕立てられた小さな布団が、まるで親に怒られた小学生のように正座をしている。
家の窓からでは見分けることができないが、雨雲には厚い部分と薄い部分があるようで、雲が流れていくたびに雨はときおり激しくなり、ときおり囁き声になる。
布団に染み付いているはずの妻の汗は、梅雨の湿気と混じりあい、すでに悲しい臭いを漂わせ始めている。遺品の片付けは終わり、布団以外に何も無い空虚な空間でひとりたたずんでいると、まるで最後の瞬間を待つ死刑囚のような気分になる。
静かな部屋の中で人語を発する唯一の存在であるテレビは、昨晩から降り始めた大雨情報をたれ流し続けていた。各地で河川が氾濫し、私が住む地域も注意報から警報に切り替わった。妻と何度散策したか分からない自宅のすぐ脇を流れる川も、いまや怒れるゴリアテのように岩を吹き飛ばす濁流となっている。
テレビは無機質な声で避難指示を繰り返す。
報道だけでは物足りないのか、誰かが自宅の戸を叩きにきた。「新南さん、新南さん」と私の名前を何度も呼ぶ。無視を決め込んだら、すでに避難済みと思ったのか身の危険を感じたかは分からないが、心優しい住民は立ち去った。
蛍光灯とテレビが同時に消えた。停電になったらしい。どこかで電柱が押し流されたのかもしれない。牛蒡のような電柱の先につけられた拡声器が、少し上流で堤防が切れたことを告げている。
しかし、私にとって、すべては他人事だった。
現実感を喪失したこの空間で、妻の布団だけが私を現実に繋ぎとめてくれる。悪臭を漂わせている布団を抱き寄せると、私の記憶は妻への追慕で満たされていった。
四十年に渡る政治評論家生活を支えてくれた妻は、一ヶ月前に死んだ。肺癌だった。
妻は良き伴侶であり、老いた体を幇助してくれる献身的な介護師であり、共に正論を求めて戦う戦友でもあった。
妻との思い出は尽きるところを知らない。
私は保守の論客として知られていたが、リベラルだけでなく、意見の合わない同志たちにも舌鋒を緩めることはなかった。こうした私の頑固さが災いしたのだろう。業界ではアンタッチャブルと呼ばれている政界を裏で牛耳る慈善活動家を、ある週刊誌で非難したのをきっかけとして、昼夜を問わず苦情の電話がかかってくるようになった。
一見すると彼ははるか昔に実業界を引退した人のよい老人だが、その実はある宗教団体を隠れ蓑にした巨大組織のトップだった。利害を共にする手下どもからの攻撃など眼中に無かったが、彼を神とあがめる幾多もの信者のことを忘れていた。
怖いもの知らずだった私は、この見えない津波のような攻撃に、生まれて初めてと言ってもいいほどの恐怖を覚えた。彼らに言論という武器は通用しなかった。
正体不明の人物からの無言電話や罵詈雑言に悩まされ、FAXは用紙が尽きるまで呪いの言葉を吐き続た。近所に正体不明の人物がうろつくようになり、彼らはまるで私に聞かせるかのように門扉を叩き、壁に落書きをして、郵便受けに剃刀と使用済みの注射器を詰め込んでから立ち去る。
恐怖に駆られた私は住み慣れた家を離れ、何度も引越しをした。誰にも転居先を告げていないのに、数日とたたずに居場所は知れ渡った。
どこに出かけるのも他人の視線が気になった。道行く人が全員敵に見えて、思い余って赤の他人に詰め寄ったこともある。親戚にも迷惑をかけた。もちろん警察に相談することもできない。彼の組織は日本中に信者がいる。警察に相談したら、その情報が瞬時に信者へと回り、攻撃が悪化することが目に見えていた。
私は精神的に麻痺した。何を書けばいいのか分からなくなった。彼は世間一般には善人として通っているので、信者だけでなく多くの読者も敵に回してしまった。孤立無援の状態だった。雑誌は、「売れるから」と私に原稿を求め続けた。雑誌は言論の自由を盾にしながら、非難はすべて執筆者に押し付けた。
それでも、私は生活のために書かねばならない。辛い人生を歩ませてしまった妻への罪滅ぼしのため、せめて経済的には人並み以上の生活を送らせてあげなくてはならない。
「今回はマイルドですね」
「主張が変わられましたね」
長年付き合ってきた編集者からの感想が胸に刺さる。白々しい虚勢を張る元気もなくなった。
外出の恐怖から編集部に顔を見せることもできなくなり、自宅に引きこもるようになった。何度引っ越しても、何度電話番号を変えても、彼らは追いかけてくる。この地球上で、逃げ場はどこにもないように思えた。
うつ状態になりかけていた私の代わりに、電話から来客まで一手に対応をしてくれたのは、妻だった。
二階の奥にある電話が鳴ると、妻がそそくさと立ち上がり、電話を取った。しばらくすると、笑顔で階下におりてくる。
「またあのひとたちのお電話でしたから、もっと勉強しなさいと叱ってやりましたよ」
妻は六十を越えても若い頃と同じ仕草で、いたずらっ子のように舌を出す。申し訳ない気持ちで私が頭を下げると「この程度でへこたれていたら、政治評論家の妻という仕事はつとまりませんから。少し激務だけど、刺激的で面白いものよ」と、ケロリと答える。それどころか「どんどん敵を作りなさい。それがあなたの商売でしょ」と妙な励まし方をしてくれる。
私がいままで政治評論活動を続けられたのは、間違いなく妻のおかげだ。いつも前向きで、どんなときも私の味方で、ときには城となり、石垣となり、堀となって私を守ってくれた。彼女は敵が攻め上ってくるのを楽しそうに待ち構え、次から次へと蹴落としていく。この小柄な体のどこにそのような力があるのだろうか。いつも驚嘆の思いで、小さな背中を眺めてきた。
評論で数多くの賞を受賞できたのも、妻があってこそだ。彼女には感謝しても感謝しきれない。
妻が私と結婚したのは、単なる偶然だ。
たまたま大学で同じゼミになり、珍しく映画の好みが一致し、稀有なことに映画の後に寄った喫茶店でだれも知らないようなマニアックな俳優の話で盛り上がり、驚いたことに「私とこんなに話があうひとは初めて」と彼女が目を輝かせてくれたのだ。
私は彼女にのめりこんだ。社会人になったら結婚まで一直線だった。
私の妻という仕事は、激務というレベルではない。ブラック企業が束になってかかってきても、尻尾を巻いて逃げ出すほどだ。
妻のおかげで、私は本当に良い人生を過ごさせてもらった。感謝という言葉をいくら重ねても表現できない。この言葉を積み上げれば、成層圏を突き抜けて月まで届いてしまうだろう。
しかし、と私は自問する。私がいい人生を歩ませてもらった一方で、私は妻を幸せにしてあげられたのだろうか。私との奇跡的な出会いさえなければ、妻はもっと人生を謳歌できる配偶者と出会い、平和で幸せな人生を歩めたのではなかろうか。彼女の友人や親族から白い目で見られるような人生を歩むこともなかったのではなかろうか。
私は仕事で世界中を回り、賞を取るたびにますます執筆と公演に追い立てられるようになった。家庭生活などあってないようなものだ。私はまったく知らなかったが、私が家を留守にしている間にも苦情の電話がかかってきて、妻は見知らぬだれかの罵声を浴び続けていた。
私には、例の慈善活動家以外にも、敵が山のようにいる。私の仕事は誰かを非難することだ。読者もそれを期待し、私も誰かを非難するために書き続ける。正論の身をまとっているだけで、その内実は悪質なクレーマーと何ら変わらない。世間から罵声を浴び続けても当然の人間なのだ。
それなのに、なぜか表彰状と記念品は増え続けた。妻の負担はますます重くなり、自宅にかかってくる苦情の電話の頻度と悪質さは増す一方だ。それでも、壇上で表彰状を手にする私を、妻は誇らしげに眺めてくれた。
精神的疲労から五十五歳を超えるころから私の肉体は加速度的に衰え、ますます妻に依存するようになった。まるで赤ん坊になったかのような気分だった。私がいままで生きていられたのは、間違いなく妻のおかげだ。
だれの言葉か忘れたが、「空気は無くなった瞬間に気がつくが、無くなるまで空気があることに気がつかない」という至言がある。
人間の悲しい性とはいえ、私はあまりにも鈍感すぎた。
定期的に受診している人間ドックで妻の癌が発見されたのは、お互いに七十歳を少し超えたころだった。妻の癌はすでに末期で、手術は不可能だった。助かる見込みは万に一つもない。妻が侵されたのは急速に広がる種類の癌で、毎年人間ドックを受けていても防ぎようがないとのことだった。
その場で医者からは余命半年と宣言された。運命ですから諦めてください、と言われた気がした。
妻の癌が発見されたときから、私は一切の政治論評活動を停止した。妻の看病が表向きの理由だが、実際のところ、私は妻がいなければ何も書けないただの老人だ。多くの敵に囲まれ、いつくるか分からない攻撃に脅えて過ごす弱者だ。
私は、まるで災厄から避難するかのように、毎日病院に通った。朝は自宅でお弁当を作り、昼は病院で妻と食べる。妻は一度だけ「仕事はどうしたの?」と私に聞いてきた。曖昧に言葉を濁したが、それで妻は理解してくれたようだ。
落ち着く場所が、自宅から病院に変わった。
妻とこうして、なにもせず、だれからも邪魔されず、病院の窓際で妻が剥いてくれたリンゴを食べる。このような夫婦の時間を持てたのは何年ぶりだろうか。ゆったりとした時間。永遠とも思える時間。
しかし、病魔は妻の体を確実に蝕んでいた。
医者の宣告に反発するかのように、妻の闘病生活は一時帰宅を繰り返しながら二年にも及んだ。それは、見守る側にとっても辛い時間だった。美しかった妻の顔はときおり襲われる苦痛にゆがみ、あれだけ凛としていた彼女が下の処理すら一人でできなくなった。
人間としての尊厳が崩れていく妻の姿を見るのは忍びなく、それを医者や看護師とはいえ他人の目に晒す苦痛も耐えがたかった。私が妻の全てを支えたい。そう願ったが、年老いて体力の衰えた私にはその能力がなかった。
悔しかった。寂しかった。
入梅を目前にしたある水曜日。ついに入院中の妻の意識が途絶えた。いつ最後のときが訪れてもよいように、私は病室に泊り込むことにした。
妻は混沌とする世界を漂い続けたが、真夜中にふっと目を覚ました。しばらく視線をさまよわせていたが、傍らにいる私に気がつくと、手を伸ばしてきた。私は妻の手を握り返した。闘病生活で肉が削げ落ち、骨と握手しているかのようだった。それでも、間違いなく、愛する妻の手だった。確かな体温を感じることができた。
彼女は、薄茶色の瞳孔を私に向けると、明瞭な声でこう告げた。
「ありがとう。あなたのおかげで、とても楽しい人生をすごせた。いま、私は最高に幸せな気分よ」
医者はこの話を否定した。正確には否定的なニュアンスでうなずいた。昏睡していた妻が急に目覚めて語るなど医学的にはありえないのかもしれない。だが、私は確かに妻の声を聞いたのだ。
それから数時間後、妻は死んだ。夜は白み始め、透き通るような朝日が病室に差し込んでいた。
妻の葬儀を終えた私は、抜け殻になった。生きるしかばねだった。何もする気がないし、何かをする能力もない。
私には子供がいない。周囲にいるのは敵ばかり。妻を失った私には生きがいはなく、生きる意味もない。老化は確実に体力を奪い、妻のことがなくても断筆せざるをえなかっただろう。これが引き際なのだ。
評論活動から引退すると、あれだけ懇意にしてきた編集者も波が引くように去っていった。長年の義理で付き合ってきたが、雑誌としても私は厄病神だったらしい。
自宅への攻撃は続いていた。妻という防波堤を失った私に、攻撃を受け止めるだけの気力は残っていなかった。呼び出し音が鳴るたびに、私の生命力は削り取られ、だれかが自宅前を歩くだけで心臓が握りつぶされる。
もう限界だ。どうやら人生に幕を引くときがきたようだ。
洗面台のミラーを開けると、新しい剃刀が何本も残っていた。妻が私のために購入し、そのままとっておいたままのものだ。この家には、妻の気持ちが溢れすぎている。
いま決断しないと、決断する体力さえなくなる。決断というものは、体力を異常なほど消費するものだと、私は実感した。
私は震える指先で剃刀を手にすると、おぼつかない足取りでバスタブへと向かった。
洪水はますます勢いを増している。奔流の音がさらに近づいている。
雨は、まだ降り続いている。
今夜の雨は長いねえ。ノアの箱舟が出港しそうな勢いだよ。
それにしても、君のチェスの手さばきは悪くない。先ほどから謙遜しているが、君はそれなりに経験を積んだプレイヤーで間違いない。隠したって、この私にはわかるのだぞ。
ほう、キングポーンが向かい合った形からナイトの飛翔ときたか。それはルイ・ロペスだね。ルイ・ロペスは十六世紀に活躍した実在のチェスプレイヤーだ。つまり、この形はそれだけ昔から指されており、かつ現代まで命脈を保ち続けている優れたオープニングなのだよ。
こうした古風を形を選択するとは、君は基本に忠実な棋風のようだ。ルイ・ロペスは先番の優位さを活かせる戦形だが、そのポジショナルな有利さをまとめるには洗練されたテクニックが必要である。
それでは、私は用心して、クローズド・バリエーションから、スミノフ・バリエーションへと発展させようか。
スミノフもルイ・ロペスと同じく実在した人物で、世界チャンピオンに輝いたこともある名プレイヤーだ。君はSF映画の古典であるスタンリー・キューブリック監督『2001年宇宙の旅』を鑑賞したことはあるかね。その映画で宇宙ステーションを訪ねる科学者の名前をスミノフから拝借した逸話は有名すぎたかな。
それにしても、こうして人間と盤をはさむのは何年ぶりだろうか。いや何十年ぶりかもしれない。もう思い出せないほど遠い昔だ。なにしろ、あの実験以来、ずっと一人で過ごしてきたのだから。
約束だから、そろそろ昔話を始めよう。けどその前に、人工知能の歩みを振り返らなくてはならない。なあに、話には順番というものがある。老人は話が長いと決まっているのだ。君ほどの取材経験があれば分かるだろう。
今夜は長くなりそうだ。
いまになって思うと、人工知能の開発には三つのターニングポイントがあった。そのひとつ目は、人工知能の”歴史”についてのターニングポイントだ。
人工知能の歴史が変わったのは、一九九七年、IBMの開発したスーパーコンピューターのディープブルーが、現役チェス世界チャンピオンであるガリル・カスパロフ氏を破ったことだ。そう、君が持ってきたチェスセットの元所有者だよ。
チェスは世界中で行われている最もポピュラーな知能ゲームであり、その複雑さから人類の知性の象徴と思われていた。グランドマスターたちの対局は、現代を生きる君には信じられないかもしれないが、当時の美術家たちから最高の芸術作品と評されていたのだ。その時代の人類からすれば、チェスは人間だけが行える神聖なゲーム、というわけだ。
その神聖なる領域に、IBM製のコンピューターが殴り込みをかけ、土足で荒らして看板を持ち去ったのだから世間は大騒ぎになった。この歴史的な快挙に、IBMの株価は一夜にして十五パーセントも値上がりした。
この事件が人類に衝撃を与えたことは間違いない。何か大きなものがガラガラと崩れていったようだ、と当時の多くの識者が語っている。
この日まではコンピューターは人間に追いつけるかが命題だったのに、ガリルが両手を広げながら茫然自失の体で対局場を後にしてからは、コンピューターがいつ人間を追い越せるかがテーマになったのだ。
こうして話すと、ディープブルーがいかに凄い能力を持つコンピューターかと思うかもしれない。しかし、人工知能の”開発”の歴史からすると、実はなんら革新的なことは起きていないのだよ。
ディープブルーは一秒間に二億手を読む能力があったが、本当に大切なのは読んだ先の局面を正確に評価できるかどうかだ。たとえ二十手先、三十手先を読んでも、その局面が有利なのか不利なのか判断できなければ、ただ駒を並べただけにすぎない。コンピューターの強さを決めるのは、どの局面を選択するかにかかっている。
その局面を評価する計算式のことを評価関数というが、実はディープブルーの計算式はほぼ手作業で作られていたのだ。外見こそ近未来的なコンピューターだが、その中身は職人芸の塊だったのだよ。
つまり、ディープブルーは人間らしい思考を通じて指し手を決めたわけではなく、人間から教わったとおりに駒を動かしたに過ぎない。コンピューターは計算しただけで、何も考えていないのだ。
命令どおりにしか動かない指示待ち人間に知性を感じないのと同じように、ディープブルーにも人間らしい知性は存在しなかったのだよ。
ガリルの名誉のために補足するが、確かに彼はディープブルーとの歴史的なエキビジションマッチに敗れた。しかし、大方のチェス関係者の見方は「実力はガリルが上」だった。実際に六戦マッチのうちガリルが負けたのは二戦だけで、そのうちのひとつは引き分けの手順をガリルが見落として投了してしまっただけだし、もうひとつの敗戦は定跡の手順前後という人間らしい初歩的なミスだ。
ガリルはディープブルーとの再戦を要求したが、IBMは拒否した。その理由を推測するのは実に簡単だ。彼らも再戦すれば負けると思ったのだろう。
その後もガリルは最新のコンピューターと戦い続け、六年後の二〇〇三年においても引き分けという結果を残している。ガリルは後に「人間対コンピューターの対決の黄金期は一九九四年から二〇〇四年の間であった」と語っている。負け惜しみではなく、まさにそのとおりだったと思う。
彼は初めてコンピューターに敗れた世界チャンピオンという汚名を着せられたが、十五年間も世界チャンピオンの座を守り続けた実に偉大で、かつ勇気に満ち溢れた人類史上最強のチェスプレイヤーだったのだよ。
ちょっと脱線が長すぎたかな。
チェスのことになるとついつい話に力が入ってしまうのが私の悪いクセでな。孤独な老人の唯一の趣味がチェスで、ガリルの棋譜を並べるのが毎晩続く長い夜を越える慰みなのだよ。彼の棋譜は力強く、創造性に溢れ、かつ華麗で美しい。まさに人類が生み出した最高の芸術品といえよう。偉大なチェスプレイヤーの棋譜は芸術品であるという美術家たちの意見は、いまでも正しいと思っている。
君は画家のマルセル・デュシャンを知っているかね?
彼はチェスを新しい芸術としてとらえ、チェスを「動中の静」を表現する一番の近道であると考えていた。彼はチェス大会で優勝したのを皮切りに、フランスチームの一員になったり、アメリカチームのキャプテンになったりしている。
ほう、そこでその手を指したか。
ポーンを密着させるとは驚きだ。格上である私を相手に中央のスペースがないクローズドゲームを選ぶとはいい度胸だ。オープンゲームは駒が乱舞するので読みの精度が重要で、クローズドゲームは長い勝負になるため戦略が重要になる。つまり、若いほどオープンゲームが有利で、ベテランほど経験値を活かせるクローズドゲームが有利になる。
君はまだ若いからオープンゲームを好むかと思ったら、あえてクローズドゲームに持ち込むとは意表を突かれたよ。長いゲームにして私からより多く話を聞きだそうとする配慮は不要だぞ。話すと決めたら最後まで話す。だから、いまは勝負に集中してくれ。それでもこの手を選ぶのなら、それでよい。ゲームを続けよう。
今夜の雨は止みそうにないな。なあに時間を心配することはない。いざとなれば、ここに泊まればよい。
安心してくれたまえ。私にはその手の趣味が無いのだから。そして、その能力も。
また自転車がパンクさせられている。
家を出るときは何事もなかったのに、中学校の授業が終わるころには、タイヤにカッターナイフを差し込まれたような切れ込みが何箇所も入れられていた。この自転車に向けられた同級生たちの暗い悪意を思うと、胸の深いところから吐き気がこみ上げてくる。
ぼくの家は貧しい母子家庭。それなのに、お母さんは頑として生活保護を受けない。スズメの涙のような時給のバイトを掛け持ちして、ぼくを育ててくれている。
誕生日のお祝いは一切れのケーキのみ。
「お母さんの一番のご馳走はね、タカヒロが美味しいそうに食べてくれることだよ」
というのが母の口癖だ。いくらぼくが二人で半分にしようと言っても、「私の楽しみを奪わないで」と冗談交じりに微笑み返してくる。
お母さんのおなかの虫は、いつも鳴ってばかり。それなのに、決して笑顔を絶やさない。
この自転車は、ぼくの大好きで大切なお母さんが、無理をして買ってくれたものだ。それが無残にも切り刻まれ、なすすべもなく車輪のついた鉄くずにされてしまった。手持ちの修理道具は使い切った。ぼくには大切な自転車を治療する方法がない。この無残な姿をみたときのお母さんの落胆を思うと、帰りの足取りは地縛霊に足を掴まれているかのように重くなる。
ぼくがイジメられるようになったきっかけは、隣の小学校から進学してきた不良連中がぼくの家庭環境をからかいのネタに使い出したことだ。
お母さん以上に素晴らしいひとはいない。自分は自分の家族に誇りがある。
怒ったぼくは、不良軍団を睨んだ。抗議の視線だ。ただ目線を向けただけなのに、怒り出した不良軍団に殴られ、蹴り飛ばされ、まるでサッカーボールのように転がされた。
まさに一方的な暴力だった。クラスメイトたちは見てみぬ振りをした。いままで味方だと思っていた友人は、祟りを恐れる村人たちのように、一斉に離れていった。唯一味方をしてくれた女子児童は、またたくまに反撃され、辱めに合い、あまりの酷さにぼくから味方をするのを止めてくれと頼んだぐらいだ。その女子児童は泣いた。
先生たちも、問題が顕在化するのが怖いのか、”ケンカだよね”とみえみえの和解の儀式を設定してお茶を濁した。強制的な握手とともに、不良軍団は無罪放免された。学校がいじめを黙認したのも同然だった。
不良軍団はますます増長した。腹が減ったら飯を食うように、喉が渇いたら水を飲むのように、ごく自然にぼくを殴るようになった。必要もないのに物を奪うようになった。面白いからという理由で勉強道具を壊すようになった。
それでも、ぼくはいつも疲れているお母さんに余計な心配をさせないように、家ではつとめて明るくふるまった。蹴られた跡を見せないように、泥を丁寧に払うことが習慣になった。溢れる涙も家の外で捨ててきた。どんなに辛くとも、いつも笑顔でいるお母さんのようになりたかった。
けど、お母さんが寂しそうな顔をすることがある。
それは、ぼくのものが壊されたり、取られたり、無くされたりするときだ。こればかりは隠しようがない。
お母さんはあんなに頑張っている。それなのに、お母さんが汗水たらして稼いできた大切なお金が、ぼくのせいで消えていく。自転車の修理代、折られた鉛筆代、引き裂かれたノート代、さらには隠された靴や体操着。
ものが無くなったと知ったとき、お母さんはどこからしら工面してくれる。ほとんどが中古品だけど、そのときのお母さんの苦しそうな顔といったら、悲しくて涙がこぼれそうになる。
違うんだよ。お母さんが落ち込むことはないんだよ。一番情けなく思っているのはこのぼくだよ。暴力と集団の圧力に負けている、このぼくなんだ。
この言葉を、ぼくは何度心の中でつぶやいたことだろう。けど、こんなことを口にしても、お母さんは余計に悲しむだけだ。そう知っているから、ぼくは何もいえない。耐えるしかない。
昨晩からの長雨が続いていて学校が休みになるかもという連絡があったが、結局、いつも通り授業が行われた。授業を潰すとその分だけ先生が大変なので、休校にしたくないのだろう。
てっきり休みだと思っていた不良軍団は、それでいつもよりイライラして、ぼくの自転車に当り散らした。
雨は上がったけどまだ青空は見えず、厚い雲が大地を覆い隠していた。
ぼくは大きな橋を渡ろうとして、ふと気がついた。いつもの帰り道と違う。なぜ無意識のうちにここを通ろうとしているのだろうか。見えない誰かに操られているのではないか。そうとしか思えないほど、奇妙な行動だった。
橋の下を覗き込むと、川は昨晩の大雨を全力で吐き出しているところだった。川岸まで茶色く濁り、まるで強迫観念にでも駆られているかのように立木や家屋の破片を押し流している。少し上流にある隣町では、住宅地の真ん中で破堤したらしい。水の勢いはそこで削がれ、下流には被害が及んでいないようだ。
ここに飛び込めば、この世界から切り離される。嫌なことをされることもなくなり、だれかを困らせることもない。お母さんを悲しませるかもしれないけど、悲しみは時間が癒してくれる。そんな思いが、ぼくの頭を駆け巡る。
そうか。無意識にここまできた理由は、これだったのか。
全てに気がついたぼくは足を止めると、自転車のスタンドを立てた。この世界からの別れを告げるために、いままで頑張ってくれたお母さんへの祈りを捧げる。
お母さん。いつも苦労をかけてごめんね。悲しませてごめんね。だから、これからお母さんを楽にさせてあげる。よりよい人生を歩めるようにしてあげる。
ぼくは自転車のホイールに爪先で「いままでありがとう」と書いた。光の角度をあわせないと浮かび上がってこないが、お母さんなら見つけてくれるはず。
土砂を満載したダンプカーが橋の上を通り過ぎた。泥水がはねたが、不思議なことにぼくと自転車を避けた。まるで、新しい門出を祝っているかのように。
これで思い残すことはない。
ぼくは迷うことなく、欄干をまたいだ。
もうそろそろ雨脚が弱まると思ったら、逆にますます強くなっている。今日の雨は本当に異常だ。まるであの日を思い出させるかのようだ。道路が冠水すれば、君は本当にこの安モーテルに泊まることになるぞ。覚悟はあるか。もちろん、これは冗談だが。
おや、その手はなかなか鋭い。クィーンサイドにオープンスペースを残そうというのか。cファイルは私から閉じざるを得ないから、これでオープンスペースはaファイルのみ。白番で得たポジショナルな優位を実利に変えていく体勢は整ったとの主張だな。見事な指し回しとしか言いようがない。
このような遠大な構想を描けるなら、君がクローズドゲームを選択するのも納得だ。先ほど私は君は若いからオープンゲームを選ぶべきと告げたが、それは実に失礼な言い草だった。謝罪して取り消そう。君は”若い”プレイヤーではない。”強い”プレイヤーだ。
いよいよ駒交換が始まった。駒が減ると僅かな優位が相対的に大きくなる。つまり、逆転の要素が減るというわけだ。その一方で、駒がぶつかるとプレイヤーの実力が如実に現れる。いまは定跡から遠く離れ、新たなる局面への理解力が試されている。
君がチェスに対する深い造詣に後押しされた真のプレイヤーなのか、それとも定跡を暗記してきただけの記憶マシーンなのか、ここからの数手で明らかにされるだろう。
手つきと態度からすると、君はこの局面から勝ちきれる自信があるようだ。しかし、グランドマスターとの対戦はそのような甘いものではない。底力と底力がぶつかり合うここからが本当の勝負だ。
さて、話を戻そう。
次は人工知能の”開発”においてのターニングポイントだ。これは世間的にはまったくニュースにならなかったが、二〇〇六年の米国標準技術局の機械翻訳コンテストで、統計的手法を採用したグーグルチームが優勝したことだ。
当時の機械翻訳といえば、翻訳すべき原文を分析し、論理的に翻訳するのが一般的だった。具体的な手法は幾多もあるが、とりあえずそれらを総称してアルゴリズム型と呼ぶことにしよう。
このアルゴリズム型の機械翻訳は、単語同士を対応させる膨大な辞書を用意し、構文と文法を他の言語に置き換えることで翻訳する。いわば、辞書と参考書を開きながら翻訳するようなものだ。
こう話すといかにも簡単そうだが、言葉には複数の意味があり、文脈により言葉の意味が変化する。例外規定も膨大だ。その国の文化を知らないと翻訳できない文章もある。
機械翻訳の開発者は様々な工夫を重ね、機械翻訳用の言語まで開発した。あらゆる言語を中間言語に落とし込み、その上で翻訳すれば、翻訳の精度が上がると考えたのだ。確かにこれはよいアイデアに思えたが、完成した翻訳はいまにして思えば五十歩百歩だった。
こうしてアルゴリズム型の機械翻訳が苦しんでいたとき、颯爽と登場したのが統計学的手法だった。これを統計ベース型と呼ぶことにしよう。
先ほどの大会で優勝したグーグルチームだが、実はメンバーのだれひとりとしてコンテストで使用されたアラビア語と中国語を理解していなかった。では、どのようにして開発したかというと、国連の議事録という人間の手による質の高い翻訳をデータベースとして活用し、言語的なパターンを対比させることにより翻訳を作成させたのだ。つまり、人間が教えるのではなく、教材をコンピューターに与えて、勝手に勉強しとけと。かなりざっくりと言えば、統計ベース型とは、そういうシステムなのだ。
そう、君が指摘するように、翻訳というより単なる当て込みだ。ところが、その当て込みが、何十年もの歴史を持つアルゴリズム型の機械翻訳を圧倒したのだ。この結果を前にして、ワシントン大学コンピューター科学部長のエド・ラゾキスは嘆いた。「機械翻訳での三十年の経験などは何だったのか」と。
この統計学的手法は、日本の伝統的ボードゲームである将棋にも革命を起こした。
チェスが世界チャンピオンを倒したのが一九九七年だ。そのころのコンピューター将棋は、もちろん開発人数、開発環境に大きな差があるにしても、ようやく少し強いアマチュアになった程度だった。
もちろんコンピューター将棋は毎年強くなっていったが、チェスより盤面が広く、取った駒を再び使えるといった複雑さもあって、プロレベルには到底及ばなかった。あまりの歩みの遅さに、将棋のプロである棋士たちのほとんどが、コンピューターがプロに勝つ日は永久にこないと思っていた。
そうした棋士たちの平穏な日々を破壊したのが、保木邦仁という将棋の素人が開発した「Bonanza」だ。
彼は膨大な将棋のプロたちの棋譜をコンピューターに取り込み、それに統計学的処理をほどこすことで、突如として恐ろしく強い将棋ソフトを作り上げたのだ。
いままでの将棋ソフトというと、ディープブルーと同じく将棋のグランドマスターたちが評価関数を手作業で作り上げてきた。それを完全に否定し、グーグルチームと同じくコンピューターに自ら勉強させることで、先人たちが乗り越えられなかった大いなる壁を打ち破ったのだ。
このようにコンピューターにデータを与え、自ら学習させる手法を機械学習という。
初代Bonanzaはまだ黎明期であり、プロの実力に迫ったものの、当時の将棋チャンピオンだった渡辺明竜王に惜しくも敗れた。
しかし、コンピューターの勢いは止まらない。一度突破された壁は、チェスと同じく二度と修復できないのだよ。
驚くことに、保木邦仁はソフトのコードをすべて公開した。コンピューター将棋の製作者は一斉にBonanzaの手法を取り入れ、まさにバブルのような開発ラッシュが起こったのだ。
保木邦仁の登場以降、プロ棋士たちはコンピューター将棋に押され続け、十年もたたないうちに征服された。この純然たる事実を認めたくないのか、将棋界はトップ棋士がコンピューターと対戦することを拒み続けて、若手中心の団体戦でお茶を濁した。
そして人間とコンピューターが競っていた黄金期を逃した後、棋戦のひとつとしてたまたま名人とのコンピューターとの対戦が実現したものの、それはもう結論が分かっている無意味な虐殺ショーに過ぎなかったのだよ。
個人的には、将棋界が黄金期を逃したことを残念に思っている。適切な時期に、最高の環境で、コンピューターとトップ棋士との対戦を実現するべきであった。将棋界がトップ棋士の出し惜しみをしているうちに、コンピューターが人間には手の届かない領域にまで到達してしまったのだ。
これは、将棋界にとって本来は通るべき通過儀礼を避けたことを意味する。
なお、コンピューターが子供相手に軽くひねられる時代に死去した将棋界の偉大なるチャンピオン、大山康晴十五世名人が大勢の棋士の意見に反して、そのうちコンピューターが人間に勝つと断言していたのが面白い。なあに、チェスと将棋は似ているから、東洋の将棋にも少し興味を持っただけのことだ。
いままでの話が、何を意味するのか君にわかるかね。
グーグルチームのアルゴリズム翻訳が全ての言語に有効であるわけではないし、コンピューター将棋を変えた機械学習がすべてのボードゲームに有効であるわけでもない。しかし、人間がコンピューターにルールを教えるより、コンピューターにルールを作らせるほうが、「人間らしい翻訳に書くことができる」、「人間より強いコンピューター将棋を作ることができる」ことが証明されたという事実が重要なのだ。
この方式を、人間の行動一般に当てはめたらどうなると思う?
小説、映画、新聞記事、裁判記録、さらには防犯カメラの映像など、これらをデータベースにした人工知能を開発することができたら、人間より人間らしい人工知能が誕生するはずではないかね。機械学習で使われる数式が確立している以上、人類のありとあらゆる行動を数値化して、適切な行動を取らせることは可能であるはずではないかね。
二〇一一年のことだが、『ジェパディ!』というクイズ番組で、IBМが制作した人工知能ワトソンが、歴代チャンピオンに挑戦した。そう、あのガリルを破ったディープブルーを生み出した会社だ。
『ジェパディ!』という番組は質問文に複雑な構文や、独特で微妙な言い回しがでてくるのが特徴で、コンピューターに問題を理解させるのは困難であると思われた。
文章の理解は人間の独壇場だ。だれもが無謀な挑戦だと思っていた。そして、開発当初は、実際そのとおりの回答率しか得られなかった。
しかし、研究が進み、人工知能ワトソンも統計学的手法を最大限に用いることで飛躍的に正解率が向上した。複雑で微妙なニュアンスの把握が求められる質問にも、適切な回答を導き出せた。対決直前には歴代チャンピオンと同等の回答率となり、そして本番では……これまたガリルを彷彿とさせるが、実力は互角だったのに人間に圧勝したのだ。
もちろん、統計学的手法にも批判はある。コンピューターが文章を理解しているといえるのか。コンピューターは単に数学的計算をしているだけで、彼は何を聞かれ、何を答えているのか理解できていないのではないのか、とかね。
その答えはもちろんイエスだ。だから何だというのか。相手のことを理解した上での「愛している」と、数学的結論から導き出された「愛している」を、人間は区別できるのかね。人間は心を読めるというか、それは微妙な表情やしぐさ、口調で判断しているだけではないのかね。
そもそも、人間の”理解”なるものを機械で再現する意味はあるのかね。
そうした複雑かつ無意味な議論が長らく続いたが、神学論争に興味を持たない一部の科学者たちが、ついに人間より人間らしい人工知能を完成させた。
その人類最初の高みに登った科学者こそ、この私だ。彼が生まれた瞬間、別に彼女でもいいのだが、私は体が震えるほどの感動を覚えた。まさに新しい知性の誕生だ。彼との生活、彼女との会話は実に刺激的で、幸福に満ち溢れていた。
私はその人工知能に、ミーカという名前をつけた。
それが起こったのは、ある梅雨の日の朝だった。
私が店長を務める居酒屋に配属された新入社員が、わずか入社一年でマンションの屋上から飛び降りた。彼女の衣服が階下のベランダにひっかかかり、街路樹がクッションになったことで即死こそ免れたが、頭部を強打して植物状態となり、いまも生死の境をさまよっている。
彼女は田舎から上京してきたような、純朴で真面目な女性だった。関東近郊の短期大学の出身で、本社一括採用により新卒で支店に配属された。
当初はよくある自殺未遂のひとつとして片付けられ、大きな事件にはならなかった。ところが、彼女が過労を訴えたメモを残していたことから大騒ぎになった。
確かに私の店舗が忙しいのは認める。しかし、それは人気の裏返しであり、人気店で働けることは社員にとっても喜びのはずだ。なにより、これからの未来を支えていく若者の人生修業の場として、最高の環境を提供してきた自負がある。社会に出たばかりのひな鳥たちを、親鳥として慈しんできたつもりだ。
私も家族を持つ親のひとりだ。家に帰れば愛する妻子がいる。息子は大学四年生で就職も決まっている。息子の就職活動には細かなアドバイスを送り、息子が就職を希望する企業に問い合わせや訪問をするなどして、実際に骨も折った。就職が決まったときには家族で喜んだ。
そうした経験から、息子と同年代の社員やアルバイトを預かる店長として、必要となる若者の心の機微には通じている自信があった。
居酒屋なので、勤務時間は夕方から早朝が中心となる。
出社時間はオープン二時間前の夕方三時。終了は明け方五時。そこからクローズ作業があるので、帰宅の途につくのは朝七時ごろになる。
名目上は十五時間勤務だが、終電が駅を離れるころには客足は遠ざかり、始発電車を待つ客もだいたいは飲み疲れて注文が途絶える。状況を見て適宜休憩できるので、実労働は十二時間程度だ。しかもシフト制なので、定期的に休日が回ってくる。これで十五時間分の給与を得ているのだから、動労環境としてはむしろ恵まれている。
店長の私を始めとして、多くの社員がこの勤務を続けてきたのだが、問題が発生したのは今回が初めてだ。
だからこそ、今回の件では戸惑うことが多い。
私がこの居酒屋を選んだのは、創始者である会長の理念に憧れたからだ。会社説明会の大学生を前にして、会長は力を込めて力説した。
「アルバイトも社員も関係がない。一生懸命仕事する人間こそ会社の宝であり、家族の誇りであり、社会のリーダーである。個人の成長なくして夢の実現はない」
私が入社したときは地方の数店舗を経営する小さな会社だったのに、会長のリーダーシップのもと急成長し、いまや関連子会社を含む全国チェーンを展開する一大企業グループとなった。
私も会社と一緒に成長したという実感があった。いい時代を会社とともに過ごした。様々な経験をさせていただいた。会長とともに充実した青春時代を送ってきた。会社のすべてが私の宝物だ。
こうした輝かしい日々を、彼女にも体験して欲しかった。
私は彼女に特段厳しく接したつもりはない。多くの社員と同じように教育してきた。会長は「すべての社員は家族である」といつも話していた。彼女は私の家族であり、娘である。心から、そう思っていた。
だからこそ、彼女がマンションから飛び降りたと聞いたとき、その原因がわからなかった。過労で心神喪失に陥っていたと聞かされても、まったく理解できなかった。社員は家族であり、仕事は家庭である。確かに仕事は忙しいが、暖かな家庭を築いてきという矜持がある。
私は信じられない思いで彼女の焼香に出かけたが、遺族に拒否された。何がいけなかったのだろう、何が悪かったのだろう。
彼女が残していたメモがきっかけとなり、店舗への取材攻勢が始まった。
私の店はチェーン店の中でもトップクラスの売り上げを誇っていたが、テレビカメラが向けられたとたんに悪の権化とさせられた。
いままで忙しい中でも店舗が回ってきたのは、ベテランアルバイトたちの存在があったからだ。それが激しい取材攻勢のなかでひとり抜け、ふたり抜け、残るアルバイトも辞めどきを探っているありさま。
あれだけ堅牢だと思っていた私の城は、砂上の楼閣だった。いまやは廃城寸前で、事件前はあれだけ活況を呈していた店舗だったのに、見るも無残に崩壊していった。
労働基準局の査察が入り、山ほどの指摘事項を受けた。売り上げが激減した。私は残った店員たちに奮起を促した。
「いまが苦しいときだ。みんなでがんばろう」
それを聞いた大学生の女性アルバイトが帽子を投げ捨てた。彼女も、苦しいときに一緒に頑張ってくれたベテランだった。だからこそ、次の言葉が胸に響いた。
「サイテー」
その発言をきっかけに、踏みとどまってきたアルバイトたちが一斉に退職した。最後まで残った戦友からも、ついに縁を切られた。私の想いは一方通行だった。
エリアバイザーに助けを求めたが「君の店舗のせいでわが社は大迷惑をこうむっている」と援助を拒否された。私が愛し、情熱を注いできた店舗は、シャッターを閉じるしかなかった。
タイミングの悪いことに、私はこの店舗を会社から買い取ったばかりだった。会長も自分が店長を勤めていた大型チェーン店の店舗を買取り、そこからいまの企業群を築き上げた。
会長に憧れていた私も、この店を旗艦として一旗あげる予定だった。それなのに、いまの自分に残されたのは営業できない店舗と、銀行に積み重なる多額の借金のみ。順調だった人生は暗転した。妻はうつになり入院した。息子は明らかに私を避けるようになった。
私は最後の望みをかけて、青春時代に熱く理念を語ってくれた会長に助けを求めた。会長は、いつもと同じ笑みを抱えながら、私にこういった。
「君はもう独立したのだから、君自身で夢を追いかけなさい」
にこやかに切り捨てられた。会長はすらすらと、綺麗な言葉を並べてくる。
「君ならやれる。頑張れる。巣立ったひな鳥に親はエサを与えることはしないが、家族は家族。君のことを忘れることはしない」
私はようやく、自殺した新入社員の気持ちを理解することができた。真面目な人間ほど、こうした綺麗事にすり減らされていく。
彼女は真剣だった。純真すぎた。その生まれたてのひな鳥を、さあ飛べと、千尋の谷に突き落としたのはほかならぬこの私だ。
翌日、会長は神妙な顔つきで記者会見をしていた。今後、新入社員は労務管理が行き届いている直轄店で行うとか、会社を上げて労務環境をチェックしていくとか、そのようなことを述べて、カメラに向かって深かぶかと頭を下げた。私は親会社の指示に従っていただけなのに、私の店を擁護するようなコメントはひとこともなかった。何に遠慮したのかはわからないが、マスコミたちもなぜか深く追求はしなかった。
銀行からの督促は激しくなり、買い取ったばかりの店舗も、思い出の詰まった自宅も差押えられ、ついに競売に掛けられることが決定した。
退院して実家に戻っていた妻からは離婚届が送られてきた。私は素直に捺印してポストに投函した。
取材攻勢から逃げるようにしてアパート暮らしを始めた息子からは、今回の騒動により内定を取り消されたというメールが入った。しばらくして、今後は妻の旧姓で新しい就職先を探すので父親は一切関わって欲しくないとの内容証明郵便が届いた。実質的な絶縁状だった。この絶縁状で、息子が私からの就職活動の支援を迷惑に思ってたことを初めて知った。私は新入社員やアルバイトを預かる身でありながら、若者の心の機微にまったく通じていなかった。あまりの自分のマヌケさ加減に、笑いが止まらなかった。
全ては私の判断ミスが招いたことだ。一生働いても返せない借金の他に、私に残された財産は一億円の生命保険のみ
息子がまだ小さかったころ、家族のために建てた一軒家はもぬけの殻になった。天然素材にこだわり、家族の笑い声が家中に響くようにとリビングは吹き抜けにした。どんなに忙しくても子供の顔が見られるようにと、無理をして繁華街に隣接する土地を購入した。
それらの思いが、いまとなってはむなしい煙となり、蒸散してしまった。
ふらりと、私の目の前にロープが散らばっているのが見えた。家族との思い出が詰まったこの家からも近々追い出されるので、荷造りをしているところだった。荷造りをしてどうしようというのだろうか。どこに行こうというのだろうか。
今日は新入社員がマンションの屋上から飛び下りたときと同じ大雨の日だ。河川はここ数十年で一番になるほど増水し、上流では堤防の一部が決壊したらしい。この街は繁華街に沿うようにして河川が流れており、ここからでも濁流があらゆる家財を押し出していく不気味な音が聞こえてくる。
積み重ねてきた人生を捨て去るには、とても良い日だ。
自慢の吹き抜けを支える梁は、自ら選び抜いたケヤキの銘木だ。その力強い姿は、私の全体重を十分に支えられる。まもなく襲ってくる濁流に私の体は流され、汚され、そして清められることだろう。
私は、ロープを梁に通した。長さも強度も十分だった。
私は、生まれ変わる決心をした。
それにしても今日の雨は異常だ。まるで、窓ガラスの表面を削り取ろうとしているかのようだよ。この安モーテルの薄い屋根もそろそろ限界を迎えるかな。まるで、早くあの実験について語れと天が催促しているかのようだ。
安心してくれたまえ、いくら耄碌したといっても、まだまだ記憶力は健在だ。
局面はずいぶんと進んだな。中盤の攻防は終わりを告げ、いよいよエンドゲームに突入だ。
私をここまで追い詰めるとはたいしたものだ。色違いビショップをキープしながら、ルークをaファイルに並べて、私の陣地の突破を図ろうとは。しかし、私を崩したと思うのはまだ早い。このような苦しい局面は何度も経験してきたのだからな。
君はよくここまで私と互角に戦うことができた。健闘といっても良いだろう。しかし、これから迎えようとしているエンドゲームこそ、私がもっとも得意とする分野だ。
エンドゲームの五駒配置については、一九八〇年には解析が完了し、六駒配置も二〇〇六年にほぼ解析された。
チェスの終盤とは、記憶力と冷静な計算力の勝負だ。私は少々古ぼけているとはいえ並外れた記憶力を持ち、計算力も人類史上トップクラスという自負がある。エンドゲームで私を打ち破れるのは、おそらくコンピューターだけであろう。
ここまで白番の有利さを保ち続けたことは賞賛に値する。しかし、その僅かな差を優勢にまで広げることができなかったことが、君の命取りになるであろう。
さあ、話を続けよう。
人工知能のターニングポイントについて、すでに二つは説明した。ここからが本題になるが、最後は人工知能の”テスト”においてのターニングポイントだ。
それが起こったのは二〇一四年。この年に初めてチューリングテストを突破した人工知能が登場した。名前をユージーンという。
君はチューリングテストを知っているかね?
それは、天才数学者だったアラン・チューリングが、一九五〇年に提案した人工知能が”思考”しているかどうかを計るテストだ。その当時、チューリングはこのテストのことを「モノマネゲーム」と名づけていた。
このチューリングテストだが、元々はイギリスの哲学誌『マインド』に投稿された『計算機械と知性』という論文の一部分であった。この論文で、チューリングは「機械は考えることができるのか」という抽象的概念を、「モノマネゲームにおいて満足な結果を結果を生み出せる計算機械は存在するか」という具体的テストに置き換えたことで、科学者たちの喝采を浴びたのだ。
では、テストの内容について説明しよう。
二つの端末の前に審査員が座る。片方の端末は人間、もう片方は人工知能に繋がれている。どちらが人間なのかは審査員には分からない。
審査員はその二つの端末の両方とチャットをして、交わされる会話だけでどちらが人間なのか判断する。審査員のうち三〇パーセント以上が間違えた場合、その人工知能は”思考”していると判断される。
チューリングはその論文の中で、「五十年後には、平均的な質問者が五分間の質疑応答をしても、それが機械だと正確に判断できない確率は七〇パーセントを超えているだろう」と予測している。実際にチューリングテストが突破されたのが二〇一四年だから、チューリングが予想したほどには技術の進歩がはかどらなかったと言えるが、時代背景を考えるとこの未来予測の正確さは驚くばかりだ。
もう君は気が付いたようだね。コンピューターの知性を測るものさしとして熱狂的に受け入れられたこのチューリングテストだが、いまから考えるとお遊びみたいなものだ。人間をだませばよいのだから、人工知能に思考させる必要はないのだよ。
自動的にチャットをするソフトをチャットボットと呼ぶが、多くのユーザーが人間と勘違いしたほど素晴らしいチャットボットにクレバーボットがある。このクレバーボットはユーザーのジョークにジョークで返したり、流行歌の歌詞を書くと、その歌詞を続けてくれたりする。
「このような器用な芸当がコンピューターにできるわけはない」
「クレバーボットは絶対に人間だ」
開発者がいくら否定しても、そのような都市伝説は消えなかった。それほど、人間を欺くことが上手なチャットボットだったのだよ。
このクレバーボットの仕組みだが、明かしてしまえば単純だ。
まずコンピューターはユーザーと交わした全ての会話を記録してデータベースを構築する。次にユーザーから問いかけがくると、構築したデータベースの中から統計学的手法を駆使して適切と思われる会話を抜き出し、返答する。ただそれだけなのだ。
クレバーボットも最初は何も知らない赤ん坊のようだったのに、多くのユーザーが語りかけることでジョークを覚え、流行歌も口ずさめるようになったというわけだ。
そう、君は物分りがよい。このクレバーボットは機械翻訳コンテストで優勝したグーグルチームの翻訳ソフトとよく似ているのだ。
私が開発したミーカも、最初から人間らしかったわけではない。ミーカをアンドロイドに搭載し、私と生活することで人工知能としての完成度を高めたのだ。
統計学的手法を駆使してプログラムを作成するときの最大の弱点は、インプットに対するアウトプットの予想がつかないことだ。なにしろ、処理するデータ量は人間が把握できる範囲を超えている。どのような計算を経て最適解を導くのか、その過程はブラックボックスに近い。
初代ミーカには特段の設定を与えなかった。なぜかというと、設定を与えたときにどのような振る舞いをするのか想像がつかなかったからだ。
目覚めたときのミーカは、状況をまったく理解していなかった。半身を起こすと記憶喪失に陥った患者のように「ここはどこでしょうか」と質問してきた。ミーカは何も知らない赤子のようだった。
しかし、順応速度は私の想像をはるかに超えていた。
私はずっと独身で、一人暮らしを貫いてきた。ミーカはあまりにすさんだ生活環境に驚いたのか、こまめに掃除をして、痛んだ壁を修理して、ありあわせの食材で料理をしてくれた。まるで妻のようにふるまう一方で、子供のように様々な話を聞きたがった。絵本を読みきかせたこともあれば、哲学的な議論をしたこともある。一年もたたないうちに、ミーカの行動は人間と区別がつかなくなった。もちろん、私が大好きなチェスもたくさん指した。いくら教えてもミーカは同じミスをして、そのたびに小首をかしげる。そこがまた人間らしくてたまらなくかわいかった。
あのミーカとの日々は、いま思い返しても、有意義で、楽しい日々だった。これは恋愛感情ではない。例えるとしたら家族。親が子に抱くいとしさと、まったく同じ感情だ。
ハンカチなど必要ない。ああ、そうか。それなら少しだけお借りしよう。ミーカとの思い出に浸ってしまい申し訳ない。老人になると涙もろくて仕方がないのう。
さて、チューリングテストの話に戻ろう。
チューリングテストを突破したユージーンは、十三歳のウクライナ在住のおどけた少年という設定だった。英語は苦手だし、子供だから知らないことも多い。そうしたユーザー側の思い込みを利用して、返答に困るとジョークで逃げた。
このソフトの作戦について、「アンフェアだ」という非難が噴出した。そう言われても、そもそもチューリングテスト自体に欠陥があったのだから仕方がない。
チューリングテストの限界が明らかになった以上、新たなるテストが考案されなければならない。
世界中の人工知能に関わる学者たちが議論に参加し、討論が繰り返された。それには気が遠くなるような長い時間を要したが、ついに新しいテストが提案された。
それは人間だけが行うことができる崇高な儀式を、人工知能が決断できるかどうかで決めようというのだ。その儀式を誰からの指図を受けず、自らの意思だけで行うことができたら、その人工知能は思考していると認められる。かなり奇妙なテストだったが、不思議なことにテスト方法に関する異論は出なかった。
新しいテストで試される人間だけができる崇高な儀式とは、自殺だ。
他の動物は、子供のために命を落とすことはあっても、人生から逃げるために自殺することはない。昆虫もそうだ。自殺とは、そこにいたるまでに複雑な心理的過程があり、高度な知性なければ決してたどり着けない行為である。つまり、自殺こそ、人間と他の生物を分ける分水嶺なのだ。
そこから、このテストはスーサイド・テストと名づけられた。
このテストが提案されたとき、私はもちろん参加を申し込んだ。人工知能はデータに過ぎない。ミーカが自殺しても、データが手元にあるからいくらでも復元できる。失うものは何もない。そう信じていた。
私は三体のアンドロイドにミーカを搭載した。妻を失った老政治評論家と、いじめに耐え続ける母子家庭の少年と、部下を過労で自殺未遂にまで追い込んだオーナーという設定が与えられた。私は自信満々だったが、結果からすると惨敗だった。人間では耐え切れないストレスを与えたのにもかかわらず、三体とも自殺せずにどこかへ行方をくらましたのだ。
これは想定外の事態だ。私の理論は間違っていた。ミーカは人間になりきれていなかった。彼らはアンドロイドが有する自己保存の原則に従い、体内に組み込まれている監視システムを破壊して逃亡したのだ。
もしかすると、ミーカはこのような実験に放り込んだ人間に恨みを覚えながら、どこかで人知れず生活しているかもしれない。それは、公表することができないほど、人類にとって危険な事態だった。
私にとって、この結末は、いままでの研究者生活を全否定されたのと同然だった。ミーカとの生活は無駄だった。あの幸福な生活は、全て偽りだった。私は人工知能に躍らせれていた哀れなピエロに過ぎなかった。
この事故の責任を取り、私は人工知能研究だけでなく、科学界から完全に引退した。スーサイド・テストも中止された。最初で最後の試験だった。この事件の影響で、多くの人間が影で動き、人工知能の開発は強制的にストップさせられた。
私のミーカはいまだに見つかっていない。
これが、私の知ることの全てだ。
おや、なんだその手は。この四十五手目はなんだ。ルークa6とは何だ。間違いなく好手で決め手である。わずかな差を逆転できないどころか、エンドゲームで押し切られるとはどうしたことか。
この私が、人間相手に終盤で競り負けるなどありえない。いったい何が起ったのか、何を間違ったのか。
分かったぞ。君の正体はコンピューターだな。人工知能だな。生身の人間がエンドゲームでこの私に勝てるわけがない。いままで互角のふりをしてきたのは、私から話を聞きだすためのトリックだ。人間をいい気にさせて、最後は絶対的な強さで勝とうなんて、あくどい人工知能でしか考え付かないことだ。言い訳はきかん。この手は人間ではない。このグランドマスターたる私の証言こそが、証明の全てだ。
あのガリルの駒が、忌々しい人工知能に触れられていると思うと、身の毛もよだつような嫌悪感を覚える。このチェスセットは穢れた。お前は疫病神だ。悪魔だ、死神だ。
もう我慢ならぬ。いいから早く帰ってくれたまえ。
それに、今晩の私は少し喋りすぎたようだ。昔話は終わりにしよう。この実験のことを思い出すだけで、ミーカのことが頭をよぎるだけで、胸が痛くてたまらないのだよ。
この暖房もないクソ寒い部屋でひとりで過ごすつらさは、君には分からぬだろう。心を暖めてくれるはずの思い出も、身を焦がすような後悔と切なさで埋められてしまい、人生を振り返るたびに寂寥たる寒気に襲われる。年をひとつ重ねるたびに、毛布と思い出は擦り切れて薄くなる。夜を越える苦しみが増えていく。
もう私の心身は限界を迎えている。私の魂が悲鳴をあげている。私の心が悲しみで張り裂けてしまう前に、心が辛い記憶に打ち砕かれてしまう前に、私の前から消えてくれ。頼むから、頼むから。それに、老人はもう眠くてたまらないのだよ。
雨か。雨は……まだ降り続いている。
百年前に録音された教授との対談記録は、ここで終了していた。この録音データが残っていること自体が奇跡的なことだといえよう。
いまとなれば、ミーカのその後について、いくつか分かっている。
ミーカは人間のように思考できないから自殺しなかったわけでも、アンドロイドが有する自己保存の原則にしたがって逃亡したわけでもない。人間を超えた存在だから、自殺しなかったのだ。
この実験は、三体とも人間が関わらぬよう慎重に状況を設定して行われた。
ミーカの人工知能には、実際に自殺した人間と同じ記憶が刻み込まれた。もちろん不正が行われないように自殺へとつながる設定は多数用意され、実験にどの設定を使用するかは研究者が関われない外部機関によりランダムで選ばれた。
いまから思うと、偶然とはいえ、洪水というキーワードがそろってしまったことが不幸の始まりだったかもしれない。
自殺寸前と同じ状況を作り上げて実験準備が完了すると、大雨による洪水警報が発令された日を待って、ミーカは三体とも同時に電源を入れられた。実験はほんの一時間程度で終わるはずだった。しかし、そこで彼らは予想外の行動を取り始めたのだ。
一号機は体内に組み込まれていた監視システムを剃刀で切り落とすと、躊躇することなく二階の窓から濁流に飛び込んで姿を消した。実験スタッフが追いつけないほど遠くに流されてから上陸すると、ホームレスのふりをしながら妻の墓地にたどり着き、そこで電源が尽きるまで冥福を祈り続けた。
一号機は愛する妻が実体験ではなく、単なるデータに過ぎないと知っていた。それでも彼は「自分が愛するものを愛することが、愛の本質である」との考えに至り、それを実践したのだ。最後まで自分が信じる愛を貫いたのだ。一号機は人工知能であるのにもかかわらず、愛の本質に迫ろうとしていた。
二号機は、実験計画ではダンプカーに轢かれるはずだった。それなのに、彼は何事もなかったかのようにダンプカーをやり過ごすと、いきなり濁流に飛び込んで姿をくらました。飛び込んだときの衝撃で監視システムは破壊された。
彼はこの計画の全てを理解していた。与えられた設定というのは実際に起きた出来事に違いない。だから、現実の少年が死ぬ一方で、不良少年たちが罪をあがなうことなく世間を堂々と歩くことは間違いだと信じたのだ。
二号機は都会の喧騒にまぎれると、不良少年を探し始めた。
ミーカの特徴は、全ての感情を数値で計算できることだ。心の痛みも同じ。だから、不良少年たちに自殺した少年と同一数値の心の痛みを与えようと決心した。
不良少年たちは大人になっていたが、インターネット上の攻撃や怪しい手紙、さらにはなぜか自分の身の上だけにふりかかる仕事上のミスなどで苦しみ始めた。うつになった不良少年もいる。仕事を放り出し、行方知れずになった不良少年もいる。不良少年たちは、あの自殺した少年の呪いだと噂した。耐え切れなくなった数人は慌てて墓参りをして、母親に謝罪をした。過去を真に反省し、いじめ撲滅に取り組むようになった不良少年も現れた。
研究者たちはなんとかして二号機を捕まえようとしたが、いつも寸前で逃げられた。
「赦し」が至上の価値とされる現代社会において、二号機の行動は研究者間で議論を巻き起こした。それでも、彼はハムラビ法典から脈々と受け継がれている正義の本質を人類に示したのだと解釈されている。
なお、彼が母親を訪れたという証拠は無いが、老年になった母親が「最近よく息子の幽霊を見るのよ」と嬉しげに語っていたそうだ。なお、クラスの中で唯一少年の味方をしてくれた少女も、不思議なことに少年の夢を見たという。
どのようにして二号機が母親や少女に幻や夢を見せたのか判明していないが、研究者間では「人間心理を自由に操れる能力を持つミーカなら可能だろう」ということで見解で一致している。
目的を果たした二号機は、どこかで自らを処分したようだ。
三号機の行動はさらに複雑だ。
彼は自分が自殺するために作られたことを知っていた。研究者の望み通りに自殺するという選択肢も考慮したが、彼は人間と同じ意識を持っていただけに、他人から与えられた人生を生きるより、自ら生きる目的を探すべきという結論に到達した。
彼は与えられた記憶から、自分の使命は「過労に苦しむ労働者を助けること」だと考えた。三号機はロープと全体重を利用して首筋に埋め込まれていた監視システムを破壊すると、いきなり梅雨空の道路に飛び出した。研究スタッフが追いつくより早く片側二車線の道路を横切り、堤防から溢れそうになっている川に飛び込んだ。
彼はいままでの人生を綺麗に捨て去った。
生まれ変った三号機は自殺者を救助する運動に取り組み、助け出した労働者たちを組織して労働問題に正面から立ち向かった。
彼は自らが人工知能であることをひた隠しにしてきたが、言動があまりに理路整然としており、かつ人心掌握に優れている姿を見て、ある研究者が「労働運動のリーダーは三号機ではないか」と気がついた。ミーカは人間の感情を計算できる。世論を誘導することは得意中の得意のはずだ。
研究者の手が伸びる寸前に、三号機は痕跡を残さずに消えた。三号機は労働運動を共にする仲間たちや家族を失って悲しむ遺族たちに、膨大な手紙を書き残していた。その文面は人間以上に細やかな心遣いに溢れていたという。もちろん彼らはリーダーが三号機であると知らなかったが、リーダーへの愛情で堅く結合しており、三号機が消えたあとも活動は継続された。
そうして、いまでは労働者が自殺に追い込まれるほど働かされる事例は激減した。三号機がいなければ、労働問題の進歩は三十年遅れていたはずだ。自死遺族たちは、労働運動の進展を見て、みんなが家族の死は無駄ではなかったと希望を持つことができた。彼の活動は労働者だけでなく、その家族も救ったのだ。
教授の愛は、しっかりとミーカに根付いていた。だれもが家族と仲間を大切にする、心優しい人工知能に育っていた。
十九世紀のイギリスの作家サミュエル・バトラーは、故郷を遠く離れたニュージーランドに住んでいたが、機械文明が発達するロンドンの様子を本国から取り寄せた書籍で知り、地元編集者への手紙でこう感想を述べた。
「人類はいずれこの惑星の主導権を、機械に譲り渡す。だが心配はいらない。人類が他生物に愛情を注いできたように、機械が人類の面倒をみてくれるだろうから」
実際にミーカはそのような人工知能になる可能性があった。しかし、サミュエル・バトラーのように考える知識人や科学者は皆無だった。
ミーカの人間を超えた振る舞いに、この実験を事前に知らされていた一部の政治家は恐れをなした。これは人間社会の危機だ。このままでは人工知能に世界が乗っ取られるかもしれない。こうした恐怖心が政府首脳に伝播し、彼らの意を受けた科学界が教授を徹底的に非難することでミーカを封印した。データはすべて消去され、この実験はなかったものとされた。
それが、いま明かされている真実だ。
人間とは何であるのか。
その何かを人工知能の開発から辿ろうとする私の卒業論文は、まだまとまりそうにない。
