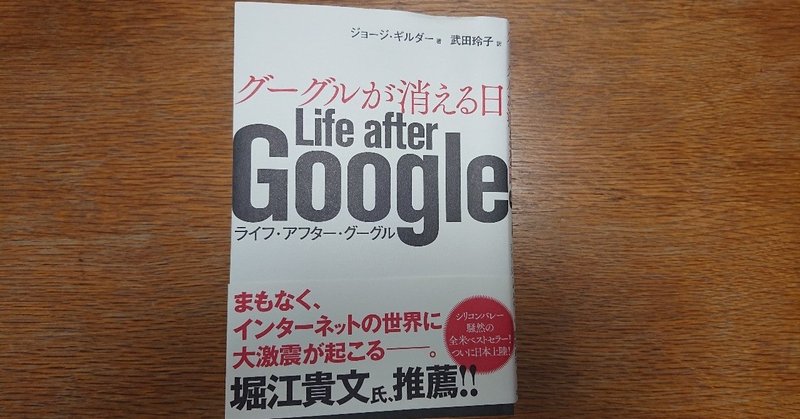
ここ5年くらい、自分がどんどんバカになっていくな、と思ってたのがこの本を読んだら気のせいじゃなかったので、TEC系の企業研究やら久々にみんながLive告知に使いそうなSNSの最新動向とかまで調べた話。|元外コン脱サラベーシストの本棚 #13
さて、長いタイトルですが。今回はこちらです。
一週間ほど前にインスタでネタフリしていましたが。
この本、めちゃくちゃ難しいです。。Amazonでは「翻訳が読みづらい」とかレビューが書かれていますが、きっと違くて、結構な予備知識がないとなんのことかよくわからない話が多いと思います。
一応解読の為に私もワンクッション挟んだくらい。
難しいです。。元IT企業勤務で上級WEB解析士だった私でも何言ってるかさっぱりな部分も多々あります。ただ、内容的には先進的なTEC系の話やAI、ブロックチェーンに興味がある方にはおすすめです。この本を書いたギルダーさんは経済学者なのですが、「未来学者」という肩書も持っています。
本書では
「セキュリティーの脆弱性」
「人を集めて広告を見せるビジネスモデル」
「無料へのこだわり」
「顧客データの縦割り」
「人工知能のビジョン」
がGoogleの次世代の世界への進歩を阻むとしています。
本書の中ではセキュリティーの問題ががつがつたたかれているけど、私としては無料のサービスを広告を見せることで成り立っている(Googleは検索広告(今もリスティング広告っていうのかしら))サービスに限界があるというのはすごくうなずけることでした。Googleはエンドユーザーからは確かに、ほとんどお金を得てないんだよね。
だんだんみんな、お金を出しても有益なものを見たいと思っているし、
サブスクリプション型のサービスも利用されているし、私たちの手の中の画面の中のシェアを奪い合う競争はさらに白熱していくんじゃないかな。
今後の世界はブロックチェーンのテクノロジーを利用したもっとセーフティーなネットワークで回っていくと提唱されているけど、AIと5Gに関してはもうちょっと掘り下げてほしかったな。
とはいえ、正直な話、本当に内容も難しく、修士課程修了後私の文章読解力も落ちに落ちまくってるので、この本をまだきちんとは理解できていないのでもうちょっとしたらもう一回読みたいと思います。やっぱり読みやすい本とかネット記事だけではなくてたまにはちゃんとした本も読まないとダメですね。わかったふりになるだけではなく、頭が鈍ります。
で、ちなみに大きなくくりでいうとGoogleの広告収入の中にはYouTubeの動画広告もあります。YouTubeは2006年からGoogle傘下。他にもintagramはFacebookの傘下、TwitterとLineは大きなサービスとしては独立系ですね。
(一応 https://ja.wikipedia.org/ 等で確認しました。)
今回、我々もよく告知等に使っている各SNSの年代別の利用者数も気になったので調べてみました。

縦軸は利用人数(千人単位)です。こちらのサイトをもとに簡易的に作成しています。
元サイトでは各メディアごとになっていたので、比較できる形にしました。
こうしてみてみてみると"Facebook離れ"と言われつつ、JAZZファンの中のボリュームゾーン、40代、50代とかだとやっぱりFacebookが強いですね。ただ、アクティブユーザーがどのくらいかとか利用時間なんかがわからないから単純には何とも言えないですね。あと、検索シェアもまた調べてみたいところです。一時期は「今の若い子は"ググる"ではなく"タグる"」と言われていましたがどうなんだろう。
さて、ここから再脱線。この本の中で情報処理に使われるエネルギー問題についても触れられています。(エコの観点ではないけど)おりしも、めちゃくちゃ暑い昨今、、省エネで温暖化を止めたいと人が思うのは1年でこの暑い夏がピークですよね。。
ネットワークの中を飛び交うデータを処理するデータセンターで使われてている電力の量は日本全体で1-2%くらいですが、東京では1割を超えるとのことです。ちゃんとしたデータソースがないから微妙ですが、PCとスマホをみんなが一日2時間ずつくらいオフにしたらヒートアイランド現象はちょっとはよくなるかもしれませんね。
ではではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
