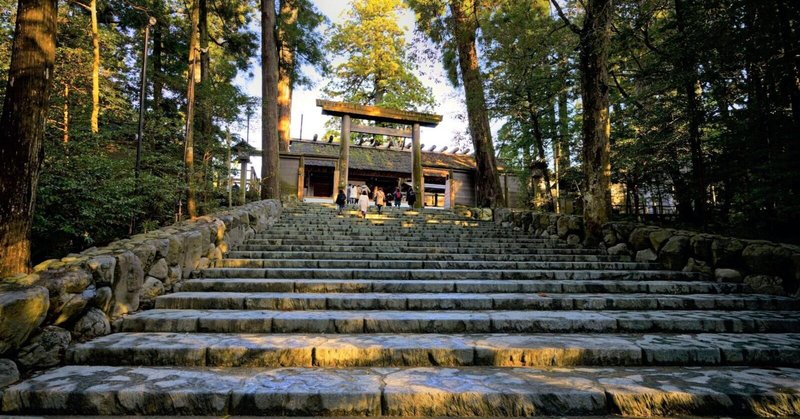
3.伊勢大神とアマテラス
伊勢神宮や天照大神に関する様々な論考にあたっていると、記紀に登場する「伊勢大神」が天照大神であることを前提とする論を見受けますが、果たしてそうなのでしょうか。もし同一神であるなら、伊勢大神と天照大神というふたつの名称を用いる必要があるでしょうか。直木孝次郎氏は地方神昇格説に基づいて、伊勢大神は皇祖神たる天照大神が国家神、至高神としての地位を確立する以前の、まだ地方神としての性格が残っていた頃の名称だとします。筑紫申真氏も神格三転説にもとづいて、天照大神へと神格が変化して皇大神宮(内宮)が成立する前の状態として地方神という表現を用いています。いずれも伊勢大神が天照大神になった、つまり両者は同一神であるという立場です。
『日本書紀』には次の通り、伊勢大神に関する記述が6カ所に見られます。
①雄略元年「稚足姫皇女、更名𣑥幡娘姫皇女、是皇女侍伊勢大神祠」
(雄略天皇の妃、葛城円大臣の娘の韓媛が生んだ稚足姫皇女(別名、栲幡娘姫皇女)は伊勢大神の祠に仕えている。)
②継体元年「息長眞手王女曰麻績娘子、生荳角皇女、荳角此云娑佐礙、是侍伊勢大神祠」
(継体天皇の妃、息長真手王の娘の麻績娘子が生んだ二人目の荳角(ささげ)皇女は伊勢大神の祠に仕えている。)
③欽明2年「蘇我大臣稲目宿禰女曰堅塩媛(中略)其二曰磐隈皇女更名夢皇女、初侍祀於伊勢大神」
(蘇我大臣稲目宿禰の娘の堅塩媛が生んだ磐隈皇女(別名、夢皇女) は最初は伊勢大神に仕えて祀っていました。)
④皇極4年(645年)「遙見有物而聴猨吟(中略)時人曰、此是伊勢大神之使也」
(遥かに見えるものがあり、猿のうめく声が聞こえた。時の人は「これは伊勢大神の使いに違いない」と言った。)
⑤持統6年(692年)「遣使者奉幣于四所、伊勢・大倭・住吉・紀伊大神、告以新宮」
(使者を派遣して幣帛を4カ所、伊勢・大倭・住吉・紀伊の大神に奉献し、新しい藤原宮の報告をさせた。)
⑥持統6年(692年)「伊勢大神奏天皇曰、免伊勢国今年調役。然応輸其二神郡、赤引糸参拾伍斤、於来年、當折其代」
(伊勢大神は天皇に「伊勢国の今年の調役を免じられましたが、二つの神郡から納める赤引糸三十五斤は来年に減らすことにしたい」と奏上した。)
ここから先は
天照大神の誕生と伊勢神宮の成立
天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
