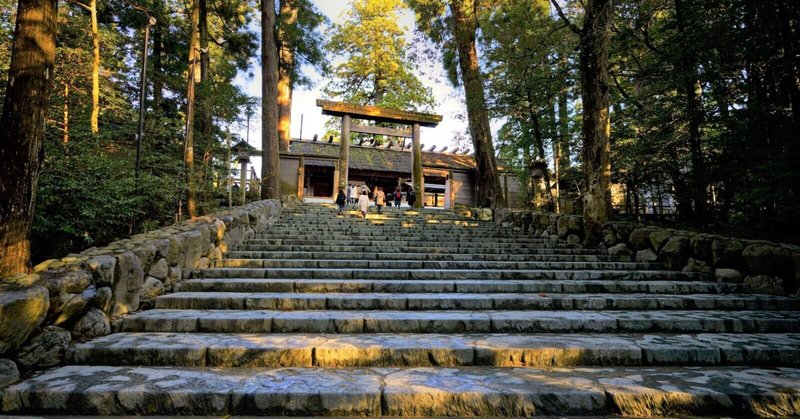
9.度会神域の移転
5世紀以降、伊勢の磯部の首長である度会氏が現在の内宮の荒祭宮あたりで祖先神であり太陽神である天日別命を祀っていたこと、伊勢の地はヤマト王権にとって東国進出の足がかりの地であり、太陽信仰の聖地と認識されていたこと、その結果、太陽神を祀る度会氏を配下におき、御食つ国として伊勢を重要な支配地域としたこと、その伊勢の太陽神を伊勢大神と称して大和で祀り、6世紀後半には日祀部を置いて祭祀を強化したこと、などを順に確認してきました。そろそろこのあたりで伊勢神宮(ヤマト王権によって皇祖神が祀られる場所としての伊勢神宮)の成立がいつ頃だったかということに迫っていこうと思います。
先に見たように、日祀部設置の翌年に斎王となった菟道皇女は伊勢に派遣されず大和で伊勢大神を祀っていたことから、このとき伊勢には内宮ができていなかったと考えられます。同様に次の斎王である酢香手姫皇女も『日本書紀』によれば用明天皇の即位から崇峻・推古の三代にわたって37年間もの長期にわたって斎王を務めたとありますが、彼女も伊勢に派遣されずに大和で伊勢大神を祀っていたことから、斎王を退く推古30年(622年)の時点で未だ内宮は成立していなかったと言えるでしょう。
ここから先は
2,977字
/
2画像
天照大神の誕生と伊勢神宮の成立
300円
天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
