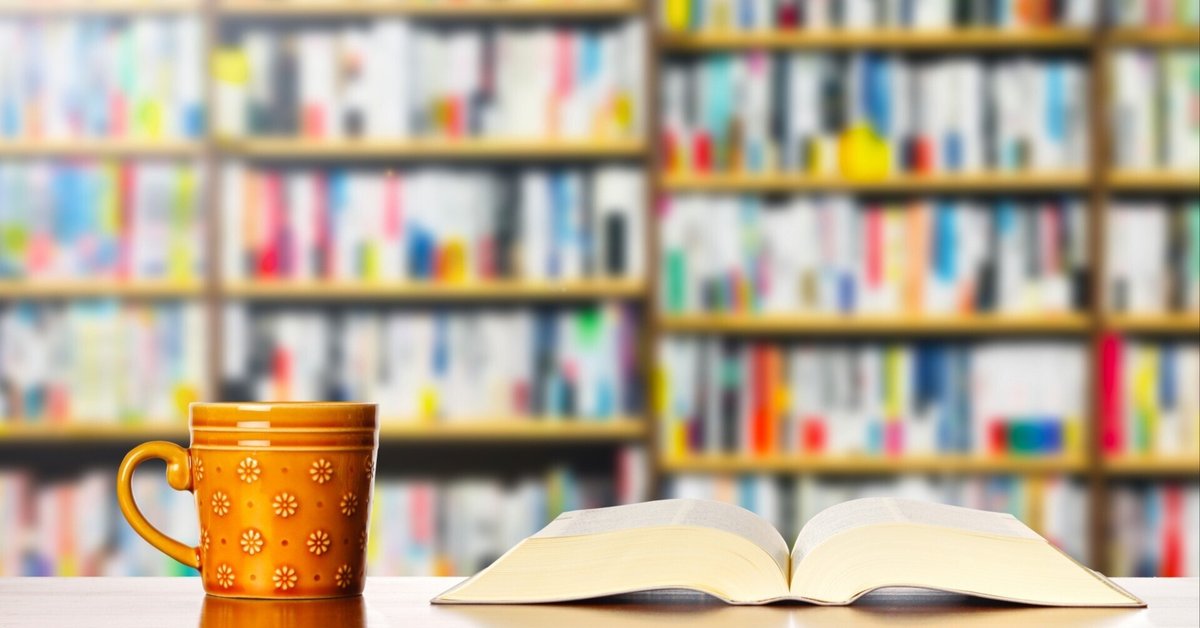
とある本紹介式読書会の記録~2023年9月編~
◆はじめに
9月3日(日)の朝、学生時代からの知り合いとやっているZoomを使った読書会に参加した。元々は東京・山手線周辺にあるカフェの貸会議室などを使って数ヶ月に1回行われていた会であるが、3年ほど前にオンラインに切り替わり、それ以降は月に1回のペースで開催されている。就職を機に関西に帰郷した僕は、オンライン化したタイミングで復帰し、以来毎回のように顔を出している。
この読書会は回によって、メンバーがそれぞれ本を紹介する方式になったり、事前に課題本を読んでおき感想などを語り合う方式になったりする。9月3日の読書会は本紹介式であった。一般にこのタイプの読書会では「ひとり1冊」のような制限が設けられているが、この会では冊数制限はなく、各メンバーのおおよその持ち時間以内であれば何冊紹介してもよいというスタイルが採られている。この日も1人だけだが、複数の本を紹介したメンバーがいた。
当日の参加者は4人であり、紹介された本は全部で5冊であった。それでは、出てきた順に本を見ていくことにしよう。
◆1.『スタジオジブリ物語』(鈴木敏夫)
経済小説やラノベの紹介が多いメンバー・urinokoさんからの紹介本。スタジオジブリのプロデューサーである鈴木敏夫さんが責任編集を務め、ジブリの足跡をまとめた、社史のような本である。500ページを超える分厚い本だが、1章が2、30ページ程度の長さであり、少しずつ読んでいけばそれほど負担を感じずに読めるという話だった。
文中では、各作品発表当時の雑誌記事の引用や、作品を生み出す過程で行われたやり取りなども紹介されており、監督たちが考えてきたことや、会社としての方針の変遷などを知ることができる。この本を読んで一番良いと感じた点はそこだと、urinokoさんは話していた。僕も小さい頃からジブリ作品を観て育ってきた身として、そういう話には触れてみたいと思った。
また、各作品のスタッフ情報も本文に登場するようだ。urinokoさんが読み飛ばしたと言うので、僕は思わず「それが面白いのに!」と抗議してしまった。そんなやり取りをしていたら、メンバーの一人が「実は知り合いの知り合いがジブリ映画のスタッフで」と口にした。僕は「エエエエエッ!!!」と絶叫し、他のメンバーは若干引いていた。本の内容よりも僕の挙動不審具合の方が印象に残ったのではないかと、今更ながら心配である。
◆2.『凍りのくじら』(辻村深月)
ワタクシ・ひじきの紹介本。近年名前を見かける機会の多い作家の一人・辻村深月さんの小説で、辻村さんの『ドラえもん』愛が詰まっていると言われる作品である。
主人公は高校2年生の芹沢理帆子。彼女の父は失踪しており、母親は入院中で余命幾ばくもない。ひとりで暮らしながら、高校にも、夜の遊び友達との集まりにも、母の見舞いにも、別れた元カレからの誘いにも顔を出しているが、そのどれにも十分な現実感をもって溶け込めないでいる。父の影響で『ドラえもん』が大好きな彼女は、藤子・F・不二雄さんが「SF」を「少し不思議」と言った話になぞらえ、周りの人を「少し・フリー」「少し・腐敗」「少し・フラット」と「SF」で特徴づけているが、自身に与えた特徴は、「少し・不在」だった。
そんな理帆子の前に、父のファンだという学生が現れ、写真のモデルになって欲しいと言う。彼とのやり取りが始まる中、彼女の家には不審な荷物が届くようになる——様々な出来事に出会う中で、理帆子は自分の置かれた状況・自分の本当の気持ちをだんだんと理解していくようになる。
理帆子を取り巻く環境や背景の描写、細かく揺れ動く思春期の心の描写など、全編にわたり繊細でしんどい内容の多い小説であるが、目の前の現実に上手く入れず孤独を感じている人間の抱えたものを丁寧に掬い上げている作品だけに、刺さる人は少なくないように思う。そして、ややネタバレになるが、『ドラえもん』が「こんなこといいな、できたらいいな」という夢や希望をもたらす作品だったのと同じように、この作品もまた、理帆子に希望が生まれるエンディングを描くことで、読者を勇気づけるものになっている。
現実が遠かった時期を知る全ての人に、ラストシーンまで読み切って欲しいと思う。
◆3.『ギフテッドの光と影』(阿部朋美・伊藤和行)
読書会の代表を務める竜王さんからの紹介本。最近よく耳にする「ギフテッド」を扱った一冊である。
「ギフテッド」は世界各国で定義が異なり、日本には明確な定義さえないそうだが、一般には、非常に知能が高かったり、何らかの特異な才能があったりする人たちを指す言葉である。そしてその多くは、周りの人たちと関係を築くのが苦手で生きづらさを抱えているという。この本では、様々なギフテッドの姿をインタビューを通じて紹介すると共に、彼らを支援する取り組みや才能教育の歴史にも触れているそうだ。
竜王さんは、ギフテッドと呼ばれる人たちがいて、しかもその数は思っている以上に多いということを伝えたかったようであるが、聞いているメンバーの方は「そりゃあそうだろう」という反応だった。そして、さらに踏み込んで、ギフテッドの受け皿をどのように用意すべきか、彼らの居心地の良さを考えることが周りの人たちとの分断を生みかねないリスクをどう考えればよいかといったところまで話していた。
後者の問題は僕も重要だと思っている。ギフテッドに限らず、個々人が互いに生きづらさを訴え、居心地のよい環境を目指す動きが、属性の近い人たちだけの集団と、それぞれの集団の分断という結果を生みかねないという問題は、これからよく考える必要があると思う。
一方で、ギフテッドの話は難しいと感じる場面もあった。なにぶん才能に恵まれた人たちのことを話しているので、妬みや羨望がイヤでも混じってしまうのである。このようなまなざしを向けられることも、ギフテッドの生きづらさのひとつなのかもしれないが、この難点とはどう向き合えばよいものか。——数々の論点を残す本紹介であった。
◆4.『女の人指し指』(向田邦子)
読書会きっての多読派・van_kさんからの紹介本。数々のヒットドラマを生み、エッセイの名手としても知られた向田邦子さんのエッセイである。この本に収められているのは中でも、彼女の最晩年の文章である。
向田さんは、ホームドラマは誰にでも書けるもので、そこに自分なりのエッセンスを出すことでオリジナリティのある作品が生まれると語っていたそうだ。しかし、van_kさんによると、向田さん自身はホームドラマで描かれるような生活からは縁遠い人だったようである。大人になって以来単身生活を続けていた彼女は、家族一緒の生活とそこで生まれるドラマを外野から見ている人だった。その特殊な立ち位置こそ、彼女が名作ドラマを生み出せた理由だったのではないか、という話であった。
また、向田さんの食に対するこだわりの強さも、エッセイから垣間見えたという。コレコレの食べ物は、どのような天候の日にどういうシチュエーションで、どの店のものを取り寄せて食べるかまでこだわり、1つでも要素が欠けたら「いらない」とさえ言ったそうだから凄まじいものである。だが、そのようなこだわりの強さもまた、良い作品を生み出すうえでは重要だったのではないかと、van_kさんは言う。
改めて振り返ってみると、向田さんが名作を生み出せた理由を分析し紹介することに終始した本紹介であった。その分析から、van_kさんは何を汲み取ろうとしていたのだろうか。
◆5.『体はゆく』(伊藤亜紗)
続いてもvan_kさんからの紹介本。様々な角度から人の身体の不思議に迫っている研究者・伊藤亜紗さんの本である。
内容のポイントは、頭では意識していなくても体はできてしまうことがたくさんあるということだいう。例えば自転車の乗り方。ペダルに足をかけて漕ぎ出して、地面から足を離して、ハンドルを動かして、バランスを取って——言葉にすると長くなるこれだけのことを、体は無意識のうちにやっている。しかも、バランスを取るという曖昧で繊細な部分まで、自然に調節している。これまで科学がやってきた現象の説明と、実際の行動とは違っているのではないか。そのことに、van_kさんは衝撃を受けたようだった。
本書の内容で特に面白かったのは、桑田真澄さんのピッチングに関するものだという。桑田さんに「同じフォームで投げてください」とお願いし30球投げてもらったところ、腕の振りはボールを投げ出す位置は最大で20センチ近く離れていたにもかかわらず、ボールの到着地点の差はそれほど大きくなかった。このことは、現実に起きた動作がどれだけ違ったとしても、目指す場所にボールを届けるために体はいつの間にか調節を図っている、ということを示している。そこには、パターン化されたフォームの説明からは零れ落ちてしまう個々の事象の具体性が、そしてそれを可能にする体の驚異が表れている。
話を聞けば聞くほど、常識的なものの見方が破られた時の興奮が伝わって来て、俄然読みたくなる、そんな本紹介だった。
◆おわりに
9月3日の読書会で紹介された5冊の本について書いてきました。小説が1冊、エッセイが1冊、あとは広く括ればノンフィクション(?)というラインナップでした。気になる本やトピックが1つでもあれば幸いです。
次の読書会は10月の半ばになりそうです。今度も本紹介式でいくとのことなので、どんな本が出てくるのか楽しみにしたいと思います。その前に、自分が紹介する本のことも考えなければいけませんが。
何はともあれ、今回はこれにて。
(第194回 9月7日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
