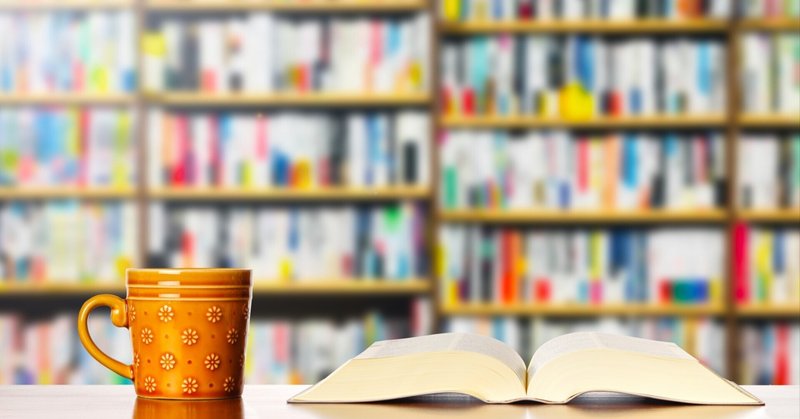
とある本紹介式読書会の記録~2023年6月編~
◆はじめに
6月18日(日)の朝、学生時代からの知り合いと毎月行っているオンライン読書会に参加した。この読書会は元々、東京の山手線沿線にあるカフェの貸会議室などを利用して対面式で行われていたが、3年ほど前にZoomでの開催に切り替えられた。就職と同時に関西に帰郷した僕は、オンライン化を機に再び顔を出すようになり、以来毎回のように参加している。
この読書会は月によって内容が変わり、メンバーが互いに本を紹介し合う月もあれば、事前に同じ本を読んでおき感想や考察を話し合う月もある。今回は前者の本紹介式読書会であった。
レギュラーメンバー6人のうち2人が用事で来られず、さらに1人が疲れの影響で遅れて参加したため、途中まで3人ぽっきりという小ぢんまりとした会であった。それでも6人でやる時と同じだけ時間を取っていたので、紹介する本の冊数も1人当たりの持ち時間も気にすることなく、話し合いはのんびりと進んでいった。
それでは、当日紹介された本を順番に見ていくことにしよう。なお、紹介された本は全部で5冊であった。
◆1.『共感が未来をつくる』(野中郁次郎)
読書会の代表を務める竜王さんからの紹介本。「共感」をキーワードに、企業・行政・市民が一体となってソーシャル・イノベーションを実現していく事例を紹介したビジネス書である。竜王さんは少し前から「共感」が自分の中でキーワードになっているという話しており、この本についても、経済合理性ばかり見るのではなく、やりたいことと共感の掛け算で物事を動かすことを説いている点を良いと思ったそうだ。
「共感」というのは案外多義的で難しい言葉であるが、この本ではおそらく2つの意味で「共感」が使われているのだろう。1つは、問題や困難に直面している人に寄り添い、「確かにそれは困ったことだ」と感じるという意味。この「共感」は、新たな行動を始めるための原動力になるものである。もう1つは、そうやって動き始めたプロジェクトに対して「それいいね」と意義を見出し、共に創り上げたり応援したりするという意味。こちらの「共感」は、新たな動きを加速させる力になるものである。
僕は「共感」という言葉を重く見がちで、「その程度の理解で『わかる』と言わない」とすぐ言いたくなってしまうところがあるのだが、最近漸く、「いいね」というざっくりした共感が物事を進める上では大切だとも思うようになってきた。この本を読んだら、「うーむ」と唸りながら、「でもイイコト書いてあるなあ」と思うのだろう。
◆2.『狼と香辛料』(支倉凍砂)
読書会のアウトプット・リーダーこと、しゅろさんからの紹介本。中世のヨーロッパを舞台にした行商人が主人公のライトノベルである。
しゅろさんがこの本を紹介したのは、最近自身が経済ネタに凝っているからとのこと。確かに、最近のしゅろさんは株の値動きや物価を気にしたり、経済関連のニュースを読み漁ったりしていることが、ブログからも窺えていた。『狼と香辛料』は、上述の通り商人が主人公の物語なので、モノの価値の地域差や貨幣の話など、経済に関連するネタが豊富にちりばめられているようである。単にストーリーを追うだけでも面白いが、経済のことがわかってから読むといっそう面白くなるにちがいない、とのことだった。
もっとも、しゅろさん自身が後日書いていた通り、経済的な側面に特化した本紹介だったため、当日の紹介からはどんな物語なのかまで窺い知ることはできなかった。ストーリー面でも評価されている作品らしく、アニメ化もされているとのことなので、機会があれば触れてみたいと思う。
◆3.『社会の変え方』(泉房穂)
ワタクシ・ひじきの紹介本。前明石市長の泉房穂さんが自らの歩みを振り返って書いた本であり、明石市長になるまでのことから、市長になってから行った施策のこと、市政を進めるにあたって大切にしてきたことなどがまとめられている。
暴言問題などでしばしば物議を醸してきた泉さんであるが、この本を読むと、やってきたことは本当に凄いと感じる。〈市民の方を向き、市民のために政治・行政を動かす〉〈弱い立場に置かれた人の声を聴き、誰一人取り残さない政治をする〉というスタンスを貫き、市民の負担を増やすことなく、予算の配分を変え、人を集め育てることで、福祉施策を充実させる。反対派も多い中で、信念を貫き、結果的に経済にも好影響を及ぼすなど当初の懸念を払拭していったという話には、驚くほかない。
この本を手に取ったのは、世の中のこと、とりわけ政治や経済について何も分かっていないと感じ、それらに関する本を読もうと思ったことがきっかけだった。もちろん、この本の中には、泉さんが手を打つまで放置されてきた数々の社会問題や行政の実態が載っており、それらを1つ1つ拾い上げてじっくり考える読み方も大切だろうと思う。ただ、僕はそれ以上に、弱い立場にある人を見捨てることなく、社会を良くするために本気で取り組む人がいるということに、強い感銘を受けた。
なお、読書会の中では言わなかったことであるが、僕はこの本をある種のビジネス本としても読んでいたと思う。自分はどこを向いて、誰のために仕事をするべきなのか。そんなことを考えるきっかけになったのである。
◆4.『世界をたべよう! 旅ごはん』(杉浦さやか)
当日お疲れ気味だったurinokoさんからの紹介本。世界じゅうを旅した著者による、ご飯の話が中心の旅行エッセイである。イラストが豊富で読みやすいうえ、読んでいると結構満たされた気分になるようだ。
urinokoさんは仕事が忙しかった時期にこの本を手に取ったという。実際に海外旅行に出掛けることは叶わないけれど、旅行気分を味わうことができるので、旅に出たいけれど出られない人にはオススメとのことであった。
◆5.『食欲人』(デイヴィット・ローベンハイマーほか)
続いても、urinokoさんからの紹介本。人間の食欲の仕組みを解説した、最近話題の本である。食事について勉強したことがなかったので、本屋で見かけて手に取ったという。科学的な根拠に基づいて書かれているので読み応えがあるうえ、邦訳がスッキリしているので文章として読みやすいとのことであった。
食や健康に関心のあるメンバーは少なくなかったので、紹介後には「気になる」という声が次々に上がった。かくいう僕も、先日健康診断の結果が返って来て、一部やや悪い数値があったので、食については一度ちゃんと勉強した方がいいかもしれない。
◆おわりに
以上、6月18日朝の読書会で紹介された本を見てきました。小説は1冊のみで、あとはビジネス本・政治の本・旅行エッセイ・科学の本が並びました。元々この読書会は小説の紹介数が少なめなのですが、ここまで少ない回は珍しかったように思います。この前日に参加した彩ふ読書会では、小説に関連する本の割合が高かったことを思うと、対照的という感じがします。逆に言えば、それぞれの読書会のカラーを感じる機会になりました。
今ここで書いた通り、僕はこの時2日連続で読書会に参加していました。しかもどちらも本紹介式。元々そんなに冊数を重ねる方ではなく、紹介できる本のストックも限られている中で、ネタかぶりを避けながら本の話をするため、この日は特に何を紹介するか悩みました。結果的に、今まであまり紹介したことのないジャンルの本を出すことになりました。そういう実験は、勝手知ったるメンバー相手の読書会だったからこそできたことなのかなと、今になって思いました。
さて、こちらの読書会は来月もあります。次回はテーマ付きの本紹介式読書会。テーマは「夏に関する本」です。ヤケクソ気味に出した季節ネタがそのまま採用されてしまいました。もっとも、夏ならまだ選べるかなという気はしています。果たしてどんな本が紹介されるのか、それは来月のお楽しみということにいたしましょう。
それでは。
(第174回 6月24日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
