
意味と無意味について
今回は、一つのテーマについて複数の作品をもとに考察を行いたいと思います。そのテーマとは、タイトルにある通り「意味と無意味」というものです。抽象的な内容ですが、本稿を読んでくださっている皆さんなら、おそらく一度は似たようなことを考えたことがあるのではないかと思います。
取り上げるテキストは、『アンドロイド基本原則 誰が漱石を蘇らせる権利をもつのか?』(漱石アンドロイド共同プロジェクト、日刊工業新聞社)より「人がアンドロイドとして甦る未来」(谷島貫太)、『美しいをさがす旅にでよう』(田中真知、白水社)。あと本ではありませんが、ボーカロイド曲の「ぼくらはみんな意味不明 feat. 初音ミク」(ピノキオP)の歌詞になります。
教科書の効用
まず、なぜ上記の作品をチョイスしたのか理由を書いておきます。
谷島さんと田中さんのテキストは、三省堂の国語の教科書『精選 現代の国語』(2022年3月発行)を読む中で見つけ、色々と刺激を受けました。最近ちょっとした事情で国語の教科書を読む機会があり、様々な教科書を見比べたところ、三省堂のものが特に面白くて買って全部読んでしまいました。
冒頭に収録されている川上未映子さんの「ぐうぜん、うたがう、読書のススメ」でも述べられていましたが、普段の自分なら手に取らないような内容のテキストに出会わせてくれることが教科書の良いところですね。自分も、小学校〜高校時代は授業をほとんど聞かずに勝手に教科書を読んでいました。国語の教科書については、またいずれ独立した形で色々書きたいと思います。
なお、恐縮ながら、田中さんの本に関しては実際にまだ手に取れていないので、本稿も教科書に掲載されている範囲の内容のみをもとにしたものになります。もし全体を読んで考えが改まったら追記したいと思います。
Nobody Makes Sense
ピノキオPさんは、ボーカロイド曲の投稿を主に活動している大人気クリエイターで、曲を聴いたことがある方も多いかと思います(1年ほど前には「神っぽいな」が特にバズっていましたね)。筆者は、特に2017年に投稿された「ぼくらはみんな意味不明」という曲が個人的な思い入れもあって大好きで(たまたま投稿日に視聴してハマった記憶があります)、歌詞が今回の考察に大きく関わるので取り上げたいと思います。
見出しはその曲名の公式英訳ですが、皆さんはどのように感じられるでしょうか。自分は最初見たとき、日本語のタイトルとはだいぶ異なった印象を受けました。英語はあまり得意ではないのですが、日本語のタイトルを直訳するなら「We are all the meaningless」の方が近いような気がしたからです(英語の感覚からすると不自然なのかもしれませんが)。しかし、色々と考えていくうちに「意味(Sense)」が「(人によって)つくられる(to be made)」という表現に重要な示唆が含まれていること、「meaningless」では失われてしまう内容があることに思い至りました。本稿の考察の中心は、この点に関するものです。
アンドロイドと魔法
では、本題に入っていきましょう。
まず谷島さんのテキストから。谷島さんは現在、二松學舍大学の准教授で、技術哲学やメディア論を専門とされている方のようです。本稿で取り上げるテキストは、少し前に話題になった夏目漱石などの著名人のアンドロイドに関するもので、今後、私たちはアンドロイドとどのように向き合っていくべきかについて論じたものです。
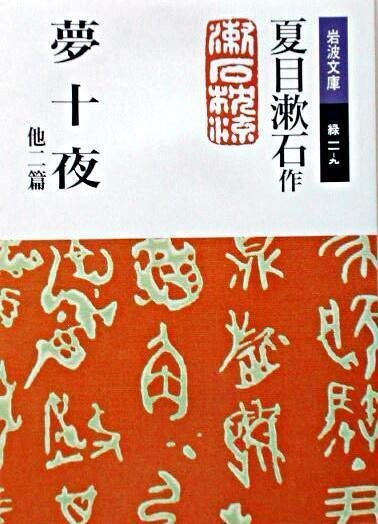
テキストの中で、谷島さんはNHKのテレビ番組「天国からのお客さま」(2018年10月20日放送)を取り上げ、そこに出演(?)した夏目漱石、勝慎太郎、立川談志のアンドロイドとその周辺について考察しています。筆者はこの番組は観ていませんが、アンドロイドに著名な故人の振る舞いを再現させ、それが周囲の人にどのような影響を与えるのかについて扱った番組のようです。そこで谷島さんは、例として勝慎太郎アンドロイドが演劇部の高校生に演技指導をするシーンを挙げ、そこに何か「特別な伝達力」が生じていると述べています。
演技指導の中で語られている内容は、勝が生前に折にふれて語り、また実践していた演技論を再構成したものです。しかしその演技論は、アンドロイドの口から直接語られることによって明らかに特別な伝達力を獲得しているように見えます。(中略)偉人を甦らせるアンドロイドは、すでに亡くなった人々が残していった足跡を、体験可能なできごととして呼び出すというポテンシャルを有しているのです。
筆者は、まだ精巧なアンドロイドをしっかりと見たことはありませんが、谷島さんが述べていることは分かるような気がします。「不気味の谷」という話もありますが、一定の閾値を越えて人に近づいたアンドロイドには、確かにモノ以上の「何か」が宿っているように見えるのではないかと予想されます。この「何か」が宿ることについて、谷島さんは「魔法」や「憑依」といった言葉を用いて表現しています。
『天国からのお客さま』という番組は、アンドロイドが可能とする特別な魔法の効果を私たちにまざまざと見せてくれます。アンドロイドはあくまでもモノであって人ではありません。しかし精巧に作りこまれ、巧みに演出されるとき、アンドロイドには故人が部分的に憑依するという魔法がかかるのです。
ここで注意したいのは、「魔法」をかけている主体とかけられている客体の区別です。谷島さんのテキストはこの点に揺らぎがあり、アンドロイドは私たちに魔法をかける主体でありながら、同時に(何者かによって)魔法をかけられる客体でもあるように述べられています。あるいは谷島さんは、そもそも主体や客体ということに関して厳密な区別を設けておらず、アンドロイドとそれを見ている私たちという「場」それ自体に魔法が生じていると考えているのかもしれません。
また魔法について、谷島さんはその範囲をアンドロイドに限定するようなことも述べています。
そしてその魔法の正体はテクノロジーです。アンドロイド技術の研究と開発が進んでいくにつれて、これからの社会はこの魔法をより自由により精密に制御していけるようになるでしょう。今はまだ、この魔法は例外的で実験的な場面でしか用いられていません。しかしおそらくは時間の問題です。十年後になるか五十年後になるかはわかりませんが、遅かれ早かれ、「アンドロイドとともに生きる世界」ははるかにずっと身近なものになっているでしょう。
上記では魔法について「制御」したり「用いる」という表現が使われていますが、やはり「誰が」それを用いるのかということについては曖昧です。
また加えて、魔法がアンドロイドの占有物であるのか否かという問題もあります。谷島さんは、現段階では魔法は「例外的で実験的な場面」に限定されており、それがより広まるには未来の技術革新を待たなければならないと述べています。たしかに精巧なアンドロイドはまだ普及していないため、「アンドロイドによる魔法」は現在では限られていると言えるでしょう。しかし、アンドロイド以外に魔法を可能にするものは存在しないのでしょうか。未来の科学技術の産物だけでなく、現在や過去の私たちの周囲にもそのようなものは見出せないでしょうか。
人形と意味
人形を例に考えてみましょう。人形とは、書いて字の如く「人」を「形」取ったものです。実際に現実の人にどの程度似ているのかは人形にもよりますが、仮に簡素なデザインの人形であっても、私たちはそれをただのモノとして扱うことはなかなかできないでしょう。アンドロイドほどではないにしても、人形にはただのモノ以上の「意味」が宿っているからです。
その顕著な例として、人形供養というものがあります。人形供養とは、不要になった人形やぬいぐるみを、神社やお寺などで「供養」して燃やす儀式のことです。筆者も一度、明治神宮で行われている「明治神宮人形感謝祭」に行ったことがあります。実際に燃やすところは見ませんでしたが、並んでいる数多の人形からは何らかの「力」や「圧」のようなものを感じました。

供養の仕方は各々の神社やお寺で異なりますが、なかにはお経を読み聞かせてから燃やすということを行っているところもあるそうです。これは人の葬式のプロセスと同等のものであり、人形に人と同様の「意味」を見出しているということを示しています。つまり、モノを人にする魔法は、既に私たちの周囲に存在しており、アンドロイドによって初めて可能になるものではないのです。この点は、谷島さんも以下のように認めています。
ただし日本にはすでに、役割を終えた人形を供養する人形供養という伝統があります。モノである人形を、あたかも命を有する存在であるかのように扱うこの文化は、欧米ではまったく考えられないものであるようです。この点で実は、アンドロイドというモノを超えるモノとどのような関係を作っていくべきかという未踏の問いに踏み込んでいくに際して、日本文化はいくらか優位な点をもっているといえるかもしれません。
もちろん、簡素な人形と精巧なアンドロイドでは、周囲の人に与える影響の大きさや、宿るものの「意味」は多かれ少なかれ異なるでしょう。しかし、そこには決して質的な差異や断絶が存在しているわけではありません。技術的な目新しさから、一見するとアンドロイドは人形とは全く異なるもののように思われるかもしれません。しかし、見た目の近似性や応対といった機能がどれだけ向上したとしても、それはより精巧な人形であるということに過ぎず、従来の人形の領域を逸脱するものではありません。周囲への影響という観点においても、よく知らない人の精巧なアンドロイドよりも、思い出深い簡素な人形の方が大きな効果をもつということもあるでしょう。つまり、モノをモノ以上にする魔法は、私たちの周囲にもごくありふれた形で存在しており、アンドロイドによる魔法は、その魔法の高度なバリエーションの一つに過ぎません。
哲学的ゾンビと独我論
先ほど、魔法は私たちの周囲にありふれていると言いました。モノをモノ以上にする魔法に関連して、ここで一つ有名な概念を取り上げましょう。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、「哲学的ゾンビ」と呼ばれるものです。
哲学的ゾンビとは、主に「心の哲学」という分野で扱われるもので、物質的な特性は通常の人と全く同一ながら、「意識(クオリア)」をもたない存在と定義されています。「バイオハザード」に登場するようなゾンビではなく、あくまで思考実験上の仮想的概念です。
このゾンビは、細胞などの体組織や神経反応、あるいは言葉を用いた応答なども人と全く同じであるため、外から見てそれが人であるのかゾンビであるのかを区別することはできません。しかし、外見上は全く同じであっても、通常の人が備えている意識というものが哲学的ゾンビにはありません。哲学的ゾンビが「ゾンビ」と名づけられている理由はここにあります。そのため、仮に哲学的ゾンビが感動的な映画を観て涙を流していたとしても、それは涙という物質的なモノを外に出しているだけであって、そのゾンビの内部には「感動」というものは存在しません。まるで松ぼっくりのようですね。水に濡れた松ぼっくりは、種子を守るためにカサを閉じますが、そのプロセスは機械的な繊維構造によるもので、そこに感情などは(おそらく)ありません。
さて、このような哲学的ゾンビは、果たして「人」と言えるでしょうか。おそらく、少なくない人が「人ではない」と考えるのではないでしょうか。それこそアンドロイドのように、人には似ているが人とは異なる、ただの機械のようなものであると。
しかし、考えてみてください。物理的に人と区別できない哲学的ゾンビが存在したとして、それを私たちは確かめることができるでしょうか。答えは否です。仮に今後テクノロジーがさらなる進歩を遂げていったとしても、物理的には人と全く同じなのですから、哲学的ゾンビが本当に哲学的ゾンビなのかを確かめる方法は原理的に存在しません。
さらに考えてみましょう。私たちは、周囲の人が本当に「人」であると確かめることができるでしょうか。皆さんの友人や家族、あるいはただ道ですれ違った人が、哲学的ゾンビではなく人であると根拠をもって答えられるでしょうか。これも答えは否です。私たちは、あくまで「人らしい」「人っぽい」としか言うことができません。

そして、この考えをさらに推し進めていくと、哲学上のブラックホールとでも言うべき(筆者が勝手に言っているだけです)大きな問題、いわゆる「独我論」に行きつくことになります。独我論については、またいずれ詳しく取り上げるつもりですが、その内容を簡単に言ってしまえば「世界には私以外存在しない」「世界は私の意識でしかない」というものです。つまり、他人の存在を含めた世界は全て私の意識によるものでしかなく、私の外部には何ものも存在しないということです。この考えに則るならば、存在するのは唯一「私」だけで、他人は私の見ている夢や幻のようなものになります。そうなってくると、ここまで使ってきた「私たち」や「皆さん」という言葉も実質的な意味を失ってしまいますね。
もちろん、あくまでこれは思考実験であって、実際に日常でこのように考えて生活を送っている人はほぼいないでしょう。私たちは自然と「私たち」と言い、他人を哲学的ゾンビではなく「人」として考えて生活しています。
これは当たり前のことのようですが、実はそうではありません。というのも、私たちの目の前にいる他人は、あくまで物質的な「人らしいモノ」に過ぎないのですから、私たちがそのモノを「人」として認識するためには、「人らしいモノ」に「人」という魔法をかける(あるいは「人らしいモノ」に「人」と感じるよう魔法をかけられる)必要があるからです。その意味で、別に人形を持ち出さずとも、私たちの周囲には魔法がありふれているのです。そして、私たちが魔法をかける側であるとすれば、私たちは「魔法使い」ということになります。
意味の生成主体
「魔法使い」である私たちは、モノをただそのままモノとして認識しているのではなく、そこに何かしらの「意味」を付与して世界を見ています。ここでは、それが具体的にどのようなものであるか、田中さんのテキストをもとに認知科学的な側面から考えたいと思います。
それでは、テキストの方を見ていきましょう。田中さんは認識ついて以下のように述べています。
……人間も他の動物も、ありのままの世界や自然を、全体として認識しているわけではない。というよりも、ありのままの世界は、見たくても見ることができないのである。ありのままの世界とは、どこにも切れ目も境界もない連続体である。それは名づけようもなければ、認識しようもないものである。例えば、我々は人体を見て、ここは頭、ここは肩、ここは腕、ここは手首というふうに、それぞれの部位を認識する。それは「このあたりを腕と呼ぼう」「このへんは手首と呼ぼう」という約束ごとに基づいている。このような約束ごとをいっさい外してしまうと、どこまでが人間の体といっていいのかわからなくなる。皮膚は人間の体の境界といえるのだろうか。人間は鼻や皮膚から呼吸をしているが、その空気は体の一部ではないのか。体から発散される熱は体ではないのか。そんなふうに見ていくと、「人体」という概念も、一つの約束ごとだとわかる。こうした約束ごとを全て外してしまうと、なにもかもがつながってしまい認識のしようがない。
私たちは、自分自身や周囲のものをそのまま認識しているのではなく、恣意的に境界を設定して認識しています。原子論的に考えてみても、モノとモノの間に本質的な区別はないのです。例えば、私たちの皮膚に含まれるH₂Oと、その皮膚に触れている空気中に含まれているH₂Oの間には、境界のようなものはありません。ただ、複数のH₂Oの分子が近接して存在しているだけです。
しかし、私たちはその連続的な世界を連続的なまま捉えることはできません。その連続的な世界にナイフを入れ、様々な境界を設定して初めて、モノをモノとして認識できるのです。田中さんが指摘している以下の事例は、この点を端的に示しています。
では、ありのままの世界とはどのようにイメージできるのか。それは生まれたばかりの赤ん坊や、先天的に目の見えなかった人が手術で目の機能を回復して、初めて目でものを見たときに感じる世界に似ているかもしれない。脳神経外科のオリヴァー・サックスは、そんな患者が初めて自分の目で世界を見たときのことを書いている。そのとき患者は「何を見ているのかよくわからなかった。ひかりがあり、動きがあり、色があったが、全てがごっちゃになっていて、意味をなさず、ぼうっとしていた。」と語ったという。普通の人は、部屋を見れば、手前にテーブルがあり、その上に花瓶があり、その向こうに壁があり、絵がかかっている、といった関係性をすぐに把握することができる。しかし、その患者は全ては見えているのに、モノや人の境界線、遠近感、関係などがわからず、色も形も動きも全てがごっちゃにしか感じられなかったのだった。
上記は、モノとモノの境界が定まっていない世界がどのように見えるのかの例であるとともに、それらの間の境界線の引き方が生得的(ア・プリオリ)ではないということを示しています。つまり、境界は客観的に決まっているものではなく主観的に決めるものであり、そこに唯一の「正解」があるわけではないということです。そして、この境界の設定こそが、ものを「意味づける」ということなのです。
「見る」とは送られてきた信号を脳が意味づけることである。先の患者が体験したような、全てがつながってごっちゃになっている世界に、切れ目を入れ、約束事やパターンをあてはめ、自分にとって理解可能なものに変換することによって、初めて「見る」ことができる。生まれつき目の見える人は、このような作業を、生まれてからずっと行い続けている。「見る」とは学習である。文化環境といった約束ごとに従って、目に入ってくる信号を関連づけ「世界」をつくるのが「見る」ことである。ありのままの世界を、見ることはできないのである。
以上で、境界とものの意味づけについて確認しました。
それを踏まえて再度、先ほどのアンドロイドと魔法について考えてみましょう。筆者は「誰が」魔法をかけるのかということを問題として指摘しました。その答えとして、私たちこそが魔法の主体であると筆者は主張したいと思います。アンドロイドに「人が憑依する」ということも、まずそこにアンドロイドという境界を設定し、その上で「人」という「意味」を付与している私たちがいなければ成立しません。アンドロイドは、自分自身に境界を設定して「意味」を見出すことは(少なくても現在は)できません。従って、意味を生成する主体は私たちなのです。
意味の希求と人生の意味
以上までの内容を踏まえて、ここではピノキオPさんの歌詞を考察したいと思います。ピノキオPさんの「ぼくらはみんな意味不明」については、自同律の不快などといった様々な要素を読み取ることができますが、ここでは特に「意味」と「無意味」に関する部分に注目したいと思います。
まずサビの部分ですが、最初と最後の部分は以下のようになっています。
生きてる意味も 頑張る意味も
ないないない 無駄かもしれない
千年後 何も残らないけど
それでも君と笑っていたい
僕らはみんな意味不明だから
僕らはみんな意味不明だから
(中略)
生きてる意味も 頑張る意味も
ないないない 無駄かもしれない
千年後 何も残らないけど
それでも君と笑っていたい
夢を叶えても 悟り開いても
結局は孤独かもしれない
おばけになっても 虚無に還っても
それでも君と笑っていたいな
僕らはみんな意味不明だから
僕らはみんな意味不明だから
基本的には「生きる意味はない」ということが歌われており、一見すると一切の価値を否定する虚無主義(ニヒリズム)が主張されているようにも感じられます。特に「千年後 何も残らないけど」や「虚無に還っても」という部分からは、結局全ては無に帰すのに何のために/なぜ生きるのかという、人生に対する根本的懐疑が読み取れます。この問題は、多くの人が一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
それでは、私たちの人生は本当に「無意味」なのでしょうか。この点について、ラスサビ前に以下のような歌詞があります。
それでもぼくらは トンネルで息を止める
折り紙で鶴を折る 肉球を触る
横断歩道の白い部分だけを踏む
こうした日常の何でもない行為は「無意味」でしょうか。基本的にはそうでしょう。病気の人の回復を願って千羽鶴を折るなどの場合を除けば、特に何の意味もない行為です。
しかし「それでもぼくらは」そうした無意味な行為を行っているのです。なぜか。それは、そうした行為自体が「目的」であり、そこに「意味」があるからです。
この点について掘り下げる前に、まず「意味がある」とはそもそもどういうことなのか確認しましょう。先ほど、無意味な行為の例外として千羽鶴を出しました。千羽鶴が無意味でない=意味があると考えられるのはなぜでしょうか。それは、千羽鶴が病気の回復という目的を達成するための手段や媒介になっているからです(実効性は置いておいて)。それでは、病気が回復することは、何か別の目的のための手段や媒介になっているでしょうか。もちろん、健康な生活に戻るため、QOLを上げるためなどといった目的を挙げることはできるでしょう。しかし、基本的には、病気の回復は何か別の目的を必要とせず、それ自体において目的となっています。つまり、「意味がある」ということは、病気の回復のようにそれ自体が目的であるか、そうした目的を達成するための手段や媒介であるかのいずれかということなのです。
それでは改めて、「トンネルで息を止める」「折り紙で鶴を折る」「肉球を触る」「横断歩道の白い部分だけを踏む」ことに意味はあるでしょうか。これらの行為は、いずれも何か別の目的のための手段や媒介にはなっていないので、その点では「無意味」です。しかし、そのようにして子どもが楽しそうに遊んだりしているように、それ自体が目的となっているのであれば「意味」があります。大人になるとそうした行為をしなくなるのは、それ自体が目的とならなくなり、「意味」が失われるからです。

この点は、そのまま人生にまで拡大しても当てはまります。人生に意味があるのか/ないのか。それは結局のところ、何を目的とするのかによって変わってきます。何か別のことを目的として人生を考えた場合、それを達成したとしても「千年後 何も残らない」ので「無意味」ということになるかもしれません。しかし、生きることそれ自体を目的として人生を考えるなら、人生はそのまま丸ごと「意味」をもちます。
そのように考えてみると、曲のタイトルが「ぼくらはみんな無意味(meaningless)」ではなく、「ぼくらはみんな意味不明」となっていることも示唆的です。「意味不明」というのは、ぼくらの人生には意味がないということではなく、意味づけが各個人に委ねられている(to be made)と捉えることができるからです。実際、サビに含まれる「それでも君と笑っていたい」という歌詞からは、「君と笑う」ことそのものに意味を見出すような「意味への志向」を読み取ることができます。そう考えるならば、「ぼくらはみんな意味不明」という歌は、決して虚無主義的ではないのです。
意味の過剰としての強迫性障害
本稿の内容に関連して、「強迫性障害(OCD)」という疾患について補足的に取り上げたいと思います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この疾患は心的な障害の一種で、厚生労働省のホームページでは以下のように説明されています。
「ドアに鍵をかけたかな?」「鍋を火にかけたままかも」と、不安になって家に戻ったという経験は多くの人がしていることでしょう。また、ラッキーナンバーなどの縁起へのこだわりも、よくあることです。
これらのような不安やこだわりが、度を超しているなと感じることはありませんか?戸締まりや火の元を何度も何度もしつこく確認しても安心できなかったり、特定の数字にこだわるあまり生活が不便になったりしている場合は、「強迫性障害」かもしれません。
強迫性障害は不安障害の一種です。たとえば、「手が細菌で汚染された」という強い不安にかきたてられて何時間も手を洗い続けたり、肌荒れするほどアルコール消毒をくりかえしたりなど、明らかに「やりすぎ」な行為をともないます。世界保健機関(World Health Organization:WHO)の報告では、生活上の機能障害をひきおこす10大疾患のひとつにあげられています。
(中略)
強迫観念とは、頭から離れない考えのことで、その内容が「不合理」だとわかっていても、頭から追い払うことができません。
強迫行為とは、強迫観念から生まれた不安にかきたてられて行う行為のことです。自分で「やりすぎ」「無意味」とわかっていてもやめられません。
ちなみに、確定的な診断を受けたわけではありませんが、筆者は間違いなくこの疾患をもっています。小学生の頃から、特定の数字へのこだわりや一部の病気への不安が強く、大人になった今でも続いています。日常生活に大きな支障が出るほどではないので、今のところ病院にかかることは予定していませんが。
なぜここで強迫性障害の話をしたのかというと、この病気の本質は、本稿で述べてきたような「意味」に大きく関わるものだからです。
もちろん、科学的・医学的な観点から疾患の説明は為されています。まだメカニズムが完全に解明されたわけではないようですが、どうやら特定の脳内物質の分泌量と関わりがあるようです。
この点について、筆者は別に近代医学の知見を否定するつもりはありません。しかし、第三者の視点から見た病気と、当事者から見た病気の様相は、必ずしも同じであるとは限りません。そして当事者である筆者にとって、この疾患の核心は、自分の意思とは関係なく「過剰な意味」を生み出してしまうことにあるのではないかと感じています。例えば、特に意味のない数字にこだわったり、現実的には考慮に値しないことが不安になったり、特定の儀式的行為をしないと気が済まなかったり……。こうしたことは全て、「正常」な人が意味を見出さないこと/意味を見出す必要のないところに、「過剰(異常)な意味」を見出してしまうことによるものです。そして、それを本人の意思でコントロールできないところが、この病気のつらいところであり不思議なところです。「意味」を見出しているのは私なのですが、私の意思はその「意味」を見出すことに関して決定権をもっておらず、避けようとしても避けることができません。
しかし、考えてみれば、こうした「過剰な意味」は、誰であっても多かれ少なかれ日常的に見出しているはずです。例えば、不運なことが続いた後にお祓いに行ったり、不動産屋で良い物件を見つけてもそれが事故物件であれば見送ったり、結婚式の日取りで仏滅を避けたり……。こうした意味は、過剰なのか/過剰でないのか。その線引きは人によって異なるでしょう。先ほども確認したように、どこに意味を見出すのか/どこまで意味を見出すのかについては、客観的な「正解」があるわけではなく、主観的な「選択」があるだけです。そしてもちろん、強迫性障害と正常の「境界」も曖昧です。
No AI Makes Sense, I Make Sense
以上、大変長くなってしまいましたが、最後までお読みいただいた方、誠にありがとうございます。初投稿なので張り切ってしまいました。次回はもう少しコンパクトにまとめられればと思います。
最後に、本稿のヘッダー画像について触れて終わりにしたいと思います。ヘッダーに少し不気味なダルマの画像があったかと思いますが、これは最近流行りのAIによる自動画像生成によるものです。

不確かな知識で恐縮ですが、最近のAIは統計処理的手法を導入することによって性能が飛躍的に向上したと聞いています。このような形のAIは、本稿で述べてきたような「意味」を志向して生成しているのではなく、ひたすら膨大なデータを統計的に処理することによってアウトプットを行っています。つまり、AIが何か意味のあるような絵を描いたとしても、それはその絵を見ている私たちがそこに「意味」を見出しているのであって、AIの側に「意味」はありません。そう考えてみると、AIは「意味」を創り出せない哲学的ゾンビのようなものですね。昨今、AI技術は日進月歩の様相を呈していますが、「意味」を創り出すことについては、まだ人が保有している特権なのです(少なくとも今のところは)。

以上になります。改めてありがとうございました。
次回に関してはまだ決めていませんが、不老不死時代における仏教の話か、映画「The Sky Crawlers」(監督:押井守、原作:森博嗣)について取り上げようかなと考えています。いつアップできるかは分かりませんが、よろしければご覧ください。
また、フォローやスキをしていただけるとモチベーションにつながりますので、よろしければそちらもお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
