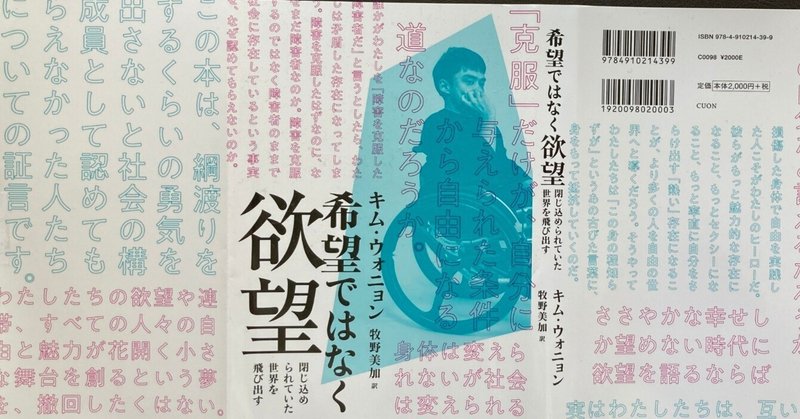
『希望ではなく欲望』キム・ウォニョン著 (牧野美加訳。CUON発行)から
年末、『希望ではなく欲望』を夢中で一気に読了しました。
今まで読んだ障害に関するどんな本よりも強い印象を受け、心を揺さぶられた本です。
著者の自己開示の潔さ、深さ、言葉の鋭さ、重さ、力強さに、ぐいぐいと引き込まれます。
子ども、十代、二十代だった著者の葛藤が、苦しみが、喜びが、まるで自分のことのように現実味を 持って、ひしひしと、リアルに伝わります。
印象に残った文章の一部を以下に抜粋します。もっと素晴らしい部分もたくさんありますが、それは、本で読んでください。
<その後、『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』(五十嵐真希訳。小学館)と『サイボーグになる』(牧野美加訳。岩波書店)を読み、さらに衝撃を受けました。ぜひ3冊ともお読みください。>

・・・・以下、『希望ではなく欲望』からの抜粋です・・・・・・
障害者は人々から希望を持てと言われ、「希望のアイコン」のように語られたりもしました。けれど、一個人として持っている欲望を語ることはできませんでした。それを口にした途端、「人と同じように生きようなんて思っちゃいけない」(映画「ジョゼと虎と魚たち」でもジョセの面倒を見ている祖母が彼女にそのようなことを言います)という、日本風に言えば「迷惑をかけてはいけない」という批判を受けたのです。
p.5
この本は、綱渡りするくらいの勇気を出さないと社会の構成員として認めてもらえなかった人たちについての証言です。
p.6
だがこの本を刊行した当時のもっとも根源的な欲望、すなわち、障害を恥じるのではなく自分の一部として受け入れ、障害のある身体で萎縮せずに堂々と、美しい存在として生きていきたいという願いは、まだ叶えられていない。
p.17
その欲望とはこういうものだ。自分が一番隠したい、目を背けたいと思っていた、だが同時に自分の属する共同体に心から受け入れられたい、包み込んでもらいたいと願っていたある特定の状態や条件がありのままに認められ、一人の人間として夢を見て、誰かを愛し、働いて、旅をして、死んでいく、そんな人生に対する熱望だ。長いあいだ拒まれ、疎まれてきた自分の一部分が共同体にありのままに受け入れられたとき、そのとき初めてわたしたちは「自分自身」として存在していることを確信するだろう。
p.20
世間も、希望という名で語られる夢はすんなり認めてくれる。
p.21
障害とはいったい何なのか、今もよくわからない。病気とは何なのか、そして、生まれついての、あるいは偶然の出来事による身体の状態のために、どうしてこんなにも人と違う人生を歩まなければならないのか、よくわからない。P.42
病気を持つ子どもは不幸だと思われがちだが、必ずしもそうではない。まず寂しくはない。いつも自分を心配してくれる親がいるならその子は、幸せだ。だがそのきょうだいは孤独だ。姉はわたしのせいでいつも寂しい思いをしていた。両親はわたしにかかりきりだったので、姉は自分一人で起きて祖母の用意してくれる朝ごはんを食べ、学校に行く支度をしなければならなかった。病気の持つ重さとはそういうものだ。家族全体がその重さに耐えなければならない。誰も助けてはくれない。まだそういう時代だった。 P47
命に別状がないという言葉は、母にとって慰めにはなっても希望にはならないだろうとわたしは思った。p.48
「命に別状がないこと」はわたしや家族にとって希望なのか絶望なのか、手術が終わったあともわからなかった。病気は子どもを大人びさせる。大人びた子どもにはそれだけの苦しみがある。P.49
今この瞬間も、数多くの障害者が家の中だけで、あるいは入所施設に閉じ込められて生活している。P.51
その狭い世界でも、わたしたちは互いに相手を見くだし序列を決めることで、かろうじて残っている自尊心を必死で守ろうとしていた。
このように、そこは外の世界となんら変わりは、なかった。よく障害者は天使だとかなんとか言うけれど、そんなの全部でたらめだと言うことが分かった。自分だけかと思っていたが実はそこにいるみんなも、人を格付けするのが好きな、どこにでもいる十代の若者の姿とそっくりだった。P.56
どんな人間でも、共に力を合わせる存在、創造性を発揮する機会、適応するための時間が与えられれば、自分なりの世界を築き上げていくものだ。P59
今日の自分が昨日とは違うということ、できることが一つづつ増えていくということ、新しい人で出会うことで自分が世界の中に与える影響力が少しづつでも増えていくということ。これほど人を幸せにすることがあるだろうかと思った。P.61
その風景を現実として生きている人間にとっては、風のようにやってきて風のように去っていく彼らの訪問は、あとに虚しさを残すばかりで、現実を生きていくうえで何の役にも立たない。P.67
また、わたしたちのような「奉仕される側」は、ボランティアの心を温かくするという義務も負う。p.72
彼女がわたしを特別扱いしなかったおかげで、わたしは、本当に特別な人間になれたのだ。p.73
リハビリ園での生活に慣れるにつれていい友だちもたくさんできたけれど、依然として自分が世の中から「見えない」存在であるという事実はつらかった。わたしは世界に存在したかった。p.74
観客席に座っているわたしは目立たず、意欲や熱望や才能を示すことができない。じっと座っていては決して光り輝く存在になれない。沈黙すると同時に劣った存在へと転落する。P.77
わたしたちは居心地のいい場所からも、時には「脱出」を敢行しなければならないのだ。p.95
その壁を打ち破って出ていくには、あくまでも障害者本人の勇気が必要だった。わたしにはそれがなかった。P.97
「これは高校に行く行かないの問題じゃない。おまえがこの先どんな人生を生きていくかっていう問題だ。一生この殻の中にいるのか、破って出ていくのか」
チャノ兄さんはわたしの目をまっすぐ見据えて言った。
「それがまさに、今だ」 P.106
「それは、おまえが人の手を借りなくてもちゃんと通えるように施設を整えるべき学校の責任だ。だから、おまえが誰かに助けを借りて迷惑をかけるとしたら、それは学校が申し訳ないと思うべきであって、おまえが申し訳ないと思うことじゃない」p.107
存在そのものを認めてもらえない人間は結局「意外な」成果をあげるしかないのだ。P.110
障害者が教育を受けるというのは依然として家族全体が向き合わなければならない大きな挑戦だ。場合によっては親のどちらかが仕事を辞めて、子どもと一緒に一日じゅう学校で過ごさなければならない。(略 )
そうやって苦労して卒業させると、人は彼らを「立派な母親」「立派な父親」だと褒めそやす。
だが長ければ16年にも及ぶこの永く孤独な闘いは、「立派だ」という一言で報われるものではない。P.114
いわゆる「スーパー障害者」になること。それがわたしの選択だった。スーパー障害者はまず、人々が思いもよらないようなことに挑戦し、明るく積極的な性格でいくつもの壁を乗り越えていく。そして常に自信を持って堂々と振る舞い、他人の視線なんて「俺のかっこよさに見とれてるんだろ」と言って退けるような、あっけらかんとしたところもある。勉強ができるのは当たり前。運動神経や恋愛能力まで兼ね備えていなければならない。もちろん、どんな状況でもひるむことなく勇気を持って行動する「度胸」は必須だ。
p.117-118
だが、私がそんなことではいけない。スーパー障害者たらんとする者が、屈辱を味わったからと挫折するようでは失格ではないか。わたしは屈辱に慣れなければならない。障害者には屈辱に耐え得る強い精神力が必要だ。「それを屈辱だと思ったらだめだよ」という人がいるかもしれないが、その場合「君の生涯を考えるとそれは屈辱ではない」という意味なのか、「それは誰にとっても屈辱ではない」という意味なのかをはっきりさせる必要がある。もし前者だとしたら、障害者が屈辱に甘んじなければならない必然的な理由を挙げるべきだろう。p.119
そうだ。わたしは確かに障害者だ。だが自分が障害者であることと「わたしは障害者だ」と叫ぶことは、まったく別の問題だった。わたしは、障害者の50%が小卒と言う大韓民国でソウル大学に通う大学生だ。自負心と夢を前に、またもや障害者というアイデンティティーを掲げたくはなかった。転落したくなかった。障害と何の関係もなく生きることはできないのだろうか。車椅子に乗ってはいるけれど、障害者であることをまったく感じさせないほどの能力や職業、学識、ユーモア、軽快さといったものを手にすることはできないのだろうか。P.139
障害者は地下鉄の運賃が無料だ。だが障害者は地下鉄に乗ることができない。地下鉄は「公共」交通機関だが、障害者は公共の一員ではない。
p.144
何よりも切実な理由のためなら、人は何だってできる。p.146
彼らはこう叫んだ。「わたしたちの身体を変えることは不可能だが、社会を変えることは可能だ」。 p .148
ただそういうアイデンティティーが「障害」になるのは、社会がそのアイデンティティーをきちんと受け入れられる構造になっていないからだ、というのだ。P.148
わたしはスーパー障害者になりたかった。身体障害1級の障害者としてソウル大学を卒業し、これ見よがしに成功すること。人生を克服し、生涯を克服し、希望や奇跡を語る人間になりたかった。だが「奇跡」を起こすためには、奇跡を起こしているあいだに利用する公共交通機関が必要で、奇跡のために読む本が必要で、奇跡を生み出しているあいだに食べるカップラーメンも必要だ。p.152
そうやってわたしは、「スーパー障害者」になりたいという欲望を次第に捨てていった。P.155
骨形成不全症あるいは障害はそれ自体がすでにわたしの身体であり、わたし自身だ。わたしはそれを「抱えて」生きるのではなく、それそのものとして生きてきたし、今も生きている。それは長い闘病の末に危険で深刻な状況を脱し、わたしの人生の一部となり、身体の独特な運用方法を編み出し、わたし自身となった。正常でない危険な状態というより、それそのものが「わたし」という人間を構成する一部なのだ。 p.162
わたしたちは障害から健康を守らなければならないのではなく、「健康至上主義」から障害や病気の経験を守らなければならないのだ。人間は誰しも常に病気のリスクにさらされているし、歳をとれば結局「障害」があるのと同じような身体の状態になる。それを「正常からの逸脱」とみなし、排除するべきものとするなら、人間が自分の身体を肯定できる期間はほとんどないことになってしまう。P.163
今も、世の中から取り残されまいと病気や障害を必死で隠し、スーパーマンになることを夢見ている人は「目を覚ます」べきだ。わたしたちのほとんどは乙武洋匡やスティーブン・ホーキングではないからだ。もしそうだとしたらめでたいことだが、そうでないからといって悲劇の主人公になる必要はない。p.165
だが障害者の人生はどうだろう。障害者の多くは、一つの世界の中で各自それぞれの位置に存在しているのではない。そもそも「別の世界」に存在しているのだ。わたし達がまったく別の世界として思い浮かべるイメージ、たとえば刑務所や動物園、病院、下水道といった場所と通じている世界。閉鎖されていてあまり目につかないけれど、日常の世界に生きる人と密接に結びついている場所。間違いなくすぐそばに存在しているのに存在していないことにされる場所。すなわち「非正常の世界」だ。まさにそこに障害者がいる。
P175-176
だが特別支援学校といわゆる「一般」学校とに分離されたシステムが根付くなかで、子どもたちは障害者と非障害者がまったく異なる存在ではないことを経験する機会を失った。 p.180
このように、ある制度を利用して得られるものが運の良し悪しで決まるなら、わたしたちはその制度の有効性や道徳的な正当性を疑ってみる必要がある。 p.184
「正常の世界の中心」で暮らす彼らにとって、わたしの存在は一つの慰めであり、自己満足であり、自身の人生を浄化してくれる観葉植物だったのだろう。 p.196
刺すような視線と同情の涙は矛盾するものではない。その二つは実際には同じ文脈上にある。そうして二つの世界はますます離れていく。 p.203
そして障害のある人も熱い血の流れる、ゆえに屈辱や挫折を敏感に感じ取る存在だということを明確にしておきたいだけだ。
わたしたちは当然、共に生きていくべきであり、そのためには互いに助け合わなければならない。だがそれはすべての人間に求められる普遍的な美徳であって、障害者が清く正しく生きながら請わねばならないことではない。
p.204
奉仕されることは、奉仕することの百倍は難しく献身的な行為だからだ。
p.204
助けるというのは傘を差し掛けてあげることではなく、共に雨に打たれながら共に歩いてゆく共感と連帯の確認であると考えられます。申栄福『獄中からの思索』(2018) p.20
悲しみと怒りの果てにはユーモアがある。ユーモアは時に人をクールにさせる。誰かに持ち上げられて階段を上りながら屈辱的な表情を浮かべるとしたら、どれほど「ぶざまに」見えることか。 p.221
クールな人間になろうとしていたわたしは、実はなんでもない存在になろうとしていたも同然だと気がついた。わたしはただ一人の人間として存在したかった。p.223
障害者の性的成熟は、マンションで飼う犬の声帯のように不必要で厄介なものと認識されているのだ。 p226
障害者は保護や施しの対象としてしか見られてこなかったため、人間なら誰もが抱く欲望や欲求とは縁遠い(縁遠くあるべき)人たちだと認識されるようになった。障害者は入所施設の中でいつも天使のように微笑んでいなければならなかった。p.226
「わたしは障害者です」と言えなかったあのころ。だがわたしは今、ごく自然に自分を障害者だと言っている。そればかりか、自分のことを障害者だと堂々と言える「孤高な」人間なのだと虚勢まで張っている。 p.230
歩けないわたしのためにエレベーターを設置することはできても、走りたいという欲望まで実現させることはできない。セクシーでありたいというコ・ボクスの欲望も実現不可能に思える。 p.241
だが、欲望すること自体が自然的秩序に反するとされる人は、欲望を果敢に表出することがすなわち社会における自由の領域を広げることになるのだ。p.243
わたしはクールな障害者ではなく「熱い」障害者、「セクシーな」障害者になりたい。(略)少々ぶざまで未熟でも、走りたいなら走りたいと言える人間、(略)、「俺の身体を見ろ。俺の欲望を見ろ。踏みにじられた俺のプライドを見ろ」と言える人間になりたい。p.246
(略)もっと率直に自分をさらけ出す「熱い」存在になることが、より多くの人を自由の世界へと導くだろう。そうやってわたしたちは「この身の程知らずが」というあの古びた言葉に、身をもって抵抗していくのだ。 P.248
わたしは自分の入っていく集団に最初から適合した人物であったことは、ただの一度もない。いつも何かが不十分で、ふさわしくなく、その集団にそぐわないアイデンティティーを持っていた。そのためいつも最初は挫折の連続だった。だが最終的にはその世界と折り合いをつけ、相互に適応する新たな方法を見いだしていた。p.252-253
こうした「劇的な」ことを試みる人たちに、わたしたちはときどき出会う。彼らの共通点は、世の中の決めた型に合わない人のために果敢に新しい型を創り出すということだ。彼らの果敢さは世界の可能性を広げる。 p.260
わたしは変化しつづけてきたし、これからも自分がどのように変わっていくのか楽しみにしている。ある日目覚めたらまた田舎の村の小さな部屋に横たわっていた、というのでさえなければ、人生で経験するすべてのことに深い感動を覚えるだろう。p.269
自分は優れた能力で障害を「克服」した人間ではないが、そのアイデンティティーは複数の世界にまたがっている。そのことは時にわたしを分裂させ、人生に対する責任から目を背けさせたりもするけれど、わたしはその複数の世界の中で常にまっとうに怒り、愛し、人生を精一杯生き抜こうと奮闘している。その過程で、異質なものが統合されて何かを超越するという、人々が思ってもみなかったようなことを経験した。 p.287
実際、ラマヌジャンやヘレン・ケラー、乙武洋匡が驚くようなことを成し遂げたのは、必ずしも彼らが天才的で人よりずば抜けて優れていたからではない。彼らにはたいてい情熱的で開放的な親や先生、友人がいた。それはものすごい偶然であり、彼らの幸運だ。そういう幸運は誰にでもいつでも訪れるわけではない。だからわたしたちは保険に入るように、社会的連帯を構築する必要がある。p292-293
⭐️試し読みと購入→https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910214399
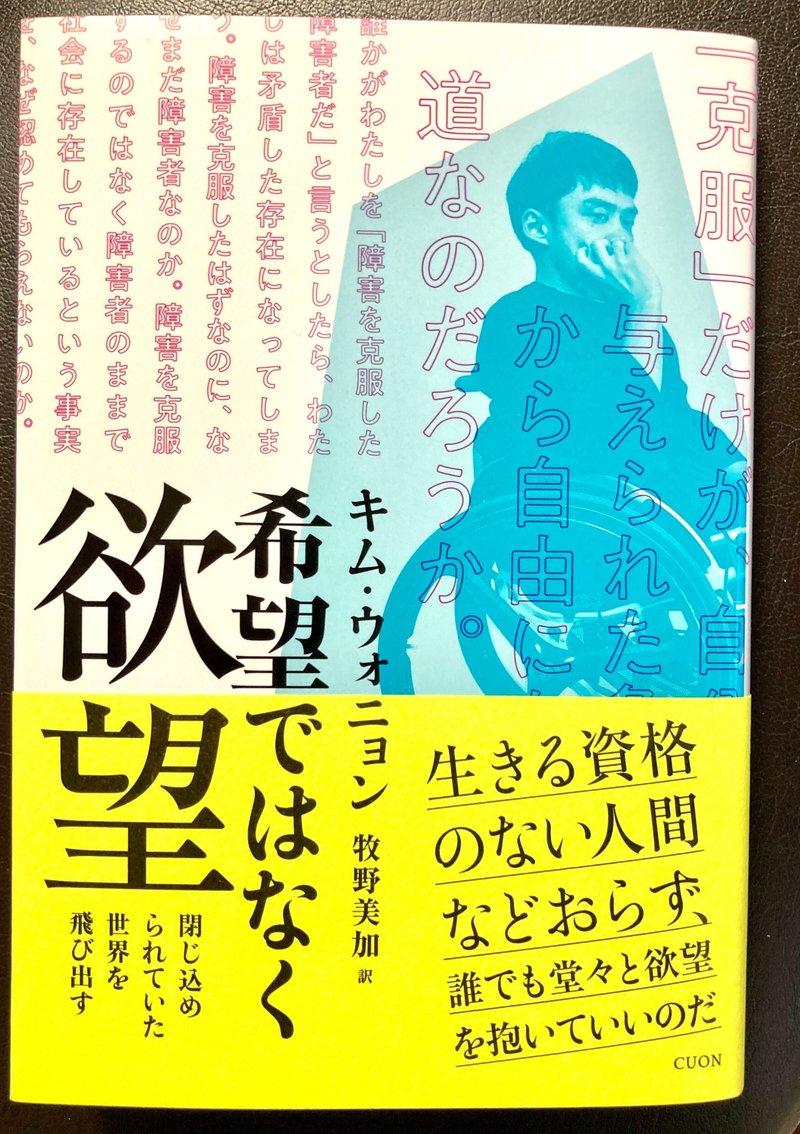


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
