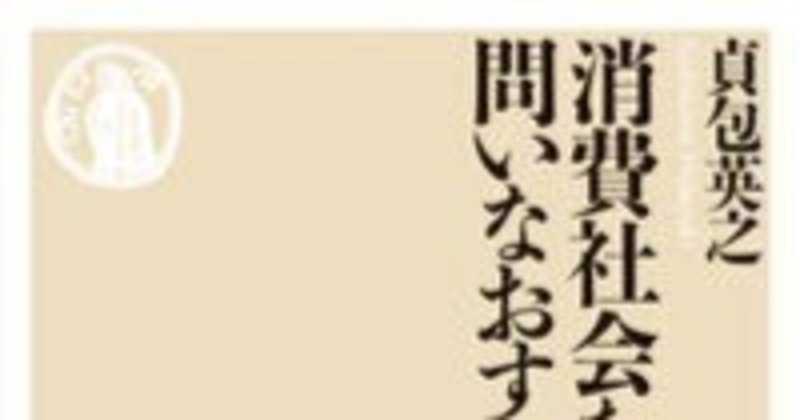
『消費社会を問いなおす』の別の序文(新海誠作品と消費社会)
以下、『消費社会を問いなおす』)の序文の別バージョンです。新海誠の作品では、消費社会についてよく考えられていると思い、それを出発点として書きました。が、かえってわかりにくい、また時事的にすぐ通用しなくなる(実際、『すずめの戸締まり』との関係を今では書き足す必要があると思います)との話もあり、より一般的な現行バージョンに書き換えています。『すずめの戸締まり』の話を書き加えれば、ひとつの原稿になると思いますが、今は時間がなく。。
はじめに
新海誠のアニメーションでは、消費社会をいかに生きるかが大きなテーマのひとつになっている。
当初、主人公たちが暮らす日常世界は、はてしがない、そしてどちらかといえば暗鬱な場として登場してくる。都市的サービスが与える豊富なモノを買い暮らす消費社会的といってよい日常が主人公たちを取り囲み、いつまでも離そうとしないためである。たとえば新海誠の名を知らしめた『ほしのこえ』(2002)では、戦争が始まり、宇宙の遠くに離れ離れになりながらも、少年少女たちは携帯メールを使ったコミュニケーションの可能性/不可能性にいつまでも拘泥している。戦争によって消費社会は脅威にさらされながらも、なお破局を迎えることなく続くのであり、それは『雲のむこう、約束の場所』(2004)でも変わりない。中学生時代の同級生を時が止まったように思い続ける主人公は、「エゾ」と呼ばれる北海道を支配する勢力との開戦を思いを通じ合わせる機会になると期待するが、一瞬しか希望は実現せず、ふたたび都市の孤独のなかに投げ出される[1]。
結果として消費社会は、逃げ場のない悪夢のように現れてくるといえよう。たとえば『秒速5センチメートル』(2003)では東京から栃木、種子島と場所を変えながらも、一人の女の子のことを忘れられない男の物語が語られる。空間を移動し、また小学生から社会人へと「成長」しながらも、日常は変わることなく主人公を縛るのであり、そのありさまはこの純愛風の作品に、悪夢といっても良い面影を付け加えている。
新海誠はこうしてさまざまな出来事が起こりながらも、それを飲み込み継続される消費社会的日常の風景に執着し、それをくりかえし描いてきた。だが興味深いのは、近年ではようやく消費社会の「終わり」、あるいは少なくともその綻びが描かれ始めていることである。
たとえば『君の名は。』(2016)では、日常に破滅の危機がついに訪れる。隕石の衝突という物理的な危機が主人公たちの世界を襲い、田舎ではあれ、楽しく送られていた日常は天変地異によって中断される。ただしここでも破壊がなお部分的、つまり消費社会の端っこで起こるものにとどまっていたことは見逃せない。災害で壊されるのは遠い「地方」の生活にすぎず、東京ではなお豊かな生活が続いていくのである。
対して『天気の子』(2019)は、消費社会の持つ問題や綻びをより端的に描いている。その映画では、東京という消費社会の内部にはらまれた格差や貧しさがはっきりと描きだされる。家族や学校という制度から抜け出した年少の主人公たちはその年齢もあって、満足な働き口をみつけられない。そのため怪しげな大人たちに頼り、漫画喫茶やラブホテルに泊まるなどして、なんとか暮らしていくしかないのである。
問題の根底にあるのは、消費社会が豊かさを振りまく一方、それが優しい顔を向けるのは、あくまで購買力を持った人びとに限られるという容赦のない事実だろう。たとえば自分で働くことのできない年少者たちは親のいうことを聞き、豊かさのおこぼれを貰い暮らしていくか、そうでなければシステムの隅で貧しさに耐えるしかない。新海誠的主人公たちは、それまで学生であれ社会人であれ、消費社会をかなり恵まれた立場で生きる者として描かれていた。しかしそうした「豊かさ」は『天気の子』では後景に退き、消費社会の限界を生きる少年少女が舞台の中心についに押し出されているのである。
こうした問題に加えて、その映画のなかでさらに根本的に消費社会を脅かす困難としてクローズアップされているのが、タイトルにも掲げられた「天気」である。映画のなかで東京は長雨に襲われ、最終的にはその多くを水没させる。天変地異が日本を襲うことは同じでも、『君の名は。』とは異なり、破壊は東京の内部にまで及ぶのである。
どこまで意図されているかは別としても、こうした危機は、毎年のように大雨洪水が襲う社会に生きている私たちにとって、他人事のものではない。後に詳しくみるが、この社会は気候変動の影響をあきらかに受け、100年という単位でみれば気温の1.5~4度の上昇と、18~60cmの海面上昇が見込まれている[2]。映画で描かれる水没する東京の姿は、その意味で荒唐無稽な虚構とはいえない。それは消費社会がこのまま生きられ続けていくかぎり、近い将来に現れる可能性が高い未来予想図なのである。
『天気の子』は消費社会が直面しつつある限界をこうして描くことで、これまでの新海誠的映画とは一線を画した。これまで消費社会はいつまでも続き、それゆえうんざりしながらも生きていかなければならない場として描かれていた。それに対し『天気の子』で消費社会は、多くの人を貧困のうちに置き去りにするともに、壊れやすく(vulnerable)、ひょっとすると終わりさえ近いものとしてさえ現れてくる。
加えて重要になるのは、消費社会がこうして限界のあるものとして描かれるにもかかわらず、その社会を主人公たちが積極的に選び取ろうとすることである。日本文学研究者の榎本正樹は新海誠の映画では「決意するのは常に女性たち」[3]と述べている。たしかに『ほしのこえ』や『秒速5センチメートル』など、新海誠作品の主人公の男性たちは決断できずに取り残されることが多いが、『天気の子』でついに主人公の男性は、「あの人を。この世界をここで生きていく」と、選択を率先して実行する側に回る。この選択は、自分や他人の多くの困難につながることを知っていながらおこなわれるという意味でさらに重い。具体的には映画をみてもらうべきだが、主人公の選択によって貧困または親への依存という問題は何ら改善されることなく残され、それどころか、東京に暮らす多くの人びとはいっそうの気候変動の被害に苦しむことになるのである。
道徳的に判断すれば、それゆえ主人公の選択は正しいものとはいえない。新海誠自身その物語を、「個人の願いと最大多数の幸福がぶつかってしまう話」[4]とまとめているが、『天気の子』では、問題があることをわかっていながら、「個人の願い」が優先されるせいで、多くの人びとのいわば「SDGs」的な幸せは台無しにされるのである。
それが『天気の子』が一部に高い評価を呼びながらも、大衆的な人気を獲得しなかった理由のひとつだと考えられる。前作『君の名は。』が、あまり期待されていなかったにもかかわらず興行収入が250.3億円を超え、当時の日本の興行収入の4位にまで上り詰めたのに対し、多くの企業とコラボし、ヒットが期待されていた『天気の子』の興行収入は141.9億円にとどまった。低い数字とはたしかにいえないが、やや期待はずれの数字だったことは否めない。罪を自覚して引き受けるというその選択において『天気の子』は、道徳的にむずかしい刺のような部分を宿している。『君の名は。』のような爽やかな恋愛劇を期待した人びとは、その棘に刺されてしまったのである。
とはいえこうした影のような部分こそ、『天気の子』を新海作品、またはそれを超え日本という国で戦後につくられた多くのアニメーション作品のなかで、特別のものとしている。結果だけみれば、消費社会的日常が続くことは、それまでの作品と変わりはない。しかし『天気の子』では、貧困や気候変動などの瑕疵や限界が理解された上で、それを引き起こす消費社会が主体的に選び直されている。その意味で、『天気の子』はきわめて倫理(エシカル)的な作品である。選択の内容の正邪はともあれ、さまざまな問題に向き合い、それを熟慮した上で、ひとつの未来がそこで引き受けられていることは疑えないからである。
※ ※
「選択」ということでいえば、本書がおこなおうとしていることも、実は同様のことである。本書の主題となる消費社会に、さまざまな問題があることはいまや隠しようのない事実である。それを認めながらも、あくまで消費社会が持つ可能性を根気強く考えていくことこそ、本書を貫くテーマとなっている。
ただしそのためにはまず消費社会がいかなる場としてあるかを、できるだけ具体的に知っておく必要がある。これまで消費社会は貨幣と交換に、大量のモノや記号を私たちに供給するシステムとだけ捉えられることが多かった。資本主義的生産様式を前提として、大量のモノや記号が生み出され、その消費が促される。それが行き過ぎることで、格差や気候変動といった問題も生まれるとみなされてきたのである。
この見方は完全にまちがいではないとしても、本書が注目したいのは、消費社会のそうした否定的なシステムとしての顔ではない。本書が知りたいのは、多様な選択肢をつくりだし、それを選択することを「私」に促す消費社会のより積極的な、そして歴史的な場としての消費社会である。金を支払うかぎりにおいて、私たちは大抵の選択が可能で、自分の意志や欲望を押し通すことが許されている。人びとがそうして国家や共同体の利害と一定の距離を置き、自由に生きていくことを後押する力を消費社会は担ってきたのである。
もちろん消費社会が完全な社会であるといいたいわけではない。そうではなく本書が主張したいのは、消費社会がどんな場であるかを具体的に検討し、それであきらかに限界があるとすれば、それを是正する仕組みや手段について臆することなく考えるべきということである。消費社会が何かと問うことを欠いた選択は、無知に基づくたんなる臆断か、既得権益を守るための党派的な決定に終わる。だとすればやみくもに消費社会を批判する前に、できるだけそれを知る努力をしていかなければならないのである。(以下略)
[1] 結末ははっきりとしないが、冒頭、成長した主人のかならずしも幸せそうにはみえない姿が描かれているという意味で、そのように判断される。
[2] ウィリアム・ノードハウス(藤﨑香里訳)『気候カジノ』日経BP、2015年、60~61頁。
[3] 榎本正樹『新海誠の世界:時空を超えて響きあう魂のゆくえ』KADOKAWA , 2021年、173頁。
[4] 「『天気の子』新海誠監督が明かす“賛否両論”映画を作ったワケ、“セカイ系”と言われることへの答え」https://moviewalker.jp/news/article/200868/p2/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
