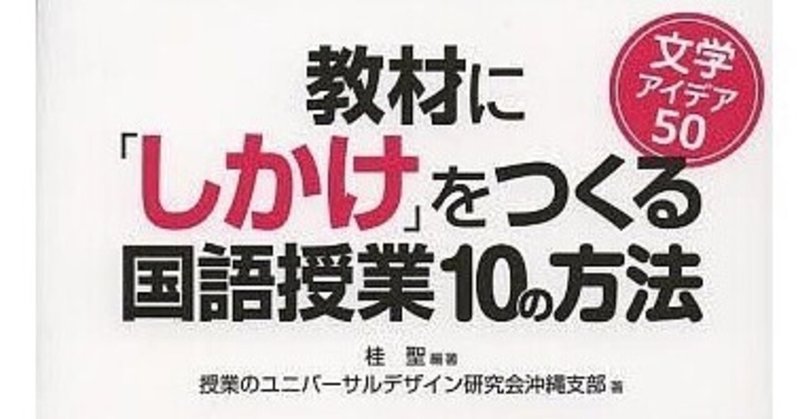
小学校国語授業づくり
桂聖編著、UD沖縄著「教材に『しかけ』をつくる国語授業 10の方法」に関する記事です。
※この記事は、教員の研修で筆者が後輩に伝えようと思っていることをnote掲載用に編集したものです。
もし、水の入ったコップが机のギリギリの端に置いてあったら?
教材に「しかけ」をつくるとは、教材の安定を崩すこと。「机の真ん中にコップを置いて!」と言いたくなるように、子ども自ら「動きたくなる」「話したくなる」…それが本書の「しかけ」です。
(本文冒頭より引用)
「しかけ」には次の10の方法があります。
①順序を変える、②選択肢をつくる、③置き換える、④隠す、⑤加える、 ⑥限定する、⑦分類する、⑧図解する、⑨配置する、⑩仮定する
これらいずれかの方法で国語の教材に手を加えます(安定を崩す)。そうすることで、子どもが能動的に国語教材と関わるように促すのです。
この本に習いながら、自分でも「しかけ」の国語授業を実践しています。

教材研究の段階で難しく思うことの一つに、「センテンスカードの内容(取り上げる叙述)は、どのように決めようかな?」という悩みがあります。これは、職場の後輩からも尋ねられたことのある悩みです。
整理しながら考えてみようと思います。
ただ、その前に確認です。「しかけ」=センテンスカードではありません。
センテンスカードを使うことは、ある叙述に着目する選択的注意を補ったり、カードを移動することで考えたことを視覚化したりするのに有効な手立ての1つだと思います。けれども、使用することで子供の「自由な着眼が奪われてしまった」、「文脈がわかりづらくなった」などとならないように気をつけたいものです。
「しかけ」≠センテンスカードを踏まえた上で、話題を悩みに戻します。
これまでの実践を振り返ってみました。文章の中から大切だと思う叙述を取り上げてセンテンスカードを作り、「しかけ」を取り入れた授業をしていました。うまくいかなかったと反省する授業ばかり思い浮かびますが、改善するにはどうしたら良かったのか考えてみると3つのポイントに気付きました。
3つのポイントは、⑴指導内容、⑵可視化、⑶学習者視点です。
ただし、これは「しかけ」をつくるポイントというより、「しかけ」をつくる際にセンテンスカードを作るとしたら「何を基準に考えるか」という視点になると思います。以下、一つずつご説明します。
⑴指導内容:センテンスカードに取り上げる叙述を指導内容から考えるということ
教材に「しかけ」をつくる上で、指導内容を意識することは非常に大切です。「しかけ」ありきになってはいけないということです。小学校国語の教科書に掲載されている「ごんぎつね」(4年生)の冒頭場面に、次のような文があります。
「二、三日雨が降り続いたその間、ごんは、外へも出られなくて、あなの中にしゃがんでいました。」
仮に、この文のある言葉を置き換えて、子供と間違い探しをするとしたら、どの言葉にしますか?
これは、語句を置き換えるという「しかけ」です。
私の質問に対する唯一の答えはありません。それは指導内容によって着目させたいことも変わるからです。例えば、指導内容を「場面の設定を捉える」と設定すると、「二、三日雨が降り続いたその間」や「あなの中にしゃがんでいた」という言葉に着目できます。(もちろん、それ以外でも構いませんが)また、「人物像を捉える」という指導内容を設定すると、先程の文より「ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、…(後略)」という叙述の方を取り上げたいと考えるかもしれません。
このように、指導内容から取り上げる叙述を考えることが、悩みへの答えの一つです。
⑵可視化する:センテンスカードによって見えないことを見えるようにすることを考える
可視化とは、物理的に見えなかったものを見えるようにすることです。視覚化という言葉もありますが、授業をUD化する視点の「視覚化」と区別するために、ここでは「可視化」を使います。
小学校5年生の国語教科書に掲載されている「大造じいさんとがん」の授業です。この物語は、狩人である大造じいさんと、狩りの対象であるがんの頭領である残雪との戦いが描かれています。残雪は優れたリーダーシップで、大造じいさんの狩りの作戦をことごとく失敗させます。その度残雪に対する闘志を燃やす大造じいさんの心情が情景描写などによって読み手に伝わってきます。
この人物の心情の変化に気づかせるために、次の3つの情景描写を取り上げました。
ア「秋の日が、美しくかがやいていました」
イ「あかつきの光が、小屋の中にすがすがしく流れこんできました」
ウ「東の空が真っ赤に燃えて、朝が来ました」
これらの表現には、大造じいさんの心情が表れていますが、直接的に書かれているわけではありません。前後の文脈を捉えられていないと人物の心情も見えてこないのです。ここでは、狩りを成功させるために必死で作戦を考えるが、残雪の知恵によって失敗する。この失敗が繰り返されているという場面のつながりがあります。その文脈が読み取れているから「うまくいきそうだぞ」とか、「次こそは必ず成功させるぞ!」という大造じいさんの心情が見えてくるのです。このように、情景描写という直接的には描かれない人物の心情を読み取っていくこと、つまり、見えないことを見えるようにするのが可視化という視点です。
また、ア〜ウの表現には大造じいさんの残雪に対する思いの高まりが読み取れます。黒板でセンテンスカードを上下に移動させる(ア→イ→ウの順に高い位置に移動させ、矢印などで気持ちの高まりを表現するなど)ことで、人物の心情の変化が見えるようになります。このように、念頭操作に偏りがちになってしまう学習内容を見えるようにする(可視化)視点は大切だと考えています。
⑶学習者視点
センテンスカードに取り上げる叙述に学習者の視点を取り入れる、もしくは、学習者の視点から考えることが、ポイントの3つ目です。これまでのポイント⑴学習内容から考える、⑵可視化と視覚化を意識するは、いずれも授業者の視点であり、主語は教師です。最後は、「しかけ」を学習者である子供の視点から考えてみたいと思います。
前のセクションと同じ事例で考えてみたいと思います。事例では情景描写を取り上げて、登場人物の心情やその変化を捉えることをねらいとしました。しかし、子供の学習する文脈から考えると、「なぜ、ア〜ウ(情景描写)が取り上げられたのか?」がわからないかもしれません。子供が「考えたいこと」ではなく、教師が「教えたいこと」になってしまっているということです。
このことを解決するために例えば、初発の感想を「1番好きな一文は?理由と合わせて教えてね。」と、してみてはどうでしょうか?
私のクラスの子は、(ウ)の文を選んで、「大造じいさんの『次こそは必ず残雪を仕留めてやる』という気持ちが伝わるようでかっこいい文だと思ったから好き。」と書く子がいました。(最後の場面の「らんまんとさいたスモモの花が…」の文も人気でした。
このような初発の感想を生かして学習課題をつくることもできると思います。例えば、「A君は(ウ)の文が好きだと思ったんだって。どんな理由を考えてくれたと思う?」のように問うてみることもできそうです。つまり、クラスの仲間の解釈を考えるという文脈をつくるのです。
極論かもしれませんが、授業で着目したい所は子供達自信が決めていければいいと思うのです。ですから、センテンスカードに取り上げる叙述も子供に委ねてみるという究極の目標があります。
以上、センテンスカードを作る視点として⑴指導内容、⑵可視化、⑶学習者視点について考えてみました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
【引用・参考文献】
桂聖編著、他「教材に『しかけ』をつくる国語授業 10の方法」東洋館出版社、2013年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
