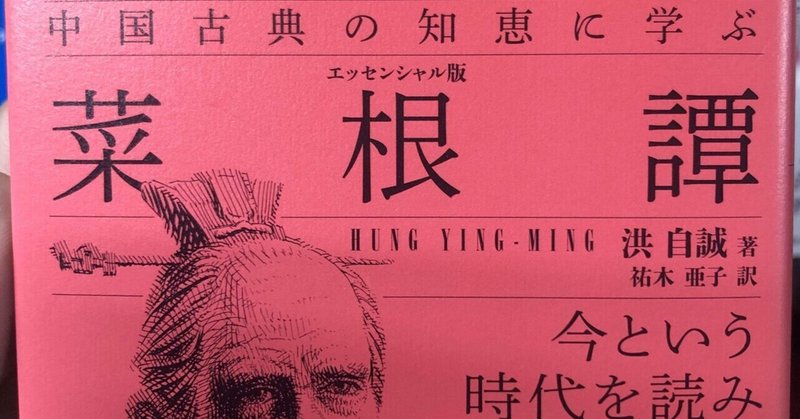
98.『菜根譚』からの格言
『菜根譚』は、人の生き方を説いた処世訓の最高傑作のひとつに数えられ、田中角栄や新渡戸稲造ら各界のリーダーたちから座右の書として愛されてきました。
「菜根」という言葉は、「人はよく菜根を咬かみえば、すなわち百事をなすべし」という故事に由来するそう。
つまり堅い野菜の根っこをかみしめるように、苦しい境遇に耐えられたとしたら、人は多くのことを成し遂げることができる。
タイトルからもわかるように『菜根譚』は苦しい逆境を生き抜くヒントにあふれた、「逆境の古典」です。
そんな『菜根譚』からいくつか引用しましたので、本質的な「生きるヒント」を味わっていきましょう。
「子どもが生まれるとき、母親の生命は危険にさらされる。財産が多くなれば、それだけ泥棒に狙われる。どんな幸せも不幸のタネにならないものはない。
貧乏だと極力ムダ使いを避けるし、病気がちだとふだんから健康に気をつける。どんな不幸も幸せのきっかけにならないものはない。
幸せも不幸も同じことだとみなし、喜びも悲しみも忘れてしまうのが、達人の生き方だ。」
「逆境にあるときは、身の回りのものすべてが良薬となり、節操も行動も、知らぬまに磨かれていく。
順境にあるときは、目の前のものすべてが凶器となり、体中骨抜きにされても、まだ気づかない。」
「長いあいだうずくまって力を蓄えていた鳥は、いったん飛び立てば、必ず高く舞いあがる。
他に先がけて開いた花は、散るのもまた早い。
この道理さえわきまえていれば、途中でへたばる心配もないし、功をあせっていらいらすることもない。」
「自分を磨くときは、金を精錬するときのように、じっくりと時間をかけなければならない。速成では、どうしても底が浅くなる。
事業を始めるときは、重い大弓を発射するときのように、いやがうえにも慎重を期さなければならない。あわてて始めたのでは、大きな成果は得られない。」
「時には喜び、時には苦しみながら、その果てに築きあげた幸福であれば、いつまでも持続する。
時には信じ、時には疑いながら、熟慮の末につかんだ確信であれば、もはや動かしようがない。」
「花を見るなら五分咲き、酒を飲むならほろ酔いかげん、このあたりに最高の趣がある。
満開の花を見たり、酔いつぶれるまで飲んだりしたのでは、まったく興ざめだ。
満ち足りた境遇にある人は、このことをよく考えてほしい。」
「名誉は、独り占めせず、少しは人にも分けてやるべきだ。そうすれば、ふりかかる危難を避けることができる。
悪評は、すべて人に推しつけず、少しは自分もかぶるべきだ。そうすれば、いっそう人格を向上させることができる。」
「他人の過ちには寛大であれ。
しかし、自分の過ちには、
厳しくなければならない。
自分の苦しみには歯をくいしばれ。
しかし、他人の苦しみを、
見過ごしてはならない。」
「人の過失をとがめる人は、
心を動かすごとに、
それがすべて自分を傷つける、
刃物となる。」
「成功は常に
苦心の日に在り。
敗事は多く得意の時に
因ることを覚えるべし。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
