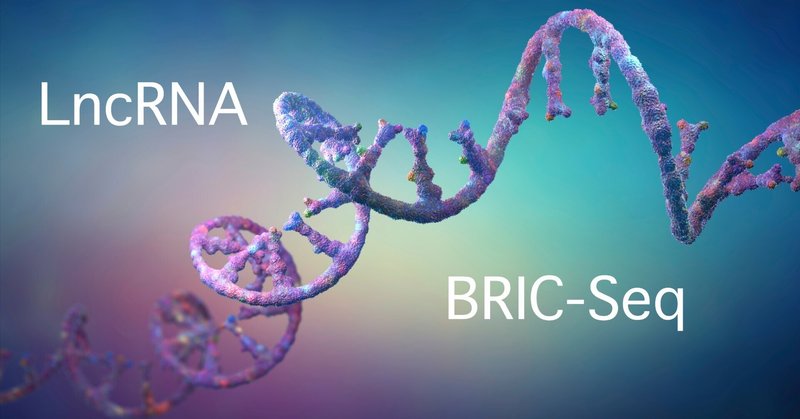
長鎖ノンコーディングRNAの神秘にせまる - BRIC-seq法 開発物語
2009年の春。28歳の私は東京大学でポスドク:博士研究員(日本学術振興会 PD)をしていた。
産業技術総合研究所の学生時代に、共同研究でお知り合いになった秋光先生が、東京大学に移ってラボを立ち上げると聞いたので、思い切って、秋光先生のところに弟子入りさせてもらうことになった。
新天地で、私は学生時代からの研究テーマを一新し、これまでのDNAの解析手法の開発、いわゆる、応用研究(社会に役に立ちそうな学問)と呼ばれるものから、ヒト細胞に含まれるノンコーティングRNA(タンパク質の設計図にならないRNAの総称)と、それに結合しているタンパク質を同定するという、基礎研究(物事の真理を追求する学問)の世界に飛び込んだ。
私が学生時代に取り扱っていたのはDNAのみで、しかも使用していた生物は大腸菌がメインだったため、動物細胞、特にヒト細胞を育てるのは初めての経験だった。そのため、RNA・タンパク質の取り扱いや、ヒト細胞の培養方法等を、基礎の基礎から秋光先生に習うことになった。
そもそも、私が研究者を志すきっかけとなったのは、生命、特に「ヒト」に関する複雑な仕組みを解き明かしたいという動機を持っていたので、このテーマはようやく念願が叶ったというわけだ。
しかし、その道程は決して平坦ではなかった。なにしろ、自分にとって未知の世界に飛び込んだわけである。何事にも新しいことに直面する日々。試薬も装置も、何もかもがこれまでと違う。楽しくワクワクすることもあったが、それ以上に苦労やストレスも多かった。さらに、学生時代からRNA研究にずっと打ち込んできた、研究者仲間とのハンディキャップもあった。特に学会に行くと、同世代との歴然とした差を痛感させられた。
後になって、学生時代のままの研究テーマ(DNAの解析手法)に取り組んだ方が、ポスドク時代でも楽に研究成果が出せていたのではないかという意見を、先輩方や仲間からたくさん耳にした。しかし、私としては、ポスドクという時期を機会に、新しい世界に飛び込みたいという気持ちの方が強かったのだ。必死の決意だった。
さて、話は研究内容に戻って、RNAとタンパク質である。生物の基本ルールとして、DNAからRNAが生まれ、RNAからタンパク質が生まれるという、セントラルドグマと呼ばれる有名な生体分子の流れがある。これは、どの生物でも共通していて、生命の神秘でもある。そして、ノンコーティングRNAはタンパク質の設計図にならないという謎に満ちた存在であり、特に哺乳動物に顕著に存在する。そこで、ヒト細胞を用いて、ノンコーティングRNAとそれに結合するタンパク質を同定しようというのが自分のポスドクでの初仕事であった。
しかし、これがまったくもって上手くいかない。ようやく手がかりが掴めたと思ったら、あえなく杞憂に終わる。そんな日々が半年も続き、季節は冬になっていた。結局、私はこの最初に取り組んだ研究テーマを成功させることは叶わなかった。それは大きな大きな挫折だった。尚、2024年の今でも、世界中でこの研究テーマを真正面から解明した研究は存在しない。それほど難しい研究テーマであったわけだ。
実験室で途方に暮れていたとき、先生の勧めで、同時並行で進めていた別のRNAの研究テーマが、上手く行く感触が掴めてきた。それは奇しくも、学生時代に培った「応用研究」の延長線上にあるものだった。
「これなら、自分のこれまでの経験を生かしてうまくやれるかもしれない」。
29歳になっていた私への、一筋の光であった。
未知のノンコーディングRNAの機能解明の研究。多大な苦労の末に差した一筋の光、そのキーワードは「RNA分解」であった。RNA分解、すなわち、細胞内のノンコーディングRNAはどのくらいの時間存在し、最終的に分解されるのか、それを調べる研究を進めることにしたのだった。
mRNA(メッセンジャーRNA)の世界において、RNA分解のスピードは、その機能とよく相関することが、Nature誌にてすでに報告されていた。簡潔に書くと、RNA分解が早いものは、細胞内の他の因子を制御するタンパク質に多く翻訳され、一方、RNA分解が遅いものは、細胞の部品になるようなタンパク質に多く翻訳される。すなわち、ハウスキーピング遺伝子である。
同じことが、ノンコーディングRNAの世界でもいえるのではないか?さらには、これが未知の世界であるノンコーディングRNAの機能を解明していく上で、ひとつの大きな指標になるのではないか?というのが出発点であった。
RNA分解を調べるには、細胞内のRNA生成を止める試薬を細胞にふりかけ、RNA生成を止めてから、数時間毎に細胞を回収し、RNA量を調べればよい。そうすると、新しいRNAは生まれてこないわけだから、RNAの分解だけが進み、RNA量はどんどん減っていく。その減る過程をタイムコースをとっていけば、RNAの分解度合い、すなわちRNAの半減期を求めることができる。
しかし、無理やり試薬でRNA生成を止めてしまうわけだから、細胞にとっては異常事態になっているであろうことは容易に想像できる。そこで、秋光先生と私は、RNA生成を止める試薬を入れたときに、細胞の状態がどう変化するかを詳細に調べてみた。そしたら、まずは細胞死が誘導されてしまうこと、さらには、RNAの細胞内局在(RNAの細胞内に存在している位置)が極端に変化してしまっていることを突き止めた。従来のRNA生成を止める方法には、重大な欠陥があったのだ。それは細胞が異常事態になり、細胞内がぐちゃぐちゃになってしまうことを示している。
それでは、RNA生成を止める試薬を使用せず、かつ細胞内変化を引き起こさないようなRNA分解を測定できる手法を開発すればよい。そこでいろいろとアイディアを練った末に出てきたのが、生成されたRNAに目印をつける方法、すなわち、ウリジン(U)の修飾核酸であるブロモウリジン(BrU)を目印にする方法であった。
細胞に過剰量のブロモウリジンをふりかけることによって、新しく生成されたRNAには、通常のウリジンではなく、ブロモウリジンを取り込んだRNAが生成される。そして、一定時間後に細胞培地を交換し、ブロモウリジンを取り除く。そうすると、RNAの生成・分解が進むにつれて、ブロモウリジンが入ったRNAは、通常のウリジンの入ったRNAに置き換わっていく。すなわち、ブロモウリジンを含むRNAは、時間を経る毎に減っていく。このブロモウリジンで目印をつけたRNAだけを、タイムコースをとって、抗体で釣り上げてやればよい。
まず、秋光先生と私は、ブロモウリジンが細胞に与える影響を調べた。というのも、RNA生成を止める試薬のように、ブロモウリジンが細胞状態を変化させては、新たな手法を開発する意味がないからである。その結果は良好であった。過剰量のブロモウリジンを細胞にふりかけても、細胞への悪影響はまったくみられなかった。
これならいける!
学生時代に培った、手法開発のノウハウを存分に発揮できる!
そう確信したのが、2010年の春のことであった。その後、研究は加速度的に進んでいくことになる。
ブロモウリジンによるRNA分解速度の小規模解析に成功した頃、これは細胞内の全RNAに適用できる方法であることが明確であったため、mRNA・ノンコーディングRNAの両方を含む、全RNA分解を一気に測定したいと考えるようになった。全RNAを測定できれば、まずmRNAによるNature誌で報告された実験成果の再現ができ、さらには、ノンコーディングRNAの世界初の知見が得られることが期待できる。
そこで、当時最新鋭の装置であった、次世代シーケンサー(RNA-Seq)を使おうという話になった。残念ながら所属する研究室では次世代シーケンサーの装置を所有していなかった。2023年現在のように、誰もがRNA-Seqを手軽に行える時代ではなかったのだ。秋光先生の人脈を頼りに、様々なRNA解析の専門家に相談にいった結果、ついにゲノム解析を専門としている、同じ東京大学の鈴木先生のもとにたどり着いた。
鈴木先生の研究室で、秋光先生とともに自身のこれまでの研究成果のプレゼンを行い、運良く鈴木先生の協力を得られることになった。そこで私は初めて次世代シーケンサーの技術に触れることができ、鈴木先生の研究室に通って、鈴木先生、及び、そこのテクニカルスタッフの方々の多大な協力を得て、ついにブロモウリジンによる全RNAのRNA分解速度の解析に成功した。
得られた結果は、明瞭かつワクワクするものであった。まず、mRNAにおいて、Nature誌と同様の結果が再現できることがわかった。これは我々が開発した新手法が、これまでの実験結果を再現できる、有用性の高いものであることを示している。続いて、ノンコーディングRNAである。2010年当時、機能が解明されていたノンコーディングRNAは、指で数えるくらいしかなかったが、それでも、RNA分解が早いものは、細胞内の他の因子を制御するノンコーディングRNAが当てはまり、一方、RNA分解が遅いものは、tRNA、snRNAなど、恒常的に細胞内で発現しているハウスキーピングライクなノンコーディングRNAが当てはまったのだった。
この成果により、機能未知なノンコーディングRNAを同定していくにあたっての大きな指標を打ち立てることに、世界で初めて成功した。すなわち、制御系のノンコーディングRNAであれば、RNA分解の早いノンコーディングRNAに絞り込むことができ、ハウスキーピングライク系のノンコーディングであれば、RNA分解の遅いノンコーディングRNAに絞り込むことが可能となった。これは非常に画期的なことで、その後のノンコーディングRNA研究に多大な影響を及ぼすことになった。
2011年3月には東日本大震災を経験するなど、紆余曲折があったが、最終的に私はこの新手法を「BRIC-seq」と名付け、Genome Research誌に掲載が決まった。2011年の秋のことだった。私のポスドクの任期は2009年4月〜2012年3月の3年間であり、まさに自分のポスドク時代を象徴するような大きな成果を世界に発信することができた。
さらに、我々と同じようなことを考える人は世界中でいて、同じGenome research誌の同じ号に、オーストラリアの大御所研究室(いわゆるビッグラボ)から、似たような成果が発信された。まさにギリギリのタイミングであった。秋光先生はとてもやきもきしていたが、私は逆に安堵していた。
というのも、同様の研究成果が他の研究室から同時期に発表されるということは、我々の考えが決して的外れではなく、世界の最先端をいくものであり、さらに、再現性のある研究成果であることが、間接的に証明されたからである。山中先生のiPS細胞の研究でも、世界中に競争相手がおり、そのゴールに最初にたどり着いたのが山中先生であったので、ノーベル賞という栄誉に輝いたわけである。科学的に重要な研究成果というのは、得てして、同時期に世界中で進められていることを肌で実感できたのだった。
こうして私は秋光先生のもとで基礎研究の真髄を学ぶことが出来、2012年4月から、産業技術総合研究所に舞い戻り、学生ではなく、独立した研究者としてのポジションを掴むことができたのである。
***Tani H, Mizutani R, Salam KA, Tano K, Ijiri K, Wakamatsu A, Isogai T, Suzuki Y, Akimitsu N*. “Genome-wide determination of RNA stability reveals hundreds of short-lived non-coding transcripts in mammals” Genome Res., 22, 947-956, 2012.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

