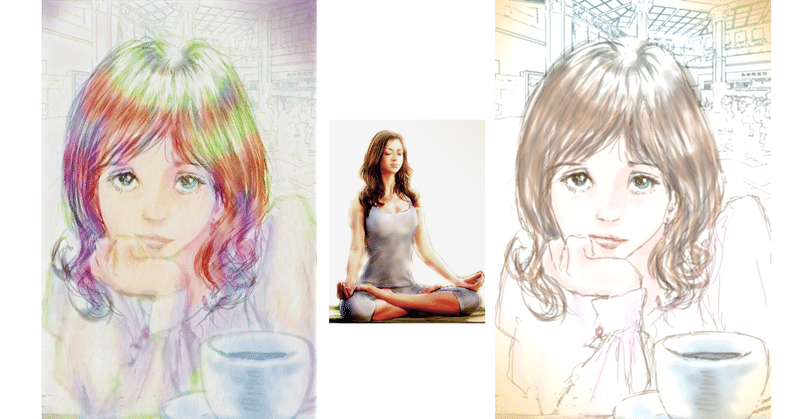
この課題も東西問わず、人間が人間たる故に避けて通れない心の働きであると言えます。
すなわち、人間が人間たるが故に、「不安」は常に存在するものである。というわけです。
「人間とは考える葦である。」
とは、パスカルの有名な言葉ですが、この言葉は何の存在目的もなく、厳然と法則のままに存在する宇宙の機械的な在り方と、そこに存在させられた「人間」の存在を言い得ているのかもしれません。
すなわち、宇宙に対する無限の恐怖の前に、たまたま迷い込んだのが「人間」である。ということです。
ですから、この大いなるものの前に存在するか弱い葦であるが、考える事ができるという尊厳を見いだすことができます。
しかし、それゆえに得体の知れない大宇宙の中においては、「不安」が生じるのはごく当たり前の事です。
すなわち、人間は「考える」という能動が備わっていると同時に、大宇宙の一角にうち捨てられ、その無機質な働きの前には、きわめて受動的であると言うわけです。
じつは、能動であり受動であるという二面性があるが故に、「不安」は必ず存在するということになります。
では、達磨大師に対し、我が腕を切り落としてまで、「不安」の存在を訊ねた慧可に対する達磨の対応はどうだったのか?という話になります。

弟子入りを懇願する慧可に、達磨は「そなたの言う不安とやらを見つけ、この場に持って参れ」と、弟子入りの課題を出しました。
結果、「不安」とは、絶対的にどこにもなかった。ということに気づき、慧可は弟子入りを許されたとあります。
しかし、それは、ないのではなく、おのれの中にあるから、「度する」事は可能だ。という事にもなります。すなわち不安の存在を認めて、それを「安心」に換えるということです。
このことは、そもそも不安を作り出す要素である「二重性」をあるがままに受け入れることであるとも言えます。
そして、東洋思想の「無為自然」はあるがままである事を受け入れることによって、人間は人間たるゆえんに気づくという境地にいたる。という事になります。
つまり、事物の究極を見通せば不安は生じないと言うことにもなりましょう。
般若心経の観自在菩薩が知り得た「般若波羅蜜多」ということにもなります。
ですから、不安から逃れ、それを紛らわすための「慰戯」は、あたかも綱渡りであるというニーチェの言にも通じます。
すなわち、不安の原因とは、そもそも人間が、偉大と卑小、幸福と悲惨、尊敬と軽蔑、愛情と嫌悪。という二重性に引き裂かれた「中間的」な存在であると感じるが故だからです。
ですから、人はできるだけ「深淵」には目を向けたくない。それがゆえに「気晴らし」によってそこから眼をそらそうとします。

しかし、それは何の解決にもならないと先哲は指摘します。
むしろ、「真理」とは何なのか。を追求することによって二重性の在り方を絶対肯定するという考えも、「不安そのものがないのだ」と述べるためには、むしろアリなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
