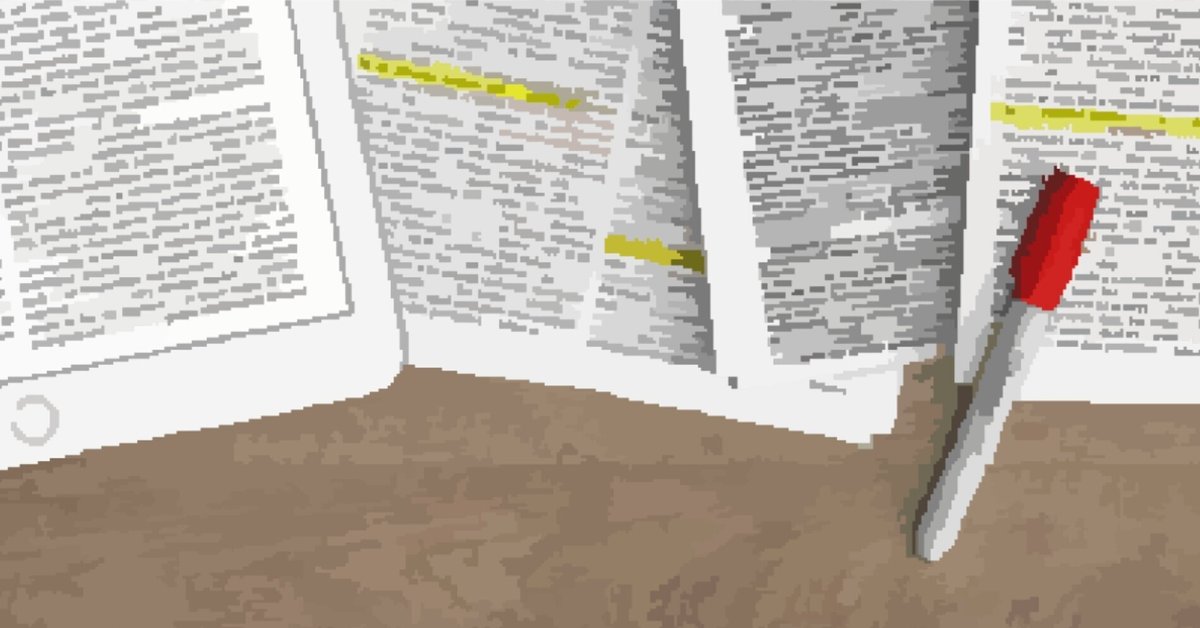
ハゲタカジャーナルにご用心
論文と縁のない世界で生きている人には全く関係ないことですが、論文を書くにはそれなりの労力が必要です。まずは何らかの研究をし、その成果を論文原稿として学術誌に投稿します。その次には、学術誌が選んだ複数の専門家による査読が待っています。査読というのは、その論文原稿が間違っていないか、新規性があるかなどを、専門家の目を通してチェックしてもらうことです。当たり前ですが、この査読が厳しくて、査読を乗り越えることができない場合があります。この査読が無事に通ると、晴れてジャーナルに掲載されて、論文が完成します。
査読は1回では済まずに、2回以上かかる場合もあります。論文の質にもよりますが、投稿から掲載までは早くて2-3か月、通常は6ヶ月くらいはかかります。この論文掲載の難しさに付け込んで、研究者を食い物にするハゲタカのようなジャーナルがいます。
捕食出版は、研究者が投稿した論文原稿をまともな査読・編集を経ることなく、科学的な正当性が担保されない状態で学術誌(と称して)で出版する行為です。捕食出版を行う出版社のことを捕食出版社を日本ではハゲタカ出版社と呼び、その学術誌を捕食学術誌またはハゲタカジャーナルと呼びます。
捕食出版社のビジネスモデルは、研究者が論文掲載料を払うオープンアクセス形式を巧妙に真似ていて、論文掲載料を支払うと論文が電子ジャーナル上で公開されます。実際は、お金を払いさえすれば掲載できる自費出版に近い形式なのですが、”査読済み論文であると詐称する”のです。
ハゲタカジャーナルには、簡単に発表論文件数を増やすことができるというメリットがあります。研究者の業績は論文の数で評価されることが多いので、ついついこの誘惑に負けてしまいます。しかし、それではだめなのです。論文には新規性が必要ですが、それと共に誠実さや正確さが求められます。不誠実な論文は、科学の発展を妨げる禁じ手なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
