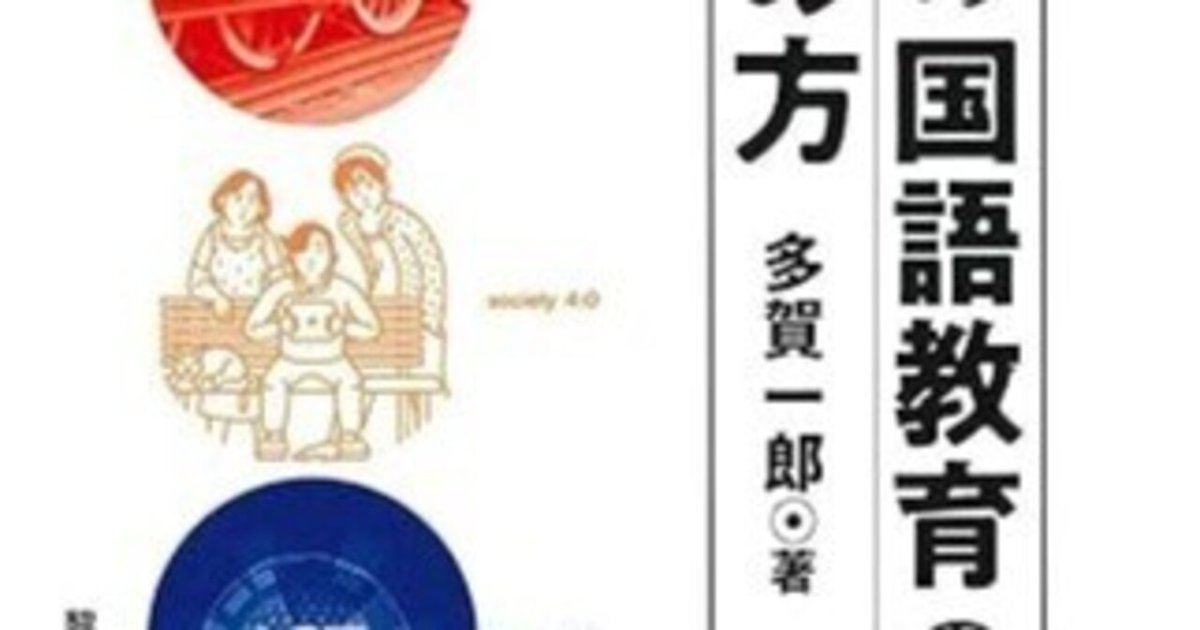
国語の授業で言語感覚を鍛える
昨年末、久しぶりに一参加者としてセミナーに参加してきた。
今回は「せっかくの自分の学びをシェアする」という発信の原点に立ち返って、その時の学びについて書く。
国語と道徳の授業についてである。
講師は、多賀一郎先生。
今回の内容は、次の著書に詳しい。
『ICT時代の国語教育の考え方・進め方』多賀一郎著 黎明書房
国語の先生の本だけに、言葉に一切の無駄がなくすらすらとすぐに読める。今回のテーマは「言語感覚と言語姿勢を育む国語授業」である。
言語感覚とは何か。
次の3つの言葉に集約されるという。
正誤
適否
美醜
この3つを瞬時に判断する力が、言語感覚であるという。
「直感的な判断力、感覚的に言葉をとらえる力」である。(前掲書より)
まずは、正誤と適否。
言語においては、誤った使い方が横行している。
むしろ、もはや誤った使い方が広がりすぎて、市民権を得て定着してしまっているものもある。
「千円からお預かりします」や「おビール」「とんでもございません。」など、丁寧にしているつもりの変な言葉もそうである。
動詞の「着替える」は「きかえる」が本来の読み方だが、「きがえる」が定着していて、もはやそっちが常識である。
(名詞としての「着替え」の読み方は「きがえ」なので、恐らくそのせいである。)
本の中でも書かれているが、「一所懸命」と書いたのを若い方に「誤り」として指摘されたという笑い話をされた。
ここから派生した「一生懸命」の方が一般的に定着しているからであり、さもありなんというところである。
言葉は生きものであり、変化するという前提があるので、ある面では仕方がないともいえる。
適否については「どちらがよりよいか?」という視点も必要である。
「どちらでも使えるがこちらの方がよりよい」というものもかなりある。
例えば講師の先生に対して「参考にさせていただきます」というのは、誤りではないかもしれないが、適当とは言い難い。
(この点は、多分向山洋一氏の著書からの学びだったと記憶している)
「参考にさせていただきます」は、「参考程度」ということと同義である。
相手の知に対する敬意として、かなり軽いのである。
しかし、それを認識して言われている側は、そんなこと思っていないだろうことは百も承知なので、指摘しないだけである。
何より難しいのは、美醜である。
これは、確実に指導しないと身に付かない。
講師の多賀先生が指摘している通り、醜い言葉の方は生活にいくらでも溢れている一方で、美しい言葉の方は教えないとわからないからである。
月の異名なども美しい言葉の一つである。
11月を「霜月」と呼ぶなど、四季の豊かな日本ならではといえる。
霜を踏む時のサクサクとした感触と音から、子どもも四季を肌で感じ取るはずである。
(温暖化の影響で、四季から二季になりつつあるというが、これは文化的に見ても問題である。)
国語の授業においては、この言語感覚を磨くことを忘れないことである。
またそのためには、言語姿勢が大切であるという。
言語姿勢とは
〇言葉が理解できるまで、納得できるまで、調べようとする姿勢
〇言葉に興味関心を持ち、言葉を楽しもうとする姿勢
〇短歌、俳句、川柳などに親しみ、自らも創作しようとする姿勢
であるという。
どれも、意識さえすれば国語の授業で身に付けることができる力である。
逆に言えば、意識しなければ全ては流れる。
国語の力が全くつかずに育つ可能性も出る。
教師の側の学びが全てである。
そして講師の多賀先生曰く、「国語は形式教科である」という。
様々な文章の読み方をしっかりと教える必要がある。
子どもの感性に頼っているようではいけないのである。
まだまだあるが、今回はここまで。
国語の授業がどうにもならないという方には、必読の書である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
