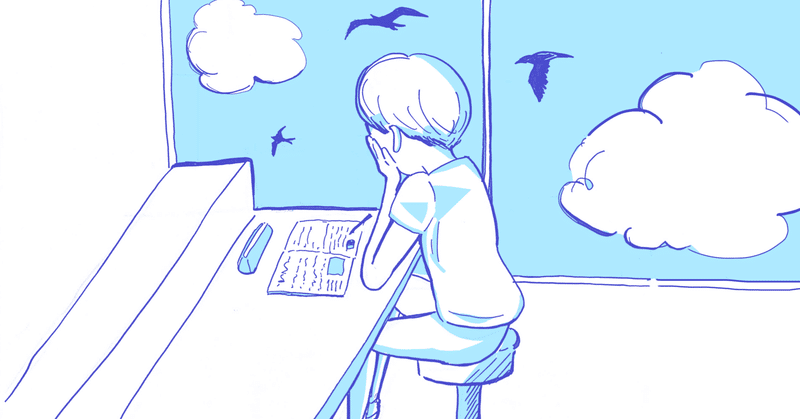
勉強しない子どもへの接し方「急がない」
前回は「何とかしようとしない」というお話でした。
親は自分の子どものこととなると、つい何とかしようとしてしまう。
その結果、空回りしてしまうことがある。そんなお話でした。
もちろん、自戒を込めて。ぼくもつい、やってしまうので(笑)
今回は「急がない」というお話です。
これを知らないと、子どもにアドバイスすればするほど、関係が悪化してしまいます。
でも、多くのお父さん、お母さん、先生がよくやってしまうことです。
ぼくは大学生のとき、家庭教師をしていたのですが、最初の頃やってしまっていましたから(笑)
・・・
今回は、具体例として勉強を教えている場面が出てきます。
でもこれは、例え話としてわかりやすいからお話ししています。
お父さん、お母さんに「勉強を教えてください」というつもりで書いているわけではありませんので。
では始めます。
●急がない
これは、ぼくが大学生の頃、家庭教師をしていたときの話です。
中学生の生徒さんと、数学の学校のワークを一緒に解いていました。定期テストが近づいてきた頃、
「もうちょっとペースを上げないと、定期テストまでにこのワークを終わりにできないな」
こう思って、とにかく終わりにすることを目指していました。
変な責任感。
・・・
何とかワークを終わらせて定期テストを迎えたのですが、結果は家庭教師を始める前と大差ありませんでした。
「ぼくの説明が悪かったのかなあ。でも、そのときは、わかっているように感じたんだけどなあ」
当時のぼくはそう思いました。でも、気づきました。
「定着しないうちに先に進んだからテストでできないんだ!これでは、学校や塾の集団授業と一緒じゃないか!」
説明をきいてわかるのと、自分で解けるのは全然違います(わかった気になりますよね)
そのあとに、似たような問題で練習して慣れないとテストでは絶対にできません。
そんなこと、ちょっと考えれば、生徒さんの状況をよく見ていればわかるはずです。
でも、「テストまでにワークを終わらせないと!」という変な責任感が対応を狂わせたのです。
「焦り」
・・・
定着しないうちに先に進むのは野球に例えるとこんな感じです。ピッチャーに変化球を教えるとして、
「カーブはこうやって投げるよ。手首をこうひねって…」
「次に、シュートはこうやって投げるよ。手首をこうひねって…」
「次は、フォークボールだよ。持ち方はこうで…」
「OK。じゃあ、試合でやってみて!教えたとおりにやればできるから」
これでは無理ですよね!こんな野球のコーチ、絶対にいないですよね(笑)
カーブの投げ方を教えたら、それができるまで繰り返し、繰り返し練習すると思います。
スポーツは目に見えるからわかりやすいのですが、勉強は頭の中のことなので、つい、わかったはずって思ってしまうんですね。
特に、先生は自分ができるからこう思い込みがちです。
・・・
今回は「急がない」というお話でした。
勉強に限らず、何をするときでも、そうカンタンにわかるようになる、できるようになるって思わない方がいいですね。
PS.
自分で勉強できなくて宿題を提出しない場合は、仕上げることを優先することもあります。宿題を出さないと通知表が下がってしまうので。
また、宿題を出さないと、クラスで一緒に授業を受けている感じがなくなります。よくいうお客さん状態。まずは提出することで、参加感を持ってもらいます。できることから。
それでは次回もお楽しみに^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
