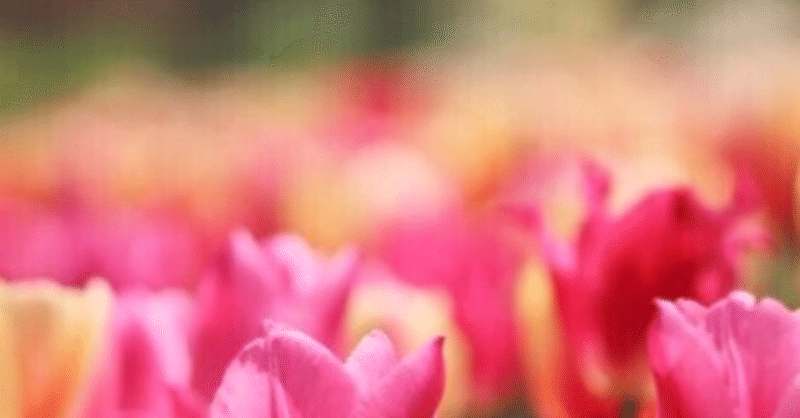
長編小説「きみがくれた」下ー⑫
「忙しい一日の始まり」
サンドイッチのバスケットが頭の上で揺れている。
霧島は昔よりもずっとゆっくりした足取りで歩いて行く。
午後の薄紅通りは行き交う人の数が多い。
前から歩いてくる人が皆一様に霧島を目に留め、それが二人組ならすれ違う時には必ず横目にささやき合う。
手前で一端立ち止まり耳打ちをする人たち、横に避け、通り過ぎる霧島をじっと見つめる人。
霧島は周りのそんな視線を気にする様子もなく、真っすぐに前を向いて目的地を目指した。
道路を渡る手前で霧島はふと立ち止まった。
こちらへかがみ、片手で肩まで抱き上げられると、さっきすれ違った人たちが足を止めて興味ありげにこちらを見ていた。
肩越しに遠ざかる緑の桜並木を眺めながら、ふわりと髪に鼻を寄せる。
耳元に抜けていく緩やかな風、首筋の温もり、体を包む腕の感触。
安心して、うれしくて、眠たくなって、喉から少しだけ声が漏れた。
「‥いいけど寝たら重くなるな」
霧島の声が首元を伝い、耳に、頬に、やさしく響く。
歩く振動が心地よく、霧島の耳に鼻を寄せ、首筋に頬ずりをした。
「‥くすぐったい」
首と肩の間に額をこすると、霧島はぴくりと肩をすくめた。
◆
出掛けにマスターが言っていたことは本当だった。
“母の日シーズン到来でお店はごった返してるかもしれない”
レジでお会計をしながらそう言うと、マスターは
“あまりにも混んでるようなら帰っておいで”と言った。
霧島はメイプル通りを渡らず、その光景を遠目に眺めていた。
アネモネの店頭には“プレゼント用”に“ラッピング”された色とりどりの花鉢が並んでいる。
それを手に取って店へ入る人、選んでいる最中の人‥たくさんのお客さんたちの間で忙しそうに動き回っている亮介が見えた。
気が付くと大きな楓の下に佇む霧島を誰もが振り返って行く。
「モデル?」
通り過ぎざまに聴こえた声に、けれど霧島は表情一つ変えない。
「何かの撮影かな」
「え、ドラマ?」
「雑誌?」
その声は少し離れた位置で立ち止まり、その周りからいくつもの視線が集まっている。
「見たことないけど超絶イケメン!!」
別の場所からそんな声が聞こえた。
「あんな人この世にいるんだ‥」
「すっごいかっこよかったねー!」
「史上一位発見!!」
霧島を見て上がる声は次第に数を増し、大きくなっていく。
遠巻きに立ち止まる人が一人、また一人とあちこちで塊に加わっていく。
霧島はポケットからメガネを出し、そっとかけた。
そして周囲の視線を割るように通りを渡り、アネモネへ足を向けた。
その先で溜まってい人だかりから「きゃあ」と甲高い声がいくつか飛んだ。
後ろからは「やっぱり何かのロケじゃない?」といくつもささやき声がした。
店頭のお客さんの群れの中へ身を隠すように入り込むと、店の中から亮介のよく通る声が飛んできた。
「いらっしゃいませ!!」
顔を上げたその汗だくの笑みは一瞬で硬直した。
目は止まり、手も止まった。
開いた口が下に伸び、その目は驚きに見開かれた。
「―――‥‥!!!」
無言の驚きの叫びの後、喉の奥で声にならない呻きが鳴った。
霧島は前かがみのままこちらを見上げる亮介にバスケットを差し出した。
「これ、マスターから」
不愛想にそう言うと、霧島は亮介が手を出すのを待った。
亮介は見開いた目をもっと見開き、霧島を凝視している。
「冷蔵庫に入れとけって、はい」
催促するように手を伸ばし、霧島は亮介にそう言った。
「―――あ゛‥――――――」
「あ゛ぁぁ‥‥―――!!」
口を大きく開けたまま何か文句を言いたそうな、けれどまったくしゃべれない亮介の前を横切って、霧島は仕方なくそのバスケットを作業台の上に置いた。
「―――汚‥」
台の上にはラッピング用紙の切れ端やリボン、葉っぱや花びら、やり直したようなセロハンや失敗したループリボンなんかが散らばっていた。
見れば後ろの棚も開け放されて、リボンの巻きも色紙も、そのほとんどが長く垂れ下がったままになっている。
「ここ置いとくから」
そう言って立ち去ろうとした霧島に、亮介はやっとのことで口を開いた。
「―――――っじゃねぇだろゴルァッッッ!!!!」
急に飛び出したそのよく通る大声に、お客さんたちが一斉に静かになった。
亮介はこちらへ身をひるがえし、霧島の肩を掴んで振り向かせた。
「てんめぇっ‥コノヤロウ!!今までいったいどこでなにしてやがった?!!連絡のひとつもよこさねぇでフザけやがって!!どんだけ心配したと思ってんだこのクソガキが!!」
亮介の剣幕にどよめきが湧いた。
「10年だぞ?!10年も音信不通で!!どういうことだえぇ?!!あり得ねえだろ?!神経イカれてんだろ!!どういうつもりだ答えてみろ!!」
霧島のシャツを引っ掴み、亮介は一気にまくし立てた。
「おまけに突然現れたと思ったらこの態度!!なんなんだよてめぇはよ!!言い訳できるもんならしてみろってんだ!あぁ?!俺サマが納得いくように今すぐ簡潔に答えろってんだ!この10年俺がどんな気持ちでいたか分かるか?!答えろ!今すぐ!!答えられるもんなら答えてみやがれバカヤロウ!!」
亮介は「クソッ!!」と霧島を突き放した。
「ぶん殴られねぇだけマシと思えよ!!」
そう吐き捨てると、今度は改めて目の前の霧島を見た。
「―――おまえ、また背ぇ伸びた?」
霧島の頭の先から足の先までまじまじと見定めるように眺めながら、亮介は今気づいたように手を叩いた。
「つかおまえメガネじゃん!!」
さっきまでの怒り顔が急に満面の笑みに変わった。
「んだよおまえー!よく見りゃちっと大人っぽくなったか?!そのメガネか?そのメガネのせいか?!超インテリジェンスじゃねぇかコノヤローが!しかも髪もさっぱりしちまってよぉ!なんだよなんだよ急に目覚めやがったのか?!やっとイケメンフル活用してやろーって気になったか?!昔はあんなに拒否ってたクセによぉ!どおゆう心境の変化だコノヤロー!」
亮介は人が変わったように霧島の肩を叩きながら、
「なんだよなんだよ大人じゃねぇか!ええ?コノヤロがぁ!何があったんだコラぁ!何かあったのかぁ?!えぇ?!」
とその髪をぐしゃぐしゃにかき混ぜた。
「‥っめろッ!」
「なんだぁ?シャレっ気づきやがって!相変わらず細っせぇ肩だけどなぁ!コノぉ!」
「‥っヤメっ‥ろって!!」
亮介は霧島のお腹を叩いては腹筋がないとけなし、背中を叩いては骨張っていると笑い、胸元を叩いては薄っぺらいと言い、最後には「もっと鍛えろ男だろ!」と思いきり背中に平手打ちをした。
「っ痛ぇな!やめろよ!」
「っはっは!!痛いわけあるかこんくれぇ!ほんとはボッコボコにしてやりてぇとこだぞ?あぁ?」
亮介の大きな手の平は一撃が重く霧島の体で鈍い音を立てる。
「おいコラ、だからこのメガネはなんだって聞いてんだよ!オシャレか?オシャレメガネか?オシャメか?」
「っせぇな!‥っ生っ活にっ‥支障が出っ‥んだよっ!!」
「はぁ?!バカタレ今更何言ってんだ!支障なんかとっくの昔に出まくりだったろうが!この万年無頓着野郎がよぉ!!」
亮介は大きな声で笑いながら霧島の背中を何度も叩いた。
「っ‥違っ―もうっ!ヤメロっ‥ってしつけぇ…!!」
霧島は亮介の手を交わしながらついに体ごと引き剥がした。
「‥うっぜぇな!!仕方ねぇだろ!!標識の区別がつかなくて、仕方なくだよっ!!」
その言葉に亮介は再び霧島の腕を捕まえた。
「っだよもう!離せ!」
「おまえ、運転できんのか?!」
亮介は霧島の返事を待たずに
「じゃあ配達行ってきて!!」と作業台の上に置いてあったマスターのバスケットを後ろのラックへ移動した。そして積もっていたやりっぱなしを一気に両手で床に落とした。
「ちょ‥はぁ?」
「母の日近いからすっげぇ忙しくてさ!今日の分の配達3件明日に回させてもらおうと思ってたんだけどよかったぁ!!マジ助かるわぁ!!3件ともちょっと遠くてさ、しかも全部あっちとこっちなんだよ!石ノ宮、分かるか?地図はあっから!すぐ準備すっからちょ待って、あ、これ、ラッピングして住所書いてもらって!あぁ色味だけ決めてOKもらったら包むのは後でもいいから!
あの、みなさんすんません、今から少しの間コイツ店に立たせるんで、宜しくお願いしまっす!」
亮介は早口でそう言い終えると、さっさと店の奥へ入って行った。
「―――‥」
店頭に残された霧島は無理やり押し付けられた花鉢を手に呆然としている。
その周りを取り囲むお客さんたちは目を輝かせ、全員が霧島を見つめている。
「オイコラとっととやれよ!おまえのせいで皆さんすっげぇ待たせちまったんだから!」
亮介は向こうで何か音を立てながらそう叫んだ。
「――は?フザけんな」
霧島は期待に溢れた視線に背を向け、亮介を追った。
「こんなんできるわけねぇだろ」
亮介は冷気が流れ出すガラスの中で切り花を手に取りながら、
「できるできないじゃねぇ、やるんだ」
と霧島を睨んだ。
「いいか、今おまえに俺サマの命令を断る権利はない。ゼロだ。分かったら戻ってお客様のお相手をしてこい。」
「なんだよそれ‥つかお客さんに悪いだろ?俺なんかがやったら」
亮介は片手に花束を作りながら、ガラス戸の隙間から顔を出した。
「何のために昔おまえに教え込んだと思ってんだ?できねぇとは言わせねぇ、ココは治外法権ダ。さっさと手ぇ動かしやがれ。」
束ねた切り花を別のオケにいれ、亮介は2つ目の花束に取り掛かった。
「イミわかんねぇ」
「一人5分だぞ5分!それ以上待たせたらペナルティだ。その辺の片づけ全部一人でやらせるからな。」
店の中はまるで突風でも吹いたかのように荒れに荒れていた。
床の上にはラッピング資材の切れ端や葉や茎が散乱している。
すべてがやりっぱなし、出しっぱなし、ゴミ箱にしている大きな段ボールは山盛りになっている。
「ほら行った!俺がこいつを仕上げる前に最低3人!しっかり働け!!」
店の入口へ押し戻された霧島は、不満そうな顔のままお客さんの前に立った。
周囲のフワフワとした空気が霧島の登場でさらに盛り上がる。
亮介は花束をオケごと作業台の下に置き、色紙を片手で一気に引き出すと、ハサミで素早く切り取り台の上に広げた。
そして束ねた切り花をそのに置き、別のハサミで茎を切りそろえると、その先に白い紙を巻きつけ水で濡らした。そこを透明のフィルムで覆い、輪ゴムをかけると、色紙で手早く包んでいく。
最後に全体をフィルムで包み、束ねたところに太いリボンを結んだ。
あっという間に大きな花束が出来上がり、亮介はまた別の色紙を引き出した。
亮介の花束作りは冴子のそれとは全く違う。
マーヤに言わせれば亮介の作業は“まさに男の仕事”だった。
“亮介さんの大きな手が作る花束は豪快でボリュームたっぷりで”
“合わせる色が攻めのビビットカラー”
“思いがけない色同士を合わせたり反対色を大胆に使ったり”
その“意外とイケてる”取り合わせを亮介は“オフランス仕様”だと自慢げに話していた。
「大丈夫よ、時間がかかっても」
「私たち、おとなしく待ってるから」
霧島を取り囲むお客さんが口々にそう言った。
「‥いや、あの俺ここの従業員じゃなくて‥」
そう霧島がいうより前に、お客さんたちは一斉にこう言った。
「そんなことはどうでもいいのよ!」
「なるべくゆっくりで構わないから!」
霧島は“妙な雰囲気”に押されるように、花鉢を作業台の上に置いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
