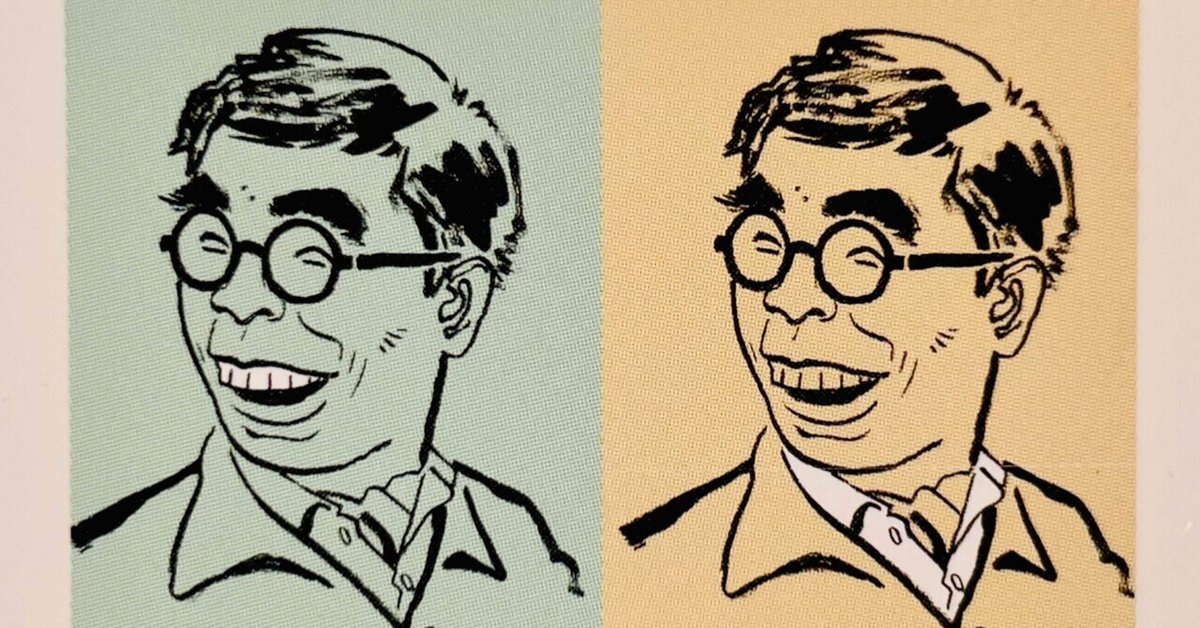
【読みもの】言葉に蓋してよいものか
ぼくは常々「使ってはいけない言葉」というのに気を揉んでいる。
いわゆる《放送禁止用語》とか《差別用語》と呼ばれるものは、それをどんな意味合いで何を伝えるために使おうと、口にすること自体がためらわれる。歌詞は言葉を使って書くので、ぼくは存在している《言葉》そのものにものすごく興味があるからいちいち考えてしまうのだ。
差別が良くないことは誰でも理解できる。ぼくだってわかる。その言葉を発しただけで、誰かが傷つくことになるかもしれないということもよくわかる。しかしだからといって「その言葉を口にしてはならない」というのはちがうと思うのだ。
「使わないようにしましょう」は「見なかったことにしましょう」と同じで、これは日本人が共通して持っている《楽をするための思考》ではないか。ぼくにはそう思えて仕方がない。れっきとしてそこに存在している見たくないものや、過去にあった忘れたいことに蓋をしてしまうという、ある意味とても「ズルい」やり方なのではないか。
使わないようにするとは、その言葉を無かったことにしてしまうことだ。存在しなかったことにしてしまう。言葉それ自体が誰かを貶めるといってその言葉を無くしてしまうことは、貶められてきた歴史自体も葬り去るということだ。そんなこと在りはしなかったんだ、消してしまえというやり方だと思う。
包丁はその「使い方」が問題なのであって、人を刺すこともできるからこれは無かったことにしてしまいましょう。そういうことで《明日から刃物禁止!》とはならないわけで、教育とはつまりそのことだ。使い方を教えることだ。どんなに口酸っぱく教えても、誰かが間違いを犯すことがあるかもしれない。その果てしない道程を歩むことを諦めないから教育なのだ。
言葉はそれを使う人を映し出す。単に語彙力の問題ではなく、同じ言葉でもどのように使うかでその人がくっきりと顕れてしまう。《差別用語》のレッテルでネガティブな印象が付き纏う言葉を、どう使えるか教養なのだと思う。蓋をするのは見ないようにすること。無かったふりをするのは、逃げでしかない。
言葉は使われなくなった時に死んでしまう。死んで思い出されもしなくなったら、歴史を失う。たとえそれが摂理だとしても、一人でも使う人がいるうちは絶滅危惧だがまだ生きている言葉だ。これは差別用語だけではなく、今はめっきり使われなくなったたくさんの美しい日本語たちも同じだ。
ぼくは言葉を殺してしまっていいのかと夜な夜な、一人で勝手に思い悩んでいる。
(井上ひさしベスト・エッセイに収録の「いわゆる差別用語について」を読んで)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
